http://www.asyura2.com/11/hihyo12/msg/629.html
| Tweet | �@ |
(��: 120�D���S�̋@���}�����V���i�P�j�@�@(2009�N12��9���L��) ���e�� taked4700 ���� 2012 �N 2 �� 01 �� 14:32:10)
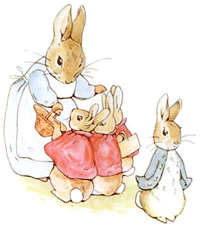

http://www.geocities.jp/yamamrhr/ProIKE0911-121.html
121�D���S�̋@���}�����V���i�Q�j�F�V���ЂƐV���̔��X�@�@(2009�N12��24���L��)
�@�O��́A�V���ƊE�̌���͂��A���s�����┄�オ����n��ԂɊׂ��āA���ɂ͐Ԏ��ɂȂ��Ă��܂������݂Ă����B����́A�V���ЂƐV���̔��X�̌���ɂ��ĕ��͂��Ă݂��B
�@����̃R�����ɗp�����f�[�^���́A�Ō�̎Q�l�����ɋL�ڂ������Ђ�t�q�k������p�����B
�}�P�@�V���̐���Ɋւ���g�D
�P�D�V�����ł���܂ŁF
�@�ŏ��ɐV�����ł�������܂ł̃v���Z�X���݂Ă݂悤�B
�@�V���̐���Ɋ֘A����g�D���E�̐}�P�Ɏ����B
�P�|�P�D�V���L���̎�ށE���M�F
�i�P�j�L���̃\�[�X�F
�@�@�V���L���́A���̂��ׂĂ��A�e�V���Ђ̋L�҂����͂Ŏ�ނ��Ď��M���Ă���Ƃ͌���Ȃ��B
�@�A�L���̈ꕔ�́A�u�ʐM�Ёv����z�M���ꂽ���̂����̂܂܁A���邢�́A����H���Ďg���Ă���i�n�����ɂ���ẮA�L���̔����ȏオ�ʐM�Ђ���z�M���ꂽ���́A�Ƃ����ꍇ������j�B
�@�B����ɂ́A�ǎ҂̓��e�Ȃǂ��L���̈ꕔ���\�����Ă���B
�@�C�L���̃\�[�X���V���L�҂����ł͂Ȃ��ꍇ�ɁA���̋L�����Ԉ���Ă����A���邢�́A��O�҂̖��_��ʑ��������̏ꍇ�A�N���ӔC���̂��A�Ƃ�����肪�N���肤��B
�@�D�Ƃ��ɁA�ʐM�Ђ���z�M���ꂽ�L����V���Ђʼn��H�����ꍇ�ɁA���̐ӔC�̏��݂��m�肷�鎖�͓���B
�@�E�{���A�������������́A�ʐM�ЂƐV���ЂŖ��m�ɂ��Ă����ׂ��Ȃ̂ł��邪�A�����������܂��Ȃ܂܂Ȃ̂�����ł���A���X�A�g���u���ƂȂ����肷��悤�ł���B
�i�Q�j�ʐM�ЁF
�@�@�ʐM�ЂƂ́A�����E���O�ɏ��Ԃ菄�炵�Ď�ނ��������A�V���Ђ�����ǂȂǂ̃��f�B�A��A��ƁE�������Ȃǂɔz�M�i�̔��j���Ă���g�D�ł���B
�\�P�@���ےʐM��
�ʐM�Ж� �{�� �x�Ћǔz�u���� �x�Ћǐ� �]�ƈ��i�T�Z�j
���C�^�[ �C�M���X 150���� 196�x�� 14,500�l
�`�o �A�����J 97���� 243�x�� 3,700�l
�`�e�o �t�����X 100���� 123�x�� 2,000�l
�@�A��ނ��������A�ǂ��ɔz�M�i�̔��j���邩�ŁA�u���ےʐM�Ёv�Ɓu�����ʐM�Ёv�Ƃɕ��ނ����B
�@�B���l�X�R�́A���E100�J���ȏ�Ɏx�Ћǂ������A100�����ȏ�̃��f�B�A�ɏ��𑽌���Ŕz�M���铙�̊�������̂��u���ےʐM�Ёv�ƒ�`���Ă���B���݁A���̊�����Ă���̂́A�E�̕\�P�ɋL�ڂ����R�Ђ����ł���B���E�I�ȒʐM�ЂƂ��ẮA����3�Ђ̂ق��ɁA�c�o�`�i�h�C�c�j�A�^�X�i���V�A�j�A�V�؎Ёi�����j�Ȃǂ�����B
�@�C���̂悤�ȍ��ےʐM�Ђ̑��݂́A���ۃj���[�X��ł���A�Ƃ��������b�g�̂ق��ɁA�卑�̗��ꂩ�����I�ɕ��āA���E���̐l�X�̏����x�z���Ă���A�Ƃ����ᔻ������ł���B
�@�D�����ʐM�ЂƂ��ẮA�����ʐM�ЂƎ����ʐM�ЂƂ�����̒ʐM�Ђ�����B���̗��҂̊T�v���E�̕\�Q�Ɏ����B
�\�Q�@�����ʐM��
�ʐM�Ж� ����i08�N�j �����x�ǐ� �C�O�x�ǐ� �]�ƈ��� �_�f�B�A��
�����ʐM�� 438���~ 51 35 1,719�l ��260��
�����ʐM�� 222���~ 81 29 1,029�l ��130��
�@�E����2�Ђ́A��O�̍���ň�{�����ꂽ�u�����ʐM�Ёv���A�s����_�@�ɕ������ꂽ���̂ł���B
�@�F���������́A�����ʐM�Ђ��V���E���W�I���́u���f�B�A��ƌ�����ʕ���v�A�����ʐM�Ђ��u��ʊ�Ƃ⊯���������v�Ƃ��������ŁA���ݕ����Ă������A1964�N�̓����I�����s�b�N���_�@�ɁA�����ʐM�Ђ����f�B�A��ƌ����z�M�ɏ��o���A���̌��ʁA���͊��S
�ȋ����W�ɂ���B
�@�G2�Ђ̔���K�͂��݂�ƁA�����ʐM�Ђ͎����ʐM�Ђ̂Q�{�قǂ̑傫���ł���B�������A���{�ő�̓ǔ��V���Ђ�2008�N�̔��㍂�i4,553���~�j�Ɣ�ׂ��10����1�ɂ����Ȃ��B
�i�R�j�����ʐM�ЁF
�@�@�����ʐM�Ђ͊�����Ђł��邪�A�����ʐM�Ђ͎Вc�@�l�ł����Ċ�����Ђł͂Ȃ��B�������_������Ă���66�ЂƂm�g�j�Ƃ�������������ċL����z�M���Ă���̂ł���B�����ʐM�Ђ̊T�v�Ɖ����ЁA�_��҂̏ڍד��ɂ��Ă͉E���N���b�N�F�@�����ʐM�Ђɂ���
�@�A�������_������Ă��Ȃ��V���Ђ▯�ԃe���r�ǂȂǂ��A�����ʐM�ЂƁu�_��Ҍ_��v�����鎖�ɂ���āA���蕪��̋L���̔z�M���鎖���ł���B�����ʐM�Ђ̎�����9����������ł���A�_���͂�������5�����炢�������ł���B�܂�A�����ʐM�Ђ́A�������_������Ă���V����m�g�j�̂��߂Ɏ�ނ����L�����쐬���Ă���̂ł����āA��ʓǎҌ����ɂ͍쐬���Ă��Ȃ��B�������A�쐬���ꂽ�L���͂��̂܂܊e���ɓ]�ڂł���悤�ɂ͂Ȃ��Ă��邪�A�ʐM�Ђ̎�ނ̗v�_�́A�ڋq�ł���V���Ђ����ł���邩�ۂ��ł����āA��ʓǎ҂���Ԃ��ۂ��ł͂Ȃ��A�Ƃ����Ƃ���𗯈ӂ��Ă����K�v������B
�@�B5������S�����̂����A�Y�o�V���Ɠ��{�o�ϐV���́A�������_������Ă��邪�A�c���3���i�ǔ��E�����E�����j�́u�_��Ҍ_��v�ɂ��A�C�O�j���[�X�̔z�M�����������Ă���B
�@�C�Ƃ��낪�A�ŋ߁A�����V���̓R�X�g�팸��ڎw���āA���O�̎�ޖԂ��k�����鎖�Ƃ��A�����ʐM�Ɖ������_������킵���B�i�E���N���b�N����2009�N11��27���̒����V���̋L�����Q�ƁF�@�V���L�� �ւ̃����N�j�B
�@�D�������_������Ă���Ƃ������́A�S���E�S���E�ɓƎ��̎�ޖԂ������Ȃ��Ă悢�A�Ƃ������ł���A���ꂾ����ޔ�̃R�X�g�ߖ�ɂȂ���킯�ł���B�������A���̃f�B�����b�g�Ƃ��āA�Ǝ���ނ��ł��Ȃ����߂ɁA�ǂ̉��������A�ʐM�Ђ��z�M����L�����f�ڂ��鎖�ƂȂ�A�܂������������Ȃ��A�Ƃ������ʂɂȂ��Ă��܂��B
�i�S�j�L�҃N���u�F
�\�R�@��ȋL�҃N���u
������������
���t�L�҉� ���@�A���t�{
�{�����L�҉� �{����
�@���L�҃N���u �@����
�i�@�L�҃N���u �ٔ�����������
���N���u �O����
���������� ������
�����N���u ������
���Œ��L�҃N���u ���Œ�
�o�ώY�ƋL�҉� �o�ώY�Ə�
���y��ʋL�҉� ���y��ʏ�
�_���N���u �_�ѐ��Y��
�����Ȋw�L�҉� �����Ȋw��
����茤���� ����
�x�@���L�҃N���u �x�@��
�C�ے��L�҃N���u �C�ے�
�C��ۈ����L�҃N���u �C��ۈ���
������E���}��
����L�҉� ����
�O�c�@�L�҃N���u �O�c�@
�Q�c�@�L�҃N���u �Q�c�@
���̓N���u �����}
�����}�L�҃N���u �����}
���Y�}�L�҃N���u ���Y�}
�Ж��}�L�҃N���u �Ж��}
�@���F�@�Q�l�����Q������p
�������s��
�x�����V�Љ� �x����
�x�����L�҃N���u �x����
�x�����j���[�X�L�҉� �x����
�s���L�҃N���u �����s
���o�ϊW��
���Z�L�҃N���u ���{��s
����y�� �����،������
�w�N���u �H�ƕi�����
�݂��كN���u �����������i�����
�o�ϒc�̋L�҉� �o�c�A
�����N���u �������H��c��
�f�ՋL�҉� �W�F�g��
���{�����L�҃N���u �i�s
�������E�|�\�E���̑���
���W�I�E�e���r�L�҉� �m�g�j
���������L�҉� �m�g�j
���������L�҉�
�����f��L�҉�
�������y�L�҉�
�̑��L�҃N���u ���{�̈狦��
�����^���L�҃N���u
�������o�L�҃N���u
�������n�L�҃N���u
���W���[�L�҃N���u
���{�͌�W���[�i���X�g�N���u
���������L�҉�
�@�@�}�P�ɋL�ڂ���Ă���u�L�҃N���u�v�Ƃ́A���{�S�y��ԗ����鋐��Ȉ�̑g�D�ł͂Ȃ��A��ޑΏہi��������n�������́A�x�@��ƊE�c�̓��j���Ƃɑ��݂��Ă�����{�Ɠ��̑g�D�ł���B��ȋL�҃N���u�ɂ��ẮA�E�̕\�R�����ė~�������A���̂ق��Ɋe�s���{���E�s�����̒��ɓ��A���H�c�́A���̏o��@�֓��X�ɒu����Ă���A���{�S���ł������邩���m�Ȑ����͕s���ł���i800�Ƃ�1000�Ƃ������Ă��邻���ł���j�B
�@�A�L�҃N���u�Ƃ́A��v�Ȏ�ސ�ŋL�҂�������ނ̑O����n�Ƃ��Đݒu���ꂽ�g�D�ł���B����������ސ�ɂ͂����Ă��u�L�Ҏ��v�Ƃ�������������A�L�҃N���u�ɑ�����L�҂́A�L�Ҏ���ʂ��Ċ���������̏��������A��ނ��Ă���̂ł���B
�@�B�������Ȃǂ̋L�҉�́A�L�҃N���u�ɑ��čs���A�L�҃N���u�ɉ������Ă��Ȃ����f�B�A�i�G���L�ҁA�t���[���C�^�[�A�C�O���f�B�A�̋L�ғ��X�j�́A�L�҉�ɎQ���ł��Ȃ��B����Ȃ̂ɁA�L�҃N���u�ɂ́A�N��������ɉ����ł���킯�ł͂Ȃ��B���łɃN���u�ɉ������Ă���L�҂̓��ӂ��Ȃ���Ή����ł��Ȃ��B�����āA�����ł��Ȃ���A�L�҉�ɂ��Q���ł��Ȃ����A���̔z�z���鎖���o���Ȃ��B���̔r�������A����Ӗ��A�V�������f�B�A�ɑ���Q����ǂɂȂ��Ă���A�Ɣᔻ����Ă���B
�@�@���F�@���ď����̏ꍇ�A�W���[�i���X�g�ł���A�L�ҏs���Ă��炤�����ŁA�L�҉�ɎQ���ł���B
�@�C����ɖ��́A�L�҃N���u�̌���ł́A�e���̋L�҂����݂���ރ����������������A���̎�肱�ڂ����Ȃ��̂����m�F�������Ă�������̂ł���B����ł́A�܂�ŁA�k�����ē����L�����������Ƃ��Ă���̂Ɠ����ł���B
�@�D�܂�A�L�҃N���u�����鎖�ɂ��A���̋ƊE�̎��ł���A�V��������������u�����̐����v�Ɓu�k���v���������X�ƍs���Ă���̂��B�����������Ԃ���A�V�����f�B�A��C�O���f�B�A����A�����A���U�v�����o����Ă���B
�@�E����ɁA�u�L�҃N���u�v�������̓s���̂悢�u��ꗬ���@�ցv�ƂȂ��Ă���A�Ƃ�����������B�L�҃N���u�ɋl�߂Ă���L�҂́A�����������𗠕t���������邱�ƂȂ��A���̂܂ܐV���L���Ƃ��Ă��܂��A�Ƃ����P�[�X�����X����B���ꂪ�A���Ƃ��A���������Ƃ��A���{�T���������ɔ����͖삳��̙l�ߔ�Q�E��Q�Ƃ������݂����w�i�ƂȂ��Ă���Ƃ�������B�܂�A�푈���́u��{�c���\�v�𐂂ꗬ�����̎����A���̋L�҃N���u�ɂ������p����Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ɗ뜜�����̂ł���B
�@�F��̏O�c�@�I���ŁA����}�́u���t�L�҃N���u�̔p�~�v���}�j�t�F�X�g�ɑł��o�������A�������Ƃ�����͍��Ɏ���܂Ŕp�~���Ă��Ȃ��B����͏d��Ȍ���ᔽ�ł͂Ȃ����A�ƐV�����f�B�A������ᔻ����Ă���B
�@�G�������A�������f�B�A�̂��������L�҃N���u��ʂ������̉ǐ藘���́A�C���^�[�l�b�g�̕��y�ɂ��������̂������ł͂���B
�P�|�Q�D�V���̕ҏW�F
�@�@�V���ЂɏW�߂�ꂽ�L���͕ҏW�ǂɏW�߂��A�ҏW��c�ŁA���̓��̎��ʂ��ǂ̋L���łǂ̂悤�ɍ\������̂������߂Ă䂭�B���̍ۂɁA�L���ǂ��L���㗝�X�o�R�ŏW�߂Ă����L���̌f�ږʂ������Ɍ��߂��Ă䂭�B
�@�A�ҏW��c�ɂ́A�������E�o�ϕ��E�Љ�Ȃǂ̊e���̃f�X�N�i�ҏW���w������ӔC�ҁj���W�߂��A�e�[�u�����͂�ŁA�ǂ̋L�����g�b�v�ɂ��邩���X���c�_�̂������߂Ă䂭�B�e���f�X�N���e�[�u�����͂�Ő���������̂ŁA�u�y�U����v�A���݂������̕��̋L�����g�b�v�Ɏ����Ă��悤�Ƌ����̂Łu�����������v�u������v�Ƃ����������ł���B
�@�B�ҏW��c�Ō��߂�ꂽ�f�ڋL���Ɍ��o�������ă��C�A�E�g���Ă䂭�̂��A�ҏW�Ǔ��̐������̎d���ł���B�����āA�����������C�A�E�g�������ʂ��Z�{�����`�F�b�N���āA�ҏW��Ƃ͏I�����A����ɉ��B
�P�|�R�D�V���̈���Ɣz���F�@
�@�@�V���Ђ͏o�ŎЂƂ͈قȂ�A�L���̕ҏW���玆�ʃ��C�A�E�g�A�g�ŁA����A���ʂ܂ł��قڈꌳ�I�ɊǗ����Ă���B��v�ȐV���Ђ͂����āA�قƂ�ǂ�����H������ЂŕۗL���Ă����B���̂��߁A�g�p�����{�ɑ���Œ莑�Y�̔䗦���ɂ߂č����i�ƊE���ς�7���O��j�B�������A���{�o�ϐV���̏ꍇ�́A�����̒n���V���ЂɈ�����ϑ����Ă���B
�@�A���݂̐V������́A�̂ƈႢ�h�s���ɂ��啝�ɏȗ͉�����A�X�s�[�h�A�b�v���}���Ă���B�܂��A�L���̓p�\�R���ɓ��͂���A�{�ЕҏW�ǂ̃f�[�^�x�[�X�ɏW���B����������R���s���[�^�Ń��C�A�E�g���A���ʃf�[�^�Ƃ��Ĉ���H��ɑ��荞�܂��B����H��ł͂��̎��ʃf�[�^����l�K�E�t�B�����̌`�ŏo�͂��A���łɏĂ�����B�����āA���̍��ł�����@�ɑ������āA���ʂ��������̂ł���B
�@�B���̂悤�ɃR���s���[�^�����ꂽ���݂̈���H�����g�b�s�r(Computerized Typesetting System�j�h�Ƃ����B90�N��̏I���ɂ́A���ĂŁA�t�B��������H�����Ȃ��ăR���s���[�^���璼�ځA���ʃf�[�^�����łɏĂ�����g�b�s�o(Computer To Plate�j�h�Ƃ����V�X�e�������y���A���̌�A���{�ł��L�܂����B����ɂ́A�R���s���[�^���璼�ڗ֓]�@�Ƀf�[�^��ǂݍ��܂���g�b�s�b(Computer To Cylinder�j�h�Ƃ����V�X�e�����J�����ł���B
�}�Q�|�P�@�V�����s�����Ƒ��]�ƈ����̐���
�Q�D�V���ЂƒʐM�Ђ̏]�ƈ����̐��ځF
�@�V���̐���ߒ����݂Ă������A�ߔN�A�h�s���̐i�W��A���s�����̐L�єY�ݓ��ɂ��A�V���ƊE�����X�g�����i��ł���B�����ŁA�����ł͏]�ƈ����̐��ڂ͂��Ă݂悤�B
�Q�|�P�D�V�����s�����Ƒ��]�ƈ����̐��ځi�}�Q�|�P�j�F
�@�E�̐}�Q�ɁA�V���̔��s�����̐��ڂƁA���]�ƈ����i�V���ЂƒʐM�Ђ̏]�ƈ����̍��v�j�̐��ڂ������B
�@���P�F�@1998�N����2008�N�܂ł̑��]�ƈ����͗��N4���̑��]�ƈ����ł���B
�@��2�F�@�V�����s�����́A�e�N10���̔��s�����ł���B
�@�@�V�����s�����́A1999�N�܂ő������������A���]�ƈ����́A1990�N��65,300�l���s�[�N�Ɍ����Ɍ������Ă���B
�@�A���]�ƈ����̌����y�[�X�́A�V�����s�����̌����y�[�X��傫�������Ă���B
�@�B1980�N��ɑ��]�ƈ����͂�������㏸���Ă��邪�A����́A�h�s���ɂ���U�͌��炵���l�����A���s�����̏㏸�ɍ��킹�đ����������߂ł���B
�@�C�������A1990�N��ɓ����āA�o�u�������A���s�����̐L�т��~�܂�A�₪�Ă͋t�Ɍ�������ɂ��������A�l���͂ǂ�ǂ�ƌ������Ă������B
�@�D������2009�N4���ɂ́A���]�ƈ�����5���l�����荞�݁A4��9��l���������ƂȂ��Ă��܂����B
�Q�|�Q�D�V���Ђ̕���ʏ]�ƈ����̐��ځi�}�Q�|�Q�j�F
�@���ɁA�V���Ђ̏]�ƈ���������ʂɂǂ̂悤�ɐ��ڂ��Ă����������݂Ă݂悤�B
�}�Q�|�Q�@�V���Ђ̕���ʏ]�ƈ����̐���
�@�ʐM�Ђ̏]�ƈ����������A�V���Ђ̏]�ƈ���������ʂɂǂ̂悤�ɐ��ڂ��Ă����������E�̐}�Q�|�Q�Ɏ����B
�@�}�Q�|�Q�̉E�[�̐����́A�V���Ђ̏]�ƈ��i���K�Ј��̂݁j�̍��v�l�i�e�N��4�����݂̃f�[�^�j�ł���B
�@�@�V���БS�̂ɋΖ����Ă��鐳�K�Ј��̑����́A1999�N4����5��8,380�l���s�[�N�ɔN�X�A��̏㉺���͂�����̂́A�قڈ꒼���Ɍ�������2009�N4���ɂ�4��7.600�l�ƂȂ����B����10�N�Ԃ̌������́A�l����1��780�l�A�������ł�18.5���ł���B
�@�A�����ʂɂ݂�ƁA�S�����2009�N4���̏]�ƈ�����1999�N4���̏]�ƈ�����������Ă���B
�@�B���̒��łƂ��Ɍ������������̂́A�u����E����E��������v�ŁA1999�N��1��3,040�l����2009�N��5,010�l�܂ŁA10�N�Ԃ�8,030�l���������B�������ł����ƁA63.7���A��3����2�̌ٗp�����ł����B����́A�h�s�����ɂ��A�o�c�̌�������簐i�������ʂł���A�Ƃ�������B
�@�C2�ԖڂɌ����l���������̂́A�u�o�ŁE���ƁE�d�q���f�B�A����v�B1999�N��4,020�l����2001�N�ɂ�4,860�l�܂ő���������A��̏㉺���͂�����̂́A�����ɓ]���A2009�N�ɂ�2,890�l�ƂȂ��Ă��܂����B�����l��1,120�l�A�������ł�27.9���ł���B�u�o�ŁE���ƁE�d�q���f�B�A����v����U�͑��������̂́A�V���Ђ������c���q���ĐV�������ƕ�����J�悤�ƃg���C�������߂Ǝv����B�������A�債�����ʂ��݂Ȃ��܂܂ɁA�{�Ƃ̕s�U����l���팸�ƂȂ����̂ł��낤�B
�@�D�R�ԖڂɌ����l���������̂́A�u�ҏW����v�ŁA1999�N��2��4,420�l���s�[�N�ɁA��̏㉺�����J��Ԃ��Ȃ��猸���Ɍ��������B�����āA2007�N��2��3,440�l�Œ��ł�����A2�N�����đ������A2009�N�ɂ́A2��3,850�l�܂ʼn����B����10�N�Ԃ̌����l����570�l�A��������2.3���ł���B�u�ҏW����v�́A�ꐔ���傫�����߂ɐl���ł�3�Ԗڂł��邪�A�������ł͂����Ƃ����Ȃ��B�V���̉��䍜��w�����Ă���̂��u�ҏW�ǁv�ł��邩��A���������ŏ��Ȃ̂��ނׂȂ邩�ȁA�Ƃ����C������B
�@�E�S�ԖڂɁA�����l���������͉̂c�ƕ���ł���B1999�N��8,110�l����2009�N��7,590�l�܂ŁA10�N�Ԃ�520�l���������i�������ŁA6.4���j�B
�@�F�����āA�c�ƕ�����́A�����l���͏��Ȃ��i270�l�j���A�������ő傫���i6.8���j�̂��u�����E�Ǘ�����v�ł���B
�}�Q�|�R�@�V���L�҂̒j���ʐ��̐���
�}�Q�|�S�@�����V���L�҂̍\���䗦�̐���
�}�Q�|�T�@�V���Џ]�ƈ��̔N��K�w�ʍ\���䗦�̐���
�@�G����ʏ]�ƈ����̐��ڂ���V���ƊE�̋ꓬ�Ԃ肪�݂ĂƂ��B
�@�@�@�j���s�����̌����ɑΉ����Đl���팸��i�߂Ă������A�Ƃ��ɂh�s�����ŏȗ͌��ʂ��}���u����E����E��������v�ł��̓w�͂������ł���B
�@�@�A�j�V���ȊO�̑��p����ڎw���āu�o�ŁE���ƁE�d�q���f�B�A����v�̑�����}�������A���܂���ʂ��オ�炸�A�������k�������B
�@�@�B�j������̃��X�g���͐i�߂Ă��A�V���L���쐬�̗v�ł���u�ҏW����v�̐l���팸�͍ŏ����ɂƂǂ߂Ă���B
�Q�|�R�D�V���L�Ґ��̐��ځi�}�Q�|�R�j�Ə����L�҂̍\���䗦�̐��ځi�}�Q�|�S�j�F
�@�V���L�����쐬����v�͐V���L�҂ł���B�����ŐV���L�Ґ����j���ʂɁA�ǂ̂悤�ɐ��ڂ��Ă����������݂Ă݂悤�B
�@�Q�l�����Q�ƂV�i���{�V������z�[���y�[�W�j���瓾��ꂽ�f�[�^���x�[�X�ɒj���ʋL�Ґ��̐��ڂ��E�̐}�Q�|�R�Ɏ����B�}�Q�|�R�̉E�[�̐����͒j���ʂ̋L�Ґ��̍��v�l�ł���i�e�N�̐����́A4�����݂̃f�[�^�ł���j�B
�@�@�V���L���̈ꕔ�́A�ǎ҂̓��e�ł�������A�Ј��ȊO�̍�Ƃ̏����ł������肷�邪�A�ʐM�Ђ���̔z�M�L���������ƁA�قƂ�ǂ̋L���͎��Ђ̎Ј��L�҂����M�������̂ł���B�������A��Ƃɑ����Ȃ��t���[�����X�̋L�҂𑽗p����G���ȂǂƂ͈قȂ�����ł���B
�@�A���{�̐V���Ђ͑��̓��{��ƂƓ������u�I�g�ٗp�v�̊��s�����邱�Ƃ������āA�V���Б��́A���Ђ̋L�҂��A�u�L�ҁv�Ƃ��Ă����u�Ј��v�Ƃ��Ĉ����A�u���v�v�����u�Љv�v��D�悷��悤�ɋ��炵�Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ɗ뜜����Ă���B
�@�B���������@�ւ̂�����́A�u�g�D�W���[�i���Y���v�ȂǂƘ_�]�����B���̕��Q�́A���Ƃ��A�푈�̍ۂɌ����B�V���Ђ́A�Ј��̈��S����邽�߂Ɋ댯�n�т��玩�Ђ̎Ј��i�L�ҁj��P�ނ�����̂ŁA��́A�ʐM�Ђ�t���[�����X����̊�e�ɗ��炴��Ȃ��A�Ƃ��������܂��B
�@�C1993�N4������2009�N4���܂ł̐V���L�ґ����̐��ڂ��݂�ƁA2���l�O��ŁA�قډ�����Ԃł��鎖���킩��B�������A��U�}���ɗ�������2007�N4���i1��9,124�l�j����̐��ڂ��݂�ƁA2008�N�A2009�N�ƒ����ɑ������Ă���B
�@�D�V���L�҂Ƃ����E�Ƃ͂ǂ��炩�Ƃ����ƒj�����S�ŁA�����̊����͒Ⴉ�����B���̂��߁A�V���L���������̉��l�ς����f����Ă��Ȃ��A�ȂǂƔᔻ����鎖������B���̂��߁A�ŋ߂͐V���Ђ������L�҂̗̍p�ɐϋɓI�ɂȂ��Ă���B���̎��́A�}�Q�|�R�Ɏ�����Ă���B
�@�E1993�N4����1,620�l�����������L�҂́A���̌�A��̏㉺�����J��Ԃ��Ȃ���A�����ɑ������Ă������B2,000�l�����߂Ē������̂�1999�N�ł��������A2008�N�ɂ͈�C��3,000�l��˔j�����B�����āA2009�N�ɂ͂���ɔ������āA3,129�l�ƂȂ�A1993�N����2009�N�܂ł�16�N�ԂŁA�����L�Ґ��́A2�{�ɔ���1.93�{�ɑ��������B
�@�F�����L�Ґ��̐��ڂ��A�����L�҂��L�ґ����ɐ�߂�䗦�̐��ڂƂ����ϓ_����݂Ă䂭�ƁA1993�N��7.8������2009�N��14.8���܂ŁA���N�����ɑ����������Ă���B�i�E�̐}�Q�|�S�Q�Ƃ��������j�B�܂�A�����L�҂̍\���䗦�́A16�N�ԂŁA1.90�{�ƂȂ�A�{���ɔ��鐨���ł���B
�@�G�t�ɁA�j���Ј��́A1993�N��19,121�l����A��̏㉺�����J��Ԃ��Ȃ���������������Ă���B2007�N�ɂ́A��C��1��6��l��ɂ܂ŗ��������A���̌�͂����A2009�N�ɂ�1��8��l���������̃��x���i1��7,974�l�j�ƂȂ��Ă���B1993�N����2009�N�܂ł�16�N�ԂŁA�j���L�Ґ��̌������́A6.00���ł���B
�@�H�܂�A�L�Ґ����̂��̂́A1993�N��2009�N���ׂ�Ɣ����ł��邪�A�j���ʂɂ݂�ƁA�j���L�҂��������ď����L�҂��������Ă���B�����̎Љ�i�o���A�j����E�ꂩ��ǂ��o���Ȃ���i��ł���A�Ƃ����Ƃ���ł��낤���B
�Q�|�S�D�V���Џ]�ƈ��̔N��K�w�ʍ\���䗦�̐��ځi�}�Q�|�T�j�F
�@���{�Љ�́A�}���ȏ��q����i�܂�A��҂͌���A����҂͑����j���i��ł���B���{�̊�Ƃł��A�o�ς̒�Ƃ����ւ��āA��҂̗̍p���������A�]�ƈ��̕��ϔN��̍�����i��ł���B
�@����ł́A�V���Џ]�ƈ��̔N��\���͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă���̂ł��낤���H
�@�N��K�w�ʍ\���䗦�̐��ڂ��E�̐}�Q�|�T�Ɏ����B�i���̃f�[�^�́A�Q�l�����Q������p�������̂ł���j�B�N��K�w�Ƃ��ẮA��N�w�Ƃ���30�Ζ����A��������̑w�Ƃ���30�`49�A�n�N�w�i����҂̓�����j�Ƃ���50�`54�A����ґw�Ƃ���55�Έȏ�A�Ƃ����l�K�w�ŕ��͂����B
�@�@1970�N�ɂ́A�S�̂�3�����i31.3���j����N�w�A���̔{��6��������������w�A�����āA�n�N�w�ƍ���ґw�����킹�Ă�1�������ɉ߂����A�Ⴂ�ƊE�ł������B
�@�A�Ƃ��낪10�N���1980�N�ɂȂ�ƁA��N�w��2����i18.5���j��10�N�Ԃ�1���ȏ�i12.8���j�����������B�����āA�������̔����͓�������w�ɁA�c��̔����̂قƂ�ǂ͏n�N�w�ւƐU�������ꂽ�B�n�N�w�̍\���䗦��1�������i12.2���j���A�n�N�w�ƍ���ґw�𑫂����킹�Ă��A��N�w���͍\���䗦�͒Ⴉ�����B
�@�B1990�N�ɂȂ�ƁA��N�w�͎�i2���j���������A��������w��1���ȏ�i12.8���j�����������B�����āA�n�N�w�������i1.9�������j�A����ґw����C�Ɍ����i9��������11.5���j���A���̗��҂����킹��ƁA��N�w������悤�ɂȂ����B
�@�C2000�N�ɂȂ�ƁA����͂���ɐi�B�}�Q�|�P���琄���ł���悤�ɁA�V���ЂɋΖ�����]�ƈ����͌����������Ă��钆�ŁA��N�w�Ɠ�������w�̍\���䗦�͒����Ɍ����i���������킹�Ă�7���ɓ͂��Ȃ��Ȃ����j���A�n�N�w�ƍ���ґw���������Ă���B�����āA�n�N�w�̍\���䗦�i17.2���j����N�w�̍\���䗦�i17.1���j�������Ă��܂����B
�@�D2004�N�̃f�[�^�ł́A��N�w�̍\���䗦������Ɍ�������14.6���ƂȂ����B����A��������w�͂�����53.6���ƂȂ����B���̗��Ђ̍��v��2000�N���͎���������A����ł�7���ɂ͓͂��Ă��Ȃ��B2000�N�Ɣ�ׂ�ƁA�n�N�w�������č���ґw�������Ă���B����͂�����u�c��̐���v���A����ґw�ֈڍs���Ă��������߂Ǝv����B
�Q�|�T�D�V���Ђ̏]�ƈ����̕��͂���F
�@�V���Ђ̏]�ƈ����̕��͂�i�߂����ʁA�ȉ��̎���������B
�@�@�]�ƈ������́A1990�N��㔼����قڈ꒼���Ɍ������Ă���B
�@�A�]�ƈ����̌����́A�V���Ђ̑S����ɋy��ł��邪�A�Ƃ��ɁA�u����E����E��������v�Œ������B
�@�B�V���̗v�ł���V���L�҂̐��ł݂�ƁA1990�N��O�����猻�݂ɂ�����܂ŁA�قډ����Ő��ڂ��Ă������A�ߔN�ɂȂ��āA�Q�����Ă���B�����A�����j���ʂɂ݂�ƁA�j���L�҂͌������A�����L�Ґ����������Ă���B�i1993�N����2009�N�܂ł�16�N�ԂŁA�����L�Ґ��́A2�{�ɔ���1.93�{�ɑ����j�B
�@�C�������Ă���]�ƈ��̔N��\�����݂Ă䂭�ƁA�����ɍ�����i��ł���A�Ƃ������Ƃ��킩��B
�R�D�V���̔̔��Ɨ��ʁF
�}�R�|�P�@��z�Ƒ����䗦�̐���
�@�o���オ�����V���͗��ʌo�H�ɏ悹���Ĉ�ʓǎ҂ɔ̔�����邱�ƂɂȂ�B�V���卑���{�i�u120�D���S�̋@���}�����V���i�P�j�v�ŏЉ�j���x���Ă���̂́A�������ꂽ�V���z�B�Ԃł���A���̍������Ȃ���z���x�ł���B�O���ɂ��A�������A��z���x�͂��邪�A���{�قNJ�������Ă��鍑�͂Ȃ��B�����ł́A��z���x�𒆐S�ɐV���̔̔��Ɨ��ʂɂ��ĕ��͂��Ă݂悤�B
�R�|�P�D��z�䗦�̐��ځi�}�R�|�P�j�F
�@�ŏ��ɁA���{�V����������̐V���ŁA��瑦���ŏ������Ă���̂́u�����X�|�[�c�v��u�[���t�W�v���A�����킸���ł���A��z�䗦��90�����Ă���B���̑�z�䗦�Ƒ����䗦�̐��ڂ��E�̐}�R�|�P�Ɏ����B
�@���̃f�[�^�́A���{�V������̖��N10���̒����f�[�^���瓾��ꂽ���̂ł���B
�@�@1998�N����10�N�Ԃ̑�z�䗦�̐��ڂ��݂�ƁA2001�N�Ɏ���������̂́A1998�N��93.20������2008�N��94.60���܂ŁA�قڒ�����ɏ㏸���Ă��鎖���킩��B
�@�A��z�䗦�̏㏸�X���Ƃ͑ΏƓI�ɁA�����䗦�͌������Ă���B�i1998�N��6.20������2008�N��4.84���܂ŁA�قځA������Ɍ����j�B
�@�B�Ȃ��A��z�䗦�Ƒ����䗦�𑫂����킹�Ă�100���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B����́A�������ւ́A�X�����ꂽ�肵�Ă��邩��ł���B
�@�C�X�|�[�c�����́A�w�̔��X���ł̑����̔䗦���������A����ł��A��z�䗦��7���O��ł���A�����䗦�i3���O��j�̔{�ȏ�ł���B
�R�|�Q�D�V���̔��X�F
�@�O���ł݂��悤�ɁA�V���卑���{���x���Ă���̂́A���E�Ɋ������z���x�ł���A��������s���Ă���̂��V���̔��X�ł���B�����ŁA�����ł͐V���̔��X�̏͂���B
�i�P�j�V���̔��X�̎�ނƐV���ЂƂ̊W�F
�@�@�قƂ�ǂ̐V���̔��X�́A�V���ЂƂ͓Ɨ�������Ƒ̂Ƃ��āA�V���Ђƌ_�������ŐV����z�B���Ă���B
�@�A�V���̔��X�ɂ́A�u�ꔄ�X�v�A�u�����X�v�A�u�����X�v�Ƃ�����3��ނ����݂��Ă���B
�@�@�@�j�ꔄ�X�F�@����̐V���Ƃ��̌n��̐V���݂̂������̔��X�B
�@�@�A�j�����X�F�@��v�n�����ƑS�����Ƃ����������ŕ����̐V���������̔��X�B
�@�@�B�j�����X�F�@��{�I�ɂ�����V���������̔��X�B
�@�B�s�s���ł́A���������������߂ɐꔄ�X���������A�ߑa�����i�ޒn���ł͍����X�������B
�@�C���j�I�ɂ݂�ƁA1952�N�܂ł́A�펞���̕��������̋K�����琶�܂ꂽ�u�����X�v�݂̂ł������B1952�N�ɂ��̋K�������������Ƒ��V���Ђ𒆐S�ɁA�Ǝ��̔̔��Ԃ̍\�z�ɏ��o���A���݂Ɏ���u�ꔄ�X�v�𒆐S�Ƃ�����z�V�X�e�����m������Ă䂭�B
�@�D�u�ꔄ�X�v�́A�Ɨ�������Ƒ́A�Ƃ͂����Ă����Ԃ́A�V���Ђ̉c�ƓX�݂����Ȃ��̂ł���A��������u�g�̒c�v�Ƃ��u�������v�Ƃ��������_�����܂�Ă��邪�A�����̖��_�͌�ŕ��͂��܂��B
�}�R�|�Q�@�̔��X���Ə]�ƈ����̐���
�i�Q�j�V���̔��X���Ə]�ƈ����Ƃ̐��ځF
�@���{�V������e�N10���̃f�[�^�Ƃ��āA�V���̔��X�̐��ƁA�����œ����]�ƈ��̐������\���Ă���B���̃f�[�^�Ɋ�Â��A���̐��ڂ��E�̐}�R�|�Q�Ɏ����B
�@�@�̔��X���́A1970�N��1��8,338����1990�N��2��3,765�܂ŁA20�N�Ԃ�5,427���������i�������ł����ƁA29.6���j�B
�@�A���x�o�ϐ���������o�u������O��܂ł́A�}�Q�|�P������킩��悤�ɁA�V���̍w�ǎҐ��͔N�X���������B�����ŁA�e�V���Ђ͎��O�Ŕ̔��Ƒ�z�̃l�b�g���[�N���ɃR�X�g�������A�ꔄ�X�̊m�ۂɑS�͂��X�����B
�@�B�̔��X���̑���ɔ����A�]�ƈ��̐����꒼����ɑ������B1970�N��33.1���l����A1995�N��48.1���l�܂ŁA25�N�Ԃ�15���l���������i�������ł����ƁA45.3���j�B
�@�C�̔��X���̃s�[�N�ƁA�]�ƈ����̃s�[�N�ł�5�N�̂��ꂪ����B����́A�]�ƈ����̕ϓ��́A�̔����̕ϓ��ɒx��Đ����邩��ł���B
�@�D�̔��X�����]�ƈ������A�o�u���o�ς�������́A�s�[�N���߂��č⓹��]��������悤�Ɍ������Ă���B
�@�E�̔��X���́A1990�N��2��3,765����2008�N��2��99�܂ŁA18�N�Ԃ�3,666�X���ł��i������15.4���j�A�Ԃ��Ȃ��A2���_�̑������荞�݂����ł���B
�@�F�̔��X�œ����]�ƈ����́A1995�N��48.1���l����2008�N��41.7���l�܂ŁA13�N�ԂŁA6.4���l�����ƂȂ����i������13.3���j�B
�@�G���������̔��X����]�ƈ����̌������́A�}�Q�|�P�Ɏ������s�����̌������i1999�N����2009�N�܂ł�10�N�Ԃ�4.2���j�����͂邩�ɑ傫���B���̎��́A��q����u�������v�������Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����^�������߂�؋��ƂȂ肤��B
�@�H�w�ǎҐ����N�X�������Ă�������ɂ́A�V���ЂɂƂ��Ă��L���ɓ������u�ꔄ�X�v�Ƃ����V�X�e���́A�w�ǎҐ���������ɓ���ƁA����ǂ́A�V���Ђ̌o�c����������悤�ɂȂ��Ă������B���̂ւ�̎���́A��ŕ��͂������B
�i�R�j�V���̔��X�̋Ζ��`�ԕʏ]�ƈ����̐��ځF
�}�R�|�R�@�V���̔��X�]�ƈ��̋Ζ��`�ԕʈ����̐���
�}�R�|�S�@�V���̔��X�œ����u�V�����N�v�̍\���䗦�̐���
�@�V���̔��X�̏]�ƈ����Ƃł͓����Ă���̂��A���Ƃœ����Ă���̂��A�Ƃ������Ζ��`�Ԃŕ��ނ����̏]�ƈ����̐��ڂ��E�̐}�R�|�R�Ɏ����B
�@�}�R�|�R�̉E�[�̐����́A�V���̔��X�œ����l�����̑����ł���A�}�R�|�Q�̏]�ƈ������Ɠ����ł���B
�@�@�V���̔��X�ŁA��Ƃœ����Ă���l�i�u��Ɓv�j�́A1998�N����2004�N�܂ł́A8���l����ێ����Ȃ���A�قډ����Ő��ڂ����B�������A2001�N��8��1,836�l���s�[�N�ɔN�X���葱���A2005�N�ɂ�8���l������荞�݁A2008�N�ɂ�7��5,347�l�ƂȂ����B
�@�A���ʂƂ��āA�u��Ɓv�́A2001�N�̃s�[�N������2008�N�܂ł�7�N�ԂŁA6,489�l���������B�������ł�7.9���ł���B
�@�B18�Ζ����̐��N�ŐV���z�B���œ����Ă���l�i�u���N�v�j�́A1998�N��5��8,889�l����N�X�������A2008�N�ɂ́A1���l������荞���9,565�l�܂Ō��炵���B
�@�C�u���N�v�́A1998�N����2008�N�܂ł�10�N�ԂŁA4��9,324�l�������i�������ł�����83.8���j���Ă��܂����B�����Ắu�V�����N�v�͂��܂�A�u��Ŋ뜜��v�ƂȂ��Ă��܂����̂��B
�@�D�������A��w����w�Z���֒ʂ��Ȃ���V���z�B���œ����Ă���l�i�u�w�����v�j���A1998�N��2��3,069�l���疈�N�����𑱂��A2008�N�ɂ�8,093�l�ƂȂ����B
�@�E�܂�A�u�w�����v�́A1998�N����2008�N�܂ł�10�N�ԂŁA1��4,976�l�����i�������ł�����64.9���j���Ă��܂����B�����Ắu��w���v�Ƃ������t�͂��܂�A�u����v�ƂȂȂ����悤���B
�@�F�V���̔��X�ŁA���́u�w�����v�Ɓu���N�v�ȊO�ŁA�p�[�g��A���o�C�g���œ����Ă���l�i�u���Ɓv�j�����́A1998�N�Ɣ�ׂ�ƁA2008�N�ɂ͎�ł͂��邪�������Ă���B�����A�N�X�̐��ڂ��݂�ƁA2003�N��33��3,311�l���s�[�N�ɔN�X�������Ă��鎖���킩��B�����āA2008�N�ɂ�32��4,164�l�ƂȂ��Ă���B
�@�G���̂悤�ɂ݂Ă���ƁA�ߔN�A�V���̔��X�œ����l�́A��Ƃł��邩�ۂ����킸�A�����Ɍ������Ă���A�Ƃ��������킩��B����́A�V���̔��s�������������Ă���A�܂�A�w�ǎ҂�����z�B���ׂ������������Ă��邽�߂ł���A�Ɛ��������B
�@�H������u�V�����N�v��u��w���v�������Ă���̂́A�Љ��̕ω����傫�ȉe�����y�ڂ��Ă���Ǝv����B�������A�u��w���v���̂��̂́A�A���o�C�g���V���z�B����A���̐E��ɕς��āA���܂��Ɍ����Ă��Ȃ��̂�������Ȃ��B
�i�S�j�V���̔��X�œ����u�V�����N�v�̍\���䗦�̐��ځF
�@�V���̔��X�ŐV���z�B�������ē����Ă���18�Ζ����̐l�����i������u�V�����N�v�j���A�V���̔��X�]�ƈ��̒��Ő�߂銄���i�\���䗦�j�̐��ڂ��E�̐}�R�|�S�Ɏ����B
�@�@�u�V�����N�v���V���̔��X�]�ƈ��ɐ�߂�䗦�i�\���䗦�j�́A1970�N�ɂ́A6���߂������i
59.1���j�B
�@�A���̌�A�A�\���䗦�́A�}���]��������悤�ɒቺ�����B1985�N�܂ł́A5�N����7���O��̌��ł��������A��������1995�N�܂ł�5�N���Ƃ̌�������10�����������B
�@�B1995�N�ɂ́A20������āA17.1���ƂȂ�A5�N���2000�N�ɂ�10�������9.34���ƂȂ����B
�@�C�����āA�����5�N���2005�N�ɂ́A�T�����������3.91���ƂȂ�A2008�N�ɂ�2.29���܂Œቺ���Ă���B
�@�D�}�R�|�S������ƁA20���I���ɂ́A�u�V�����N�v�Ƃ����̂́A�����M�d�ȑ��݂ɂȂ��Ă����A�Ƃ��������킩��B
�S�D�V���̔��X����������_�F
�@�V�����s�������������钆�ŁA��z���͐L�тĂ���A�V���Ђ̌o�c�Ƃ��āA�V���̔��X�͂܂��܂��d�v�ȑ��݂ɂȂ����B�������A�V�����w�ǂ���l��������鍡�A�V���̔��X��������̌����ȊO�ɂ��傫�Ȗ�������Ă���B
�@�����̖��_�́A���łɁA1970�N�㍠����w�E����Ă������̂���ł��邪�A�̔������������ɐL�тĂ���Ԃ́A���㑝��ɂ���ĕ����B����Ă����B�������A���㌸������ɓ����āA��C�Ɍ��݉����Ă������̂ł���B
�S�|�P�D���������F
�@�ŏ��Ɏ��グ��̂́A�u�������v�ł���B����́A�Â��ĐV�������A���݂͌��R�̎����ł���̂ɐV���Ђ���Ƃ��ĔF�߂Ȃ����A�V���E�ő�̈łƂ���������A���X�A�l�X�Ɍ`�e����Ă��邪�A�V���E���������畅���Ă��鎖�������d�v�ȏ؋��ł�����B
�i�P�j�������Ƃ�
�@�@�u�������v�Ƃ́A�ꌾ�ł����A�V���̔��X���̔��ł��镔�����āA�V���Ђ������I�ɔ[�i����Ă��镔���̎��ł���B�V���̔��X�ƐV���Ђ̊Ԃɂ́A�������Ȃ���̂͑��݂��Ȃ��B���݂̌ċz�ŕK�v�Ɣ��f���ꂽ�������A�V���̔��X�̈ӌ��Ƃ͊W�Ȃ��A�V���Ђ������I�ɑ����Ă���B�����āA�K���i�ƌ����Ă������߂��ł͂Ȃ��j�A�������̐V���͔���c��B
�@�A��U�A����ꂽ�V����Ȃ���������A�Ƃ������R�ŕԕi���鎖�͋�����Ȃ��B����Ȃ����������̑�����̔��X�͐V���Ђɕ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v����ɁA�V���̔��X�͕s�v�ȕ������u���������Ă���v�킯�ł���B�����ŁA�K�v�ȕ������đ�������Ă���V�����u�������v�ƌĂ�ł���킯�ł���B
�@�B�V���Б��́A�����āu�������v�Ƃ͌���Ȃ����A���̑��݂���ے肵�Ă���B���Ƃ��A�����V���́u�A�W���X�^�u���ڕW�v�A�����V���́u�c���v�ȂǗl�X�Ȗ��̂�p���Ă��邻���ł���B
�@�C�u�������v���V���Ђ̔��s�����ɂȂ�A����Ɍv�コ��邩��V���ЂɂƂ��Ă̓����b�g�͑傫���B����A�̔��X���͂��̎d����R�X�g���܂�܂邩�Ԃ鎖�ɂȂ邩�炻�̕��A�����ƂȂ�A����I�ɕs���Ȃ悤�ɂ݂���B�Ƃ��낪�A�K�����������Ƃ͌�����Ȃ��Ƃ��낪�A���̖��̂�₱�����Ƃ���ł���A���o�E�̔��S���^�f�̂悤�ɁA���\�N��������ł͏����A�����Ă͕�����ł���w�i�ł�����B
�@�D�̔��X�̎����́A�w�ǎ҂��x�����V����ł��邪�A���̂ق��ɑ傫�Ȏ������Ƃ��āA�܂荞�݃`���V�̔z�B���ƐV���Ђ���́u�⏕���v�Ƃ�����B���̌�҂̓�́A���̔̔��X����舵�������ɂ���Ď����z���傫���ς���Ă���̂��B���������āA�u�������v�́A�V���̔��X�ɂƂ��Ă������b�g������b�Ȃ̂ł���B�i�V���̔��X�̎����\���ɂ��Ă͍��ڂ����߂ĕ��͂���j
�@�E�������A�������́A���ǂ͔p�������킯�ł���A�����̖��ʌ����ɂȂ��Ă���A�G�R���_�ɔ������s���ł���B������傫�����グ�A���҂����������e���Ă���V���Ђ��A���̂悤�Ȏ����̖��ʌ��������Ă���A�����������F�߂��A���Ƃ��Ēp���Ȃ��A�Ƃ����̂ł́A�u�U�P�ҁv�Ɣ���Ă���ނ����Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���H�B
�i�Q�j�������̊���
�\�S�@�������̐��蕔���Ɣ䗦
�V���� �`�a�b���� ���艟����
���� ���艟����
���i���j
�ǔ��V�� 70,769 13,025 18.4
�����V�� 62,587 21,508 34.4
�����V�� 26,910 15,432 57.3
�Y�o�V�� 11,164 6,392 57.3
���̑� 69,117 30,991 44.8
���@�v 240,547 87,348 36.3
�@�@�u�������v���A���̔��s�����̉������߂�̂��A����́A��������̂������Ƃ�������ł͂��邪�A���N�i���\�N�H�j���O����T�����������グ�Ă��邵�A�̔��X���V���Ђ�i�����ٔ��̒��Ŏ��グ��ꂽ�肵�Ă���B
�@�A�����ł́A���N�������ꂽ�u�T���V���v6��11����(��s���ł�2009�N6��5������)�Ŏ��グ��ꂽ���ꌧ�̃|�X�e�B���O�Ǝҁu����N���X���f�B�A�v��2009�N5�����_�ŁA1,700���~�������čs���������i���i�Ύ��ӂ̑�ÁA���ÁA��R�A�I���A��F��5�s�A�l����64���l��Ώہj���ʂ��Љ��B���̒������ʂ���܂Ƃ߂��̂��E�̕\�S�ł���B�i�Q�l�����P�����p�j�B
�@�B�\�S�̂`�a�b�����Ƃ́A���c�@�l���{�`�a�b����������Ĕ��\���Ă��锭�s�����ł���B�������A�����ƌ����Ă��A�e�V���Ђ̕��������̂܂ܗp���Ă��邾���ł���A���̋q�ϓI���t���͖R�����A�ƌ��킴������Ȃ��B
�@�C�\�S�̍��v�����݂�Ƃ킩��悤�ɁA���̒����ł́A���̕�����3����1�ȏ�i36.3���j���������ł���B����́A����Ӗ������ׂ������ł͂��邪�A����ł����Ȃ����炢�ł���A�Ƃ�������������l�����邻��������A���ۂ͂ǂ��Ȃ̂��A�܂��Ɂu�����a�v�̐��E�ł���B
�@�D�Ƃ����̂́A�ǔ��V���̐��艟���������u�킸���v18.4���ł��邪�A����́A�ǔ��V�����S���I�ɉ��������T���Ă��邩��ł͂Ȃ��B���ꌧ�V���̔��J�g���A80�N��ɓǔ��V���̉���������Njy�������ʁA���ꌧ�ł́A�ǔ��V���̔̔��X������������f��Ղ��u��C�v�����܂�Ă�������ł���i�Q�l�����P�����p�j�B
�@�E�`�a�b����A�ߋ��ɍs���������i�`�a�b�����j�ł͈ȉ��̔䗦�ŐV�����p������Ă���Ɛ��肳��Ă���B
�@�@�@�j2001�N�`2003�N�ɂ����čs��ꂽ�u�����v�ł́A������7.5���A�[���ł͓ȏオ�̔��X�Ŕp������Ă���B
�@�@�A�j2003�N�`2005�N�́u�����v�ł́A���̔p�����͂���ɑ傫���Ȃ��Ă���B
�@�F�`�a�b�l���́A����Ӗ����������ł���A���ۂɔz�B����Ă��镔��������̂��ړI�ł����āA������������̂��ړI�ł͂Ȃ��B���̂��߁A�����ł̐����́A�ɂ߂čT���ڂȐ����ł����ĐM�p�ł����A���ۂ̔p�����i���������j�͂��̉��{������A�Ǝw�E����Ă���B
�i�R�j�����������ݏo���u�ƍ߁v
�@�@�������̐��m�Ȕ䗦�͕s���ł��邪�A�ǂꂾ�����Ȃ����ς����Ă�10���ȏ�ł���A�ƌ��������Ǝv����B�܂�A�`�a�b�����̏��Ȃ��Ƃ�1�����p������A���ʂɂȂ��Ă���ƌ������ł���B����1���̖��ʂ́A�ȉ��ɏq�ׂ�悤�ȁu�ƍ߁v�ݏo���Ă���B
�@�A�L����̍��\�F�@�V���L���̒l�i�́A�`�a�b�����ɂ���Č��߂��Ă���B���������āA���̐�����1���̐�����������A�L�����1���]���ɕ��킳��Ă��邱�ƂƂȂ�B����́A�V���Ђ��L��������܂��Ă��鎖���Ӗ����A���h�ȍ��\�s�ׂł���B�B
�@�B�܂荞�݃`���V�⎩���̂̂��m�点�܂荞�ݓ��̎萔���ɂ�����鍼�\�F�@�V���ƈꏏ�ɔz�B�����܂荞�݃`���V�⎩���̂���̂��m�点�܂荞�ݓ��̎萔���́A�`BC�����ɂ���Č��߂��Ă���̂ŁA������A�L����Ɠ������A�˗�������܂��Ă���킯�ł��邩��A���h�ȍ��\�ł���B
�@�C�n�����ɗ^����e���F�@���́A���ꂪ�ł��[���ł���B�Q�l�����T�i�u�V���Ёv�A�͓��@�F�A�V���V���j�ɂ��ƁA�V���ƊE�S�̂Ŏg�p���鎆�̗ʂ͔N�Ԃ�370���g������炵���B����1�����p�������Ƃ�����A�N��37���g�����p������Ă��鎖�ƂȂ�B��������z�Ɋ��Z�����486���~�A�p���v�ނ̂��߂̖؍ނɊ��Z����Ǝ���220���{�A�ɂȂ邻���ł���B
�@�D���̑��ɁA�܂荞�݃`���V��10���͖��ʂɂȂ�킯�ł��邩��A������n���ɂ͂ł��Ȃ��B��f�B�A����2006�N�łɂ��ƁA�܂荞�ݍL����͔N�Ԗ�4,800���~�A�܂荞�݃`���V�̖����́A��s���ŐV��1��������N��7,642���B������1�����p�������ƍl����ƁA�����̖��ʂ���ł͂Ȃ��A�����ɁA�n�����������߂Ă��邩�A�ǂꂾ������Ă��d���������ł��낤�B
�@�E�����ŁA�����w�E�������́A�V���͂��납�A�e���r���܂��������グ�Ȃ��B���̋ƊE�������悤��1���̖��ʂŒn�����������߂Ă���ΓO��I�ɔᔻ����ł��낤�V���E�e���r�Ƃ������}�X���f�B�A���A�u�m��ʊ�̔����q�v�����ߍ���ł���̂́A�u�U�P�ҁv�ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ��B
�S�|�Q�D�V���ЂƉ��������F
�@�@�u�������v���́A�قƂ�ǎ����ł���ɂ��ւ�炸�A�V���Ђ���Ȃɂ��̑��݂�F�߂Ȃ��̂ɂ́A�Ɛ�֎~�@�ɂ��u�V������w��v�̑��݂�����B����́A�ǂ��m��ꂽ�u�Ĕ̐��x�v������ɋ��������K��ŁA�ȉ���3�_���֎~����Ă���B
�@�@�@�j�V���Ђ́A������n��ɂ���āA�������i�ɍ������Ă͂Ȃ�Ȃ��i�������A�w�Z���狳�ޗp���ʈꊇ�w�ǎҌ����Ȃǂ̏ꍇ�͗�O�Ƃ���j�B
�@�@�A�j�V���̔��X�́A�V���̏����艿�i�ɍ������Ă͂Ȃ�Ȃ��i���̋K��ɂ��ẮA��O�͈�Ȃ��j�B
�@�@�B�j�V���Ђ͔̔��X�ɉ����������Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@�A�܂�A�V���Ђ��V���̔��X���l���������Ŕ����L�����͋֎~����Ă���̂����A����Ɠ����ɁA���������֎~���ꂢ��̂��B
�@�B���́u�V������w��v�́A�ߋ��ɉ�����p�~�̑ΏۂƂȂ������A���̓s�x�A�V������͑S�͂������Ĕp�~��j�~���Ă����B������A��������F�߂Ă��܂�����A�p�~�Ɋi�D�̌�����^���Ă��܂��B�����āA����w�肪�p�~���ꂽ��A�u���i�����v���n�܂�A�V���ƊE������Ȑ퍑����ɓ˓�����B
�@�C���̋ƊE�ɂ́A�K���ɘa�Ŏ��R���������߂邭���ɁA�������������͋K���ł����������Ă������B�V���ƊE�Ƃ͑S����������ȋƊE�Ȃ̂ł���B
�@���F�@�V������w��ɂ��ẮA�E���N���b�N�F�@�V������w��
�S�|�R�D�V���g���c�F
�@���Ɏ��グ����́A�V���̍w�ǎ҂��l�����邽�߂ɁA����i�H�j���Ă���u�V���g���c�v�ł���B
�@�@�V���̔��X�́A��舵��������������Α�����قǁA���v��������r�W�l�X�E���f���ɂȂ��Ă���B�����āA�̔������𑝂₷���߂ɁA�u�V���g���c�v������B�u�V���g���c�v�̒��ɂ́A�u�A�J�������A���N�U�������āA�o�J���ǂށv�Ɲ���������������܂��قǁA���N�U�܂����́u�V���g���c�v�������肵�āA�傫�ȎЉ���ƂȂ�ꍇ������B
�@�A�u�V���g���c�v�̐l�����u�g�ށi�V����z�_��ƌ����ōw�ǎ҂ɒ����T�[�r�X�i�j�v�̍w����p�́A��{�I�ɐV���̔��X�̕��S�ł���B���ꂾ���̔�p�������Ăł������𑝂₻���Ƃ���w�i�ɂ́A�u�����w�v�i�w�ǂ���V����ς���l�j�̑��݂�����B
�@�B1995�N�Ɍ�������ψ���s���������ɂ��A�u1�N�ȏ㓯���V��������Ă���v�l��89.2���������ł��邪�A�t�ɂ݂�ƁA�c���1�����́A1�N�ȓ��Ɏ��V����ς��Ă���̂ł���B����1�����̕����w����荞�ނ��߂Ɂu�V���g���c�v������킯�ł���B
�}�S�|�P�@�V���̔��X�̎����\��
�S�|�S�D�V���̔��X�̎����\���F
�@�V���̔��X���A�l�X�Ȗ�肪����ɂ�������炸�A�u�������v��u�V���g���c�v������Ă���̂́A�������鎖�ɂ���āA���̓I�Ɍ��āA���ʂƂ��ĐV���̔��X�������A�Ƃ��������\���ɂȂ��Ă��邩��ł���B�V���̔��X�̎����\���ɂ��ĉE�̐}�S�|�P�Ɏ����B���̐}�́A2006�N�ŏ�f�B�A��������ɂ����Q�l�����T�̐}������p�������̂ł���B
�@�@�V���̔��X�͑S���Ŗ�2��1,000�X�A���̑�������1��2,800���~�ł���B�V���w�ǎ҂�����V����1��7,700���~�͂��̂܂ܐV���Ђ֔[�߂�̂Ŏ茳�ɂ͎c��Ȃ��B
�@�A�V���z�B�̎萔���Ƃ��āA�V���Ђ���6,500���~�i�V���̔��X��������50.8���A�V���㍇�v��36.8���j���V���̔��X�Ɏx������B�܂�A�V����̖�4�����V���̔��X�̎����ƂȂ�̂ł��邪�A����́A�V���̔��X�̑������̔����ɂ����Ȃ��B
�@�B�V���̔��X�ɂƂ��āA�z�B�萔���Ɏ����傫�Ȏ��������܍��݃`���V�̔z�B�萔���ł���B����́A���z�ɂ���4,800���~�ł���A��������37.5�����߂�B���̎萔���́A��舵�������ɂ���Č��܂��Ă��邪�A���̎�舵�������́A�\�S�ɋL�ڂ����`�a�b�����Ɋ�Â��Ă���B���̂`�a�b�����́A���������܂����ł���B�����ŁA���������Ȃ��Ȃ�ƁA���̎���������̂ŁA�V���̔��X�́A�����������܂葛�����ĂȂ��̂ł���B
�@���F�@����������������̂́A�قƂ�ǂ��|�Y�܂��͔p�Ƃ����V���̔��X�ł���A�c�ƒ��̐V���̔��X�́A���ق�����Ă���B
�@�C�V���̔��X�������̎c��1,500���~�i�䗦�ɂ���11.7���j�́A�V���Ђ���x�������u�̔����i��v�ł���B����́A�u�V���g���c�v�Ɩ��ڂɊ֘A���Ă���B���̂��߁A�V���̔��X�́u�V���g���c�v�𗘗p����킯�ł���B
�@�D�܂�A�V���̔��X���������グ�悤�Ƃ���ƁA�������ɖڂ��ނ�Ȃ���A�u�V���g���c�v���g���čw�ǎ҂𑝂₵�A�`�a�b�����𑝂₹�悢�A�Ƃ������ɂȂ�B�Ƃ��낪�A���̂��߂ɂ́A�������ɔ����p�����X�ƁA�V���g���c�̐l�����g�̍ނ̍w����ȂǂS���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ł́A�ŏI�I�Ȏ��x���Z�͂ǂ��Ȃ�̂ł��낤���H�B���̂�����������ŕ��͂��悤�B
�S�|�T�D�������ƐV���g���c������u���炭��v�F
�@���X�Â��f�[�^�ł��邪�A1995�N�A��������ψ���́A�Ĕ̐��x�ƐV������w������������߂ɁA��X�I�Ȓ������s�����B���̃f�[�^��p���āA�Q�l�����T�ŁA�������ƐV���g���c������J���N���͂��Ă���̂ŁA�����ŁA���̊T�v���Љ�悤�B
�\�T�@�̔����i��z���̈��
���� ���������ɑ��銄�� ����
�i�{�Ђ֔[�߂�j �����ʏ����
�i�{�Ђ���x�������j
��� 70�`80�� �艿�w��60��
�i�e����2,300�~
�^1��������j ����
��� 10�`30�� 10�`20�~�^1��������
��O� 0�`10�� ���\�~�^1��������
��l� �����̂� �����Ƃقړ��z
�@�@�V���̔��X���A�V���Ђɕ��������̕��ϒl�́A���[���Z�b�g�ł�1��1������2,300�~�B����A�܂荞�݃`���V�̎萔���́A�V��1���ɂ�1�����ŕ��ϐ�~�O��B���������āA���̂܂܂ł���A������1������邽�тɁA1,300�~�O��̑������鎖�ɂȂ�B�����ɁA�o�ꂷ��̂��̔����i��Ƃ������ڂ̐V���Ђ���̕⏕���ł���B
�@�A�V���̔��X��������11.7�����߂�̔����i��ǂ̂悤�ɔz�������̂��A���̗���E�̕\�T�ɏ]���ĉ������B�z�����@�͋ɂ߂ĕ��G�ŊȒP�ɂ͐����ł��Ȃ������ł��邪�A������ȕ։����ĕ\�T�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��i�Q�l�����T��肻�̂܂܈��p�j�B
�@�B�V���̔��X�̈��������́A�w�ǎҐ��̑����ɂ�����炸�A�ߋ��̎��ѓ�����A������x�Œ艻����Ă��邻���ł���B���̕����̂V�`�W���́A�Œ�q�����Ƃ��čl�����Ă���A�u����v�ƕ��ނ����B���̕����ɑ��ẮA�z�B�萔���͖�S���ŁA�⏕���͈�Ȃ��B
�@�C�V���̔��X�̒n��ł̋����ɉ����āA�u����v�Ƃ��āA�戵��������10�`30�������蓖�Ă���B���̕����ɑ��ẮA��S���̔z�B�萔���̂ق��ɁA�P��������10�`20�~�̔̔����i��x�������B
�@�D�������������n��ł́A�u��O��v���݂����A�戵��������10���ȉ������蓖�Ă���B�⏕���́A1�������萔�\�~�������ł���B
�}�S�|�Q�@�⏕���̃J���N��
�@�E����Ɍ����Ő키�V���̔��X�ɂ������ẮA�u��l��v�Ƃ��āA�����Ƃقړ��z�̕⏕�����x�������i�܂�A�����ŐV�����d����鎖���o����j�����ł���B
�@�F�����̑��ɂ����L����悤�ȑ���ނ̕⏕��������Ƃ̂��ƁB
�@�@�@�j�g���⏕�F�@���̊g��������ꂽ���̔�p�̈ꕔ��V���Ђ����S�B
�@�@�A�j�o�c�⏕�F�@�̔��X�̌o�c�i�����̔̔��X�̏W���U���ŋꋫ�ɗ������Ƃ��A�V�K�J�X�Ŏx�����K�v���X�j�ɉ����Ďx������Վ��⏕���B
�@�@�B�j���[������F�@��������100���[������������i���̂悤�ȏ�����̑��݂��A�t�ɁA�V���̔��X�̋ꂵ���������Ă���j�B
�@�@�C�j���̑��A�V�����w���ւ̊w��⏕�A�X��E�]�ƈ��̑ސE���ςݗ��ĕ⏕�A���X�A���푽�l�ɂ킽���Ă���B
�@�G���������⏕����p���āA�������ł��Ȃ�ł���舵�������𑝂₹�Α��₷�قǁA�V���̔��X�̎�����������d�g�݂����o���Ă���̂ł���B�܂�A�E�̐}�S�|�Q�Ɏ����T�C�N���ŐV���̔��X�̎����͑����Ă����̂ł���B
�@�H���́A���̐�ł���B�������āA�w�͂������ʁA���ۂ̍w�ǎҐ��������Ă䂯�A�\����������A�̔��X�ł́u�������v�p�����X������̂ŁA���v�������Ă䂭�A�Ƃ����D�z�ɂȂ��Ă䂭�B���̍D�z���������͍̂��x��������o�u������O��܂łł���A���̍��́A�V���ЂɂƂ��Ă��A�̔��X�ɂƂ��Ă��u�Â��ǂ�����v�������̂ł���B
�@�I�Ƃ��낪�A���ۂ̍w�ǎҐ��������Ȃ��A���邢�́A�t�Ɍ����Ă��܂����A�Ƃ����ꍇ�ɂ́A�������\�����́A�̔��X�ł́u�������v�p�����X�𑝂₷���ƂȂ�A���ǂ́A�̔��X��Ԏ��ɓ]�������Ă��܂��������肤��B���ꂪ�A�o�u�����猻�݂Ɏ���ł���A���ʂƂ��āA�}�R�|�Q�Ɏ����悤�ɁA�̔��X�̐����N�X�������Ă���̂ł���B
�T�D�Ō�ɁF
�@����͐V���ЂƐV���̔��X�̏͂����B���̏�m��Βm��قǁA�V���ƊE�̏����͈Â��ƌ��킴������Ȃ��B
�@�@�O��i�u120�D���S�̋@���}�����V���i�P�j�v�j���w�E�������L�́u�Ɛ��ԁv��������̂ɂ���ɑ���K�ȑ���ł���Ă��Ȃ��̂ł���B
�@�@�@�j�L�҃N���u�ɂ����\�[�X�̓Ɛ�B
�@�@�A�j��z�V�X�e���ɂ�闬�ʃ`���l���̓Ɛ�B
�@�@�B�j�Ĕ̔����i�ێ����x�ƓƐ�֎~�@�̐V������w��ɂ�鉿�i�����̐����B
�@�A��������肪�n�������ɂ܂Ŕ��W���悤�Ƃ��Ă���̂ɁA���܂��ɁA�u�m��ʑ����ʁv�Ŕ����Ƃ����Ă���B
�@�B���������ԓx�́A�ǎ҂̔������A�C���^�[�l�b�g�̕��y�Ƃ����ւ��āA�v�X�A�ǎҗ����U���A�V�����s�����̌����������炷�B
�@����́A�C���^�[�l�b�g�ƐV���̊W�𒆐S�ɐV���ƊE�̊�@�͂��Ă䂫�����B
�Q�l�����F�@�P�D�u�}�X�S�~����v�A�O���@�M���A�}�K��
�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�D�u�}���@���{�̃}�X���f�B�A�v�i���Łj�A���|�@�ŁA�m�g�j�@�a����ks
�@�@�@�@�@�@�@�@�R�D�u�����V�����Ȃ��Ȃ���v�A�{��@���O�A�v�`�b
�@�@�@�@�@�@�@�@�S�D�u2011�N�@�V���E�e���r���Łv�A���X�@�r���A���t�V��
�@�@�@�@�@�@�@�@�T�D�u�V���Ёv�A�͓��@�F�A�V���V��
�@�@�@�@�@�@�@�@�U�D�u�V���͐����c��邩�v�A���n�@�����A��g�V��
�@�@�@�@�@�@�@�@�V�D���{�V��������f�[�^
�@�@�@�@�@�@�@�@�W�D�d�ʁF�u���{�̍L����v
�@�@�@�@�@�@�@�@�X�D�ǔ��V���L���K�C�h
���̃R�����ɑ��銴�z�A���ӌ����͉E�փ��[�����������F�@���[��
�R�����쐬�҂̃v���t�B�[�����͉E���N���b�N���Ă��������F�@��ҁ@�R��@�h�@�̃v���t�B�[��
�}�X�R�~�Ɋ֘A����R�����͈ȉ��̒ʂ�
120�D���S�̋@���}�����V���i�P�j 121�D���S�̋@���}�����V���i2�j�F�V���ЂƐV���̔��X
122�D�ꋫ�ɗ��e���r�ƊE�i1�j�F�e���r�ǂ̌o�c�� 123�D�ꋫ�ɗ��e���r�ƊE�i2�j�F�����ƊE�ƃe���r�ƊE
124�DNHK�i1)�FNHK�̌��� 125�DNHK�i2)�F�@���x�Ɛ��{�̉��
126�D�ꋫ�ɗ��e���r�i3�j�F�����җ���? 127�D�ꋫ�ɗ��e���r�i4�j�F�����җ���? (2)
128�D�e���r�ƃX�|�[�c�i1�j�F�T�b�J�[
�@�@�@�Ƃ茾�̖ڎ��ɖ߂�
�@�@�@�S�̖̂ڎ��ɖ߂�
1 �@
���̋L����ǂl�͂���ȋL�����ǂ�ł��܂��i�\���܂�20�b���x���Ԃ�������܂��B�j
- 122�D�ꋫ�ɗ��e���r�ƊE�i1�j�F�e���r�ǂ̌o�c�@�@(2010�N1��15���L��) taked4700 2012/2/01 14:41:45
(3)
- 123�D�ꋫ�ɗ��e���r�ƊE�i2�j�F�����ƊE�ƃe���r�ƊE�@�@(2010�N2��13���L��) taked4700 2012/2/01 14:48:57
(2)
- 126�D�ꋫ�ɗ��e���r�i3�j�F�����җ���?�@�@(2010�N4��24���L��) taked4700 2012/2/01 14:56:43
(1)
- 127�D�ꋫ�ɗ��e���r�i4�j�F�����җ���? (2)�@�@(2010�N6��3���L��) taked4700 2012/2/01 14:59:27
(0)
- 127�D�ꋫ�ɗ��e���r�i4�j�F�����җ���? (2)�@�@(2010�N6��3���L��) taked4700 2012/2/01 14:59:27
(0)
- 126�D�ꋫ�ɗ��e���r�i3�j�F�����җ���?�@�@(2010�N4��24���L��) taked4700 2012/2/01 14:56:43
(1)
- 123�D�ꋫ�ɗ��e���r�ƊE�i2�j�F�����ƊE�ƃe���r�ƊE�@�@(2010�N2��13���L��) taked4700 2012/2/01 14:48:57
(2)
�@
�����̃y�[�W�̂s�n�o���@�@�@�@�@ �����C���� > �}�X�R�~�E�d�ʔ�]12�f����
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B���ׂẴy�[�W�����p�A�]�ځA�����N���������܂��B�m�F���[���͕s�v�ł��B���p�������N��\�����Ă��������B