03. 2011�N5��11�� 07:33:31: cqRnZH2CUM
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/7143
�u��l���q����v�͏I���Ȃ��A���{��Ƃ��̂�ׂ���Ƃ́H
2011.05.11�iWed�j �@�h ��
�����@�������{�͐V���Ȑl���Z���T�X�̒������ʂ\�����B����ɂ��ƁA�����̑��l����13��3900���l�ƌ����A�ˑR�Ƃ��đ����X���ɂ���B�����A�l���������͂��łɒቺ���Ă���A2015�N���ɂȂ�ƁA�}�C�i�X�ɂȂ�ƌ����Ă���B �@�U��Ԃ�A�������{���l���̗}���ɏ��o�����̂͂����悻35�N�O���炾�����B����܂ŁA�ё͉p�Ăɒǂ����A�ǂ��z�����߂ɁA�l���𑝂₷�ׂ��o�Y������Ăт������B1950�N���60�N��̓x�r�[�u�[�����������B�������A�����A���N���͑�����w�i�Ƃ���u���������v���J��L�����A��Ƃ̐��Y�����͒�؏�Ԃɂ������B�����o�ς͉p�Ăɒǂ����ǂ��납�A�j�]���O�ɂ܂Ŋׂ����B �@���Y�����̒�Ɛl���̔����������炷��Ԃ̕��Q�͐H�ƕs���̖������������B70�N��ɓ���A�}�X�R�~�ł͎Љ��`�̗D�ʐ��ɂ��Ė����̂悤�ɐ�`����Ă������A�����̐������x���݂͂�݂�ቺ���A�H�ƂȂǐ��������̔z�����̎��{��]�V�Ȃ����ꂽ�B�����͍̏��̖k���N�Ƃ�������ł���B �@78�N�ɕ��������������͌o�ω��v�ɒ��肷��O�ɁA�܂��l���}���ɏ��o�����B���������͕ʂƂ��āA�����̑命�����߂銿�����ɂ��āu��l���q����v�������̂ł���B
�v�����������x�o�ϐ����Ɋ�^������l���q���� �@��������l���q��������Ȃ���A���̒����̑��l����26���l���Ă���Ɨ\�z�����B��l���q����ɂ����10���l�ȏ�̐l�������}�����ꂽ�v�Z�ɂȂ�B �@�l�������̗}����ړI�Ƃ����l���q����́A�m���ɐl�������̗}���Ɋ�^�����B�����ɁA�v�������l���}������́A30�N�O�ɓ������ꂽ�u���v�J���v����̉��ł̌o�ϐ����ɑ傫���v�������B �@��l���q���������O�̒����Љ�ł́A���L��Ƃ��Љ�ۏ�@�\��S���Ă���A���Ȃǂ͉Ƒ��ɂ���čs���Ă����B1�Ƒ��̎q���̕��ϐl����4�`5�l�ɏ�邽�߁A���҂��ł����Ă��A�v�w�̋��^�����ł͐������������A�����K���i�ȊO�̔������◷�s�Ȃǂ̏���͂قƂ�ǂł��Ȃ������B �@��l���q���������ꂽ���Ƃ́A���҂��̕v�w���}�{����q���̐l����1�l�ƂȂ�A�������S���傫���y�����ꂽ�B���̌��ʁA80�N�㏉�����瓭������̕v�w�ɂ͐������y���ޗ]�T���ł��āA����U���ɂ��傫����^�����B �@���݁A�����̓s�s���ƒ�́u4�{2�{1�v�Ƃ����Ƒ��\���ɂȂ��Ă���B4�͕����ƕ���̑c����ł���B�܂�A��l���q��6�l�̑�l�Ɉ͂܂�Ĉ���Ă���B���̂��߁A�����ł͎q���p�i�̔���s�����D���ł���B
�����_�Łu�J���͂��s�����Ă���v�ƌ���ّ̂͐� �@��l���q����́A���R�̌��ʂƂ��āA������J���͂̋��������������邱�ƂɂȂ�B�����܂ł����A�����o�ς͑傫���������鋰�ꂪ����B����͍��̓��{�o�ςɂ悭�������ۂƂȂ�B �@�������Ƃ��āA�����ł͂��łɘJ���͕s���̌��ۂ�������B�L���ȂȂǂ̉��C���ł́A�ߋ��@�B���i�ȂǘJ���W��^�����Ƃ̉�Ђ��J���҂��W���Ă��A�ȑO�قǏW�܂�Ȃ��Ȃ����B�����ɁA�J���҂̒����͑傫���㏸����悤�ɂȂ����B �@�����������ۂ��āA�o�ϊw�҂�o�ϕ]�_�Ƃ̊ԂŁA�����ł͘J���͂��s�����A�u���C�X�̓]���_�v�i�_�Ƃ̗]��J���͂���������Ɓj���߂��Ă���A���̐�A�o�ϐ������͏��X�ɒቺ����Ƃ̎w�E������B �@�Ƃ͂����A���l���̐L�т͂����ꓪ�ł��ɂȂ邪�A����ł́A�J���͂��s�����Ă���Ƃ������f�͂��ّ��߂���悤�Ɏv����B �@���ۘJ���s����悭����ƁA���v�Ƌ����̃~�X�}�b�`���N���Ă���B �@�����ł͒��N�A�o�҂��J���҂𒆐S�Ƀu���[�J���[�̒������Ⴍ�}�����Ă����B���̑_���͗A�o�U���ɂ������B�������A���N�������C���t�����㏸���Ă��邽�߁A�o�҂��J���҂ɂƂ��ēs�s���ł̐��v������Ȃ��Ă���B �@2008�N�̃��[�}���E�V���b�N�ȍ~�A�_���ɋA������2000���l�̏o�҂��J���҂̈ꕔ�͔_���Ɏ~�܂�A�s�s���ɂ͉�A���Ă��Ȃ��B�o�҂��J���҂̋����s���́u���H�r�v�ƌĂ�A�J���͕s���ƌ�����w�i�ƂȂ��Ă���B �@�������A����͖{���̈Ӗ��ł̘J���͕s���ł͂Ȃ��A�o�҂��J���҂ɂƂ��ĘJ���������܂荇��Ȃ������ł���B �@���C���e�Ȃł́A���{�哱�̂��ƂōŒ���������肳��A���N20���������グ���Ă���B�ߋ��A�p�������H�Ȃǂ̘J���W��^�̊�ƂɂƂ�A�����o�҂��J���҂̑��݂͗���ɂȂ邪�A���ɁA���{���Œ�������グ���Ƃ���ŁA�o�҂��J���҂͊�Ƃɖ߂�Ȃ����낤�B����́A�����ɂ�����Y�ƍ\�������x�����Ă��邱�Ƃ̌��ʂł���B ��l���q����̗l�X�ȕ��Q �@�����ŁA��l���q����̕��Q�ɂ��ĉ��߂Č������Ă݂����B �@30�N�ȏ�������Ă�����l���q����́A�u���q����v�Ƃ������������炵�Ă���B���A�̐l�����v�ł́A������2005�N�ɂ��łɍ���Љ�ɓ˓������ƌ����Ă���B���Ƃ��ƐƎ�ȎЉ�ۏᐧ�x�́A����A�ۏ�\�͂����������s������Ǝv����B �@��l���q�������炷����1�̖��͒j���̃o�����X������Ă��܂����Ƃɂ���B �@�ꕔ�̕v�w�ł́A�j�̎q�݂������܂�A���̎q�̐Ԃ�����l�H���Y���Ă��܂��X��������B���̌��ʁA�j���̃o�����X���傫������Ă���B �@����̐l���Z���T�X�ł��A���̖�肪��������ɂȂ��Ă���B��̓I�ɂ́A�����̒j���̊����́u105�F100�v�ɂȂ��Ă���ƌ����Ă���B�܂��A���A�̒����l�����v�ł́A20�Έȉ��̎�N�w�ł́A�j���͏����ɔ�ׂ�3000���l�����Ƃ����v�Z�ɂȂ��Ă���B �@�����̐l���w�҂ƌo�ϊw�҂̑����͍���̐l�����Ə��q����̐i�W�����O���āA��l���q����̓P�p���Ă��Ă���B�������A���{�ł́A��l���q����̓P�p�ɂ��Đ^���Ɍ�������Ă��Ȃ��悤���B���̌����͂ǂ��ɂ���̂��낤���B �@���́A��l���q������ѓO���邽�߂ɁA�������{�ƒn�����{�̂�����ɂ����Ă��u�v��o�Y�ٌ����v�Ƃ����������ݗ�����Ă���B�����̌v��o�Y�ٌ����ł́A�t���^�C���̐��K�̐E����50���l�ɏ��A�p�[�g�^�C���̔K�E����660���l�ɒB����B �@�_���Ȃǂň�l���q����Ɉᔽ����2�l�ڂ̎q�����o�Y�����Z���ɉȂ����������ŁA���N�A���S���h���ɏ��ƌ����Ă���B�v��o�Y�ٌ����́A�E���̌ٗp�̊m�ۂƁA�����Ƃ����������v����邽�߂ɁA��l���q����̓P�p�ɖҗ�ɔ����Ă���B �@�����ł́A��l���q���l���̗}���ƌo�ϐ����ɑ傫����^�����̂͊m���Ȃ��Ƃ����A���ʁA�s���߂����l���}���̕��Q�����łɖ��炩�ɂȂ��Ă���B�ɂ�������炸�A���f�B�A�ł́A��l���q����̑��p�Ɋւ���c�_����^�u�[�ɂȂ��Ă���B �@����A�ǓƎ��̘V�l�����������Ɨ\�z����A�������肷�猩����Ȃ��j�����吨�o�����邾�낤�B�Ӌџ����Ǝ�Ȃ�����u�a�~�Љ�v�i���a�̎�ꂽ�Љ�j�Â���͂��ɂȂ�Ύ�������̂��낤���B
�l����̏㏸�ɓ��{��Ƃ͂ǂ��Ώ����ׂ��� �@�Ō�ɁA���{��Ƃ����ׂ��Ή��ɂ��Č������Ă݂悤�B��l���q�����ʌp������邱�Ƃ��l����A����A�����ɂ�����J���͂̋����͏��X�ɍׂ��Ȃ�Ɨ\�z�����B �@����ȏ�ɁA��l���q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�J���҂̐E�̑I�ѕ����傫���ω����A���{��ƂɂƂ��āA�����ȘJ���͂��������钆���̖��͂͏��X�Ɍ��ނ��邩������Ȃ��B �@����2009�N�����璆���̓��n��Ƃł́A�J���҂̃X�g���C�L���������Ă���B���̂��Ƃ͒����ɐi�o������{��ƂɂƂ��đz��O�̘b�ł���B���������Љ��`�̒����ł́A�J���҂̃X�g�͍l���ɂ������Ƃ��B �@���̔w�i�ɂ���2�_���w�E���Ă��������B �@1�́A��l���q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�J���҂͐e�̐���ƈ���āA����̌��������ӎ��������Ȃ��Ă��邱�Ƃł���B����1�́A���{��ƂɂƂ��ĘJ���҂̃X�g���z��O�̎��Ԃ��������߁A����ɑΏ�����t�@���N�V�����͎Г��ŗp�ӂ���Ă��炸�A�Ώ��̒x��ɂ���ăX�g������Ɋg�債�Ă��܂����B �@�����ł́A�l����̏㏸�͂��łɎ~�߂��Ȃ��B��l���q����̌p���ɂ���ĘJ���͂̋�������������̂͗\�z����邱�Ƃł���B�����ɁA�o�ϐ����������Ă��邱�Ƃ���A��������������ɔ�Ⴕ�ď㏸����͓̂��R�̂��Ƃł���B �@�����܂���ƁA���{��ƂɂƂ��Đ�����n�A�A�o��n�Ƃ��Ă̒����̖����͏��X�ɒቺ���A���̑���ɁA�l����̏㏸�ɂ���āu�s��v�Ƃ��Ă̖��͂����܂��Ă�����̂Ɨ\�z�����B���������āA���{��Ƃ͒������H��ł͂Ȃ��s��Ƃ��đ�����悤�ɁA�ς���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�K�R�I�ɂ����ŋ��߂���悤�ɂȂ�̂́A�����ō�������i���C�O�ɗA�o����]���̐헪�ł͂Ȃ��A�����ɔ̔�����c�Ɨ͂̋����ł���B�c�O�Ȃ���A����ł͑����̓��{��Ƃ͒����ł̂��̕ω����@�m���Ă��Ȃ��悤���B
�@
�@
�@
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/7316
�����F�ł��ӊO�Ȑl�����Ԃ̊�@
�iWed�j �i�p�G�R�m�~�X�g���@2011�N5��7�����j �ŐV�̍��������̌��ʂ́A�����̈�l���q����̏����ɋ^����N���Ă���B �l������������Ĉ�l���q���������Ă����������A�v���Ă��݂Ȃ������l�����Ԃ̊�@�Ɍ������Ă���i�ʐ^�͒����암�E�L���ȂɌf�����ꂽ��l���q����̍L��Ŕj�kAFPBB News�l
�����̐l���͑���Ă���̂��낤���H�@����͔n����������Ɏv���邩������Ȃ��B�����뒆���͒��N�A���E�ő�̐l��������A�l��������}�����邽�߂Ɍ��i�ȑ[�u����������ƂŗL���������B
�@�����l�A�O���l���킸�����̐l�́A�����߂ŋ����I�ȓx���z������l���q����ɜ��R�Ƃ��Ă������A����Ȑl����}�����邽�߂ɒ������������łK�v�����邱�Ƃ��a�X�F�߂邱�Ƃ����������B
�@�������A�ŐV�̐l�����v�̐����́A�������Ⴄ��ނ̐l�����Ɋׂ��Ă���Ƃ����A�������N�����Ă����咣�𐨂��Â����邱�ƂɂȂ����B���Ȃ킿�A�o�������Ⴗ����Ƃ�����肾�B
�l�����������}�ቺ���A�Љ��C�ɏ��q���
�@��N���{���ꂽ�S�����������Ɋ�Â��Ă܂Ƃ߂��A4��28���ɔ��\���ꂽ�ŐV�̐����ł́A�����{�y�̐l���͍��v13��4000���l�������B�܂��A���̒����ł́A2000�`10�N�̔N�Ԑl���������̕��ϒl��0.57���ƂȂ�A���̑O��10�N�Ԃ̐��l�i1.07���j�̔����ƁA�������ቺ�������Ƃ����炩�ɂȂ����B
�@���̃f�[�^�͍��v����o�����i�o�Y�K����̏������ꐶ�̊Ԃɐ��ގq���̕��ϐ��j�����݁A�킸��1.4�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ������Ă���B�ŏI�I�ɐl�������肷��u�l���u�������v��2.1�����Ȃ艺��鐔���ł���B �@�l���������̓݉��Ƒ����𑵂݂��A�l���̌��I�ȍ�����i��ł���B60�Έȏ�̐l���͌��݁A�S�̂�13.3�����߂Ă���A2000�N��10.3������㏸�����i�}�Q�Ɓj�B
�@����������14�Ζ����̐l����23������17���ɒቺ�����B
�@���̌X���������ƁA����̐g�����x���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�J��N�w��A���{���Ǐ�����N���E��Õی����x�ɂ܂��܂��傫�ȕ��S��������B�����̑傫�ȁu�l���̔z���v�i���Y�N��̐��l�̊����̏㏸�j�͂قڏI������̂��B �@��l���q����� �����̔N��z��c�߂������ɁA�j����̒������s�ύt�������������ƍl������B�����ł́A�����������|�I�ɑ����̒j�������܂�Ă���B���̓_�́A���� �Ɍ������b�ł͂Ȃ��B�ق��̍��X�A���ɃC���h�́A�����I�Ȑl���}���������Ă��Ȃ��ɂ�������炸�A���l�̖��Ɍ������Ă���B
�@�����������̓��ǎ҂����́A��l���q�����������s�ύt�Ɉ��̖������ʂ��������Ƃɂ͔��_���Ă��Ȃ��B�Ƃ����̂��A�j�n�q�����c���˂Ȃ�Ȃ��Ƃ��������̕����̂��߂ɁA�����̉ƒ�͈�l�����F�߂���q���𑧎q�ɂ��邽�߂Ȃ��i��I�Ȃ��悤�ɂȂ����B
�@��l���q���������ꂽ�����́A����͎��ɏ����E�Q���Ӗ������B�����g�����Z�p�����y����ƁA���ʑI���ɂ��ق��L���s����悤�ɂȂ����B
��l���q���������M���c�_ ���̎q��������l�ɂȂ鍠�ɂ́E�E�E�i�ʐ^�͖k���̌����ɏW�܂����q�A��̂��ꂳ���j�kAFPBB News�l
�@����̐l�����v�ł́A���̖��ȕ����ɑR���铮���ɐi�W�����܂茩���Ȃ������B2010�N���_�ŁA100�l�̏��̐V�����ɑ��A�j�̐V������118�l�ȏア���B
�@�����2000�N�̐������킸���ɏ��鐔���ŁA�����炨�悻20�`25�N��ɂ́A���݂̒j�̐Ԃ����̖�2���Ɍ������肪���Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���B���̂��Ƃ́A���ݓI�ɋɂ߂đ傫�ȕs����v���������炷��������Ȃ��B
�@����̍��������̌��ʂ͒����ŁA�l���}����i�߂鋭�͂Ȋ����@�\�ƁA����ɐ����Ɉ�l���q����̊ɘa�����߂�悤�ɂȂ����l�����v�w�҂̃O���[�v�Ƃ̋c�_�ɔ��Ԃ������邾�낤�B���҂̘_���́A��l���q����̏��������łȂ��A�i�����ł͂悭����悤�Ɂj���̉ߋ��ɂ��y�ԁB
�@�w�҂�1�l�ł���u���b�L���O�X�E���،�������Z���^�[�����̉��L���́A1980�N�Ɉ�l���q���n�܂������ɂ́A���ɒ����̐l�����Ԃ̃p�^�[�����}���ɕω����Ă����Ǝ咣����B1950�N�ɂ͍��v����o������5.8�������Ɠ����͎w�E�B���ꂪ�}�ቺ����1980�N�ɂ�2.3�ƂȂ�A�l���u���������킸���ɏ�����x�ɂȂ����Ƃ����B
�@�ق��̍��X�ł��������Ԃɓ����x�̏o�����̒ቺ������ꂽ�B�]���͗c�����S���������������߁A�l�X�͏��Ȃ��Ƃ����l���������т�悤�Ɏq����������������Ă������A�ی���Ẩ��P��c�����S���̋}�ቺ���͂��߂Ƃ���i���̉��b������I�ȉe����^�����Ɖ����͍l���Ă���B
�@���ꂪ�ÂɎ������Ă��邱�Ƃ́A�����I�Ȑl���}���́A������ɂ���N�����Ă����o�����̒ቺ�Ƃ͂قƂ�NJW���Ȃ��Ƃ������Ƃ��B
�@�Ⴆ�^�C��C���h�l�V�A�ȂǁA�����P�ɔ�D��𗘗p���₷�����������̍��ł��A���i�Ȑ��������������Ɠ������炢�o���������������B�������{�������̓y�̈ꕔ���ƌ��Ȃ��Ă����p�́A�l����}�����邱�ƂȂ������Ɠ������炢�o�������ቺ�����B
���{����l���q�����i�삷�闝�R
��l���q����ɂ��4���l�̏o��������ł����i�ʐ^�͍��N2���A�����̌Ζk�ȕ����w�ŁA�t�߂̋x�ɂ��I���ċA�Ȑ悩��߂�l�X�j�kAFPBB News�l
�@�������{�́A��l���q����ɈӖ����Ȃ������Ƃ������Ƃ�ے肵�A���̐���̂�������4���l�̏o����������ꂽ�Ǝ咣�B��l���q���Ȃ���ΐ��܂�Ă����l�X�𒆍��͗{���Ȃ������Ƃ����B
�@�������Ɠ��v�ǂ̔n�����ǒ��́A�u�����̐l���}���̐����͉Ƒ��v�搭��̂������Ō��ʓI�ɗ}�����ꂽ�v�Ƙb���Ă���B
�@�������{����l���q�������Ƃ��Ă����̂ɂ́A�l�X�ȗ��R������B1�́A�����͓Ɠ��ȍ��ŁA�����̌o���͈Ӗ����Ȃ��Ȃ��Ƃ����A����Ȃ�ɗ����ł��錩�����B
�@2�Ԗڂ́A��l���q����͓����o�����̒ቺ�ɂ��܂���ʂ��Ȃ�������������Ȃ����A���͏o������Ⴍ�ۂ��Ă��邩������Ȃ��A�Ƃ������̂��B3�Ԗڂ́A�����l���}���P���A�l���͍Ăё������邩������Ȃ��Ƃ��������ł���B
�@���̂Ƃ���A���̂悤�Ȍ��O�ɂ́A�قƂ�ǐ������͂Ȃ��B�Ƃ����̂��A���ۂɂ͈�l���q����͒n��ɂ���đ傫���قȂ�A�����̏��������ɂ͂قƂ�ǓK�p����Ă��炸�A�_���n��ł͏_��ɓK�p����Ă���B�����āA���������n��ł͐l�������͌����Ȃ������̂��B
�@�u�����_�C�X��w�w���[�Z�i�Љ��E�o�c��w�@�j�̃W���[���E�J�E�t�}�����́A���{����l���q������x�����闝�R�́A�F������Ă��闘�_�Ƃ͈ꕔ�����W���Ȃ��Ƙ_���Ă���B����́A�����̉Ƒ��v��𐄐i���銯���@�\�̒�R�̎Y���ł�����̂��B
�@�����̉Ƒ��v�擖�ǂ͋���ȗ͂��������g�D���i�����āA�n�����{�ɂ͈ᔽ�҂���W�߂锱���Ƃ����������v������j�B�u��l���q����͖�l�̑��݈Ӌ`���v�ƃJ�E�t�}�����͌��B
�u��l���q����v�ɓ]����
�@�����Ƃ��̓����́A��l���q�������߂�ׂ����Ǝ咣���Ă���B�o�����ቺ�̖ڕW�́A�Ƃ��̐̂ɒB�����Ă���B���݂̏o�����͐l���u�������ȉ��ŁA�����s�\���B
�@�傫�ȑ����ݏo���A��l���q����ɓ]�����鎞�������B�����̃O���[�v�����{���������́A�����ł͎q����3�l�ȏ㎝���Ƃ�]�މƑ��͂������Ȃ����Ƃ��������Ă���B
�@�l���Ɋւ���c�_�̐����F����߁A���؋��Ɋ�Â��c�_�ɂ��悤�Ƃ���w�҂����̎��g�݂����������߂���Ƃ�������������B���Ɠ��v�ǂ̔n���́A�Ƒ��v�搭��ɌŎ����邾���łȂ��A�u���o�����X�̎�ꂽ�����̐l�������𑣂����߂ɁA�T�d���i�K�I�ɐ�������P����v���Ƃɂ��Č���Ă���B
�@�Ӌџ����Ǝ�Ȃ͍ŐV�̍��������ɑ���R�����g�ŁA�߁X���v�����蓾��Ƃ������R�Ƃ����q���g���ق̂߂������B�����͒Ⴂ�o�������ێ�����ƌ� ��Ȃ͌�����B�������A���s�̉Ƒ��v�搭����u�т��A���P������v�Ƃ�������B����́A�N�ł����R�Ɏq���ނ��Ƃ�e�F���������ɂ͓���v���Ȃ��B���� ���A�u�N�ł�2�l�܂Łv�Ȃ�A���O�ł��Ȃ����낤�B
|
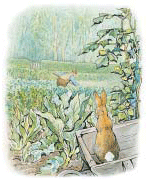
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B