http://www.asyura2.com/11/genpatu19/msg/828.html
| Tweet | �@ |
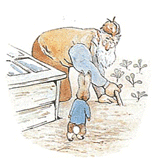
�������L�ƌo�ϓW�]
http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu255.html
http://blog.goo.ne.jp/2005tora/
--------------------------------------------------------------------------------
�n�k���̂̃��X�N�͉��艺�ɐ����u����Ă����B�Ƃ��낪���ꎖ��
�ɂ����߂ăV�X�e���Ƃ��Ă̎�_����������ɂ���A�����������B
2012�N1��5�� �ؗj��
���E�����h�ɓ˂������鋆�ɂ̑I���@�P���S���@�R�c����
http://agora-web.jp/archives/1419807.html
�����A�傫���͌����^���E���Ƃ����_�_���肪�N���[�Y�A�b�v����A�S��������₳��Ă���B�����A���߂����ꂪ���Ȃ̂��A�E�����h�̓��ւ̘_�_���B�傫��������}�i�h���Q�i�h�i�������i�ށj�Ƃ������ƂɂȂ낤���A��҂ł�10�N����20�N�̎�����ݒ肵�����h�ƁA�V�K���݂��֎~���Ď�����������珇���p�~���Ă����悢�Ƃ���h�ł́A��͂�傫���قȂ闧�ꂾ�낤�B��܂��ɂ����A�ȉ��̎O���ɂȂ肻�����B
�`�āu�����S�p�v
�a�āu10�N����20�N�����đS�p�v
�b�āu���R���ɂ��S�p�v
�E�����������I�ɂ͋}���Ɍ�������ттĂ������A�h���ł̋c�_���}���ׂ��ł͂Ȃ����낤���B�Ƃ����̂��A�ꌩ����Ɖ��Ă��Ƃ̂Ȃ��O�������A���͕\�ʂ���ł͌����Ă��Ȃ��A���ɂƂ�������Η��_���܂�ł��邩�炾�B�Ƃ��ɁA�͔C���Ƃ�������`�ĂƁA�t�F�[�h�A�E�g�i��������j�Ƃ�������b�Ăł́A�����E�����h�Ƃ����Ă��V�ƒn�قǂ̊J��������B�܂��A�`�Ă��Ƒz���ȏ�Ɍo�ϓI�ȑ��Q���傫���Ǝw�E���˂Ȃ�܂��B
�P�E�d�͕���ɖ�Q�R���~�̋���s�Ǎ���������B
�����͓d�C�Y���A���������҂ɔ��邱�Ƃɂ���āA���g�̃��C�t�T�C�N���i���݂���ێ���A��̏����A�����x�����ː��p�����ۊǃR�X�g�܂Łj�ɗv����o���P�o���Ă���B�悭�����������A���ݔ�����p����ςޘb�ł͂Ȃ��A�l�Ԃł����Ε��̈ێ���܂ʼn҂��˂Ȃ�Ȃ��B��G�c��100��kW���̌������ɂƂ낤�B���U�ғ����V���A���d�P���T�~�Ƃ���ƁA�N�Ԕ��㍂���珃���v���̂R����������������R�O�O���~�������������t�z���Ǝv����B�ϗp40�N�Ƃ���A100��kW���̌����͂��̐��U�ɖ�P��2�牭�~�̎����āA�悤�₭���x���g���g���ƂȂ�v�Z���B�܂�A���ɑ���20�N�Ŕp�~��]�V�Ȃ����ꂽ�ꍇ�A��U�牭�~�̑��Q����������B���̍l�����ꎖ�̊������50��ɓK�p���Ă݂悤�B�X�ɂ��o�͂��ғ��N�����قȂ邱�Ƃ��炩�Ȃ�ώG�����A�ʂ��ƂɌv�Z���ďW�v�������̊T�Z���ʂł́A���N�S����̂܂ܔp�F�ŁA�Ȃ��22�E�U���~���̑��Q�ƂȂ邱�Ƃ����������B
�Q�E�lj��R����P�T���~������B
�����A�d���́u�ċG�̂P���W��kW�̎��v�s�[�N�v�Ɓu�N�ԂP��kWh�̏���ʁv�̗����̃j�[�Y�ɑΉ����Ă���B�s�[�N�͉Ă̂قڈꃖ���Ԃ��B�Η͂Ɛ��͂̍��v�ݔ��e�ʂ����v�s�[�N�̂��I�[�o�[���x�̂��Ƃ���A�����ғ������炷��ƃs�[�N�ɏ����͂��Ȃ��Ȃ�Ǝv����B�����A����͑S���I�Ȑߓd�A�Η͂̑��݁A�܂��͂��̗����̑�ŏ��邱�Ƃ��ł��悤�B�^�̖��͂ނ���N�Ԕ��d�ʂɐ����錇�������B�������S���Ă����u�ʁv�̌����߂����邽�߂ɂ́A����ł͉Η͂̔��d�ʃA�b�v�ȊO�ɂȂ��B���͌�����~���g�傷��ɂ�A���łɂ��̑��{����Ă��邪�A���̌��ʂƂ��ĉΗ͂̔R����}�����Ă���B�ŏI�I�ɂ͒lj��R������N�R���~�Ƃ������Z���o�Ă��邪�A��������͂قڐ������Ǝv���B���R�G�l���M�[�̊J�����ł��̒lj��R������Ȃ������߂ɂ́A�Œ�10�N�͂����邾�낤����A���̊Ԃɖ�15���~���̗]���Ȍo��������邱�ƂɂȂ�B
�R�E���̑��̑��Q�����X����B
�����S�p���ƁA���ړI�ɂ͂S�E�T���l�����Ƃ��邪�A�����Y�Ƃ͐��삪�L���̂ŁA���ۂɂ̓��[�J�[��n���o�ό��Ȃǂ��܂߂Ă��̉��{���̐l���d���������B���̌��ʂƂ��ĎЉ�ۏ������傷��B�����͉B��R�X�g�Ƃ�����B�ӊO�ƌ��߂�����Ă��邪�A�����ɂ����Ă͌o�ς̖�肪�l���ɒ������Ă���B�n�����l���E���ƌ����邪�A���E�E�a��Ȃǂ̔w�i�ɂ��o�ώ�����ޏꍇ�������B�o�ς̈����Ŏ��l��������̂͊m�����B
�Ƃ����킯�ŁAA�Ă̑����S�p�ōŏI�I�ɖ�40���~���炢�̑呹�Q���������S��������Ǝv����B���̂悤�ɂ`�Ă͔��ɔ������傫���B�������ꎩ�̂����Y�ݔ��ł���A���g�̃R�X�g��P�o���Ă���ȏ�A�ꋓ�S�p�ɂ��d�C�����́u�啝�l�グ�v�͐�Δ������Ȃ��B���d�����łȂ��S�d�͉�ЂŁu�\�N�Ԑ��������v�͊o�傷��K�v�͂���B�ƒ�͑ς����Ă��A�ʂ����Đ����Ƃƌٗp�͂ǂ��Ȃ邾�낤���B���Ԃ��̂͂����B
���āA�b�Ắu���R���v�ƁA��ɋ������������قƂ�ǔ������Ȃ��B���łɎ��g�́g�N���h��ςݏI�����V���������d�����班�����E�����Ă����������B�������Ƃ����y�[�X�Ȃ̂ŁA���̕������R�G�l���M�[�J����Η͂̌������㓙�ŕ₤���Ƃ��\���B���Ǝ҂��������Ȃ̂ŁA����̃o�b�N�A�b�v�őΉ��ł���B����āA������������p�F�����Ă��������̂b�ẮA�O���̒��ł����Ƃ��Љ�I���a瀂̏��Ȃ����@�Ƃ����邾�낤�B���̂悤�Ɂg�����E�������j�h�ł���Ȃ���A�����I�����č��ꂽ�V�X�e�����������@�����A����Ƃ����Ԃ������ĉ��ɂ���āA�������傫�ȈႢ���o��̂��B
�Ƃ��낪�c�ł���B�Ȃ�b�Ă����Ȃ��Ǝv������A���͂����P���ł͂Ȃ��̂��B�Ƃ����̂��A�o�ϓI�Ɉ�Ԓɂ݂̏��Ȃ��u���R���v�ł���Ƃ��Ă��A���_��ς���ƁA�O���̒��ł����Ƃ����X�L�[�Ƃ��l������̂��B
��k�Ђ̍ہA�s���̃I�t�B�X�r���Ɏc�������l�Ȃ�Ύ��m�̂��Ƃ����A�G���x�[�^���~�܂����܂܂������B�G���x�[�^������͕����̂��߂Ƀt���ғ���]�V�Ȃ����ꂽ�B���́A���ɖZ���������̂��z�lj�����ł���B�Ƃ����̂��A���r���ǂ��h���Ԃ��A���������̃r���Ő��R�ꎖ�̂��������Ă������炾�B�N���Ƌ��Ɍp���蕔�������H�E��J���₷���̂��z�ǂ̎�_�ŁA�����ɗ͂������Ɛv�������e�Ղɔj�����Ă��܂��̂��B
�������ꌴ�����̂̌����Ɏv���������̂́A�^�[�r�������̏��Ɂu��̉������v�����܂��Ă���Ƃ����ɐڂ��������B����͘F�ƃ^�[�r�����s�������Ă�����T�C�N���̐��ȊO�ɂ��肦�Ȃ��B�n�k�̗h�ꂩ�A�S�d���r���ɂ�鈳�͂̋}�㏸�ɂ��A�z�n���ɉ��炩�̔j�����������̂��B�������玄�́u��p�����������������g�_�E���v���m�M���邱�Ƃ��ł����B��̔��\�ɂ��ƁA���ꂪ�ŏ��̈���ŋN�������炵���B
����́u���^�C�v�̌����͍��{�Z�p���炵�ĊԈ���Ă���̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����^�O���������ɏ\���ȍ����ł���B���͗e�킪�����ɕ������|�S�����Ƃ��Ă��A�����ɘA�����A�c���ɍs�������Ă���z�ǂɏ����̋T�����������ŏ��C���R��A�F�S������s�\�Ɋׂ��Ă��܂��B����܂ł͈��͗e���i�[�e�킪�n�k�͂��납�q��@�̏Փ˂ɂ��ς�����Ƃ��āA�n�k���̂̃��X�N�͉��艺�ɐ����u����Ă����B�Ƃ��낪���ꎖ�̂ɂ����߂ăV�X�e���Ƃ��Ă̎�_����������ɂ���A���̃��X�N�����S�Ɍ����������Ƃ����悤�B
���̒n�k���̃��X�N�����Ă���Ƃǂ��Ȃ邩�B�n�k�w�ł́A�k�C�������m���A�[�����A���C�E����C�E��C���̋���n�k�Ƃ���ɂ���Ôg���z�肳��Ă���B�����\�N�̊ԂɘA�����Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��炵���B�b�Ăł͂������ɏ�ɋ������o�ϓI�ȑ��Q���Ȃ���������Ȃ��B�Ƃ��낪�A�ǂ����̊�n�k�ł܂��d�厖�̂��N�����A�s�s���Ɍ������ĕ��˔\���T���U�炷�悤�Ȏ��Ԃɂł��Ȃ�A����Ȕ�Z�p�͈ꋓ�ɐ�����ԉ\��������B
���āA��C�Ɍ�������E����A�ĂȂ�A�o�ϓI�ȑ呹�Q����э����̑ϋv�����͔������Ȃ����A���͂�r�N�r�N���Ȃ��Ă��ށB���́u���X�N�����v�Ɓu���S���v�͑傫�ȃA�h�o���e�[�W���낤�B�v���C�I���e�B���u�T�o�C�o���v�ɒu���Ȃ�A���͖{�\�I�Ɋ댯���@�m���Ă���Ƃ�������}�i�h��������Ԑ�������������Ȃ��̂��B
��������ƁA���͒E�����h�ɂ͋��ɂ̑I�����˂������Ă��邱�Ƃ�������B
�u40���~�̌o�ϓI���Q�����������ɒn�k���̃��X�N���������[���ɂ��邩�B����Ƃ��o�ϓI���Q���[���ɂ������ɈȌ�30�N�ȏ�ɂ킽���Ēn�k���̃��X�N�����������邩�v�c�ł���B
���ꂪA�Ă�C�ĂƂ���A���X�N���Ɍ��炷����ɗ����Ƃ�������̂�B�Ăł���B����Ӗ��A�ǂ���Ƃ��Ă��n�����B���ނ̃��X�N�̓V�[�\�[�W�ɂ���B����̃��X�N�����₵�悤�Ƃ���A�ʂ̃��X�N���ہX�����˂Ȃ�Ȃ��̂��B40���~�������x�����A���������̃T�C�R���Q�[������~��邱�Ƃ��ł��邪�A�x�������a��Ɣۉ��Ȃ����̓q���ɎQ����������B�����͍��܂Ŏ^������������_�����Ă������A���ꂩ��͓����E�����h���́A���̃W�����}�ɂ�����������˂Ȃ�Ȃ��B
�ł́A�E���������܂����Ƃ��āA�����ɂǂ�����悢�̂��낤���B���Ƃ��AC�Ă�I��ł��A�����̑ϐk����S�ʓI�Ɍ������A�����~�����đS���⋭�H��������Ȃ�̃��X�N�͌y���ł��悤�B���邢�́A�ꕔ�̌����ɂ`�Ă�K�p���Ĉꋓ�ɔp�~���A�c��ɂa���͂b�Ă�K�p����Ƃ����悤�ɁA���Ă̑Ë��Ƃ������A�ܒ��Ă�����B�Ȋw�I�Ȋϓ_����n�k�w�I���͍H�w�I�Ƀn�C���X�N�Ȋ�𒊏o���A�@�����������Œ�p�~����̂��i���ۂɂ͌��ݒ�~���Ă������ĉғ��������p�F���Ƃ����[�u�ɂȂ�j�B�n�k�w�I�Ɋ댯�Ȃ͕̂l�������A�H�w�I�Ƀn�C���X�N�Ȃ̂̓}�[�N�T�^�C�v��V����c�Ƃ�������ɁB���̐ܒ��ĂȂ�A�ǂ���̃��X�N������͂ł��Ȃ����A���ꑊ���Ɍ��炷���Ƃ��ł��悤�B
���l�Ƃ��ẮA�E�����̍ۂ́u�`�E�b�ܒ��āv�𐄂������B�O�A���^����n�k�������Ă��邱�̎����ɁA�h����̊����𗝗R�ɕl���������ĉғ����ꂽ�̂ł́A��s���̃��X�N����������B�����́u����v�����f���ׂ����B�������A���̎��Z�ł͕l���R�E�S�E�T���@��p�~�����ꍇ�A�Q���T�牭�~�̐��U�������o��B���̑��A���C�Q���@���ǂ����������߂�����A�ĉғ������ɂ��̂܂ܔp�~�����ق��������B�s������������f����Ȃ�A���R�����͎s���̕��S�ł���ׂ����B�����ʂ�u�g���v�����Ƃ��A���P�ʂ̌o�ϓI�ȑ��Q����т�����U���邽�߂̓d�C�����̒l�グ�A�i�C�̈������͊o�債�đR��ׂ����B�܂��A�lj��R������ł��邾���}���錻���I�ȑ�֎�i�̊m�����}�����B�E�����h�͎��������̑I�����铹���ǂ�قnj����������̂ɖ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i�t���[�����X���C�^�[�@�R�c����
�i���̃R�����g�j
�����͓��{�̃G�l���M�[�����l�������Ǝv���܂����A�u�������L�v�̈ӌ��Ƃ��Ă͌��݂̌y���F�^�̌��q�F�͊댯�Ȃ̂ŁA�V�����������̂���p�F�ɂ��Ă����ׂ����낤�B�����������������牭�~�������č�����̂�������S�������߂�H�������Ďg���Ă����ׂ��ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B������ꌴ���̎��̂͂���ȏ�̈��������d�Ȃ邱�Ƃ��l�����Ȃ��قLj��������d�Ȃ��ċN�������̂��B
�����̌���̍�ƈ����g�����S���u�̑��삪������Ȃ��Ƃ�����������܂������A�������S�_�b����l���������Ď��̑�}�j���A���������ɂȂ��悤�ȏŌ������^�p����Ă����B�����������͂P�R�����Ɉ��͒�~���Ĉ��S�_�������鎖�ɂȂ��Ă��܂������A�ً}��p���u�Ȃǂ̑�����@�Ȃǂ�r�C�ق̎蓮�J�Ȃǂ̑���菇�Ȃǂ̌��C�͂���Ă��Ȃ������B����ł͉��̂��߂̈��S�_������������Ȃ��B
���ڂ̈��S�Ǘ��҂́A�o�ώY�ƏȂ̌��q�͈��S�ۈ��@���Ǘ��҂ł����A�d�͉�Ђ̊Ǘ��^�p���A����̌o������������Ă��炸�A���Ӑݔ��̐Ǝ㐫�����P����Ă��Ȃ������B�z�ǂ͔j�f���ĔR���␅����C���R���Ό����S�̂��̏Ⴕ�Ă��܂��Ǝ㐫������B���Ɍy���F�^�̌��q�F�͔z�ǂ����H�̂悤�ɔz�ǂ���ă����e�i���X��ɂ���肪����B
������ꌴ�����Ôg�����ł͂Ȃ��A�n�k�ɂ���Ă��傫�ȃ_���[�W���Ă����\��������܂����A�����̒Nj��𖾂������ɂ悭�������Ă��Ȃ��B��������������n�k�ƒÔg�ɏP���Ă����Ƃ������ōς̂́A��������肩�͊�{�I�Ȑv�ł����S�����͂����Ă�������ł���A�W�[�[�����d�@�����q�F�����ɂ���z�d�Ղ����v���邱�ƂȂ��A�C���g���|���v���P�䂪�����Ă����͓̂����Ŏ���Ă������炾�B��������S�������߂�ЊQ�͖h����B
����������̒n���̐l�ɂƂ��Ă͌����ЊQ�œ{��S���ł���A��x����I�ɂȂ��Ă��܂��ƌ����A�����M�[�͓��{�S���̌������~�߂��˂Ȃ��ɂȂ��Ă���B�u���܂Ő��e���r�v�Ȃǂ����Ă����������̓{��͐S���ɒB���Ă���A����Ɍ������Δh������悤�ȍ\�}���o���Ă���B�}�X�R�~�ɂ��Ă��������i�Ɣ������̓�ґ���I�Ș_��������Ă���悤�ȏł����A�������S���̌������~�߂Ĕp�F�ɂ���͕̂��Q���傫�����B
�����̊�{�I�ȉ�����i�Ƃ��ẮA���������ƊǗ��ɂ���ׂ��ł���A���Ԃ̓d�͉�Ђł͊������ꂽ�Z�p�Ƃ͌����Ȃ������ŏ��Ɣ��d�����Ă������Ƃ͖������o��B�t�����X�̂悤�ȍ��ƊǗ��ɂ��Ă����Ȃ���Έ��S���̉^�]���o���Ȃ��B������ꌴ���ɂ��Ă�������Ƃɓ��d�����邩�琭�{�͏����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�������厖�̂��N�����Γ��d�ɂ͑��Q�����\�͂��Ȃ��B
���{�̌�������́A�A�����J��GE�̌y���F�������t����ꂽ�Ƃ��납��Ԉ���Ă���̂ł���A�̐S�ȂƂ���̓u���b�N�{�b�N�X�ɂȂ��Ă��܂��āAGE�̋Z�p�҂łȂ��ƌ����̒Nj��͓���̂ł͂Ȃ����낤���H�@������GE�̋Z�p�Ҏ��g���}�[�N�T�^�̌��ׂ��w�E���Ă��Ă��A���{�ɂ͂��̏�\���ɓ`����Ă��Ȃ������B
�Ⴆ�S���F�͉^�]��~���Ă����̂�������͂Ȃ��͂��Ȃ̂ɁA�R���v�[���ւ̗�p�����~�܂��Ă������ʐ��f�������N�����Ă���B�܂萅�������Ȃ�Β�~���̌����ł��������̂��N���肤��B����قNJ댯�Ȃ��̂Ƃ͒m��܂���ł������A���ۂɐ��f�����N�����܂Ō�������d�����{���C�����Ȃ������B�S���F�̃v�[�����n�k�ł����邩������Ȃ���Ԃł���A����������Δ������N�������낤�B
��̂���ȂɊ댯�Ȃ��̂���邱�Ǝ��̂��Ԉ���Ă���̂ł����A���Ƃ����͌��q�͔��d���S�_�b���T���U�炵�č���Ă��܂����B�ŐV�^�̌��q�F�͂���ł����ǂ���Ĉ��S���͍��܂��Ă���̂ł��傤�������J���\���ł͂Ȃ��A���Ƃ̘b���M�p���o���Ȃ��B���{�͐����Z�p�͗D�G�ł��v�i�K����̋Z�p�͂͂Ȃ�GE��WH�̊�{�Z�p�����p���Ă��邾�����B
������e�ʔ픘�̖��ɂ��Ă��A�f�[�^���Ȃ���ΐ��Ƃ��͂����肵�������������A�N���킩��Ȃ��B�u�����v�ł������Ă����悤�ɐH�i�̃x�N�������v�邱�ƈ�Ƃ��Ă��Z�V�E������X�g�����`�E���܂ł��낢�날���Čv�������ƂłȂ��ƌv�����̂ł͂Ȃ��悤���B�܂��̊O�픘��̓��픘�������፬���ɂȂ��Ă܂��܂��������Ă���B
���͌��������p�~�ɂ͔������A����̎��̂̌o�������Ɉ��S�������߂Ă��������Ǝv���Ă��܂��B�V�[�x���g��x�N�����Ƃ�������l�̖����������Ă���A���˔\�Ől���o�^�o�^���ʂ悤�ȏł͂Ȃ��A�_�o���ɂȂ肷���Ă���悤�ȋC������B��������^���Ƃ������Ă��邩�畗�]��Q�Ȃǂ̖����o�܂����A���{�̓������݂�����]�v�ɍ����̕s�������߂�B����������Q��V�^�E�C���X�̂ق�����قǖ��Ɋւ���肾�B��ʎ��̂Ŗ��N�T�O�O�O�l����ł��邩�玩���Ԃ�S���������ƌ����l�͂��邾�낤���H
�����������ł���A�����Ԃ͖ғł��܂r�C�K�X���o���Ȃ��瑖���Ă��܂����A����Ŕx�K���ő����̐l������ł���B����ƒ�����e�ʔ픘�Ɣ�ׂ�ƕs�����ȋC������B�܂莩���Ԃ�����������Љ�ɂ����Ă͕K�v���ɂȂ��Ă��܂��Ă���A������ꌴ���͕����̒n���ɐl�ɂƂ��Ă͔��ɕs�K�ȏo�����ł����A�s�^���d�Ȃ��ċN�������̂ł���A���P�����Ĉ��S���ł��Ďg���錴���Ŕ��d�𑱂���ׂ����낤�B
������A�������}�̏d���N���X���ږ�ɖ���A�˂�u�n�������q�͔��d���������i�c���A���v����������B�n�����Ƃ͍����K�X�F�̎��B2011�N6��1���@�������L
http://blog.goo.ne.jp/2005tora/d/20110601
�i���̃R�����g�j
�����K�X�F�ɂ��ẮA�S���Q�P���̊������L�ł��Љ�܂������A���{�ł����������̎��̂Ōy���F���獂���K�X�F�ւ̐�ւ����i�ނ̂��낤���H�@�y���F�������q�F�ł��邱�Ƃ͕��������ŏؖ�����܂������A�d�C���~�܂��Ă��܂������Ń����g�_�E�����N�����Ă��܂��B����ł͊댯�Ŏg���Ȃ��킯�ł����A�ǂ������y���F���g��ꑱ���Ă����B
�y���F�͗�p�ɑ�ʂ̐����g���킯�����痧�n���C�ӂɌ����A��p���u���ꎞ��p�Ɠ�p�ɕ������Ĕz�ǂ����G�ɂȂ�A����ʂ��z�ǂ͔N�����o�ĂΕ��H���₷���������K�v���B��p�����������ꂽ������ʂɔ������Ă��܂����A�z�ǂ��n�k�ʼn��ĒÔg�̑O�ɗ�p���o���Ȃ��Ȃ��Ă����悤���B
���{�ŏ��̌��q�F�͓��C���̈ꍆ�F�ł����A�p���^�̃K�X��p�F�ł���y���F�ł͂Ȃ������B�������A�����J����v���g�j�E�������o���₷���Ɖ����������ăA�����J���̌y���F�������t����ꂽ�̂��B�܂蕟�������̑�{�̐ӔC�̓A�����J�ɂ���B�������y���F�͒n�k���������{�ɂ͌����Ȃ����q�F�ł��邱�Ƃ͍ŏ����番�����Ă����B
�����g����p���ǂ�ȂɊ댯���͕�������������Ε�����܂����A�O�����d����|���v�����ꂽ�����œ��{�����j�����ł���قǂ̈З͂�����B�C�ӂɂ��邩������͂���~�T�C����ł����܂ꂽ��ꔭ�ł����܂����B��p�����z�����邽�߂ɂ͐��߂��^�^���N���K�v�ł���A���u����|����ɂȂ�₷���B
�u�����K�X�F�́A�R���͓����E���������A��p�ނ͐��̑���Ƀw���E���K�X���g���B�����g��Ȃ��̂ŋ@��A�z�ǂ��ȑf���ł���B�w���E���͉��w�������Ȃ�����R����z�ǂ����H���ɂ����B�܂��A�F�S�\�����ɑϔM���̍����������g�p�A�F�S���n�Z���Ȃ��v���\�Ƃ����B�v���Ƃł����A����Ȃ�n���Ɍ��݂��āA�O������̌R���U���ɂ��ς�����n���Ɍ��q�͔��d�����ł��邾�낤�B
�����猻�݂���y���F�^�̌��q�F�͔p�F�ɂ��āA���q�͔��d���͒n���Ɍ��݂��Ď��̂�O������̍U���ɑς����錴�q�F�ɂ��ׂ����낤�B���E�I�ɂ��K�X�F�����y���Ȃ������̂̓A�����J�̊�������̂ł��傤���K�͂̑傫�Ȍ��q�F�ɂ��鎖���o���Ȃ��������߂��B�y���F�Ȃ�P�O�O���L�����b�g���d�ł��邪�K�X�F���ƂS�O���L�����b�g���炢���K���K�͂ɂȂ�B
���{�ł������K�X�F�̊J�����i��ł���A���S�����؎��������{���āu�F�S�̗�p�\�͂�����ꂽ���Ƃ�z�肵�������ŁA�R���̉��x���ُ�ɏ㏸���邱�Ƃ��Ȃ��A���R�ɏo�͂���������肵����ԁv���m�F����Ă���B�Y�o�V���̋L���ɂ�����悤�ɖ���}�⎩���}�̒��}�h�̋c�A���o���āA�n�����̌��q�͔��d�̐��i�𗧂��グ�Ă���B
�������̃T�~�b�g���������������悤�ɁA���{�͔��������i�ɑǂ�낤�Ƃ��Ă��܂����A���R�G�l���M�[�����ł͓��ʂ͓d�C��d�����Ƃ��ł��܂���B������Ȃ��̓d���J���Ői�߂Ȃ���Ȃ�܂��A�����K�X�F�̂悤�ȑ�l����̌��q�F�Ŕ��d���Ă����悤�ɂ���K�v������B�����������̗����������邾�낤���H
�����g�͌�����ނȂ��h�ł����A���݂̌y���F�͔p�F�ɂ��ĐV����̈��S�Ȍ��q�F�ɐ�ւ���ׂ����낤�B���������݂̌��q�F�̉�͓̂���j�p�����̖����c�邾�낤�B�n���ɍ��ƂȂ�ƌ��݃R�X�g��������܂����A���S���͍��܂�B�Η͔��d���V�R�K�X�Ȃǂ̊J�����i��ł��܂����A���ꂾ���ł͎��v�ʂ�d�����Ƃ��o���Ȃ����낤�B
���q�͔��d�������Ă��d�C�͏\������Ă���Ƃ����_�҂����܂����A�Η͔��d����N�����x�Ŕ��d�������邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�t�Ɍ��q�͔��d�͂�������ғ�������Ǝ~�߂鎖�͓���Ȃ�N�����d��������B�d�C�̎��v�͈���ł����Ɩ�ł͎��v�ʂ��ω����邩��d�͉�Ђ͌��q�͂ƉΗ͂�g�ݍ��킹�ēd�C���������Ă���B
������s�[�N���������Γd�C�͗]������ԂȂ̂ł����A�^�Ă̏������̌ߌ�͓d�C������Ȃ��Ȃ�B�t���ғ�������Α���Ă���Ƃ�������̂ł����A���d�@�͂܂߂ɓ_�����Ȃ��ƌ̏Ⴕ���莖�̂��N�����B�D�Ȃǂ��W�[�[���G���W���œ����Ă��܂����A�q�C����A�邽�тɃ����e�i���X�̓_����Ƃ��K�v���B�������Ȃ��ƒ��������Ȃ��B
�j�R���T�C�N���͋Z�p�I�ɍs���l�܂��Ă���A���̂܂܊J���𑱂��Ă������͂Ȃ����낤�B�܂�g���I������R���_�͂ǂ����ɉi�v�ɕۊǂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������L��ȍ��y�̃A�����J�ł���j�̃S�~�̕ۊǏꏊ��������Ȃ��B�����������K�X�F�Ȃ�M�Ő��f�����V�G�l���M�[����邱�Ƃ��o����B������y���F�͎���x��̌��q�͔��d�Ȃ̂��B
�@
���̋L����ǂl�͂���ȋL�����ǂ�ł��܂��i�\���܂�20�b���x���Ԃ�������܂��B�j
�@
�����̃y�[�W�̂s�n�o���@�@�@�@�@ �����C���� > �����E�t�b�f19�f����
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B���ׂẴy�[�W�����p�A�]�ځA�����N���������܂��B�m�F���[���͕s�v�ł��B���p�������N��\�����Ă��������B