http://www.asyura2.com/11/genpatu11/msg/852.html
| Tweet | �@ |
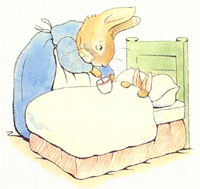
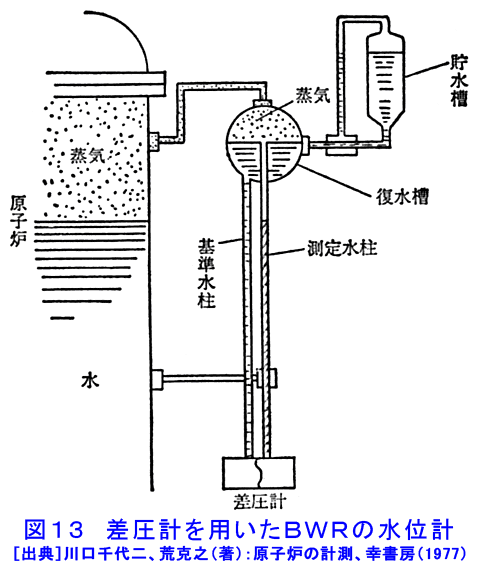
�������Ǝv���Ă��ď����Ă��Ȃ��������Ƃ���B
���̎��_�őS�F�S�̃����g�_�E�������\���Ȃ��������R�i������j�Ƃ��āA���q�F���ʌv���R���_�̔������炢�܂ł̐��ʂ������Ă����Ƃ������̂�����B
���ʂɂ��Ă͎������܂���Ă����N�`�����A���̑�̎x���ŋ삯�������ł�����̋Z�p�҂����ʂ̂������������͂≷�x�ȂǑ��̃f�[�^�Ƃ̊W�Œm���Ă������Ƃ͊m���ŁA�g�c�������͂��߂Ƃ��铌�d�̋Z�p�҂ɂ����ꂪ�m�炳��Ă����͂����B
�Ȃ��Ȃ�A���ł�����́A���q�F�̐��ʌv���u���g�s����h�Ȃ��̂Ɨ������Ă�������A��������鑕�u��V�^���ʌv�̊J���ɗ�ݓ������擾���Ă���B
�������^���q�F�ɑ�������Ă��鐅�ʌv�́A��}�̂悤�ȍ����v�𗘗p���Ă���B
����́A��ʊ�ɂȂ��Ă��镜�����i�ሳ���j�ƈ��͗e��ɐڑ����ꂽ���o�z�ǁi�������j�̊ԂɎ��t����ꂽ�����v�ɂ��A���x������Ȃ���A���͗e��̐��ʂ����o����Ƃ������̂ł���B
�܂��A���������������ƒ��������玩���I�ɐ�����������A������̍��������ɕۂd�g�݂ƂȂ��Ă���B
���̐��ʌv�̖��_�͑�������w�E����Ă���A�X�N�����ȂǂŌ��q�F���}���������Ƃ��A�������Ɏ_�f�␅�f�Ƃ�������Ïk���C�̂��C�A�ɂȂ��ė��܂�A������̐������͗e��ɉ����߂���ʂ̖������ʂ����Ȃ��Ȃ�Ƃ���Ă����B
�i�������͋Ïk���Ɠ��`�ł���A���C�͋Ïk���C�̂Ő��ɖ߂邪�A�_�f�␅�f�Ȃǔ�Ïk���C�̂͂�������Ő��ɗn������܂���������ŋC�̂ɂȂ����肷��j
����̎��̂̏ꍇ���A���͂̋}���ቺ�ɂƂǂ܂炸�A�k�n�b�`�i��p�ޑr���j�̋ɒv�ł���g���h�ɂ܂Ŏ���A�R���햌�ǃW���J���C�̎_���ő�ʂ̐��f�i��Ïk���C�́j�������������A�{���̃V�X�e���ɂ��Ȃ��O������̒������s��ꂽ�B
��}�Ō����A���萅���́A���͗e��ɐڑ����ꂽ���o�z�ǂ̍����łƂǂ܂葱�������ŁA���Όn�⋋���n���g���������͑���������A���C�ƕ��ː��ɂ�鐅�����Ŏ_�f�␅�f�������Ă���B
���̂悤�ȏ������ł܂Ƃ��Ȑ��ʂ�����ł��Ȃ����Ƃ́A�v�G���W�j�A�ɂ͎����������͂����B
�P���@�����������Q���@���R���@�������������āA���ʂ��}�C�i�X�P�U�O�O�`�Q�O�O�O�����i�R���_�̔������炢�ɑ����j�Ɂg�����h���Ă���B
�H�w����ɋ����l������ꂽ��A��}���ʌv���V�X�e���̎d�g�݂ɉ����āA�_�E���X�P�[���ł���Ȃ���A�R���_�̔������炢�̐��ʃf�[�^�ɂȂ闝�R�������Ă������������Ɗ���Ă���B
���_�������A���{�E���d�́A���̒���̊e���q�F�̐��ʂ��}���ɒቺ������������A���ʃf�[�^�����ĂɂȂ�Ȃ����Ƃ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ������Ǝv���B
��������Ȃ��܂܁A�S�F�S�����g�_�E�������\���Ȃ��B�ꖪ�Ƃ��Đ��ʃf�[�^���g�����������Ƃ͋����Ȃ��s�ׂł���B
�@
|
|
|
|
���̋L����ǂl�͂���ȋL�����ǂ�ł��܂��i�\���܂�20�b���x���Ԃ�������܂��B�j
�@
�����̃y�[�W�̂s�n�o���@�@�@�@�@ �����C���� > �����E�t�b�f11�f����
|
|
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B���ׂẴy�[�W�����p�A�]�ځA�����N���������܂��B�m�F���[���͕s�v�ł��B���p�������N��\�����Ă��������B