http://www.asyura2.com/11/genpatu11/msg/124.html
| Tweet |
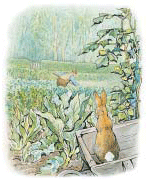
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20110513-00000015-pseven-pol
「技術者が不完全なものを造るわけにはいきません。しかもあれほど危険なものを平気で造ることなんて…」
目に涙を浮かべてこう話すのは、千葉県在住の元エンジニア谷口雅春さん(69)。東芝の子会社である「日本原子力事業」の技術者として、谷口さんは30年以上も昔、浜岡原子力発電所2号機の設計に携わった。1970年ごろから神奈川県横浜市にある東芝の工場に出向し、原子炉の炉内構造物の設計を担当。当時、建設中の浜岡原発2号機については「炉心支持構造物」という原子炉の中枢部分の設計にかかわり、耐震計算に必要な重量データを集計していた。
“事件”が起きたのは1972年5月だった。数十人の設計者のうち代表3人だけで開かれた会議に谷口さんも出席していた。そこで代表者のうちの1人がこう打ち明けたのだった。
「いろいろ計算したがダメだった。この数値では地震が来ると2号機はもたない」
担当者がダメだという最大の理由は岩盤だった。浜岡辺りでは200年周期でマグニチュード8クラスの大地震が起きているため、岩盤が極めて脆かったという。
「浜岡の地盤はそもそも岩どころか、握りつぶすことのできる砂利の集まったシャーベットのような状態でした。さらに、大地震による断層や亀裂ばかりでぐちゃぐちゃになっていたんです」(谷口さん)
さらに原子炉建屋と核燃料集合体の「固有振動数」が、想定される地震の振動の周期に近いことがわかった。固有振動数と同じだと揺れが何倍にも大きくなる「共振現象」を引き起こし、地震のリスクが激増してしまう。
あまりにショッキングな報告に「建設中止もやむをえないか…」と思った谷口さんの目の前で、先ほどの担当者がこう言った。
「データを偽装して、地震に耐えられることにする」
2号機は通産省(当時)に設置許可申請を出す直前だった。谷口さんが振り返る。
「担当者は“岩盤の強度を測定し直したら、福島原発並みに岩盤は強かったことにする”“固有振動数はアメリカのGE社が推奨する値を採用し、共振しないことにする”などと次々と“対策”をあげていくんです」
堂々の“偽装宣言”を耳にした谷口さんは、良心の呵責に苛まれた。
「事故を起こしたら大変なことになるのは明白でした。技術者として、そんな危険な原発を造るなんてできるわけがありません。悩んだ末、私が辞めることで何かしら警告になるのではないかと思い、会社を去ることにしたんです」(谷口さん)
上司に辞意を伝えて自分のデスクに戻ると、耐震計算の結果がはいった3冊のバインダーがなくなっていた。
「隠ぺいが漏れないようにということからか、関連会社の仕事をいろいろ斡旋され慰留されました。でも、続けていても飼い殺しになるだけ。きっぱり辞めることを決めました。しかし残念ながら私の退社はまったく警告になることなく、彼らは原発建設を強行してしまったんです」(谷口さん)
※女性セブン2011年5月26日号
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 原発・フッ素11掲示板
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。