http://www.asyura2.com/10/social8/msg/419.html
| Tweet |
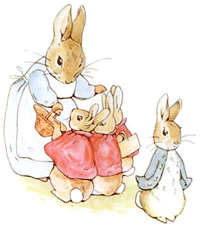

貧しいゼロ年代を覆った『殺して忘れる社会』〜“チェンジ=善”論の落とし穴
2011年8月1日 月曜日
赤木 智弘
『殺して忘れる社会――ゼロ年代「高度情報化」のジレンマ』武田徹著、河出書房新社、1680円
いくぶん物騒なタイトルの本書は、ジャーナリストの武田徹が産経新聞に連載した時評をまとめた1冊。2004年から2010年に起きた様々な出来事が取り上げられている。
私たちが、こうした「過去の論評」をまとめた本を読む時には、自ずと「私たちがその当時、その事柄に対してどう考えていたか」を思い出すことになる。
例えば、2006年の記事では、著者がグッドデザイン賞の選考委員を務めていた時代の携帯デザインの話をしている。その中に〈国外ではフルキーボード付きの携帯電話、いわゆるスマートフォンが急増中だ。一方日本では未だにテンキーしか持たない機種が主流〉といった当時の携帯事情を表した記述がある。
今や、日本でもスマートフォンの利用者が急増し、市民権を得ている。しかし当時は、日本の携帯がガラパゴス状態であることに大半の日本人は気づいていなかった。日本でスマートフォンの存在を知らしめたiPhoneの日本での販売開始は、この記事の2年後、2008年の7月になってからである。
日本でもスマートフォンが急増中の現代、それが一般的でなかった過去の時代に、私たちが携帯に対してどのような意識を持っていたのかは、徐々に忘れていく。
「殺す」と「忘れる」は表裏一体
本書のタイトルにある「忘れる」は、比較的分かりやすい概念であるように思う。
特に昨今のテクノロジーが大きく変化していく社会において、過去にどんな社会生活を送っていたか、そしてその上でどのようなことを考えていたかといった、生活に密着した部分の意識を私たちは忘れ去ってしまう。
では「殺す」とはなんだろうか?
筆者がまえがきで挙げているのは、マスメディアにおけるバッシングである。
妻子ある国会議員との密会が報じられた女性ニュースキャスターに対し、社会が加えたバッシングと、その後彼女がバラエティー番組などで復帰したことを示し、前者を「殺す」、後者を「忘れる」としている。
そして〈すぐに忘れられるほど他者の存在が軽くなっているからこそ、(社会的)生命を奪うまで抵抗感なく追い込むことができる。そして、すぐに忘れてしまうから、追い詰める側は自分たちの冷血さに気づくにも至らない〉として、「殺す」と「忘れる」は矛盾せず、表裏一体であると示す。
これをそのまま、人間の話として読むこともできるが、テクノロジーの話として読み替えることも可能だろう。
例えば、ブルーレイディスクに対するHD(ハイディフィニション)DVDのように敗北した規格もあれば、ビデオカメラにおける8ミリビデオのように、過去に隆盛を極めながらも置き換えられた規格もある。競争や盛者必衰は世の理ではあるが、それは単純に「よりよいものが生き残る」ということではない。
2006年の記事に、ライカの主力シリーズであったMシリーズが、それまでのフィルムカメラからデジタルカメラになったという題材がある。そのなかで著者はそれを〈ライカらしくない〉と論じている。
「ライカよ、おまえもか」
フィルムカメラは、「レンズ前の光の真実」をあるがままに写しとる〈その特性がゆえに写真は歴史を記録し、忘れず固定するメディアとなった〉と著者は表現する。
その一方で、デジタルカメラで記録した映像は、素人でも簡単に加工することができてしまう。〈デジタルカメラの時代に報道写真が真実であると主張するには、そこに捏造がないことを改めて示さなければならなくなった〉と述べている。これはどういう意味だろうか。私の考えを述べてみよう。
フィルムカメラの時代に捏造がなかった訳ではない。1934年にロンドンの外科医が撮影したネス湖のネッシーの写真は、公表されて以降、本人がいたずらであったと語る93年まで、その真偽を疑われながらも、その真偽をめぐっての話題をふりまき続けた。それはフィルムカメラで撮影されたものが真実であるという前提が、あまりにも自明であったから、単純に「作り物だ!」と否定することが難しかったのであろう。
ところが、フィルムカメラがデジタルカメラに置き換わると、カメラは単なる画像データ作成のためのツールとなってしまった。
例えば、ゲームセンターなどに置かれるプリクラでは、写真に文字を書くのはもちろん、肌の色がキレイに写ったり、黒目が大きく映るなどの加工までが当然の機能となり、そこには真実性のヴェールはいっさい存在しない。今、もしネッシーの写真があったとしても、最初に加工を疑われて当たり前の時代になってしまったのだというのが、著者の認識であると私は理解している。
そうした「写真」に対する意識の大きな変動を免れない、フィルムからデジタルへのカメラの変化に対して、一般の家電メーカーであればともかく、報道写真の歴史を作ってきたはずのライカが十分な思慮を示せていないことに対し、著者は「ライカよ、おまえもか」という、嘆きにも似た心情を吐露している。
私たちは過去のプロジェクト。特に敗北したプロジェクトに対して、「ああ、そんなものもあったね」などと、冷笑的に扱ってしまいがちである。そして現状で普及している「勝ち組」を支持した自分を、さも優秀な選別眼を持った存在であるかのように思い込み、安心してしまう。
過去の論評を読む価値
著者はあとがきの中で、首相がコロコロと変わる昨今の政局に触れて〈役者が入れ替わるたびに古い役者を次々に「殺して忘れ」てゆくが、結局、何も経験値として積み上げられていないゼロ年代・日本の貧しさについて思い至った人は、どの程度いたのか〉と述べている。
不都合があれば置き換えて、次々に変化していくことだけを善しとするだけでは成長は望めない。
敗れたモノを冷笑して悦に浸るといった、軽んじて殺すような態度をとるのではなく、失われた過去を意識的に忘れずに記憶し、そこで失われた様々な事柄を慎重に掘り起こすことが、私たちが成長するために必要なのではないだろうか。
冒頭にも述べたが、私たちが「過去の論評」をまとめた本を読む時には、自ずと「私たちがその当時、その事柄に対してどう考えていたか」を思い出すことになる。
本書のような、過去の論評やエッセイを読む価値は、そうした忘れてしまった過去を思い返し、現状に染まりがちな私たちの価値観と過去を突き合わせ、そこから様々な物事を拾い上げ、未来を生み出すための糧にすることにあるのではないかと、私は考えている。
ネットなどで最新の情報を仕入れて、未来指向に物事を考えていくのは多くの人がやっているが、その考え方の濃度とでも言うべきものを煮詰めるためにも、過去のうまくいかなかったプロジェクトのフォルダの封印を、ひも解いてみるのはどうだろうか。
(文/赤木智弘、企画・編集/連結社)
このコラムについて
超ビジネス書レビュー
本屋さんやネット書店のビジネスコーナーにある本だけが「ビジネス書」ではない!普通は「ビジネス書」とされない一冊を、オン・ビジネスの視点から読み解き、仕事に役立つ知恵や技術や考え方をご紹介する週刊連載です。面白本を厳選しておりますので、貴方の頭脳を柔らかくする情報ソースとしてもお使いください。
⇒ 記事一覧
著者プロフィール
赤木 智弘(あかぎ・ともひろ)
1975年8月栃木県生まれのフリーライター。長きにわたるアルバイト経験から、非正規労働者や社会的弱者でも安心して生活できる社会を実現するために提言を続けている。著書に『若者を見殺しにする国』(双風舎)、『当たり前をひっぱたく』(河出書房新社)など。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。