http://www.asyura2.com/10/social8/msg/167.html
| Tweet |
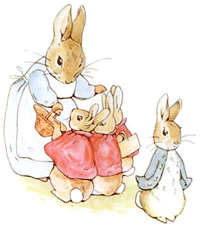
雨宮処凜がゆく!マガジン9条
http://www.magazine9.jp/karin/101110/
(転写開始)
『助けてと言えない』。の巻
最近、深く考えさせられる本を読み、とても一人では抱えきれないのでみんなにも共有、というか無理矢理感染させたいと思う。
その本とは『助けてと言えない いま30代に何が』(文藝春秋 NHKクローズアップ現代取材班)。この連載の132回でも触れたNHKの同名の番組が書籍化されたものだ。
09年4月、北九州市で39歳の男性が孤独死(死因は餓死とみられている)しているのが発見されたことから取材が始まったこの番組の第一回を私は見ていない。この本で詳細を初めて知ったのだが、男性の経歴は、現在の30代にとってまったく珍しいものではなかったことに改めて衝撃を受けた。
ざっくり振り返ると、69年生まれの男性は20歳で専門学校を卒業した90年に金融関係の会社に正社員として入社。時代はまだバブルだ。が、過酷な勤務から体調を崩し、退職。しかし、その頃は既にバブルがはじけたあと。地元の北九州市に戻り、飲食店などでアルバイトを始める。30代になってからは少なくとも七つのアルバイト先を渡り歩いたそうで、真面目なフリーターだったものの、生活は不安定。そんな男性には少なくとも5つの消費者金融から150万円以上の借金があったと見られている。そうして08年には勤め先の居酒屋に借金の取り立ての電話がかかってくるようになり、退職。08年12月に最後の給料およそ6万円が振り込まれ、その4ヶ月後、遺体で発見されるのだ。
家族はというと父親は十数年前に蒸発して行方不明、母親は05年に亡くなり、母亡きあとの男性は母の住んでいた家賃2万5000円の借家で暮らしていたという。唯一、離れた場所で暮らすお兄さんがいたが、男性は兄に資金援助を頼むことはあっても、かなり厳しい状態にあることは打ち明けていなかった。
遺体が発見される3ヶ月前の1月には生活保護の相談に訪れるものの、「何か仕事があるはず」と言われた彼は「幅広く仕事を探してみます」と答え、それきり相談には訪れていない。2月には生前の母が飼っていた犬2匹(母が亡くなった後も飼われていたが、男性が散歩に連れ出す姿が見られることはほとんどなく、また空の餌箱が目立つようになっていたという)が放される。近所の人は「もうこれ以上犬を食べさせることができない、せめておまえたちだけでも生きてくれと、放したのではないでしょうか」と語っている。が、放された犬は最初の頃は近所の人たちに世話してもらうものの、二週間後、人を噛みそうになり、保健所に連れていかれてしまう。
そうして犬を放してから2ヶ月後、遺体が発見された。所持金はたった9円。冷蔵庫は空で、家賃は12月から滞納していたという。傍らには、親戚に宛てた「たすけて」とだけ書かれた手紙があったそうだ。
本書には、09年頃から急増した30代のホームレスの人々も多く登場する。その中には、37歳で路上死してしまったホームレス男性もいる。男性は支援団体から生活保護の申請を勧められていたというが、申請していない。生活保護の申請をすると、家族に連絡が行く。本書では申請しなかった理由を、「おそらく、亡くなった男性はこのことを知っていたのだろう。生活に困窮した自分の姿を家族には知られたくなかったのだ」と綴っている。
なぜ、家族にも兄弟にも友人にも支援団体にも役所にも「助けて」と言えないのか。これが本書の最大のテーマだ。
本書に登場する30代のホームレス男性・入江さん(仮名)には実家があり、親がいるものの、「いまさら、助けてとは言えません」と言い、今の状況を親には「口が裂けても言えない」と言う。友達にも「負担をかける」ことになるから助けてなどは決して言えない、と。そんな入江さんは住所もなく、携帯も止まっていることからいくら仕事を探しても見つからないのだが、それでも「自分が悪い」と繰り返す。そうして食べるものに困りながらも身なりを常に気にし、「どう行動すれば自分がホームレスに見られないかという一点に集中して」生活を送っている。
私自身、今まで「親がいなかったりして親に頼れない」という事情からホームレス化した同世代の人々に話を聞いてきた。しかし、実家があり、親が健在でありながらも「助けて」と言えない人の話をきちんと聞いたことはない。なぜなら、私が出会う人々は既に支援団体などのセーフティネットにひっかかっている人が多いからだ。ある意味で「助け」を求めることができた人たちで、しかし、決して「助けて」と言わない人たちは支援団体との接点も薄い。
「二十代のころは、人に助けてもらうこともあった」と語る入江さんは、「三十代はもう、責任逃れができない年齢」だと言う。34歳の別のホームレス男性は「親に心配をかけたくない」「とにかく自分の力で頑張ります」と言い、また別のホームレス男性は、支援団体の人に声をかけられても「大丈夫です。自分でなんとかします」と言い返す。そういえば私自身も昨年末、「派遣村」関係のボランティアに参加した際、同世代らしき男性に「支援団体への紹介」を断られた。「大丈夫です、自分でなんとかしますから」と。家も所持金もないのに、どうやって自力で頑張ればいいのだろう。「でも・・・」と引き止めようとすると、「本当に大丈夫ですから!」と強い口調で言われた。あの人がどうなったか、ずっと気になっている。
翻って自分がそのような立場だったら、誰かに「助けて」と言えるだろうか?と思った。散々反貧困運動とかプレカリアート運動にかかわっている私が言うのもなんだが、「言えないかも・・・」というのが正直な気持ちだ。それよりも、とにかく「今の状態を誰にも知られたくない」と強く思うのではないだろうか。本書には、こんな一文がある。「もしかすると、『助けて』と口に出すことは、入江さんの根幹になっている重要な部分が崩れ落ちてしまうことを意味するのではないか」
なんだか、ものすごくよくわかる。私にもその「重要な部分」が強固に存在するからだ。だからこそ、「助けて」という言葉のハードルはとてつもなく高い。でも、それはどうしてなのだろう?
作家の平野啓一郎氏は本書で30代を、「社会で自己実現しなければいけないということと、努力次第でいいポジションを得られるということ。この二つを十代の頃に強く叩き込まれた世代だったのではないか」と述べている。確かに、自分の10代を振り返っても「誰でも頑張れば成功できる」ことは盲目的に信じられていたし、「機会平等」が保証されているという前提が信じられている社会は、「負けたのはすべて本人の責任」という自己責任論を強烈に内面化させる社会だ。
そうしてもうひとつ、思ったのは「親」のことだ。もっとも頼れるはずの親にこそ「助けて」と言えないという同世代の思いが、何かものすごくわかるのだ。
私の親はいわゆる団塊世代。本書には、仕事を解雇され実家に戻るものの、親と上手く行かずに家を飛び出してホームレスとなった30代も登場するのだが、「定職につけない息子を厳格な両親は一人の大人として認めることはできないと、厳しく接した」とある。
現在30代の親世代には、「定職についていない」「自立していない」ことなどを許さない価値観がものすごく強固にあるような気がしてならない。まぁどの世代もそうなのかもしれないが、何か「努力すれば絶対に報われる」という、おそらく経験に基づいた信仰のような価値観が恐ろしく強いように感じるのだ。だからこそ、そうではない息子や娘を許さない。許したふりをしていても、どこかで絶対に許していない。時代前提が違うのにもかかわらず、そんな子どもに対して「軽蔑」や「恥ずべき者」といった意識を持つ人々を少なくない数、目にしてきた。それはどうにもならない軋轢となり、時に子どもは「ホームレスの方がマシ」と家を飛び出すだろうし、時に親への「あてつけ」のように命を絶つことだってあるだろう。実際、どちらのケースも見聞きしてきた。
「助けて」を言うことをどこかで許していない親や社会と、自らのプライドをかけ、「助けて」と言わない当事者。
その背景にあるものの複雑さに、何か気が遠くなる思いだ。
(転写終了)
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。