http://www.asyura2.com/10/idletalk39/msg/849.html
| Tweet |
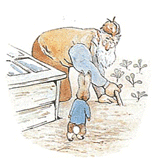
株式日記と経済展望
http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu262.html
http://blog.goo.ne.jp/2005tora/
--------------------------------------------------------------------------------
高収入ほど読書時間が長いこと。(年収500万円台〜800万円台は、
一日5~30分未満なのに対して、 年収1500万円以上の平均は30分以上)
2012年4月17日 火曜日
◆低年収ほど「本を読む時間がない」はホント? 4月16日 田中伶
http://blogos.com/article/36720/
新生活な4月が始まって、早くも折り返し地点を過ぎました。Twitterを見ていると、周りの人たちのライフスタイルの変化を顕著に見ることができて、情報収集とは違った楽しみ方があるなあと思う日々です。
そして、毎号読んでいるのですが最近すっかり面白くなくなったな・・・なんて思っていたビジネス誌、PRESIDENT。
「年収別!こんなに違う読書の質、量、読み方」・・・なんて言われたら、ついつい手に取ってしまいますよね。笑今月号は、かなり興味深い特集でした!
イケてる大人たちが一体どんな本を読んでいるのか?年収別に読んでいる本の傾向をまとめていたり、読書時間についての詳しい習慣をアンケートしていたのですが、私も常に書籍を鞄に入れているタイプなので、この特集には興味津々!
分かりやすいのが、高収入ほど読書時間が長いこと。(年収500万円台〜800万円台は、一日5~30分未満なのに対して、 年収1500万円以上の平均は30分以上)
そして、月間読書量も年収とキレイに比例。もちろん本への投資額や、書店や図書館に行く回数も比例。
稼ぐ人の6割は「いつもカバンに本が入っている状態」なんて聞くと、沢山お金を稼いでいるからこそ、仕事に余裕があるんじゃない?と思ってしまいがちですが、高収入の人ほど努力して「読書のための時間」を作っているというアンケート結果。
ほかにも興味深かったのは、稼ぐ人ほど「学術書」を読み、低年収ほど「自己啓発書」「漫画」を好む。稼ぐ人は「著者」で本を選び、低年収は「タイトル」で本を選ぶ。・・・といったデータ。
もちろん一概には言えませんが、行きつけの書店があったり、お気に入りの著者がいたり、鞄に常に本を入れていたり・・・どれだけ自分のライフスタイルに「本」という存在が落とし込まれているか?どれだけ習慣化しているか?というのがポイントになっているようですね。
”忙しいから” は本を読まない理由にならない!
自分のインプットであり、アウトプットのための読書。私の場合は、情けないかな、本をちゃんと読んだのは21歳が初めて。しかしそれからは、師匠に今読むべき本をお奨めいただいて、”ビジネス書”ではなく、”学術書”や”経営学の専門書”を読むように!と、弟子入りしたての頃は、常に指導されていました。
せっかくお金と時間と労力をかけて「本を読む」という作業をするのだから、出来るだけヒット率の高い本を読みたい。出来るだけ自分の蓄積になる時間やお金の使い方をしたい。
だからこそ、自分にとってのメンター的な存在や、読む書籍の指南をしてくれる人の存在は大切ですよね。
以前、「つべこべ言わずに本を読め!;インプットとアウトプットの関係」という記事を書いて、インプットとアウトプットの驚きの関係を、自分自身のケースを使ってご紹介しました。
本を読めば読むほど、仕事が入って、忙しくなって、インプットとアウトプットが回る。そして本を読んでいないときほど、仕事が回らず、いつまでもダラダラと過ごしてしまう。今回のPRESIDENTのアンケートでも、同じような結果が出ていました。
それが、低年収ほど「読む時間がない」と言っていること。そしてそれと同じくらいの数の人たちが「読書があまり好きではない」と言っていること。こうなってしまえば「読む時間がない」というのは、ただの読書嫌いの言い訳。
自分で創ろうとしなければ、読書をする時間なんてない!・・・というのは、みんな一緒。
その中でいかに、自分にとっての読書の必要性を感じているか?ちゃんと本を読まなければ大変なことになる!とまで思い込んでいるのが実は出世している人の思考パターンなんだと学びました。(そして往々にして、そういう方たちが必要としている知識はネット上では手に入らない情報だったりするんですよね)
「自分のお気に入り」を見つけよう
先ほど、稼ぐ人ほど「本」という存在が習慣化しているということを書きましたが、今あまりライフスタイルに「本」が染みついていない方は、是非この方法を試してもらいたいと思います。
それは「自分のお気に入り」を見つけること。
自分のお気に入りの著者を何人か見つける、自分のお気に入りの書店を見つける、自分のお気に入りのカフェで読書をする、などなど。
「賢者に学ばなければ」という危機感をちゃんと持つことはもちろんですが、ちゃんと自分が読書を楽しめなければ、習慣にはならないですもんね。
優秀な編集者は売れる本はつくれますが、価値のある本は価値ある情報を握っている人にしかかけない。
これはエリエス・ブック・コンサルティング代表の土井英司さんの言葉。自分のお気に入りの著者を見つける基準は、最初は誰かからの推薦だったり、たまたま手にとってものかも知れませんが、それらがホンモノかどうかを見極めるためには、やっぱり普段からの読書量が決め手になりますよね。
私は速読のスキルも無いですし、読書量が人の何倍もあるわけではありませんが、常に鞄の中に書籍を入れて、暇さえあれば読むようにしています。
まだまだインプットもアウトプットも十分とは言えませんが、これから続く成長の道の中で、質の高い読書時間から得られることは多いはず。
皆さんも一緒に、「読書習慣」始めましょう!
◆理由 4月8日 社長ブログ
http://www.speedia.co.jp/~namisato/2012_04.html
「田舎オヤジのくせに、おまえ、なんでそんなにくわしいんだ?」、って、ときどき思われる方もいらっしゃることでしょう。それは、研究のたまものです。(笑)
じつは、2009年にとてもくやしい思いをしたんですよ。2008年の秋、リーマンショック後、世界経済はガタガタになりました。日本も同時に崩落しましたが、もともと失われた20年で疲弊しまくっていた地方経済の惨状は、もう目もあてられない状況でした。
そんななか、当社はある銀行から貸しはがしにあいます。データセンターの設備更新のために借りていたんですが、さすがに100年に一度といわれる世界大恐慌を目の前にし、わたしは設備投資の延期を決断。なにがおこるかわからないため、手持ちキャッシュは温存する方針に変えたわけです。
ところがですよ、しばらくして、予定通り設備更新がされなかったことに気づいた某銀行さんは、「使途違反」に抵触するおそれがある、とのたもう。使わないのなら、いったん返してくれと。
おまえバカか? この状況下で、予定通り設備投資するアホウがどこにいる?うちに倒産しろとでもいうのか? って、怒り狂って抗議したんですが、金融機関は聞く耳持たず。
ちょうどある大型の案件に億単位で投資した直後であり、そこへ100年に一度の巨大な世界恐慌がおそってきて、受注予定だった新規案件はのきなみ吹っ飛んでいた。とうぜん資金的にはタイトであり、当社にとっては最悪のタイミングでの貸しはがしだったわけです。
くやしくて、くやしくて、涙が止まらず、その晩は一睡もできませんでした。そのとき、思ったんですよ。このタイミングで世界恐慌が襲ってくると知っていたら、その直前に大型の投資なんてしなかったし、データセンターの設備更新タイミングも、最初からずらしていた。
まえもって資金繰りを調整していたし、膨大なマンパワーをかけて吹っ飛ぶ運命の新規プロジェクトなんかも、、、、って。
そうなんだ。吹けば飛ぶような田舎の中小企業だからこそ、吹かれて飛ばされないように、世界情勢のダイナミックな動きを読んでおかなければいけないんだ、って。
それ以降、いろいろ本を読んだり、セミナーに参加したり、世界情勢と国際金融に関する勉強をはじめた、というわけです。
もちろん、いまでも毎日勉強をつづけています。異様にくわしくなっちゃったのは、そのおかげ。
もちろん、いまはかなり先回りして動いており、資金繰りの心配もありません。(笑)
(私のコメント)
「株式日記」でも時々書籍などを紹介していますが、これは紹介したい本を一部公開して私のコメントをつけています。私の机の上には買って来て積んでおいた本が山積みになっている状態ですが、3,11の地震の時は本が崩れ落ちて部屋中に散らかってしまった。だから本棚に整理して置くようにしましたが、やはりしばらくすると本が積み上がってしまう。
私の読む本の種類としては、経済書から歴史書から社会分析的なものが多い。小説とが文学本はほとんど読みませんが、学生時代しか小説や古典ものは読む機会は無いだろう。私のように不動産業を経営していると社会の動きに敏感にならざるを得ませんが、目には見えない変化を読み取らなければなりません。
銀行員時代にも感じたことですが、会社のサラリーマンで本を読む人は本当に少ない。銀行員だから日本や世界の金融情勢や経済情勢に関心のある人はほとんどいなかった。だからバブルの崩壊はいつかは起きると見ていましたが、私は早めに銀行を辞めて不動産業に転進した。しかしバブル崩壊後の不況がこれほど長引くものとは全く予想が出来なかった。
ゼロ金利がどうしてこれほど長く続くのかも全く分かりませんでしたが、ゼロ金利のおかげで返済金額が少なくなり何とか生き延びることが出来たのも事実だ。億単位の借金をしていると僅かな金利の急騰でも命取りになってしまう。この世の日本の金融情勢を解説してくれる本は無く、リチャード・ヴェルナーの「円の支配者」と言う本を読んで、ようやく日本の置かれた金融情勢が分かってきた。
だからテレビなどで経済学者やエコノミストの言うことは嘘ばかりで、彼ら自身がまるで分かっていはいないことは分かった。分かっている人はリチャード・クー氏ぐらいで、財政出動論者でテレビから排斥されてしまって出られなくなってしまった。彼のバランスシート不況説を読んで始めて日本が超低金利が長引いていることが分かりました。
現在の欧米で起きている事も、バランスシート不況であり銀行による貸しはがしや貸し渋りで、景気回復はFRBがいくら金をばら撒いても難しいだろう。税収が落ち込む中での財政出動は財政赤字の問題が出てきますが、国が金を使わなければ金が回らなくなってデフレ経済になってしまう。では何に金を使えばいいかというと、自然エネルギー資源開発などの科学技術だろう。
このように私の関心が広がれば広がるほど読まねばならない本は増える一方だ。ネット上にも情報はありますが本に比べると質量ともに落ちる。ブログなどを探してみても政治や経済や金融などを論じたものは非常に少ない。普段から専門書などを読んでいないとコメントすら出来ないだろう。欧米に比べると専門家の書いたブログが少ないことも気になりますが、ポール・クルーグマン教授のように専門家こそブログで書いて欲しいものだ。
田中伶氏の記事にもあるように、読書量と年収とは深い相関関係があるようだ。読書と言っても漫画や小説では意味が無いのであり、学術省や専門書と言った硬いものを読む必要がある。まだ誰の本を読むべきかといった判断も自分でする必要がありますが、福島第一原発の事故を受けて原発の専門書などを買って読んでみましたが、水素爆発の事も書かれてはいなかったし、福島第一よりも女川原発が危険だと書いてあった。このように専門家でも分からないし間違った事を書いている。
私がこのように毎日膨大なコメントが書けるのも、今まで読んできた本の知識がベースになっているからであり、「株式日記」を新聞記者とか学者とか、海外の人も翻訳されて読まれているようだ。出来れば英語での情報発信もしたいところですが、それだけの英語の能力も時間もない。しかしグーグルなどには翻訳機能が付いているのでそれで読まれているのだろう。
コメントには翻訳機能で日本語で書かれたものがありますが、このようにしてみると英語を勉強することよりも、専門知識を蓄えることであり、「株式日記」のように日本語で書かれたものでも世界中の人に読まれるようになって来ました。コメントのいくつかを紹介させていただきます。
2012-04-10 23:53:37
私はあなたの記事を読んで、それは私がこの偉大なリソースを見つけたことを大きな喜びをもたらしました。あなたはきっと私の研究を手伝ってくれた。私の周りの散歩をされ、私は他の貴重なリソースを見つけることができる場合、私は表示されます。しかし、あなたは私の同級生にこのサイトをお勧めしますことを確認することができます。
2012-04-08 18:44:54
るすべての人々の仕に感謝します。問題の非常にシンプルかつ明確な説明が与えられ、それが誰にとっても開かれています。は、データベースしているものです
2012-04-05 16:33:22
投稿ニース!
我々は、uがあなたのブログで表現したテキストを楽しんだ。それを維持する。すぐに次のアップデートを探しています。
2012-04-05 14:14:37
の仕に感謝します。問題の非常にシンプルかつ明確な説明が与えられ、それが誰にとっても開かれています。は、データベースしているものです
(私のコメント)
文章からして機械翻訳されたものなのでしょうが、意味は大体分かります。最近ではツイッターやフェイスブックなどでリンクされて読まれているようですが、世界に見ても「株式日記」レベルのブログは少ないのだろう。だから英語の勉強に時間を費やすよりも専門知識と日本語の文章力を磨いたほうがいいのではないかと思う。いくら英語で流暢な文章を書いても中身の無いブログでは誰も読んではくれないだろう。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。