http://www.asyura2.com/10/idletalk39/msg/562.html
| Tweet |
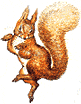
身体で動く人と頭で動く人の違い/内田樹
http://www.asyura2.com/10/idletalk39/msg/552.html
投稿者 藪素人 日時 2011 年 9 月 13 日 19:59:54: BhHpEHNtX5sU2
を、読ませていただいて、触発というか成程なと思ったところがあっての下記転載投稿です。
下記転載記事に関してですが
アランも、(情念である)怒りにわれを忘れた人と、(単なる身体症状である)咳の発作に身をまかせている人の間に大きな相違はないと書いていたと思います。
また、病気は情念によってもっと悪くなるが、これは――理性によってからだの動きを支配することを知らない――ほんとうの体操を知らなかった者の運命だとも書いていたと思います。
http://kokoroniseiun.seesaa.net/article/221580350.html 《1》
http://kokoroniseiun.seesaa.net/article/221788100.html 《2》
http://kokoroniseiun.seesaa.net/article/221977952.html 《3》
http://kokoroniseiun.seesaa.net/article/222193505.html 《4》
《1》
作家・開高健の傑作とうたわれる小説『夏の闇』にはこんな記述がある。
「私はすりきれかかっていて、接着剤が風化して粘着力を失い、ちょっと指でついただけでたちまち無数の破片となって散乱してしまうように感じられてならない。いつか女が駅前広場の早朝の酒場で外国暮らしをしていて“人格剥離”が起きるとつらいといったと思うが、私には人格と呼べるほどのものがあると思えないのに、“剥離”だけがひどく感じられる。」
「気がついたときはいつも遅すぎて私は茫然として凍え、音も匂いもない荒涼の河原にたって、あたりをまじまじと眺めている。そうでなかったら、酒瓶や、皿や、コックの頬肉や、ピカピカ光るガラス扉や、その向こうに見える巨大なビルなどが、壮大で無慈悲な塵芥の群れ、手のつけようのない屑と感じられ、私は波止場におりたったばかりの移民のようにたちすくんでしまう。」
「子供のときから私は名のないものに不意をうたれて凍ったり砕けたりしつづけてきた。いつ剥離するかしれない自身におびえる私には昂揚や情熱の抱きようがなかった。情熱は抱くのもおそろしいがさめるのもおそろしかった。」
……
『夏の闇』は、簡単に言ってしまえば、主人公の「私」が休暇でパリに行っている間に、昔の恋人だった「女」とアパートで過ごす一夏のありようを描いている。主人公の「私」はほとんど開高自身を色濃く投射していると見えるが、ほとんどベッドの上で過ごしていて、眠るか食うか「女」と情事にうつつを抜かすかしているという話である。
こういった記述は、小説(フィクション)とはいいながら、彼・開高の心の状態を描いていると見てよかろう。なぜなら、開高健は釣りやグルメなどのエッセイでもしきりにこういう自分の精神状態について記述していたからである。小説はだから私小説に近くなった。
私は開高健のファンだったけれど、それは主に初期の「非私小説」つまり「外へ向かって書いた作品」やルポの類いであって、彼がヴェトナム戦争取材以降、内部の己にこだわって小説を書くようになってからのものは評価できなくなった。
引用したような心の闇を、私は共有し得なかった。
ずばり言えば、精神病者の繰り言には付き合いきれない、という思いである。
開高は己の心の闇を、科学的に(医学的に)分析することなく、華麗な修辞の実力で描写してみせた。実に描写の巧みさには感心するけれど、開高のような“人格剥離”などとはこちらは無縁だった。
その開高の心のありようを、近代日本人の置かれた精神状況と読み替えて評価する向きは多かったのかと思う。だから『夏の闇』が傑作と言われたのだろう。
文芸評論家の山崎正和氏は、『曖昧への冒険』(新潮社)で、開高の『夏の闇』を日本人の精神史的な観点から捉えて激賞していたけれど、私はあまり共感できなかった。
山崎正和氏は開高に「なんでヴェトナム戦争に関わって取材やエッセイ、小説を書くのか」と激しく非難していたのに、一転『夏の闇』は絶賛していた。山崎にしてみれば、作家が自己の内面の「なぜ書くのか」を離れたところで、いうなれば自分と関係ない他国の戦争なんかにうつつを抜かしているのは正道を逸していると言いたかったのだろう。戦争を書くのなら記者か国際問題評論家などの仕事じゃないかというのだろう。
しかし開高は『夏の闇』で自己の内面を凝視した作品をものしたので、山崎に評価されていたのである。開高は「山崎正和の認識論はすばらしい」みたいな感謝の仕方をしていた記憶がある。
「山崎正和の認識論」という言葉に大変違和感を覚えたものだった。もうだいぶ以前のことになってしまったが…。それは端的には、山崎も開高も、認識とは何かを何も説かずに、それこそ曖昧なままに解釈を重ねていこうとしていたからであった。
《2》
さて。
本稿を書くキッカケは、仲間秀典著『開高健の憂鬱』を読んだからである。
仲間秀典氏は公衆衛生が専門らしいが、作家の精神病を扱った『開高健の憂鬱』(文芸社 2004年)をものしている。これは開高の作品からその精神病理を読み解いた著作だ。
仲間氏の専門が精神医学ではないからかもしれないが、既存の精神科医師らの分析を細かく紹介しているにとどまっているように思える。なぜなら彼もやはり認識とは何かが解けていないからであるが…。
仲間氏の手法は、「病跡学」というそうで、端的には天才と狂気を関連づけようという試みである。その研究対象に、開高健が選ばれ、縷々作品を取り上げ、さまざまな評論家たちの分析を紹介している。
しかし、日本の作家たちの多くは、明治以降、どれもこれも精神病に関わる人間ばかりである。夏目漱石もかなり心を病んでいた。胃が悪くなったのは精神的ストレスのせいであろう。芥川龍之介は、自殺にまで追い込まれるほどの病が進行してしまった例である。
どうも一般的に言って、芸術家なるものはみんななにがしか狂気を抱えているものなのではないかという“常識”があるような気がするほどである。
たとえば絵画におけるゴッホとかダリとか、音楽におけるモーツアルトだとか、枚挙にいとまがない。天才と狂気は紙一重、みたいな言われ方をする。
芸術家は要するに自己の感覚を至上のものとして、世に問うものであり、その作品が絵であれ音楽であれ文芸であれ、鑑賞に堪え得るものなら、世間の認知を受けることができる。
それが狂気であっても、鑑賞に堪えさえすれば、「芸術」たり得る。
そもそも芸術家は(とくに画家と音楽家は)、貴族のお抱えとしてスタートしているのだから、狂気だろうがなんだろうが、パトロンである貴族が満足すれば良かったのであろう。
文芸の場合も、フィクションはとくに作家の創り話であって、要はありもしない空想をこねくりまわして、本当の話らしく書いているものだから、まともじゃないとは言える。自分が億万長者でもないのに、あたかも億万長者になったかのような小説を書いても許されるのだ。つまりは嘘つきである。それでも鑑賞に堪えれば、世間の評価を受ける。
すなわち、文芸には根本的に狂気を孕んでいるのかもしれない。
しかしながら開高の場合の特異性は、その作品が精神変調とリンクしている点にあるのだろう。加賀乙彦氏はこう解説する。
「躁病性の輝くような、溢れるような緊張感の高い文体で生命の躍動感に溢れた世界を描くと同時に、鬱病性の虚ろな、抜け殻のような倦怠感を基調とする文体で物憂い疲労感に満ちた日常も表現するという、作品群の振幅の大きさ」(「開高健と躁鬱」『開高健 その人と文学』所収)
冒頭の小説『夏の闇』はまさに鬱の状態をそのまま描いたものだろう。私はそんな鬱のものなど読みたくなかった。躁状態の作品のほうがなんぼも面白かった。
しかし、その開高文学を、「躁と鬱の両極端があったればこそ、晩年になると珠玉になった」と評価する向きも多かったようである(精神科医・高橋英夫氏)。
そう言えることもあろうが、鬱状態を凝視し続ける恐ろしさにはいささか辟易を覚える。開高は、小説を書くために自宅に居て座っていると、鬱になってくるから、釣りと外国旅行に出かけることで鬱病の克服を図っていたのはおそらく衆目の一致するところで、 仲間秀典氏も『開高健の憂鬱』で、多くの評者の言葉を紹介している。
開高自身もあらゆる作品で自分の鬱を告白している。それで稼げるのだから良い身分だといえなくもない。彼はただのお調子者ではなく、元来が内面の苦しみにのめり込むタイプなので、心に奥行きが生まれ、作品にも奥行きが生まれたとは言えよう。
ただ、その鬱が度を超していると思われる。
* * *
新進作家としてデビューした頃、「たちまちもみくちゃにされるままとなり、三作目の『裸の王様」で芥川賞をもらったまではよかったが、あと『なまけもの』という一作を書いたきり、ひどい抑鬱症に陥ちこみ、ウイスキー浸りとなって、書けないばかりか、肝臓がへたばってしまった』(「頁の背後」『開高健全集 第22巻』)
「何年も以前のことになるけれど、ノイローゼになったのである。これは、はじめのうち、芥川賞をもらってドサクサさわぎに巻き込まれ、書キタクナイ、 書キタクナイ、と泣きつつ局部をおさえて逃げまわっているうちに、半真性になってしまった。
モノが書けないばかりか、頭もなんとなくかすんでにぶくなり、眠たげな蒙古系の眼をうっすらとひらいて町を歩いていると、いつもあまり明るく見えない世のなかが、なにからなにまでまっ暗に見えてならなかった。神経だけがむやみにささくれだち、つまらないことにそよいで分裂を起こした。」(『食後の花束』)
* * *
デビュー当時の開高は、サントリー宣伝部の花形社員で多忙を極めていたようで、そこへ望んでなったとはいえ芥川賞作家としての仕事も抱えるようになった。サントリーのトリスなどの宣伝コピー(たとえば「人間らしくやりたいナ」とか)は今日も名作の誉れ高いし、「洋酒天国」の編集者としての腕は今みても抜群だった。
言ってみれば持て余すほどの才能を絢爛と開花させていたのだ。
その上に日本文学を背負って立とうかという野望をひっさげて文壇に登場すれば、それこそ開高の言う「もみくちゃ」になって当たり前だった。
むちゃな生活をしたものだった。緊張と集中がそんなに続けられるはずもなく、食事も不規則で栄養が十分でなくなり、仕事柄酒に浸るチャンスがあるとなれば、鬱に陥ちいるのも当たり前じゃないかと言いたくなる。本当はまず開高は生活過程を正すべきであったのである。
それを酒に逃げ、愛人に逃げ、グルメに逃げ、海外に逃げ…あげく抑鬱状態になった自分をひたすら見つめてどうする、ということなのだ。
開高の場合は、真性の鬱となって終生苦しめられることとなったようだが、決して医者にもかからず、薬も呑まなかったという。気力だけで「つきあった」というべきか。
彼の『輝ける闇』『夏の闇』『花終わる闇』の“闇三部作”の「闇」とは、鬱になって見つめる自分の心の闇なのであろう。
開高は、最後は食道癌で亡くなるのだが、これは酒とグルメの果てであった。外食で、しかも鯨飲馬食ばかりしていたことは、以前のブログで取り上げたことがある。ちゃんとした食事をして、昼夜逆転の乱れた睡眠をやめ、運動を怠らなければ、鬱に苦しむことは少なくなったであろうに。
《3》
『開高健の憂鬱』の著者・仲間秀典氏は「開高の告白にはまた、西洋近代小説の呪縛と苦闘する日本人作家の姿を垣間見ることができる」と述べている。
日本の小説家たちも、西洋近代の文学に漂う心の問題について無縁ではなく、ともに悩みを共有しているという認識があるというわけだ。
やや嫌みな書き方をすると、西洋人が精神病になるほどに悩みを抱えている状況を、日本人作家もいっしょになって精神病になるほどに悩みを抱えこんだのが、明治以降の日本の小説世界であったのである。
それで。
仲間氏は、そうした日本文学の事情を開高がそう書いているかを紹介している。
* * *
少なくとも第一次大戦後の多彩な精力と原理と情熱の噴出ぶりにくらべて第二次大戦後の西洋文学はひどく受胎力や勃起力を失ったように見受けられる。バスに乗り遅れてはいけないと思って私はつぎからつぎへ輸入、翻訳される作品をノミとりまなこで読んできたけれど、感想を野蛮に短くつづめてみると、おもしろくないのである。
新しい試みだと思わせられるものがあって読みにかかっても、すぐに、ああ、これはいつかどこかで読んだと思ってしまうのである。新しい本を寝床に持ち込んで第一頁を開くときのたのしさ、未知数性だとか、謎だとか、冒険、鮮烈、新しい開花、とつぜん活字の群れのなかに白い窓がひらいて風が吹き込んでくるような感触、あるいはキラキラ輝く暗い淵をいきなり覗きこませられるような不安などをおぼえることがほとんどなくなった。
本の腰や最終頁の解説文にはおごそかな主張や神話的託宣があふれているけれど、作品そのものは退屈でならない。隙間風がいたるところから入ってきて心を冷ましてしまう。
(開高健『告白的文学論』)
* * *
仲間氏は開高の著作からたくさん引用しているが、これだけでも十分であろう。
開高は「気分的述懐」を延々と漏らしているにすぎまい。引用した箇所を見るだけでも分かるように、文章の絢爛たる修辞と饒舌な物言いには感心するが、いささかも論理的ではないからだ。
開高は芥川賞をもらった作家としてのデビュー当時、たしかにこれまでの日本文学がいささかもその文章を支えるものが論理性でないことを指摘し、自分は文章を論理が支える小説を書いてゆくのだと宣言したのだった。
その意気やよしと、私は開高に期待したが…。
しかし開高は、当時の日本社会というものも、ヴェトナム戦争も、心の闇についても、論理的に捉えることに失敗した。
そして最後の絶筆となった『珠玉』ではついに好きな愛人に小水をかけてもらう性行為を書いて、自分の文芸の出発点も、また解決を求めて苦闘してきたものは「女だった」と呟いて、それをひとつの到達点であるかにしたためてこの世から去った。
あんた、それは違うんじゃないの?と私は情けなかった。
言わせてもらえば、開高がいうところの第二次世界大戦後の文芸が面白くなくなった理由は、もっと論理的に究明すべきであったのだ。
文学の力が衰えたという事情はいかにもあったであろうが、それを論理的に究明するのならどうしても、弁証法と認識学との研鑽が必須であるのに、開高にそれを教えてやる周囲の文学界は存在しなかった。
あの読書家としては日本で最も本を読んだらしい、開高の親友だった谷沢永一氏も、完全スルーした南郷継正の著作の中にしか、開高が本当は求めてやまなかった答えがあったのに…。
『なんごうつぐまさが説く看護学科・心理学科学生への“夢”講義(4)』(現代社白鳳選書)には、「認識の成立の過程性を説く」として、心理学がどのように人類に誕生してきたか、その発展史を見事に捉えてある。
ここを真摯に学ぶことのなかにこそ、開高が己が文学の支えとすべき金の鉱脈があったのだ。
むろん、「“夢”講義」は開高の死後刊行された著作ではあるが、『武道の理論』や『武道講義』の連載なら生前に読めたものを…。
それからもう一つ。
これは私の勝手な推測であるが、第二次世界大戦後の西洋文学が面白くなくなったわけは、第二次世界大戦(第一次大戦もそうだが)が八百長の戦争だったことと無関係ではあるまい。
戦争の論理性が作家たちにはつかまえられなくて当たり前なのではなかろうか?
例えば、ロスチャイルド家の初代マイヤー・ロスチャイルドの夫人グートレ・シュナッパーはこういっている。
「息子たちが戦争を望まなかったら、戦争は一つも起こらなかったでしょう」と。
ロスチャイルド家の初代マイヤー・ロスチャイルドは息子5人をそれぞれロンドン、パリ、フランクフルト、ウイーン、ナポリに配置させて、その国の王権から財政・金融を奪取していった。そのために戦争は引き起こされたからである。
その根本を抑えない学問も芸術も、すべては対象に肉薄するにあたって隔靴掻痒にならざるを得まい。
レストランの料理がまずいとすれば、それは第一に経営者の責任であるのに、料理人の腕や素材や食器の善し悪しなどをあげつらってもしょうがないようなものだ。
開高だけではなく、大江も石原も三島も、みんな捉えそこねた文学でしかなかった。作家としては晩年の林秀彦氏だけが、捉えかけたのみである。
《4》
開高健は自分の鬱病を医者にもいっさいかからず、薬にも頼らずに治した…のではなく、開高流の言い方をすれば「うっちゃった」のであった。薬には頼らなかったとはいえ、アルコールには頼りっぱなしだったが。
まして開高は無類のタバコ好きであった。若年のころからヘビースモーカーだったようだ。私はタバコはいっさい吸ったことがないのでよくはわからないが、紫煙をくゆらせている「至福の時間」というものは、内面との対話には格好のおもちゃなのではないか。激しい運動をし、外界を反映しながらではタバコは吸っていられない。勢いタバコは静止してじっくり内界の反映(心のなかでの自問自答)を促しているかのようになる。
だから鬱というものを、ある種仮病でやっている人にとってタバコはそれにどっぷり浸らせてくれる薬にもなってしまうのではないか。
『開高健の憂鬱』の著者・仲間秀典氏は、開高の精神病についてこう説く。
「開高のこのような性格特性を考慮すると、彼の五十八年十一ヶ月の生涯のなかで、躁鬱の双方の病相の時期が存立したと推察すること、言い換えると躁病を一つの病相として含む双極性躁鬱病と診断することは、臨床的に十分可能である。
前者はこのような躁と鬱の並存を基盤とした仮説であり、『輝ける闇』を執筆する数年前に軽躁状態に陥り、行動意欲が高揚して頻繁に海外旅行を試みたとする推論である。開高が一生のなかで鬱状態と軽躁状態を数回繰り返したとみなす山田和夫は、彼を典型的な「内因性躁鬱病」と診断している。」
開高は躁期と鬱期で作品を書き分けていたらしいのだ。その時期がどうなっていたかは、仲間氏の著作に詳しい。
さて、私は作家・開高健は本当はどうやって鬱状態から(薬を使わずに)脱出すべきだったかを最後に書いて本稿を終わらせたいと思う。
開高を評した作家や評論家は共通して指摘することだが、小説を書こうとして部屋に閉じこもって原稿用紙に向かっているときは、気分が鬱になるのである。そこで彼は戦争ルポを書くためや、釣り竿片手に世界中の海や河を渡り歩いたのだが、その間は見事に鬱から抜け出ているのである。
取材とルポを書き終えて、また本業のノンフィクションを書こうと机に向かうと、鬱に襲われる。その繰り返しだったようである。
開高は書いている。
* * *
……石川淳氏と会って酒を飲んだとき、バクチでもいいから手を使えと孔子が言っているぞ、と聞かされたことがあります。……これがその夜の私にはたいそうひびき、いまだに忘れられないでいます。ヒトの心のたよりなさ、あぶなっかしさ、鬼火のようなとらえようのなさをよく見抜いた名言と感じられたのです。
孔子が太古の異国の哲学者というよりは現代の最尖鋭の精神病理学者のように感じられたほどです。現代人は頭ばかりで生きることを強いられ、……これでは発狂するしかありません。発狂か、自殺か、または、そうでなくても、それに近い状態で暮らすか……孔子のいうようにバクチでもいい。台所仕事でもいい。……手と足を思い出すことです。それを使うことです。私自身をふりかえってみて若くて感じやすくておびえてばかりだった頃、心の危機におそわれたとき、心でそれを切り抜けたか、手と足で切り抜けたか、ちょっとかぞえようがありません。
落ち込んで落ち込んで自身が分解して何かの破片と化すか、泥になったか、そんなふうに感じられたときには、部屋の中で寝てばかりいないで、立ちなさい。立つことです。部屋から出ることです。
(『知的経験のすすめ』)
* * *
鬱から抜け出すのに、手と足を使えとは、まあいい線はいっている。実際、開高はそれで自分をある程度治したのだろうし、部屋から出てもまた部屋に戻ってくるから、同じことの繰り返しだったとしても、当たらずとも遠からずの正解には近かった。
孔子が鬱の治し方を言ったかどうかは定かではないし、石川淳氏も半端なことを呟いたものであった。
開高が自宅の部屋にたれ込めて小説を書こうとすると鬱に襲われるというのは、一つには結婚した相手が悪すぎたせいもあろうし、だから開高が何人も愛人をこしらえて逃げたせいもあるが、それはこの際、どうでもいい。
精神病の原因を考える際に、大事なことはあくまで認識とはいかなるものか、という学問としても捉え方である。
認識は対象の反映であるというのが、認識形成の原理である。だから開高が鬱になるのは、まずは外界の反映に依るのだ。
開高が海外へ出かければ反映が強烈に変わるから、認識が大きく変化するのである。だから毎日嫌な奥方と顔を突き合わせていなければならない自宅にいれば、反映したくない事物事象を24時間反映してしまうから、(簡単に言えば)憂鬱になってくる。海外へ出れば、もしかして愛人ともおおっぴらに逢えるし、同伴もできようし、異国の風物に接してウキウキした感情のままに反映するので、憂鬱は解消されるのだ。
それと孔子が言ったとかいう「手や足を使え」というのも、これは末端の感覚器官を磨くからである。自宅にいて、ゴロゴロ寝転んで、酒とタバコの日々を送っていれば、手も足も使わなくなって、感覚器官は極端に鈍くなり、だから外界の反映も悪くなり(反映しなくなり)、自分の内界の声にばかり耳を傾けるようになる。
ただし「バクチでもいいから」はお粗末な譬えである。何もしないよりいいかもしれないが、本当は意図的意識的にこれまでやったことがないような手と足の動きをすることなのである。
開高が趣味とした釣りは、やらないよりいいレベルである。河の中を移動するのは多少運動にはなるが、河の中でじっとしていなければならないから、あまり運動にはならない。
海での釣りは船に乗るだけで動かないからダメだ。とはいえ、作家として机の前に座り続けてまったく運動しない生活をしている職業の御仁にはそこそこの運動にはなったのだ。
だから開高は海外に出ると鬱が軽快した。
ここでも開高は、惜しむらくは、いささかも論理的にはならなかった。ただ己の経験と感覚に頼っただけである。
開高は「台所仕事でもいい。……手と足を思い出すことです。それを使うことです。」と言いながら、実際は台所仕事はやらなかったようだ。嘘はつくなよ、である。
自分で料理でも作れば、もうちょっと鬱で苦しまなくて済んだのに。あろうことか稀代のグルメになって、他人が凝りに凝った料理にいい気なって舌鼓を打ったために、鬱も治せなかったし、短命で終わってしまったのだ。
それから開高は晩年、背中の痛み「バック・ペイン」に悩まされて、水泳を始めたようだが、水泳で体調は整えられても、体の歪みは治せまい。部屋にたれこめてじっと座っているよりは遥かに良いけれど。
内臓の疾患が彼の言う「バック・ペイン」になっていた可能性もあったのだろう。
晩年は鍼灸にも通って治そうとしたとエッセイに書いていたが、鍼灸師に治せる技量がなかったか、いくら治そうにも彼自身が宿痾たる「憂鬱」を抱えていたのでは、どうにもならなかったのか…。
最新刊の「綜合看護」に南郷先生が「“夢”講義(51)」で説いておられるが、ラジオ体操のほうが「整体」には良かったのではないかと思う。
みなさんもラジオ体操は毎日1回はやって「整体」したほうがよいのです。岡目八目さんにうかがいましたが、夜ラジオ体操をやってから寝ると良いそうです。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。