| Tweet |
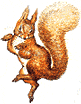
2009-12-04 19:06:05 映画「沈まぬ太陽」については、すでに次の二つのエントリーで取り上げた。 人間の誇り守り抜く/映画 沈まぬ太陽をみて 山田 敬男【しんぶん赤旗】 「不毛地帯」の方はというと主人公の壱岐正のモデルと擬せられている瀬島龍三について次のエントリーで取り上げている。 <瀬島龍三の訃報に寄せて>住む時代、住む世界が変わっても暗躍体質は死ぬまで変わらず。 上記エントリーでは、壱岐正のことを小説の主人公というよりも、瀬島龍三その人として人物評価をしてしまったように思う。この種小説の主人公はややもすると、完璧に近い人格を兼ね備えた人物になりやすい。その上、小説の主人公であるにもかかわらず壱岐正=瀬島龍三と考え違いをしたきらいもある。「不毛地帯」はノンフィクションではなくあくまでもフィクションであることをついつい、失念してしまったのだ。 フィクションとしてこのドラマを観るとやはり面白い。毎週次回はどう展開するのだろうかと気になって仕方がない。だが戦闘機の売り込み場面で「ラッキード」とか「グラント」などの社名が飛び交うとフィクションなのだと言い聞かせても、どうしても「ロッキード」と「グラマン」を思い浮かべてしまう。 そして連想ゲームではないけれども、大本営参謀の壱岐正が終戦後はソ連軍の捕虜となってシベリアに連行され、1956年まで抑留されていたことと関連して、いま高杉一郎さんの著作を三点購入して読みふけっている。 「極光のかげに―シベリア俘虜記―」(岩波文庫)、「征きて還りし兵の記憶」(岩波現代文庫)、「わたしのスターリン体験」(岩波現代文庫)―――以上の三点だ。 高杉さんの抑留体験記で特徴的なのは、単に過酷な強制労働が書き連ねられているだけではなく、この種著作には珍しく、ソ連をできるだけ客観的に見ようとしていることである。それは高杉さんが戦前、雑誌「改造」の編集者だった前歴から来るものかも知れない。それでも、事態をあくまで公平、冷静に見ようとする客観的姿勢には驚かされる。 ブラーツクでは高杉さんは事務能力の高さを買われて収容所の事務所で事務処理を手伝っていた。ある日のこと高杉さんはブラーツクの街頭でこんな経験をする。 >「君、プーシキンを読んだことがある?」 また3人いる女性事務員のひとりである通称マルーシャとの交流は、プラトニックラブ小説の一場面、一場面であるかのようにほのぼのと描かれていく。 また収容所で俘虜の管理にあたる所員たちの一人一人が個性豊かに描かれる。虐待だけをこととするかに見えたごりごりの共産党員が、実はそうではなくて、人間味を見せることがさりげなく語られていく。 逆に日本人俘虜の醜い、利己的な動きも包み隠さず語られる。全体として見ると理不尽で過酷な体験であったはずの抑留生活がこれほど客観的に語られることは希有である。ロシアはこんなにひどいと否定的なことだけを書いておけば戦後日本でのうけは良かったのではないかと思われるのに…。 編集者として親交のあった宮本百合子を帰国後はじめて訪ねていったときのことを高杉さんはこう語る。 > 宮本百合子が私のシベリアの話を聞きおわったころ、彼女の部屋の壁の向う側が階段になっているらしく、階段を降りてくる足音が聞こえた。その足音が廊下へ降りて、私たちの話し合っている部屋のまえまで来たと思うと、引き戸がいきおいよく開けられた。坐ったままの位置で、私はうしろをふり向いた。戸口いっぱいに立っていたのは、宮本顕治だろうと思われた。雑誌『改造』の懸賞論文で一等に当選した「敗北の文学」の筆者として私が知っている、そして宮本百合子が暗い独房に閉じこめられている夫の目にあかるく映るようにと、若い頃のはなやかな色彩のきものを着て巣鴨拘置所へ面会にいったとはなしていた、そのひとだろうと思った。 > やがて彼は戸を閉めると、立ち去ってゆき、壁の向うの階段を上がってゆく足音が聞こえた。私は宮本百合子の方へ向きなおったが、あのせりふを聞いたときの彼女の表情はもうたしかめることができなかった。 もちろん戸口に立っていた人物は夫の宮本顕治氏以外の誰でもない。後の日本共産党の自主独立路線からは想像することができないほどのスターリンへの傾倒ぶりである。高杉夫人の妹は大森寿恵子といって宮本百合子の秘書になり、百合子の没後に宮本顕治が再婚した女性である。しばらく後には、宮本顕治と姻戚関係で結ばれることになるのだから、これは高杉さんにとってその後思い出すのも辛い記憶になったことだろう。 その後、宮本顕治がこのときのおのが不明を高杉さんにわびたかどうかはどこにも書かれていない。おそらく何のわびもなくそのままになったことと思われる。すごく悲しい。 とにかく高杉さんの記述はあくまで淡々と、高ぶりもなく、続いていく。しかも文学性の高さが伝わってくる。このエントリーを閉じるにあたって「極光のかげに」の「小序」にフランス文学者の渡辺一夫さんが書いた一節を引用しておこう。 『極光のかげに』は、少くとも僕の疑問に答えるものを持っていたし、全体の印象として、他のシベリヤ俘虜記に勝るとも劣らぬ公平率直なソヴェート・ロシヤ見聞記のように、僕には受取れたのである。いかなる制度にも長短はある。そして、その制度での人間の優劣賢愚によって、制度は生きもし死にもする。こんなことを僕は証明されたように思った。党員のなかにも愚劣な人間がいて、制度の短所を一身に集めているかと思うと、実にほれぼれするような人間的な党員もいる。そして、非党員のなかには、新らしい制度に納得がゆかぬながらも、巧みに制度から利己的な甘い汁のみ吸おうとする人々もいるし、今更新らしい制度に希望は持てないにしても、周囲にいる人間に対する愛情を生かして、下積みの苦しい生活を静かに送っている人々もいる。ドリュオンの言葉を使って僕は僕なりのことを言えば、「人間のどす黒い血は、清められねばならず、明るく澄んだ血にせねばならない」ということになるが、これは、単に制度の変革だけから為され得るものではない。各人の人間性の優秀さを形成することにも、重大な能因をもとめられるべきであろう。アンドレ・ジードが、「制度か人間か」と度々悩んだことは周知のことであるが、「制度及び人間」という形に問題を置きかえねばならぬのではあるまいか? 『極光のかげに』は、こうした僕の願いを裏附けてくれたように思えてならない。
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10403582169.html から転載。
gataro-cloneの投稿
「不毛地帯」からシベリヤ抑留体験記の「極光のかげに」へ/高杉テーマ:戦争責任(歴史)一郎さんのことなど
山崎豊子さんの小説を映像化した作品二つがいま注目を集めている。ひとつは映画「沈まぬ太陽」であり、いまひとつはフジTV系で放映中のドラマ「不毛地帯」である。
「映画『沈まぬ太陽』公開 JALがマスコミに圧力か 【週刊金曜日】」「極光のかげに」は高杉さんが最初に収容されたラーゲリからアンガラ河畔のブラーツクという町に移されたところから始まっている。ラーゲリでの強制労働ですっかり消耗しきった高杉さんは、この町でソ連の抑圧体制の中でも、プーシキンやチェーホフが描き出した古き良きロシアが失われずに息づいていることを見い出し感動する。
>「『エウゲニイ・オネーギン』は、僕の好きな本です」
>背の低い男は、黙って手をさしのべると、私の手をかたく握った。・・・十ルーブリ紙幣を二枚取り出すと、私にわたそうとした。」
>「僕に?何のために?」
>「プーシキンのために。それで煙草を買いたまえ」「征きて還りし兵の記憶」は4年後に帰還した高杉さんを待ち受けていた日本での戦後体験が綴られている。ソ連を賛美も否定もしなかった客観的著述の「極光のかげに」は左からの激しい批判にさらされる。ソ連こそ万国労働者の祖国、ソ連賛美一色で染まっていた当時の日本の左翼世界では当然といえば当然の反応だったかも知れない。
> 宮本百合子が、坐ったままの場所から私を紹介した。雑誌『文藝』の編集者だった、そしてこのあいだ贈られてきた『極光のかげに』の著者としての私を。
> すると、その戸口に立ったままのひとは、いきなり「あの本は偉大な政治家スターリンをけがすものだ」と言い、間をおいて「こんどだけは見のがしてやるが」とつけ加えた。私は唖然とした。返すことばを知らなかった。
<参照>
高杉一郎(Wikipedia)
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。