| Tweet |
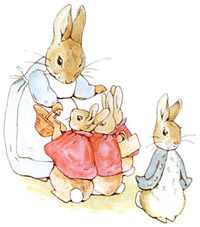
http://jcj-daily.seesaa.net/article/126214993.html#more
| 【日本人の好きなキーワード】 特別に「いま」と「ここ」を尊重する心情とは別に、『「昭和」を点検する』(保坂正康+半藤一利の対論/講談社現代新書)では、編集部が対論の前に用意したのが、次のキーワードであった。つまり「世界の大勢」「この際だから」「ウチはウチ」「それはおまえの仕事だろう」「しかたなかった(しょうがなかった)」の5つである。 どれも、日本の社会でよく聞かされる言葉である。だがそれは同時に、昭和という時代を動かし、歴史を左右する重要な局面で “軍部や国家の意思決定”として作用した言葉でもあったのである。 この編集部提案に対して半藤一利氏は、次の言葉で大方の日本人の気持ちを表せるのではないかと答えている。それらは「せめて」「いっそ」「どうせ」で、他に「なまじ」や「ままよ」を加えてもいいという。いずれも外国語に翻訳するのが非常に困難で、それこそ流行歌・歌謡曲などに頻繁に使われてきた、日本人の心情にぴったりくる言葉群である。 【受け身で始めた戦争】 対論が始まるとまず、5つのキーワードがいずれも受け身の言葉だという認識で二人は一致する。戦争初期に連戦連勝をしてから、あるいは戦後になって、「あの戦争は、植民地支配打破やアジア解放の聖戦だった」という人がいるが、『開戦の詔書』にはそんなことは一言も書かれていない。詔書には「中国は当方の真意を理解しようとしない。蒋介石は米英の庇護を恃んでみだりに東亜の平和を攪乱するし、米英は友好の精神なく不当な圧迫を日本に加えてくる。もう我慢できないから日本は自存自衛のため決然と起つ」という趣旨だけで、早い話が“堪忍袋の緒がきれた”というだけである。 “自存自衛のためにやむなく米英と戦う”というのは、「しかたなかった」ということでしかない。日本を戦争する国にしたい靖国派の人びとがいう「東洋平和のため」という言い分がいかに事実とかけ離れたものかという証拠に、緒戦後の快進撃に気をよくして、1943(昭和18)年の1月の大本営会議や4月の御前会議では、占領地の帰属を「いずれこの島々を全部日本の領土とする」と決定している事実を挙げておこう。 太平洋戦争の日時に=“欧米の植民地支配の打破”が少しでもあるならば、当時日本が植民地としていた「台湾」と「朝鮮半島」をまず解放するのが筋であり、己だけでできる施策であった。自分が植民地を抱えながら“植民地体制の打破”を主張できるはずがない。そんな理屈は支配層や軍部の念頭にもなかったのは確かで、どうみても“アジアの解放戦争”論は成り立たない。「世界の大勢」といっても、日本は1933(昭和8)年に国際連盟から脱退して“世界の孤児”になり、大切な国際債報が途切れてしまった。もともと現状の客観的分析や大局的・長期的な戦略の立案が得意でないのに、その上情報が不十分では、見通しや分析・方針・判断などがどれほど実態からかけ離れた(自己本位な)ものになるか、想像がつこうというものである。 【中国を支援したドイツ軍事顧問団】 日中戦争でも、陸軍上層部では“いずれ対ソ連戦になる”という一致をみながら、手順の点で「国防力増強論」を説く皇道派と「対支一撃論」主張の統制派が事ごとに対立し、結局、対支強硬派が軍の主導権を握って日中戦争に突入する。中国は弱いから戦争はすぐに片付くという統制派の予測ははずれて、国民政府は諸外国の援助を受けて長期持久戦に持ち込む。アメリカが一貫して蒋介石を支援したことは周知のことだが、後に日本と同盟を結ぶナチス・ドイツも国民政府軍に軍事顧問団を送り込んでいた事実は、日本国民にはほとんど知られていない。 戦況が好転しないので「蒋介石を相手にせず」の方針を決め、傀儡政権として汪兆銘を擁立するが、蒋介石の国民政府軍と毛沢東指揮する中共軍が手を結んで抗日統一戦線が成立して、日本はさらに苦境に立たされることになった。 【日米の長期戦は考えていなかった?】 太平洋戦争直前でも、アメリカの実力を無視した南方武力作戦に批判的だった連合艦隊司令長官の山本五十六も、対米戦の方針が決定したとき、「最低1年は暴れてみせる」と言ったのは有名な話である。彼が1年と言ったのは、その当時日本に石油の備蓄がちょうど1年分あったからだとされている。その後はどのような目算があったのだろうか。東南アジアの石油産地を占領するしかない、と考えていたのである。 日本の軍指導部のかなりの部分に、その当時のヨーロッパではドイツ軍が優勢で占領地を増やしていたから、米英もその対応に勢力をとられて苦慮し、日米戦はそれほど長続きせずに終わるだろうという、まるまる“他人頼み”の、なんとも虫のよい読みがあったと言われている。 長期戦を考えていなかった典型例を、太平洋戦争開戦からしばらくした時期の実際として、半藤一利著『昭和史(上)1926~1945』から引用する。 《こうやって、戦争がはじまりました。とにかく緒戦は威勢がよかったのです。連合艦隊は勝利に次ぐ大勝利ですからまことにいい調子で、軍令部などが万が一を恐れおののいてハワイ作戦に反対したことなど忘れて、毎晩、ハワイ、マレー沖の凱旋を祝って赤坂や新橋で宴会を繰り返していました。(略) いや、最初から長期戦になることはわかっていたはずなのに、そうしたくない思いのほうが強いものですから、「したくない」が「ならないだろう」の思いに通じ、最後は「長期戦にはならないのだ」と決めつけてしまって、第二段、第三段作戦を考慮の外においていたのです》(p397~398) 【肥大化する“思い込み”】 特に最後の部分で説明されている「したくない(してほしい)」→「ならないだろう(なるだろう)」→ 「きっとならない(きっとそうなる)」という思考バターン――希望的観測から始まった“願望”が、自然発生的に強力な“確信” へ変化しはじめ、それは間もなくゆるぎない“信念”にまで成長して、それ以外はまったく考えられなくなってしまう構造は、現在でも日本人の心情の特徴として数々思い当たるであろう。 この思い込みからスタートした発想は、現在でも各種スポーツの国際大会やオリンピックの度ごとに飽きずに繰り返されている。スポーツ試合がいくら筋書きのないドラマでも、勝利の女神だけに頼るわけにはいかない。記録や実績など一定の実力が必要だ。しかし〈願望〉が〈信念〉に肥大化するのは、根拠や裏付けなしの思い込みだけだから、予測は期待はずれるになる可能性が強い。 特に日本では、メディアが率先してこの思い込みパターンで煽り立てる。勝手に騒がれる選手やチームこそ迷惑で、不相応な期待を負わされて実力を発揮できないまま、結局は“贔屓の引き倒し”に終わることが多い。
いつの場合でも、国家間の駆け引きや、その極限としての安全保障や戦争を考えるときには、太平洋戦争当時の政治指導者や軍の責任者などの考えや具体的な行動を知らずに、気楽に論じたり気分で支持したりするわけにはいかないことが、理解されるであろう。判断次第では正に“取り返しのつかぬ問題”になることを、歴史が証明しているからである。 (つづく) |
| 拍手はせず、拍手一覧を見る |
| 拍手はせず、拍手一覧を見る |
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。