03. ���엲 2013�N3��01�� 20:51:53
: 3bF/xW6Ehzs4I
: W18zBTaIM6
�����i1936�j�����̖閾��
�@�������₻�̎x���҂ɑ���T�m�̈��|�I�����́A�����̍ŏ��̈ÎE�̐����O���炷�łɎn�܂��Ă����B�ߑO�T���A�{�����]���͓����k�����̎���ŁA���t�c�̏��тɂ���ėh�蓮������Ėڂ��o�܂����B���̏��т́A���t�c�̂T�O�O���̎m���ƕ��m���������������Ă��łɕ��c���o�����A����ȏ�̏���������ɑ����Ă���A�Ƃ̖����̎R����т���̒m�点�������Ă��Ă����B�{���͗����オ��ƁA�������ɖ߂�A�R����тɁA���m�ɔ�������߂����A���c�ɖ߂�����悤�A���̏��тɖ��������B �@ �u�������A������x��ł��v �Ə��т͓������B �@ �u�őP�������v �Ɩ{���͖������B�����ēd�b�Ɍ������A�������i�ߊ��ƁA�V�c�̐Q���̋߂��ɍT���Ă���{���̖�ΔԂ̎��]�ɓd�b���������B��l�Ƃ����������Ă���A��������̂Ȃ��ԓ��������B�{���͎Ԃ��ĂсA�{�����������B���̓r���A�c���̂������ɂ���p����g�ٕt�߂ŁA�قڈꒆ���̕��m�����Ƒ��������B�ނ́A���̕��m�����̌R������A���s�̋߉q�����̋{���q�����ł͂Ȃ��A�ނ̖����̑������t�c�̔��������Ɣ��f�����B�����ނ́A�Ԃ��~�߂Ĕނ�ɂ�����m���߂悤�Ƃ͂��Ȃ������B �@�{���́A�ߑO�U���A���{�ɓ������A�T�m�����łɋN�����A�����ɕt���Ă���̂�m�����B�������ēV�c�ɉy������ƁA�V�c�͔ނɁA �u�����Ɏ������I��点�A���̍Ђ���]���ĕ��ƂȂ��Ȃ����v�A�ƍ������B�����ĂƂ��߂�悤�������B�u���]���A����݂̂��A���̎������N����Ɨ\�����A�Ă��Ă����ˁB�v �@�����̖����̂��Ƃ�z�������ׂȂ���A�{���͓������B �u���m�������͂����A�����݂�����A���ׂĂ��������V�c�̐��������E�̒��ɁA�ނ�̐��`��������ꏊ���݂��悤�Ƃ��Ă��邾���Ȃ̂ł��B�v(68) �@�،ˍK���݁\�\���O�܂ł͖q�����b�́A�P�T���O�܂ł͍֓�����b�̔鏑�\�\�́A�ߑO�T���Q�O���A���̍֓�����b���P�����ꂽ�Ɠ`����{�삩��̓d�b�ŋN�����ꂽ�B�،˂͑����ɁA�u�d�厖���ł��邱�Ƃ����Ƃ����v�B�ނ͌x�����ɓd�b����ꂽ���A�����R�ɕ�͂���Ă��āA�N������������ɂ͘b���Ȃ��ł��邱�Ƃ�m�����B �����Ŕނ́A���p�Ԃ̎Ԍɂɓd�b���A�����ɋ{��܂ōs���Ă������悤�ɗ��B���̎Ԃ̓�����҂ԁA�،˂́A�߉q�e���Ɛ������̃X�p�C�鏑�̌��c�ɓd�b���āA���̃j���[�X��`�����B �Ԃ���������ƁA�ނ͗p�S�[���A�����R���苒���Ă���Ǝv����n����I�āA����肷��悤�Ɏw�������B(69) �@�ߑO�U���A�c���O���ɂ���{�����̎����̊��ɒ������B�����Ŕނ́A���������邽�ߑ����̓d�b�����������A���̈�{�́A�U���S�O���̋��Â̐�������ɂ��������̂������B�d�b�ɏo�������́A�m���ɘV��l�Ƃ��̉Ƒ��͐Â��ɏA�Q���ł���ƍ������B�،˂́A�����������}�C�����ꂽ�É����m�����@�ɂ��邱�Ƃ��A�m���Ă������ǂ����ɂ��āA�ǂ��ɂ����炩�ɂ������Ƃ͂Ȃ��B�،˂͎����̓��L�ɁA�u�傢�Ɉ��S�����v �Ƃ̂L�����Ă��邾���ł������B(70) �@���܂��̓d�b�ŏo�������̏�����A�،˂́A�{�������ŁA�X�p�C�鏑�̌��c�̓�����҂����B�ނ́A�����R���m�Ɍ��₳�ꂽ���ɔ����āA�{���Ȃ̏ؖ�������ɁA�ߑO�V��������ƑO�ɁA�k���ł���Ă��āA�،˂���̎w����������B���̎�̌�A���c�́A�c���k�̖�Ɍ������̂ł��A�܂��A�C���Ƃ��Đ������Ɏd���邽�ߋ��ÂɌ����̂ł��Ȃ��A�������m�̐苒����n��̎���ɖ߂�A���̓���Ԃ��A�ߏ��Ƃ̉B��Ƃ���A�ʏ�̂悤�ɓd�b���������ƂŔ�₵��(71)�B ���c�͎@�m���Ă��Ȃ�������������Ȃ����A�ނ́A �u���߉�ȏ��j�j�݁v �Ƃ��āA�����m���̎��� �u��������ˎE�v �̃��X�g�ɂ������Ă���(72)�B���������ނ́A�����̋ߏ���ɐ��݂Ȃ���A�E���ȃX�p�C���������Ă����B�ނ͖،˂ƖȖ��ɓd�b�A�������Ȃ���A��ɂ͊댯���������ĊO�o���A�����R�̖�c���Ď����Ă����B �@�،˂́A���c�Ɏw�����o������A�c�����̒뉀������ĉ���A���{�̗T�m�̋��Z���������ɓ����Ă������B�����āA�T�m�̎������̊O�ɂ��łɏW�܂��Ă����A���]�����A����{���ȑ�b�A�L�c�����]���ɍ��������B�ނ�́A�،˂��d�b�ł��̏��҂����W�������̂��A����ɐV��������ނɗ^�����B����ɂ��ƁA���]���A�A�����A�����ē���b�A�̑S�����P������Ă����B�M������Ă���V�c�̑��̒��b�Ɠ������A�،˂͂��̌��T�ԁA�{��ɂƂǂ܂�Â����B�ނɂ́A�c���}���ق̗T�m�̎���������L�����s������ɁA���̏��Q�����^����ꂽ�B�ނ́A���̎��]�̕����̏������ɁA�z�c�������ĐQ���B�ނ́A�Q�S���ԁA���ł��V�c�̌Ăяo���ɔ����Ă����B(73)
�K�N��ӏ�
�@�Q��26���ߑO�V���A�쓇�����́A�����̐Q������悤�₭�K���ɍ~��ė��āA�@��̈�K���߂������R�m���ƌ��t�����킵���B�ނ�͗����ɁA�K�N��ӏ��̐��{��n���Ă����V�c�ɒ���悤�ɗv�����A���̎ʂ��̕����́A�苒�n��̂�����Ƃ���ɒ��肾����Ă����B�����ɖ��L����Ă����v�������́A���{�͓V�c�̎����̑S�ʉ�錾���A���R�͔h����`��P�p���A����܂ł̉A�d�́u��d�ҁv �ł����A����A����A�����ĉF�_�e����ߕ߂��A�T�m�̓����W�c�̏����͌R�E����Ǖ�����A�r�ؑ叫���֓��R�̎i�ߊ��ɂ��� �u���V�A���Ј����v�A�����āA�����͂��������v����V�c�ɒ���ɐ旧���āA�k�i�h�w���҂̐^��Ƌ��c����悤���߂Ă����B���̕����͂܂��A�������A�������œV�c���M������q����Ƃł���Ñ����Y�����A����сA�{��̉B�ꂽ�X�p�C�\�\�����R�l�����ɂ͒m���Ă��Ȃ������\�\�ł���R�������Ƙb���������Ƃ𐄂��Ă����B�쓇�����͂��������v�����d�X�����������A�������ł��邾���̂��Ƃ�����|�A�����B(74)
�@�ߑO8���A�C�R�R�ߕ������̕����e�����{���ɓ������A�������ܗT�m�ɉy�������B�ނ́A�e�͑��́A���{��C�R��n���瓌���p�ւƍq�s���ł���A�V�c�̍��߂ЂƂŁA�����R�n��ւ̖C���̏����������Ă���A�ƕ����B�����ē����ɔނ́A�V���t���ɑg�t���A�����R�ɏ��X�̏�����������悤�������悤�ƍl���Ă����B�����R�̑����́A�����e���̐e�����F�l�ł���A�ނ��]��ɉߍ��Ɉ����̂͗ǂ��Ȃ������B�V�c�͓��ӂ����̂��낤���H(75) �@����܂ŕ����ɂ͎^���ł��Ȃ����Ƃ���������A�܂��A�c�_�ɂ��������܂�Ă������Ƃ�m���Ă����T�m�́A���������������B �u���͊C�R�̏ɂ��āA�M�a�̕����߂��������B���̎����Ɋւ��鎄�̈ӌ��ɂ��ẮA���łɋ{���ȑ�b�̓���ɏq�ׂĂ���B�v �@ �u����ł́A����Ɏf���Ă�낵���ł��傤���B�v
�@ �u���̗v�]�ɂ��ẮA�ԓ��͂܂��̋@��ɂ��悤�v �ƗT�m�͕ԓ����A�����e���͑ސȂ����B��������Ȃ������́A��Z�ŏ܌M�ǒ��̖،˂̂Ƃ���ɒ��s���A���ׂ��̐e�������ɁA���̂��������̌���������悤�A�������B
�@�ߑO9���A�쓇�����́A�����R�Ƃ̌�������I��点�Ē����ɋ{���ɓ������A�V�c�ɉy�������B�ނ́A�����R���K�N��ӏ�# 1�̊������o���A�����V�c�ɐT�d�ɓǂݏグ���B(76) �@# 1�@�� �k�o�[�K�~�j�l �́A�K�N��ӏ��̌������ȉ��Ɉ��p����B���̐[���ŋ߂Â����ۂ́A�v��������Ȃ����߂ł���B�����āA����܂łɑ��݂���B��̖|��ł́A1936�N�Ƀj���[���[�N�^�C���X�̓����������œ��{�l�|��҂ɂ���ĂȂ��ꂽ�Ɠ��̕��̂����������̂ł���\�\����́A���{�ߑ�j�̐����̕����ɗl�X�Ȍ`�ň��p��Ă���\�\�B����́A�����̓��e�������ނ˂͕\�킵�Ă��邪�A�肪�������A���̎ܔM�n���̂悤�ȓ����͎����Ă���B �@�k�l�@�ȉ��ɂ́A�p���̖M��ɉ����āA�����̂܂܂̈��p���f�ځB(�������A�J�^�J�i�������Ђ炪�ȏ����ɉ��߁j �B �@�@�@�@�@�@�@�@�@���̂��쎝���钼�ڍs���̂��߂̎�ӏ� (77)
�@�i���̐_�A�V�c�ɁA���̓����̉��ɂ����X�́A�_���̎q�̂��܂Ȍ����ł���Ȃ���A���̕s���̈ӂ��o����B�䍑�̖{���́A�Ȃɂ����A��̂��Ȃ��P�ƍ��Ƃ̌p���I���W�̐��A�ƁA�V�̉��̑S�n���̕�܂ɂ���B�����̗D�G���ƍ��̂̑����͑̌n�I�Ȑ����ƁA�_���V�c�ɂ�鍑�̐ݗ��ȗ��A�����ېV���Љ�ϊv�ɂ����钍�Ӑ[���{��ɂ����̂ł���B���܂�ĂсA�����̏H�ɓ��B���A��X�͍L���O�n�̓y�ɒ��݁A�V���Ȍ����ւƂ̊�Ɍ�����i�W�𐋂��Ȃ�Ȃ��B �@��̊�@�I����ɂ�������炸�A�������킵���s痂̓k���J��̒|�̎q�̂��Ƃ����o���āA��X�́A�䗘��~�ɂӂ���A�瑊�Ȍ`���������čc�ʂ̑��������t���A���ׂĂ̐l�X�̑n���I�O�i��j�Q���A����{��ƔߒQ�̂����ɋꂵ�܂��Ă���B���{�͉v�X�ƊO���Ƃ̂��������Ɋ������܂�A���̒����ɉ���������A�O���̂�������̓I�ƂȂ��Ă���B���V�A�d�b�A�R���A�����A�����A���}���͊F�A�w���҂Ƃ��Ă��̍��̂�j��ɓ����Ă����B �@�i�����j�O��������A�����w�ҁA�������Y�}���A�t���I���c�����k�}�𐬂��ĉA�d����āA�C�t����Ȃ��܂܂ɁA�ł����������������Ă����B���̈����͌��œV�n���������A�������`����\������Ɏ����Ă���B�����c�̋]���I��i���i�����j�A5�E15�����̕��o�A�����̓��̑M���́A�ނ炪�Ȃ��ׂ����R�Ɣނ��Q���������R���܂�����������Ă���B �@���̂��̏I���Ɏ����Ă��Ȃ��A�͂��Ȕ��ȂƔE�ς̂��߂ɁA���x�ɂ킽���āA�����������̒n��G�炷�̂��B���Ă̔@���A���������A���邢�́A��~�ƕېg���ނ��ڂ��Ă���B����A���V�A�A�����A�p���A�����ĕč��Ƃ́A��G������Ԃɂ���A�_����_���A�䂪�����Ƒc��ȗ��̈�Y�̔j��̐��O�ɂ���B����͉������薾�炩�Ȃ��Ƃł͂Ȃ����B���ہA���O�ɂ͐[���Ȋ�@�����݂��A���\�c���△�\�Ɛb�����̂���̉����A�c�ʂ̐_���Ȃ�P����܂点�A�ېV��x�点�Ă���B�i�����j �@���t�c�̊C�O�ړ��̓V�c���߂���������A�E�E�E�������������݂炴��Ȃ��B�E�E�E�o���������A��X�Ɠ��u�̐��_�́A�{��̓��ǂ��A�t�����a�鎩��̓w�߂��ʂ����˂Ȃ�Ȃ��B��X�́A�P�Ȃ�Ɛb�ł���Ȃ���A�c�ʂ��M�����ꂽ�����Ƃ��Đ�����i�܂˂Ȃ�Ȃ��B���Ƃ��A��X�̍s��������̖��▼�_���Q�����Ƃ��A��X�ɂ��������̓��h���Ȃ��B
�@�����ߒQ�ƈӎu�����L�����X�́A���̋@��Ɍ��N����B�t�������A�����̐��`�𐳂��A���̐��n�̎q�Ƃ��Ă̎g����S�����A�䂪�S�g�S������̉ɓ�����B��X�͑�_�Ƒc��ɗ�q���A���̉��b�Ƃ������������Ƃ��B
�@���a�\��N��\�Z�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�K�N��ӏ��i�����j
�@�ނ�ň҂�ɉ䂪�_�F���鏊�Ȃ͖�����n����V�c�É��䓝���̉��ɋ�����̐�������𐋂����ɔ��h��F����������̍��̂ɑ����B���̍��̂̑����G��͓V�c�����_��������薾���ېV���o�ĉv�X�̐��𐮂֍�����ɖ��M�Ɍ��ĊJ���i�W�𐋂��ׂ��̏H�Ȃ�B �@�R��ɍ������ɕs痋����̓k�Əo���Ď��S��|��(�~)�ɂ�������̑������W�����G��V�ꓭ�������̐��������j�V���ēh�Y�̒ɋ���Ⴙ���ߐ��ĊO���O�����𒀂��Č������A�������V�A�d�b�A�R���A�����A�����A���}���͂��̍��̔j��̌����Ȃ� �@�ϓR�k���A���ɋ��瑍�čX�R�ɉ����铝�������Ǝ������n�匠�̙G�ނ�}�肽��O����������͊w�ً��ّ�t���c���̗��Q������ʼnA�d���炴��Ȃ����͍ł�����������ɂ��Ă��̟�V�̍߈��͗������{�^��栂֓���Ȃ�B�����A�������A�����c�̐��̐g�A�܁E������̕����A�����̑M���ƂȂ集�Ɍ̂Ȃ��ɔA�������x�����d�����č����������������ȂȂ��R���ˑR�Ƃ��Ď������|�ɋ���䑊����������Ƃ���B�I�A�x�A�p�A�ĂƂ̊Ԉ�G�������đc�@�␂�̍��̐_�F���ꝱ�j�łɑ炵�ނ�͉������薾���Ȃ�B���O�^�ɏd���}���ɂ��č��̔j��̕s�`�s�b���n�C���ňЂ��Ղ��ېV��j�~�������@����䌏�����ɔ��čc敂���� �@�������t�c�o���̑喽�Д������N����ېV���^�𐾂Џ}���̐g�̕�����������肵��s�q���̉䓙���u�́A���ɖ������r�ɓo���Ƃ��Ď����Ȃ݂ē��̖S��J�S�]�X�ւ���\�͂��A�N���̛@�b�R�����a�����Ĕނ̒����ӂ���͉䓙�̔C�Ƃ��Ĕ\���Ȃ��ׂ��B �@�b�q����ҍn����̐�Γ������ɂ��Đs������Δj�Œ��˂�|���ɗR�Ȃ��A䢂ɓ��J���u�@����ɂ����K�N���@�����n�ł��đ�`�𐳂����̗̂i��J���Ɋ̔]��⑂��ȂĐ_�B�Ԏq�̔�����������Ƃ��B �@�c�c�c�@�̐_�줙b���ΏƗ������𐂂ꋋ�͂Ƃ��B
�@���a�\��N��\�Z��
�@�T�m�͓ǂݏグ�����ӂ�ق��ĕ����Ă����B���̍��g�������t�ƕ��m�����_�̔w��ɁA�ނ́A�����̐푈����ւ̊��S�Ȕے�����o���Ă����B���̉B���ꂽ�A�܂݂��������`���ɁA�����������́A����̊O��I�����̊댯�̒��ÂƁA�ނ̐��͂����Ɖ����Ɠ��{�̓`���ł���f�p�ȏ�O�ւ̌��g��T�m�ɐ����Ă����B
�@ �u�������Ȃ�ł��낤�ƁA���͕s���ł���B�ނ�͂��̍��ɓD���ʂ����B���R��b�A�M�a�ɁA�����̒����𖽂���v(78) �ƁA�T�m�͗₽�������n�����B �@�쓇�́A���@��苒�������m�����ɗ^���邢���炩�̗P�\�悤�Ɠw�߂��B�������T�m�͐쓇�ɁA�c�ʂ����̎�ӂ��Ƃ������ƈȊO�ɂ́A�c�ʂɂ�邢���Ȃ铯��������̈ӂ����\�����Ƃ��ւ����B �����ߏ���(79)
�@�쓇���R��b�������̋ꋫ�ɂ��čl�����邽�߂ɑސȂ���ƁA�����ɗT�m�́A�R���Q�c�@�̂��ׂĂ̏����ƁA�X�ɖʉ���n�߂��B�ނ�͂��̓r��A���R�̔������ɂ���Ďx��͂������A�܂��A�c�ʂɎ���̒��������������������邱�ƂɓĂ�����������ނ�́A�S���A�܂��t����叫�̌��Ȃ��ڗ��������̒���������A�{��ɎQ�サ�Ă��Ă����B�T�m�́A���R�͔ނ�u�\�k�v ��������ĐӔC���ʂ����ƁA�ނ�ɂ��̈�_�݂̂����������B�������ꂪ�ł��Ȃ��̂Ȃ�A�C�R�ɖ��߂��o���A����ł����߂Ȃ�A���猻�n�ɏo�����ς�ł������B �@�V�c���A�Ӗ������R���V��Ɏ���w����^���Ă���ԁA�������@�Ŏw���ɓ�����Z���̎�菫�Z�́A�v���ɑ����҂��Ȃ���A����ɂ����āA�������]�������Đ₦�ԂȂ�����ė���㊯�����ɑΉ����Ă����B���ہA����͐M�����������Ƃł��������A�������@��߂��̗��R�ȁA�Q�d�{���ł̋Ɩ��́A���������������̌ˌ��̂�����Ƃ���ɗ����Čx������݂��Ă���ɂ��S��炸�A�����ɑ������Ă����B �@�ߑO10���A�Бq���k�������l�����\�\���B���ϓ����̓엤���̉��\�\���쓇�@�ɒʏ�A���C���ł���ė������A���������̕s���a���I�悵���B�Бq�����́A1934�N�̎m���w�Z������\�I����菕�����s���A���̍ہA���x�̔����ɎQ�����Ă��鑽���̎��m���𗠐��Ă����B�����܂ł��Ȃ��A���̂����̈�l�ŁA�����q���쐬�����镔�\�\�s���_�ȑޖ������ƂȂ����\�\���A���̔ނ̓��ւ̈ꔭ�̒e�ۂł�����}�����B�Бq�́A��Ƀr���}�ŕs�^�ɂ��A���R�̕ߗ��ƂȂ�A1944�N�ɎE���ꂽ �k����͌���1991�N���S�l ���A���̎��͐��ōς݁A�����B�ނ̓����̎m�������́A���̕����͓��R�̂��ƂƂ��Ď��A����ȍ~���A���@�ɏo���肷��K��҂͑������B �@���߁A�Ō�̌R���Q�c�����y�������������A�쓇�����́A�R���������{���̎��]���������甾���R�ւƔh�����A�ԓ���^�����B����͊ȒP�Ȃ��̂ŁA �u�V�c�͏��N�̈Ӑ}�͂������ɂȂ����B���R��b�͏��N�̓��@�̐^���Ȃ���̂�F�߂�B�R���Q������W����A���̂̕ێ������肳�ꂽ�B�v �@���̒ʒm�قǂ̒v���I�Ȃ��̂͂Ȃ������B���ɐ��܂����Ⴂ�����҂́A�ނ�ɑ���V�c�́A�X�̂悤�ȑԓx������������B�ނ�̔s�k�ł������B�����ނ炪�����ʂ̂ł���Ȃ�A�ނ�́A�Ō�̈�l�܂Ő苒�����ʂ����Ƃ��A�R���ɐ錾���邵���Ȃ������B �@�R���͋{��֓d�b�����B�ނ͑Θb�𑱂���ƌ����A�����̑������m�ꂽ�B�����Ă�����A��̍L����ؒ��卲�\�\�V�c�ɋ߂��l���Ƃ��Ēm���\�\�ƁA���t�c�i�ߊ��A�����b�卲�\�\�����̎w�����ɂ�����m���ւ̐ӔC���Ă����\�\���A���`�[���ɉ�������B �@�����A�����I���_�_�ɑ����Ƃ��Ēx�X�Ƃ��Ă���ԂɁA�T�m�́A�����ōō��̊e����c�����W���A���̌ߌ��ނ�Ƃ̑Ή��ʼn߂������B�܂�A�{��̂���ꎺ�ł́A�V�c�̗ՐȂ̂��Ƃɐ����@��c���J����A���̈ꎺ�ł́A�悤�₭�{���ւƓ����������t�t�����W�܂��Ă����B��O�̕����ł́A�R���Q�c�@�����W����Ă���A�k�i�h�w���҂̍r��^�肪�Q�����Ă����B���t�́A�V�c����A���c�\�\���̎��͂܂���������̒��ɋ����\�\�����������{�̌p���ɂ��Ė��ꂽ�B �@����́A�����ߌゾ�����B�T�m�́A���{�ɂ����鉽�炩�̕ω��́A�����ւ̈���ł��蔾���̐��ʂƂ݂�ꂩ�˂Ȃ����߁A�V�̎w���͂������Ȃ�����# 2�B����ɁA�R���Q�c���̐Ӗ����y�����邱�Ƃ��A���Ƃ����悾���̉��_���Ƃ��Ă��A�����]�܂Ȃ������B�����������c�ɂ��ǂ������A�T�m�͌��ݓI�Ȑ��{���ĊJ������肾�����B�]���Ă��̎��܂ŁA����̏����������A�����s�����ł���ȊO�A������̑��ɂ������Ȃ��Ƃ̎p�����ێ������B �@# 2�@���c�������Ă���Ƃ̒m�点�́A���������̓��̌ߌ㑁���T�m�ɒm�点�����̂Ɛ��肳���B�������A���苒�n�悩��E�o�ɐ��������ߌ�x���ɂȂ�܂ŁA���̑����̒m�点�͗T�m�̎��͂̋{��l�ɂ͒m�炳��Ȃ������B �@���t�́A������b�̌㓡���v���㗝�ɑI�B�܂��A�R���Q�c�@�́A���ɁA �u�������v �� �u���߁v ���R�ɔ����邱�Ƃɓ��ӂ����B�������́A�u���N�͓V�c�̒��ӂ����N���邱�Ƃ�]�݁A����͒B����ꂽ�B���N�̍��̂̌�����]�ސ^���Ȋ肢�͒��ڂ���Ă���v �Ƃ̂ݏq�ׂ��Ă����B���߂́A�u1935�N�x�̍��h�v��ɂ̂��Ƃ�A���N��̎t�c�̑������ƂƂ��ɁA���N��́A�����h�q�̂��߂̏���z�u�ɂ��ׂ��v �Ƃ������̂������B �@����A�����@�̌�O��c�ł́A�V�c����̒��ږ��߂��o�����ƂŁA�����R�����U������̂��悢�̂��A����Ƃ��A�����߂�錾���A�����̐ӔC�𗤌R�ɗ^����̂��悢�̂����߂����ē��c���ꂽ�B�T�m�́A���R�ȋc�_�̊O�����ێ����邽�߂̕K�v����A���Ӑ[�������݂̂ŁA����̔��������Ȃ������B�����Ŕނ́A�̂�ׂ����̍s�����N�����A�ȒP�ȕ֖@�ɏo���B���Ȃ킿�A�Q�O�Ȃ����R�O�����ƂɎ��]�������̖{�����ĂсA���������j���[�X�����̂悤�ɁA�u���R�́A�C�Ⴂ���݂��������̒����ɐ����������ˁv�A�Ɣނɐq�˂��B�������Ă��ɐ����@�́A���Ԃ闤�R�ɉ����߂������悤�������邱�Ƃɓ��ӂ����̂ł������B �@�ߌ�3���A���t�c��1935�N�x�ً̋}���Ԍv��ɂ��ƂÂ��A���m��h�q�z�u�ɂ����A���������������������m�Ɛ藣�����B�ߌ�5���A����̂Ȃ������̌��̌�A�R�������́A�̂��߂ɋ{���ɂ��ǂ����B���̍ہA�O���̔����R�m�������̐�����ɓ��낤�Ɣނɑ��������A�x�����ɂ���đj�~����˂Ȃ�Ȃ������B �@�R���̗��_���������A����{����b�́A�M���ɑ���Ɛb�͂��ׂĂ��̖�͋{���ɏh�����A�R���Q�c�@����Ɍ��肵�������߂����̐^�钆��蔭�߂���A�Ƃ̗T�m�̗v����`�����B�쓇�����͂���ɏ]�����Ƃ��m�����A�����߂����ʓI���ǂ������^�����B�ނ͓������b�ɁA�������t�ɗ��R���]�ސl���̃��X�g��V�c�ɒ��Ă��炦�Ȃ����Ɨv�]�����B����͂��̗v�]�S���ċ��ۂ��A������A�V�c�̑匠�̊��Ƃł���ƌ��ߕt�����B�쓇�����́A�u�T�������l�q�v �ŁA�����ߖ{���̐ݒu�Ɏ�肩�������B��p�C�R��b���A�ߌ�6��30���A�y����������A�b����t�Ǝb����w�����邱�ƂŁA�����̕s�����������Ă͂ǂ����ƒQ�肵���B �@�V�c�͂�������ۂ��A �u�������R�����ْ̋�����������Ɩ]�ނ̂Ȃ�A���t�ɂ��m������炢�����v �Əq�ׂ��B���̖�A�������@�̌ܖ��̔����R�m���́A�сA�^��A�r�A������A���Ȃ��Ƃ������̏����ƑΒk�����B���������㋉�����g�̓o��ł��A�P����Ԃ͑ŊJ�ł��Ȃ������B�����R�͐�̗v�����J��Ԃ��A�t���Ƃ���ĂȂ��悤�ɂƂ��������B �@���̖�A���t�́A��x�ɂ킽���ĉ��U�����B�ŏ��́A�ߌ�9���A�㓡�㗝�����t�����E��錾�����B����́A���ƓI�ȍГ��������ɍs����A�ʗ�I�ȑΉ��ł���A�V�c�́A������ʗ�I�ɂ�����p���������̂������B�u���a�ƒ����������܂ŁA�ނ���^���ɂ��̐ӔC���ʂ����ׂ����v�A�V�c�͌������B �@�������A����͂���ł͏I���Ȃ������B�V�c�̑O����ޏo�����t�������́A���̌ߌ�������ŋc�_���Ĕ�₵���T���̊Ԃɖ߂����B���̒��̈ÎE�ŕ|�������A�܂��쓇�����ɂȂɂ������̓��������āA�e���̎��\���Ƃ�܂Ƃ߂��B�ނ�͂��̒�o���ߑO1���ɍs�����B�T�m�́A����������ȊO�ɑI���͂Ȃ��A���ꂼ��̑�b�ɁA�u�V���t���g�t�����܂ŁA�����ɗ��܂�悤�v �������B�ނ͖��炩�ɁA�����Ă����B�ނ͂��̓��A���������Ă����B �@�T�m���g�̉Ƒ������A�T�m���댯�Ȃقǔ�Ë��ȑԓx���Ƃ��Ă��邱�Ƃ��Ă��Ă����B�����e���ƒ����e���́A�c����c�̊J�Â����߂Ă���A�T�m�̒�A�����e���́A�ނ�̌��������A�n�����炻�̉�c�ɎQ�����邽�߂ɌĂяo����Ă����B����b�鏑�̖،˂́A�����e���Ɠ��v玐e���̗����������邽�߁A���̗[���l�ƂƂ��ɉ߂����A�ނ�̒������Ċm�F���ĕ����B �@�������T�m�́A�Ċm�F������镵�͋C�ł͂Ȃ������B�ނ́A���̒����璅�Ă��邵�킭����ƂȂ����R�����܂������Ă���A�ߑO2�������O�A���t����o���ꂽ���\��ǂނ��߂ɍ������B�ߑO2���A�ނ͎��]�������̖{���ɓd�b���A�Q���ɂ���ނ��N�������B�u�쓇�����͎��\���o���A���̊t�����������B�ނ́A�N�������ӔC���ƍl���Ă���̂��ˁB����Ȋ��o�ŁA���������܂�Ƃ͎v����B�v �@�{���́A �u�a���͂��̌�ŁA�i�q�˂�ʂ�A�������̐Q���֓���ꂽ�̂��Ǝv���܂��v �ƁA�T�m�Ƃ̓d�b������̂��A���L�ɋL�������B
�����(80)
�@2��27���̖邪�������A���N����ځA��͂���̂́A�����͑����Ă����B�����߂͂��̖����A2��50���Ɍ��z���ꂽ�B�ߑO5���A���]�������{���́A�����e���̎��I�K��ɂ���āA�{���̊Ԃɍ��킹�̐Q��̒��ŁA�Q����ʖڂ��o�܂�����ꂽ�B�����͖{���ɁA���m���������钆�A�����@��K��A������������������Ƃ��ē���b�̒n�ʂ����߂Ă����ƕ����B�ނ��{���́A����Ɍ����͗^���Ȃ������B�ߑO7���A�T�m�̏f���A�����e���́A�T�m�̒�̍����e�����C�R�m���w�Z�ɖK�ˁA�T�m���V���t�𑁋}�Ɏw������悤�A�ނ̌㉟�������߂��B���������͂�������ނ����B
�@�{���ł́A���]�����̍T�����A�܂�œ���e���̗l�����Ă����Ă����B����̊t���A�����A�e���A��݂炪�Q���p�Œ��т⒃���Ƃ�A�Q�S�n�̈����������̌�A���ꂼ��̉�b�����킵�Ă����B�c���̖�O�ł́A�����R�̕������A��̒����s�������Ă����B�n���S�k�u�Ȑ��v �̂��Ƃ��l�� �u�������v �́A�^�s���~���Ă����B�r�W�l�X�X�Ⓦ���암�̍`�p�n��ɒʂ��ʋΐl�����́A�c�����ӂ̐苒�n�������邽�߁A���x����肩�����������Ă����B�T�m�͒x���܂Ŗ����Ă����B�����̃I�[�g�~�[���Ƌʎq�̂����Ղ�Ȓ��H�̌�A�ނ����ɂ͌��������̂́A8����9���̊Ԃł������B �@���]�������̖{���́A�V�c�ɒ��̈��A�����ɍs�����ہA�ނ̗����ȂقƂ���ӋC�Ɉ��|���ꂽ�B �u�����A�����̖\�k�������A���R�ō��i�ߊ��̖��߂ɂ������ɏ]��Ȃ��Ȃ�A���͎���A�ނ�̂Ƃ���ɏo��������肾�B�v �@����ɓ����Ė{���͌������B �u���ڍs�������̎m���́A�V�c�̕����ɏ���ɖ��߂�����ɏo���𖽂��܂����B����́A�V�c�̓�������Ƃ����Ƃł��B���R�A����͋����ꂴ�邱�Ƃł����A�ނ���s�������Ă��鐸�_�͍l���ɒl������̂ł��B�ނ�͊����Ɉ����I�m�M�ƍ����ɐ������v�z�ɂ���čs�����Ă���܂��B�ނ�̐S�ɂ́A�É������v���悤�Ƃ��A�É��̗͂����p���悤�Ƃ��ƍl����ς�͖ѓ�����܂���B�v �@���炭������A�T�m�͖{�����Ă�Ō������B �u�ނ�͎��̉E��ł���Ɛb�������E�����B�����������\�Ȃ�m���ɂ́A�����Ȃ�S�I���@�����낤�Ƃ��A���o�ٖ̕������肦�Ȃ��B���̍ł��M��������Ɛb��|�����Ƃ́A�^�Ȃ������Ď��̎���i�߂�ɓ������E�C���B�v(81) �@�{���͓������B �u�V�����Ɛb���E�����菝�����肷�邱�Ƃ́A�ň��̔ƍ߂ł��邱�Ƃ͌����܂ł�����܂���B�������A�ނ�͍���������͂��Ă�����̂́A���̂��߂ɍs���Ă�����̂ƐM���Ă���܂��B���ꂪ�ނ�̐M�O�ł���܂��B�v �@ �{���͓��L�ɂ����L���Ă���B �u���͂����A���낢���������@�ŕÉ��ɐ\���グ���B�v �@�T�m�́A �u���]���A���Ȃ��́A�ނ�̍s�����A�P�ɁA�������~�ɂ����̂��Ƃ������Ƃ��F�߂��Ȃ��̂��ˁv�A �Ǝ���ӂ�Ȃ��猾�����B �@�{���́A�ӂ��킵���ԓ����ł��ʂ܂܁A���L�ɂ��������Ƃ߂Ă���B �u���̓��͂܂��A�É��͂����ւ�V�Ԃ��Ă����łŁA�s��������������闤�R�̓w�͂́A�ǂ��ɂ������ʂƌ���ꂽ�B�����Ď��Ɍ���ꂽ�B�w��# 8�́A�߉q�t�c�ɖ��߂��o���A����A�����������������x�v(82)�B �@# 8�@ �u���v �Ƃ́A�����̂����Ă̍c�邪�p���� �u��X�v�B���̕\�ӕ����́A�V�̎��ɘb�������錎��\���Ă���B(83) �k���̐����͂��₵���͋r���̂悤�ɒ��҂��C�t���Ă���B �u���v �ɂ��ẮA�|��̑��̌��ł͂����Ă��̗p��͗p�����A �u���v �Œʂ��Ă���B�l �@���̓��͊ۈ���A�����͋ٔ��ɂ��炳�ꂽ�B���̂����A�T�m�͎��X�ɁA���Ȃ��Ƃ��P�R��͖{�����Ăт��A���R���s�����J�n�������ǂ�����q�˂��B�쓇�����ƘV�����̂قڑS���́A�c�����琔�n��k�ɂ��錛�����{���ɁA�����ߎi�ߕ���ݒu���鏀���ɒǂ��Ă����B�ߑO10��30���A�߉q�t�c�������R�苒���̖k���p�ɁA�����������Đw������B�܂��A���t�c�̒������ێ����Ă��镔�����A���̓쐼����ѓ쓌�n��ɔz�u���ꂽ�B�苒���̖k�����́A�c���̂��x�ł��������Ă����B���̓��̌ߌ�A�����R�͍c����قɉ�������A�����킹���l������Ђ��ς�����撲�ׁA16�l�̌�݁A���݁A�q�݁A�j�݂������ЂƂ܂Ƃ߂ɂ��āA���̗[���܂ŁA���e��˂����Ă����B �@�������̃X�p�C�鏑�̌��c�́A�����R�̌x������˔j���Đ������A�S������Ă���c���̊��l���ƐڐG�������A���̋A�H�A�ނ̊��m�锾���R�m���ɑj�~���ꂽ�B���̎m���͌�ɂ����،����Ă���B�u�����ނ��|�����Ă���l�q��\�킳���A���邢�́A�R�����ē��S��}�����Ȃ�A�����͔ނ��E�������낤�B�������A�ނ́A�x�����邾���Ō������Ăق����ƁA�����ɂ����ׂ����Řb���Ă����B�v(84) �@�ߌ�A�������Â���ƁA�N�����A�T�m�̒�Ŕ����R�w���҂����̗F�l�ł���A�����e���������ɓ�������̂�҂����B�����e���́A���̖�ɗ\�肳��Ă����c����c�ŁA�T�m�ɉ����������Ă������̂Ɗ��҂���Ă����B����b�鏑�̖،˂́A�قڊۈ�����₵�āA�����A���v玗��e���� �u�ŊJ��v �ɂ��Ęb���������B�ߌ�5��17���A�����e���̗�Ԃ����ɒ��������A�����R�������͗��R���e����U������Ƃ̉\�����������߁A�ނ͎��]��x�@�̌��d�Ȍx��Ō}����ꂽ�B�����Ĕނ̎ԗ�́A���悻4�}�C���k6.4km�l�̎s�X���A�T�C������炵�ăt���X�s�[�h�ő��蔲���A30���ōc���ɓ��������B�ނ͒����ɓV�c�ɉy�����A�V�c�A�c�@�Ƃ̓��ւ̗[�H���Ƃ����B �@�ߌ�7�����A�ނ�ɑ��̐e���������������āA�c����c���J�Â��ꂽ# 4�B���]�����̘b�ɂ��A�����͐\�����킳�ꂽ���̂ŁA���̕��͋C�͏�i�Ȃ��̂ł������B�T�m�́A�e�X�̐e���Ɏ��X�Ɏ�����������A�p�ӂ��ꂽ�Z������\���\�\�������͂��߂Ƃ���l�X�Ȏ����A�����R���v��A�����č��������Ȃǁ\�\�Ɏ���݂����B�������A���̎�v�Ȍ��O�́A�V���t�������ɑg�t���ꂸ�A���R�ƂƂ��ɏ������ł��o����Ȃ���A�����R�̐������n���ɍL����Ȃ����Ƃ������Ƃ������B�T�m�͐e���ɗ���q�ׁA�����������ӌ��ɂ��Č������邱�Ƃ���A�ߌ�W��30���A�������鐷��オ����Ȃ��܂܁A��c�͎U����B���̌�A�����e���͑�Z�̖،˂ƁA���悻30���ԁA�b���������B(85) �@# 4�@�c���T�͂ɂ��ƁA �u�c���͓V�c�̔z���ɂ���v�A�c����c�́A �u���N�ɒB�����j�q�c���ɂ���č\�������v �Ƃ���B�����āA�V�c�́A�O���̗���ҁA���ƂɁA����b�A�{����b�A�@����b�A�ō��ْ����̏o�Ȃ����߂邱�Ƃ��\�肳��Ă���B�P�X�R�U�N�i�K�ł́A�P�U�e�������̎��i��L���Ă����B���̂����A�U�����u�e���v�A�P�O�����u���v�ł������B�U���̐e���Ƃ́A�T�m�̂R�Z��ɁA�c���I���ɂ���Đe���ƂȂ�A�����n�̉Ƒ��̂R���̉��q�\�\���R�Q�d�����̊Չ@�e���A�C�R�R�ߑ����̕����e���A�����āA1934�N�Ƀq�b�g���[�ɉ�������M�I�ȉ�z�e���\�\���������ʁX�ł������B����2��27���̍c����c�ɎQ�������e�������́A��̒����A��̍����A�]�Z�̕����A�i�S�����e���j�A�����āA�f���̓��v玁A�f���̒����A�]�Z�̗��{�A�����āA�Չ@�e���̑��q�̏t�m�k�͂�ЂƁl�i�S�������j�ł������B(86) �@���̍c����c�́A��̌��ʂ������炵���B���̂ЂƂ́A���c���̕ʑ��ňӋC�������Ă������R�Q�d���̊Չ@�e���������ɌĂ�A �u���Ƃ��s���������Ƃ��v�A�V�c�̔w��ɒ������Ƃ����߂�ꂽ���Ƃ������B�����A�Չ@�͂���ɏ]�������A�ǂ��������Ƃ��A���ꂩ���T�ԁA�ނ̌N��Ƃ͉�킹�Ă��炦�Ȃ������B���́A��c�̖�A�����e�����A�F�l�Ŕ����R�̍ō��̒n�ʂɂ���A�쒆��т��Ă̎��M�������A�ނ̕����̓P�ނ������������Ƃ������B�쒆�́A����l�������A�����̌��Ɍ��e�����킦�Ĉ����������Ƃ����ԓ����s����(87)�B���]��́A�e�������������Ɣ����R���m�������Ƃ̌�F����ۊW���䂦�ɘT���������Ă��Ȃ���A����ł��������������̒��ŁA�T�m�̑��ɂ��Ă���̂����Ĉ��g���Ă����B�����e���́A�ߌ�9��10���A�x�@�̌�q�ƂƂ��ɋ{�����ɂ����B �@�����A�T�m�́A�c����c�ɂ��Ă̌������A�{��̌����L�^�Ƃ��邽�߁A��Z�̖،ˁ\�\�܌M�ǒ��\�\�Ɏ��̂悤�ɕ����B �u�����{���ł��ǂ낵���B�����{�́A�T�E�P�T�����̎��ȗ��A�傫�����������B���{�{�́A�k���̔����R�Ɂl���̉��͂����߂����A�܂��ׂĂ����B���͔ނ𗧔h���Ǝv���B�t�m�k�Չ@�̑��q�l�͋C�i������B�����e���́A���`�̌l�ɂƂ��Ă̈Ӗ��ƁA�c�ʂ̑�`�ɂ����邻�̈ʒu���ׂ̂����A�ߌ��v�z�̉e�����Ă���A���_������B���v玐e���ɂ��ẮA�������o�������Ă����B�v(88) �@�T�m�́A�ꑰ�̖͔͂������҂Ƃ��āA���v玐e���̍ŋ߂̋��������Ə@�����\�Ɋւ���x�@������ǂނ��Ƃ����߂��Ă����B�����V�c�́A�����̐e�����A�ʏ�̓��{�l�̓����ςɂ���Ăł͂Ȃ��A�����ɒ��`�ł��邩�ǂ����Ƃ�����Ŕ��f�����B�����ȍc����c�Ŕނ́A�����̐e���ɂ����Ȃ�ʎx�z�͂��ؖ����Č������̂ł������B �@��c�����U���Ă��炭���āA�^��A�����A���̏��������́A�������@�ɂ����ނ��A���̈�K�Ŏw�����Ƃ�ܐl�̔����R�m���ɁA�]�݂��̂ĂēV�c�̈ӎu�ɏ]���ƍ������B�����A�ނ炪����ɏ]��Ȃ��ꍇ�A�k�i�h�̎w���Ґ^��́A�ނ��������邽�߁A������h�������w�����˂Ȃ�ʂƐ鍐�����B��J���A�ߒQ�ɂ��ꂽ�Ⴋ���m�����͍~���ɍ��ӂ����B�ߌ�11��30���A�O�����́A�߉q�t�c�Ƒ��t�c�̕����ɁA���̖�A�����R�苒�n�悩��E�o���悤�Ƃ����ʕ��m�ɂ͊���ł���悤�ɂƖ��߂��o�����ƁA�{��ɕ����B �@�������A����Ŏ����I������킯�ł͂Ȃ������B�����R�́A������@���ʂ��āA�����x�O�̉B��Ƃɂ���}�i�I�k�i�h���_�Ɩk��P�ƁA�����A������葱���Ă����B�E�Ɗv���ƂƂ��Ă̂���܂ł̒����o���̒��ŁA�k�́A�N�[�f�^�̍��d�ւ̕\�������Q���͔����Ă��Ă����B����������́A�ނ͂����[���ւ��A�������������s�����ꍇ�A���Y����鋰�ꂪ�������B����܂ł̓���ԁA�ނ͖����@�ɕt��������ŁA���̓x���Ƃɔ����R��E�C�t���A�����I�삯�����̏�����^���A�܂��A��}�̗͂����Ƃ̕]���̂���Ȃɂ�邨������`���Ă����B �@����2��27���̖�A�O�������������@�������グ����̂قڐ[��A�k�͓�l�̔����m���Ƙb���A�܂�������߂Ă͂Ȃ炸�A�{��ւ̈��͍͂��܂��Ă���B�������A�������ׂĂ����ڂɏo���ꍇ�A�ނ�ɂ͐R���Ȃ��̗����̎��Y���Ȃ���邾�낤�ƍ������B�����Ėk�́A���̎��m�������ɁA�Ȃ��������̘b��t�����킦���B����́A�n���̂Ȃ��Ɋy��y�Ŏ��m���������������j������Ă����B�����R�͂���ɕ�������A����Ɏ^�������B ��O��(89)
�@���N����ڂ̂Q���Q�W���́A�ĂсA�ܓV�������B���]�������̖{���́A�ߑO�V���A���������̊j�S���ω��������Ƃ�m�炳�ꂽ�B���Ȃ킿�A�����R�͒�������Ȃ���Ȃ�ʁA�Ƃ������̂ƂȂ����B�Ƃ������Ƃ́A�{���̖����A�R���ꑾ�Y��т��A���܂▾���Ȕ��t�҂Ɖ������҂����ɉ����̎��݂����Ƃ������ƂŁA�Y��������ƂȂ邱�Ƃł������B����͂܂��A�{�����g�̒��N�̒��`�̌o�����p�J�ɂ܂݂��Ƃ������Ƃł��������B��ɁA�ނ̒m�l������������b�ɂ��A�ނ͂��̓�����ŁA�ꋓ�ɁA�\�N�ȏ���N�V�����Ƃ������Ƃ�����(90)�B �@�ߑO�P�P�����A�R���͉����ߖ{���֍s���A�����R�͒������锭�߂ɑ��A�قƂ�Ljꎞ�Ԃ������āA����ɔ����鉉�����s�����B���������́A����Ɋ��S�ȓ���������ĕ������������A���������͂��Ȃ������B���ߑO�A�����ߎQ�d�̐Ό��Ύ��卲�\�\���B���𗧂Ă����]�����ȁk���@�@�l�M�҂ŁA�ȗ��A�Β��a�����������Ă����\�\�́A������c���̒[���痧���������Č������B�u��X�́A�o������葬�₩�ɁA�������˂Ȃ�ʁv(91)�B �����Ĕނ͕������o�āA�O�̎g���ɁA���ߏ���z�B����悤�������B �@��ꂨ��ы߉q�t�c�́A��c�ƂȂ��Ē����ɂ�����A�����R�̃o���P�[�h�j����v��ɓ������B�����R�m���́A �u�~������A�����Ȃ��Β��������v�Ƃ̃��W�I���������B����ɑ��A�����R�́A �u�c�ӂ��߂�����@���_�҂ɂ���Đ����ꂽ���߂ɂ͏]���ʁv �ƕԓ�����(92)�B �@���̒i�K�ł́A�����e���̓`�����쒆��тɓ`�����A�܂��A�R���������Ë��Ɏ������ލŏI�Ă������Ă������߁A��͂�������R�ɂ́A �u�ҋ@�v �Ɩ��߂���Ă����B�o���P�[�h���ł̌��̌�A�R���͐쓇�������āA�ߌ�ꎞ�A�{���̎��]�������ɖ߂����B�����ĎR���͖{�����]�������ɁA�����R�m������̐���\�\���ꂪ��@�ɑ��������̂ł���ƓV�c�ɓ`���钺�g�̗���̂��ƂŁA�S������������\�\��`�����B�{���͒����ɂ��̒�Ă�T�m�ɕ����B �@ �u�����ނ炪���E�������̂Ȃ�A����ɂ����Ȃ����B���������������ɋ{�삩�痧��l�𑗂�̂́A�Ƃ�����A���肦�Ȃ����Ɓv�A�ƗT�m�͌������B �@�{���́A�����̖������m�����߂���t�c�́A�ȑO�̓����ɑ��čs������������̂��������Ă��܂��A�ƈ�����ۂ��i�����B �@�T�m�͐��ɉs���������߂Č������B �u�������t�c�̎i�ߊ����L���ɍs���ł���ƍl���Ȃ��̂Ȃ�A�ނ͎����̐ӔC�������������Ă��Ȃ����Ƃ��v�B �@�{���� �u�É��ɁA���̂悤�Ȍ������Ɠ{��������̂͂����ĂȂ������v �Ɩڂ������炳��Ă����B���R�̎w���҂����́A������Ăւ̗T�m�̋���Ɉ��R�Ƃ������Ă����B�����̎R���́A�ߒQ�ƕs���̒��Ŗ{���ɓd�b���A�ēx�A�V�c�ɓ��������Ă��炤�悤���肵���B�{���͎R���ɁA�V�c�͂��łɂ����Ȃ�B�������܂܂Ȃ����f�����A����ɕ\�����͉̂����Ȃ����낤�A�Ɛ��������B����ł��A�Ȃ����������������߂閺���ɁA�{���́A�߂����ɂ��̓d�b������B(93) �@�ߌ�R���A���ڒ��ȎQ�d�����̐��R�\�\���̕\��� �u�܂�œ��a�̔��̂悤�ɂڂ₯�Ă��āv �\�\�́A�T�m�ɉy�������߁A����Ȃ�������肢�o���B���������Ɣނ͌����A�����҂́A���������̎����ɒ��g�̗�������߂Ă���̂ł͂Ȃ��B�����A����Ɛb���A�ނ�̈�̂����͂��A�É��ɁA���܂萳��������̋V�����ʂ����Ă��邩����Ăق����݂̂ł���B�T�m�́A�{����ĔR�����āA���̐V���Ȗʎq���[�u�����̂Ă��B���̕m�炳�ꂽ���A�����R�̂���m���́A�u�������A��s�@���̂ł���A�É��ɂ͕���邾�낤�Ɂv�A�ƒQ���Ȃ��猾�����B �@���R�Q�d�������V�c�̂��Ƃɖ߂�A�قڈꎞ�Ԃ�v���āA�V�c�������Ǝ��ߐ[�������悤�ƁA����������ǂ̓w�͂��s�����B�����čŌ�ɂ́A�L���ɐg���������A�V�c�ɁA�����݂��Ă��炢�����Ƃ���i�����B�V�c�͂����A�ނ��܂����Œʂ�߂��A���ő҂������Ă��鎟�̗p���Ɏ��|�������B�ߌ�S���R�O���A���ǁA���R�Ɖ����ߌR# 5�i�ߊ��A���ō_���k������ �����ւ��l�����́A���̓��̒����s���͂��łɒx�����A�����A��Ԃɑ��s�����Ƃ���ƓV�c�Ɋm���B�����T�m�͂����f���C�Ȃ��p�����A�{�����]���������ĂсA���R�w���w�̂����ȂׂĂ̕s���]������B �@# 5�@���Ȃ��Ƃ�23,491�̕�����350�̏������A1,483�̔����R�ɑ��W�����Ă����B �@�T�m�́A �u���R�͓V�c�ɑ����Ƃ����b�����邪�A���R�͎����̏d�v�����Ӑ}�I�ɉ�����Ă���Ƃ̘b������v�A�ƌ������B �@����ɖ{���́A �u�R�����{���������悤�Ƃ̈Ӑ}�̂��ƂŁA�ډ��A���R�͕É��̂��ӎv�ɏ]�����Ƃ�������Ă���ƁA���̐����ԁA�l�X�͐\���Ă���܂��B�����������͓V�c�̗��R���ɂ߂ĕ��J���A�����𑬂₩�����a���ɉ������悤�Ƃ��Ă��闤�R�̐^���ȓw�͂�������̂ł��v �ƕԓ������B�{���͌�ɁA���L�Ɏ��̂悤�ɋL���Ă���B �@���͕É��ɁA���R�ɑ��鐢�_�̌���́A�����Ɋ������ʂقǂɌ������A�Ɛ\���グ���B���������Ȃ���A������������邱�Ƃ��ł����A�ߒQ�ɂ���Ă��܂��A�b�����Ƃ��܂܂Ȃ�Ȃ������B�É��͈ꌾ����������炸�A�������o�Ă����ꂽ�B �@�ЂƎ����āA�É��͎����ĂсA���������ꂽ�B �u���]�������A���R�ɑ���ӂƂǂ��Ȕ������A�����͂��̂悤�ɗ܂��āA���̗��R�������Ă��ꂽ�B�����A�������̎��������݂₩�ɉ�������˂A��낵���Ȃ����Ԃ��N����B���łɎO�����߂��A���{�̒n�ʂ͗h�炢���܂܂��B�O���בւ͂قڒ�~���A��s����������Ȃ�̂��߂��B����s���͎�s�ȊO�ɂ��L����A�����̊댯������B���t�c�̒����������A�䂪�������E���A���V�����ɖ�ȍs�����������u�����ƍ����������m��ʁB�䂦�Ɏ��͋M�a�A���]�������ɁA���g�̈٘_�Ɗ�����R���Q�c�@�ŕ\������悤����^���A���ɉ�������悤�ɋ��߂�B�v �@�{���́A�R�����Ɋւ��A���ׂĂ̓V�c�̌����ɐ��������I�ӔC������ɂ������B�ߋ��ɂ����āA���̗��҂̊ԂɌ����̈Ⴂ�����������A�T�m�����̘V�����Ȃ��߂���A���������������肵�Ă��̈Ⴂ�߂Ă����B��������A�T�m�͓��ʂɁA���̖{�������������ӔC��������A�k�R���Q�c�@�ɂ̂��݁l���̔ނ̈٘_�������L�^�Ɏc�����悤�Ƌ��߂Ă����B�����ē����ɗT�m�́A�{���Ɍ����M���������Ă���A���S�Ƃ��Ă̔C������������Ƃ��Ă����̂ł������B �@�i�{���̓��L�ɂ��Ɓj ���̋��߂ɏ]���A���͌R���Q�c�@�ɁA��\�҂����̕����ɂ悱���悤�ɂƋ��߂��B�k�i�h�̍r�ؑ叫������Ă����̂ŁA���͔ނɁA����Ŏ������g�̐S��ƁA�����ŁA�V�c�̂��ӎu��`�����B����ƍr�ؑ叫�͂����������B �u����܂ŁA�V�c�̖��߂́A�R�����������A�L�������킹�ʂ��̂ł���ƐS���Ă���܂����B�v �@�T�X�̍r�A�U�O�̖{���̓�l�̑叫�́A�������ɕ��߂������ߍ������B��l�́A1989�N�ɗ��R�m���w�Z�𑲋Ƃ����������ł���A����ȗ��A�Q�d�{���ɂ����āA���܂��܂̔C�������ɉʂ����Ă��Ă����B��l�́A�ߋ��ɂ����ėT�m���A�قȂ�ӌ��̏����҂̊Ԃ���I��ł����̂�m���Ă����B�܂���l�́A�T�m���A�������~����s�����Ă��Ă��鏕���҂������邽�߂ɁA�����̓����O�����Ƃ��m���Ă����B�������T�m�́A����܂łɌ����āA�R���Q�c�@�̏������������Ƃ͂Ȃ������B��������A����35�̌��l�_�́A�e�̌���̓�����o�����A�ꐧ�I�ӔC�̑S�Ă����Ƃ��Ă����B���̓�l�̔N���̑叫�́A�݂��Ɍy�����������A���̍c�ӂɓ����������B���̌�A���R�̂��ׂĂ̒��V�́A������������̐ӔC�͂Ȃ����̂悤�ɍs�����A�����A���̎҂ɒǐ�����悤�ɂȂ����B����͗��j�I�u�Ԃł���A���̓�l�̑叫�́A�܂���킸���ɓ������ȏ�̐H���Ⴂ���Ȃ��A�����F�߂��̂ł������B �@�R���Q�c�@�́A�T�m���댯�Ȓn�ʂɂ��炷���Ƃ���\�h���邽�߂̈�̓w�͂��s�����B�ߌ�7��30���A��g�̑�\�c�\�\�r�ؗ����A�O�����̗ё叫�A�����ĎQ�d�����̐��R������\�\�́A���c������̗�ԂŒ������Չ@�e���Ɖ�A�T�m�̍l����ς���悤�ނɐ������Ă��炨���Ǝ��݂��B�Չ@�e���͂����f��A���@�ւƈ����グ�Ă������B���R���V����Ȃ��\�c�͉����ߖ{���ւ����ނ��A�����ŏ��Z�Ƃ̉�c���J���A��������A�u���R�̌R�I��j�镐�͐����́A�����Ȃ�]�����Ăł������˂Ȃ�Ȃ��v �Ƃ����ӌ������L���邱�Ƃɓw�߂��B �@�����ߌR�Q�d�A�Ό��Ύ��卲�\�\���B��헧�Ďҁ\�\�́A���߈ȍ~�A�����̔��������߂��Ղ��Ă��邱�Ƃ����Ă����B���̈Ӑ}�͗�������Ă��炸�A�Ό��͂����ŗ�������āA���̑�\�c�𗦂���r�ؑ叫���Î����A�����Č����������B�u����͓������̊��Ƃł���B�M�a�̖��O�ƊK���𖼏��ꂽ���B�v �@ �u�M�l�͎����r�ؑ叫�Ƃ悭�S���Ă��낤�B�M�l�͏㊯�ɖ�������Ƃ���̂��B����T�߁B�v �@����ɐΌ��́A �u�ł��܂��ʁB�c�R���c�ʂɑ��ėp���邱�Ƃ́A�f���ċ������邱�Ƃł���A�펯���z���A�R�I�ǂ���̖��ł͂���܂���B�M�a�͎���叫�Ə̂���邪�A���{�ɂ������������ȑ叫��������Ƃ́A�M���������v�A�Ɖ������B(94) �@���̐M�`���������̕\�o���䂦�A�Ό��́A��������̑�l�R�ɂ����āA���R���ɗ��܂蓾���B���̌�Ό��́A �u�Ō�̖k�i�_�ҁv �ƔF�������悤�ɂȂ����B�ނ������Ǝw�ߎ�����o�čs������A�r�₻�̑��̑叫�����́A�����Ɍv�悳��Ă�������s����j�~���鉽�̎肾�Ă��Ȃ������B�������A�ނ�͍��ʼn����ߎi�ߊ��ɁA���͂ɂ�炸�A�����R���o��������������悤�ɂƐ������B���̖��ʂ��A���W�I�����┾���R�̎��͂𑖂�g���b�N���A�u�~�����A�����Ȃ��Β������v �ƌJ��Ԃ����B�����Ԕ����@����́A���m���╺���͉��͂����Ə������r�����������ꂽ�B�閾���ɂ́A�����R�ɁA�Ȃ�q�������̂��߂ɍ~������A�Ǝ������A�h�o���[�����グ��ꂽ�B �@���̖�A�R���卲�\�\�{�����]�������̖����\�\�́A�����ɂ���t�߂̌��^�őߕ߂��ꂽ�B
�T�m�ɂ����� (95)
�@���Q���Q�X���A�K�N�R���ڂ̒��A���t�c�̕����́A�����R�̋��E���̖��h���ȕ�����ʂ��Ĉړ����A�\�z�����퓬�n�悩�疯�Ԑl������n�߂��B�܂��A�����R���́A�������ɐ苒�n��̎�v���_�ւƏW�������B�ߑO�X���A���Łk�������l�����ߎi�ߊ��́A���W�I��ʂ��č����ɂ����ʍ������B �u���m�������͐��ɁA�����҂ƌ��Ȃ���鎖�ԂɎ������v�B�ߑO10���A�����ƓS��Ԃɂ���Ĕނ�͕����߂��A���h���������R�������A��l�A�O�l�ƁA�ނ�̐苒�n�_�̉��̐�̐ς������Ő���L�������A�E�o���n�߂��B���߁A�����e���̗F�l�̖쒆��т͎��E����(96)�B2���߂��A���ׂĂ̕������~�����A�������ɂ���čS�����ꂽ�B
�@�T�m�́A�Ō�̍Ō�܂ŁA�^�O����łɂ��������Ƃ͂��Ȃ������B��8��30���A���R�̍s���J�n���ŏ��ɖ��炩�ɂȂ������A����b�̖،˂́A�T�m�ɁA�u�V���t���w�����āA���������S�����Ắv �Ə��������B�����T�m�́A �u��������������܂ő҂������v �ƕԓ������B�����āA�������I��������A�ނ͂���ł��������Ă��Ȃ������B�ߌ�2���A�ނ́A���ÂɌ����̎g�҂��o���̂ł͂Ȃ��A�d�b�ł����āA�������e���ɏ]���̗v���\�\�㋞���Ď�t�E�\�\���s�����B���ɂ𗝗R�ɁA�������́A�㋞����܂łɏ����̎��Ԃ��~�����ƕԓ������B�ߌ�4���A�T�m�͐������ɍĂјA�����A�g�t�ً͋}�ɕK�v�ŁA�o���邾�������㋞����悤�ɂƍ������B �@���������C���������Ă���ԂɁA������߂���3��1�����}�����B���̓��͓��j�ŁA�����͂��̓��j����́A�A���m�`���̋x�����y���݂̂Ȃ炸�A�{���ɔ�J�Ƌx�{�̈���ƂȂ��Ă����B�����A�T�m�͗�O�������B�ނ͒������ɋN�����A�R���𒅂��A�[���x���܂Ŋ��Ɍ������Ă���(97)�B����́A���̐�̐��T�ԂɎ����ɉۂ�����̓��ۂ������B�ނ͖����ꎞ�Ԃ̉^����f�O���A3��18���ɂ́A��v�Ɛb�̑�\������Ă��āA�|���ւ��̂Ȃ��g�̂ɔz������悤�ɍ��肵�Ă��A�Ȃ����i�ʂȒ��ӂ͕���Ȃ������B�T�m�́A�Ō�̕����~������܂ŗe�͂Ȃ��U�ߗ��ĂȂ����菟���͊낤���A�Ƃ����R���I���������̂܂��s���Ă����B �@3��2���A�V���������������ɓ����������A�T�m�̑�Z�����������Ă����i���́A�W�����A�X�E�V�[�U�[��낵���A�ނ�̎w���ҁA�߉q�e���ɁA�ŏ��͎̍��A���ɓ���b�̍��ւ̏A�C���A���ꂼ�ꋑ�ۂ���悤�����������̂ł������B����́A���������Ƃ̐푈���J�n���ꂽ���A���̎��߉q�ɂ��鏀���Ƃ��ẮA��̍��ŋ��������B�߉q�͂���܂ł����Ȃ���E�ɂ����������Ƃ͂Ȃ��A�����M���@�̎w���҂Ƃ��Ă̂ݒm���Ă����B�܂荑���ɂ́A�ނ��ɂӂ��킵����ł���Ƃ̍l�����Z������K�v���������B�����āA�]���Ȑl�X�͔ނ����ꂽ�����m��Ȃ��������A���R���������l�R�ɖʂ��Ă��鎞�A�ނ͂�����������킯�ɂ͂����Ȃ������B�����A���̂��Ƃ́A�푈���A�ނ̗��R�ɑ���w��������߂邱�Ƃɂ��Ȃ����B �@�������́A�߉q�̎����̕s�����𖾂炩�ɂ����悤�Ɠw�߂��B�߉q���e���ʂ̗L�͐����Ƃ��琄����Ă���̂�m���āA�������͋߉q�Ɖ�A�ނ����̋C�łȂ����Ƃ�m�����B�V���ł́A�߉q�̉��䂩�����Ə̎^���ꂽ���A�������͋߉q�̎��ނ��悻�ɁA����ł������ɔނ�V�c�ɐ��E�����B�T�m�͎���A�߉q�̌��N���[���łȂ��Ƃ��ċ��ۂ��邱�ƂŁA�O��������������B�����������́A�Ȃ��������̐��E���J��Ԃ��Ď咣�������߁A�T�m�͊��s���ނ������A3��4���A�߉q���Ă�őg�t�����߂��B �@�V�c�Ƃ̉y�����I�����߉q�́A����b�鏑�̖،˂ɁA �u�܂����������Ă���v �Ƒł��������B��ӂ����������A�߉q�͐������ɍĂщ�A�e�͂����߂��B�ނ͂��̎��A�����̈�҂̐f�f�������Q���Ă����B����́A���Ȃ��Ƃ����ƎO�����A���̌��N�͐E���𐬂�����������̂ł͂Ȃ��A�Əq�ׂĂ����B�O������Ƃ́A���R�̏l�����������鎞�������B �@�����Ő������́A�߉q�͂��̊�@�̎��ɂ����Ă��A���{��������Ƃ����V�c�̖��ɏ]�����Ƃ����ۂ����ƌ��\���A��������p���錌���҂̌o����䖳���ɂ��邱�Ƃ��A�s�\�ł͂Ȃ������B�����A�����c�_�̌�A����������ɁA�������͑ԓx��a�炰���B�ނ́A���̂��߂Ƃ͂����A����̌��N���]���ɂł��Ȃ��吭���Ƃ̋ꂵ������������ƁA�V���L�҂Ɍ�����B�����������ŁA�ނ͉y�����ɖ߂�A���ɍ��f�������邱�Ƃł����A�����̐��E��ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƕ����B�������č��x�́A�T�m�̑��ߏW�c�̂�艺�ʂ̒��N�ҁA�L�c�O�B�O����b�𐄑E����# 6�B �@# 6�@���������O�����̍L�c�́A�n���g�D�̎�́A���R�̎艺�Ƃ��Ă��̌o�����n�߂��B1921�N�ɋ߉q�e���ƒm�Ȃ̊W�ƂȂ�A������̓������A�ނ̏��҂̈�l�ƂȂ����B �@�L�c�́A3��5���A�T�m�����t��g�t����悤������ꂽ���A3��9���ɂȂ�܂ł��̐E�͗^�����Ȃ������B�Ƃ����̂́A����4���ԁA�R����ѐ��E�́A���t�̐����A�l���̗��ʂɂ��āA���ꂼ��ɖ����ȗv����˂��t���Ă������炾����# 7�B�u�L�c�̍���v�A�u���{��g�߂Ȃ����{�v�ƁA�V���̌��o���߂Ă���ԂɁA�T�m�͎���̋��łȊO��������������ʂ����B �@# 7�@���R�̋��v�ŁA�q�씌�݂̖����A�g�c�\�\1946�N����1954�N�̊ԁA5�x�ɂ킽���Ď��Ƃ߂�\�\�́A�x�@���NJ����������b�̒n�ʂ�艺�낳�ꂽ�B �@3��4���A�T�m�ՐȂ̂��Ƃł̐����@�́A�����R�̎��m�������J�̌R�@��c�ɂ����邱�Ƃƌ��߂��B�Ƃ������Ƃ́A���̏㍐�͂ł����A���̌Y�̎��s�������ɂȂ����Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă����B3��2���A���R�̊e�叫�́A�u�ŋ߂̋���������v �̈⊶�̈ӂ��c�ʂɕ\�킷���߁A���̑S�����E�����C�����B3��6���A�T�m�͂��̑�ʎ��C������ꂽ�B����́A�P�Ȃ�`�����̂��̂ł͂Ȃ��A4��23���t�������Ď��s�������̂ł������B����ɁA�T�m�͎O���̌R�K��̗�O���c���Ƃ����K���̂��܂����F�߂��B���Ȃ킿�A�l�R�h�w���ҁA�����叫�Ƃ��̓����ł��鐼�叫����ѐA�c�叫�͎��C���Ȃ������B���̎����͗����ƂȂ�A���͋��瑍�ĂɁA�����ĐA�c�͊֓��R�i�ߊ��ƂȂ����B �@�{��̘L���������R�c�̐��Ə����肷�鑫�����Â܂������A���g�̋`���I�ސE��O�ɖʎq����������ɂȓ�T�Ԃ�҂�����Ă������]�������̖{���́A���̗�O�́u�V�c�̑匠�̍s�g�v �Ƃ��̓��L�ɋL���Ă���B���l�ȗ���ŁA3��9���A�T�m�́A�R���Q�c�@�Ɨ��R�ō��i�ߊ��̃����o�[�A�Չ@�����A���������A���v玒����͎��E����K�v���Ȃ��Ƃ̑[�u���Ƃ����B �@3��9���A�L�c���t���悤�₭�ɑg�D���ł߁A�@�\�𐬂��n�߂����A�T�m�͍��Ђ̓���ɐ�O���A������^�钆�܂ŁA���Δh�ɑ��A��@���ɗ�����������قǂ������B�����Ĕނ́A���������̌����������A�u����{�鍑�匠�v ���� �u����{�鍑�_���V�c�v �ւƉ��߂�# 8�B�ނ́A���̔����ɉ��S����4�A���̔p�~���l���Ă������A�V�c�ւ̒����ɑ����ʂ������邽�߁A�A�������c���A�ꕔ�̕������ێ����邱�Ƃ͔F�߂��B �@# 8�@����́A�T�m���ꌎ������l���Ă����i�W�������B �@����Ɠ����ɁA�T�m�́A���h�̂��߂̐V���Ȓ����v����ĂƂ��ď��F�����B����́A�l�̕��傩��Ȃ���̂ŁA���̍��h�̐����ɂ͂��܂��܂ȕ������݂����Ă����B���̎l����Ƃ́A�@ �u���@�����ɏ]���v ����ɐ}�����������A�A���t�ɕ����헪�Ƒ����v�敔��A�B�ɕ���铮������ѐl������A�����ćC�V�c�Ə����̎Q�d�����݂̂��֗^����ڍ�핔��ł������B�����Ă���1936�N3���ɑg�D���ꂽ��啔���̂ЂƂ��A�k���ߍx�ł̖�ԍ��v��ŁA����͒����Ƃ̑S�ʐ푈�ւ̌��ƂȂ���̂ŁA�܂�16������ɂ͎��ۂɂ����Ȃ����v��ł������B �@���̐V���h�v��̔����́A�Β�����ɔ�����Ƃ������A���̑����I��͂��\�z���邽�߂Ɋ�^������̂������B���{�́A������ɏ����˂Ȃ�Ȃ������łȂ��A���m��������̉����j�~���˂Ȃ�Ȃ������B�L�c���t�́A���łɂ��̓����u���펞�o�ρv �Ƃ��Ēm��ꂽ�����v���ł����ĂĂ����B�����ČR���x�o�͂��̌��12�����ԂɎO�{�ȏ�ɖc��オ�����B�Ԏ��\�Z�\�\�����ňÎE���ꂽ���������A�����ɂ���čŒ���ɗ}�����Ă����\�\�́A���܂⎞��̗v���ƂȂ��Ă����B�H��̐��Y���蓖�Ă���ב����܂ŁA�o�ς̂����镔��́A���ՂȂ����̑����Ɛ��{�̌����������ɗꑮ������̂ƂȂ����B �@����Ɠ����ɁA���R�̋K�͂��P�V�t�c����Q�S�t�c�ւƊg�傷�邽�߁A�ڍׂȔ閧�[�u����������ꂽ�B�V�݂��ꂽ�V�t�c�́A�\�������璥�p���ꂽ�B�Β����킪�J�n�����旧���T�Ԃ̂����ɁA�]��Ɏ�ۂ悭�A���������A���Z�A�����čČP���{�݂��p�ӂ��ꂽ�̂ŁA���������V�t�c�́A���ɂ��Đ퓬�����𐮂��邱�Ƃ��ł����B�������āA���������L�^�����̂܂܂ɐM�p����Ȃ�A��114�t�c��1937�N10���ɑn�݂���A�Ђƌ����o���Ȃ������ɁA�������ɂ����āA�싞�ɂނ��Đi�R���Ă����B(98) �@���R�̑��̋K�͂�41�p�[�Z���g�ɂ��Ȃ邱�̌��I�Ȋg�傪�v�悳��Ă���ԁA�����ɕ��S���Ă����T�m�́A������w�������m���̗e�͂̂Ȃ��l���𖽗߂��A����ɂ��A���̌�̓�N�ԁA�P�����Z�ɐ[���ȕs���������炷�قǂł������B�����A���̏l�R�̕K�v�ɋ^���͂Ȃ��A�܂��A3��3���̊Չ@�e���Ɛ������̃X�p�C�鏑���c�Ƃ̉�b�ɔ@���Ɍ���Ă���悤�ɁA�u�ߓ��̖\���Ɋ��N����Ȃ���ΐi�߂��Ȃ������悤�Ɂ\�\�����A���ꂪ�N�ł���A����̓��̏L�����̂ɂ͂ӂ�������Ƃ̌X���̏����ɂ��ā\�\�A��X�ɂ́A���R�̏l�����A�e�͖��������܂ŁA�O�ꂵ�Đ��������邱�Ƃ����߂��Ă���B�v(99) �@��|���Ƃ����N��������d����S�����̂́A�l�R�h�̎����V���R��b�ł������B1936�N��3������8���̊ԂɁA���R�̔���l�]��̎m���̂����A���l�����������ɂ���(100)�B�k�i�h�̋��_�����ƂƂ��ɁA���R�̐헪�I���]�̗D�G�Ȕ������A�قڈ�|���ꂽ�B���̏l���͌R�̏�w���ɂ����Ƃ��Ō���^�������A���̌��Ԃ�ɁA�V�����Ⴂ�l�ނɏ��i�̓����J�����ʂƂȂ����B �@���̓V�c�̐ꐧ�I�Ώ��̌�ɕs��I�ɕ����o�������S��V���Ȑ��R�A�g�ɑ��āA��Z������11�l�N���u�͂ЂƂ̍��҂ݏo�����B����́A�T�m���ӂ��킵���Ɣ��f�ł��Ȃ����t�ɂ͔ނ����ی��������A�܂��A���̌��Ɉ�̌`�Ղ��c���Ȃ��ł��ꂪ�閧�̂����ɂȂ����Ƃ������̂������B�ǂ̓��t���A���R����ъC�R��b���܂߂Ȃ���Ȃ�Ȃ������B1913�N�ɉ��肳�ꂽ�@���́A��������ї\�����̗��E�C���R�叫�̒�����A���̗���b��I�Ԃ��Ƃ��ł����B�Ƃ��낪�A�������Z�݂̂��V�c�̖��߂ɂ��S�����������̂ŁA���_�I�ɂ́A�����������E������҂ɂ́A�V�c�̋����Ȃ��Ƃ��A�t����b�̈�l���w�����邱�Ƃ��ł����B�V�c�́A���R�ɁA�����������t�̏��F�����ۂ��邱�Ƃ͂ł������A����͋V�犵�s�ɂ������̂ł͂Ȃ��A�ނ̕����������邱�Ƃɂ��Ȃ肩�˂Ȃ������B5�����߁A�����@�́A�V�c�ՐȂ̂��ƂŁA���C�R��b�͌����R�l�݂̂Ɍ���Ƃ����@���������L�c���t�ɐ��������B ���t�͂��̉����ɓ��ӂ��A�T�m�͒����ɂ���ɏ������ĉ����@�����������B5��18���A���̉����͊��������ƂȂ�A�������ꂪ���������邩�݂̂��E�Ɛ��Ԃɒm�炳�ꂽ�B�T�m�Ƌ{������W�c�́A���̔������c�_���A�]�܂����Ȃ����t�̑g�t��j�~������A�Ǝ��Ɂk�{��̈ӂɂ���Ȃ��l�ړI��i�߂���t���܂Â����邽�߂̏퓅��i�Ƃ����B�������� �u�R�v �Ƃ������̕s���̉�������绂��͂��߁A���|���������A�h�i�ŁA�^�u�[������鍑���́A���������\�\�����ȍ~�A�T�m�������Ƃ��ɌR�̍ō��i�ߊ��ƂȂ����\�\�����ɂ������ɖ��m�ł���悤�ɂȂ����B# 9 �@# 9�@1913�N����1936�N��23�N�ԂɁA���������I�C�͉\�ł������ɂ��S��炸�A�\�����R�l���痼�R��b���I�ꂽ����͂Ȃ������B�������A1944�N�A�����ɂ͈�@�ł���Ȃ���A�T�m�́A�����C�R�l�������ĂсA�ē��Ƃ����������𖼕�ɕ��������邾���ŁA�\�����̊C�R��b�݂������B �@���������d��ȉ��ς����{�̍\���ɉ������Ă������A2�E26�����̎句�҂����́A���ق̂����Ɏp�������������B�{�����]�������́A�ŏ��A���������ɂ���Ă��̐E�ɂƂǂ܂�悤���߂��Ă����B3��8���A�����͖{���ɁA�u�������A�����̖�����������n�ʂɂ���܂��B�ǂ������E�͂Ȃ����ł��炢�����v �Ɨ��ӂ����߂��B �@������3��16���A�{���͓��L�ɂ����L���Ă���B �u���������āA�����̎R���̍ߏ�ɂ��Ă̏ڂ�����������A�S�z���Ă���ƌ����Ă��ꂽ�B�E�E�E���̓��A�R���̉Ƒ������̉ƂɈ����z���Ă����B�ނ�̉Ƌ�́A�R���̎��Ƃɂ��������B���Ƃ��̎q�����������̂Ƃ���ŕ�炳�������A�Ƃ����̂����̎��Ƃ���̗v�]�������B�v �@������3��17���A�{���͍c�ʂɎ����̎��C�̈ӎu��`�����B �u�É��� �w�ǂ̒��x�A�����̉Ƒ��͊֗^�����̂��x�ƕ����ꂽ�B���́A �w�ǂ̒��x�͑����܂��ʂ��A�ډ����ɂ����āA�D�掖���͗��R�̏l���ł���A��������������˂Ȃ���Ȃ�A���C����ӔC�������܂��x�Ƃ����������B�É��́A�w����͂����ł��낤�B�悭�l���Ă����x �Ɠ�����ꂽ�B�v �@3��28���܂łɁA���̎��C�͎��ꂽ�B�{���ɂ́A�����A���p�i�A���g�̊���̈�̕����Ȃǂ�����ꂽ�B �u�������M�a�ɑ��肽���B���������g�������̂Ȃ̂Łv�ƓV�c�͌������B�c���@�́A�v���`�i�̃J�t�X�{�^���A�N���A�����āA�ޏ��������炦�����݂����B4��22���A�{���́A��叫�\�\���B���ώ��A�{�����d���������\�\�Ɣ��ɁA�\���R�ɒ������Ƃ𖽂���ꂽ�B �@ �u�����̏���ւ����Ȃ��v �Ɣނ͋L�����B �@���̔�^�҂́A�͂邩�Ɍ���������ꂽ�B�������������Ȗk�i�h�̓�Ԏ�w���҂̐^��叫�́A��N���ɂ킽��A�����ɂ���čS�����ꂽ�B1936�N�̍Ō�̏T�A�����܂ł��ߏ��F�߂ʔނ́A�ꃖ���̃n���X�g���s���A���̍Ō�ɂ́A���������ۂ���(101)�B�a�@�ɒS�����܂�A��i�̌��ʂŌ��N��������ꂽ�ނ́A���ǁA�F�l�̍r�ؑ叫�\�\�k�i�h�̈�Ԃ̎w���ҁ\�\�� �u���j������Ƃ������̖@�����v�ƌ��������������āA���ߕ��ƂƂȂ����B���̕����́A�^��̑�t�߂ւ̂��ׂĂ̊ւ��������Ɏw�E���A����ĕt�����悤�Ȏ啶�ɂ��A���߂����Ă����B�ނ͖̎Ƃ́A�߉q�e���̓w�́\�\���h��`�̏�������A�푈�ɔ����鍑���I��v����낤�Ƃ���\�\���傫����^���Ă���(102)�B �@�R�������\�\�{��̂��߂ɖk�i�h�̕������X�p�C���A���m���̔����ɂ͂ǂ��������̑ԓx���������\�\�́A���N�R�̗��c�i�ߊ��ɍĔC�����ꂽ�B����܂ł̐������ԁA�ނ́A�{�삩��̎w����]��ɍL�����߂��A���������߂������߂ɂ��̒��É����������Ă��܂����̂ł͂Ȃ����ƈĂ��Ă����B�ނ̍Ȃɂ��A�ނ͗��_���A���Ԃ̎d����T���n�߂Ă����Ƃ����B������1936�N12���A�ނ̋{��ł̐ړ_�ł����������]�����̐�ݕ��O�Y���A�ނ̏�i�̎i�ߊ��Ƃ��Ē��N�ɕ��C���Ă����B��݂͂��̍ہA�V�c����̊��ӂƌ���̕��������Q���Ă����B�����ǂ�A�R���͑傢�Ɍ��C�t����ꂽ�B�����Ĕނ͂������ɗT�m����̐M����悤�ɂȂ�A1942�N�ɂ́A�鍑�̂��߂Ƀ}���[�𐪕����邱�ƂƂȂ�B(103) �@�����ɉ���������m���́A�e�E�Y�ɏ�����ꂽ�B�����\�\��ԉG�i�c���ÎE�����\�\�́A������͕삳��Ă����R�@��c�ɖ߂���A5��7���A���Y�̔���������A6��3���A���s���ꂽ�B9����A�����c���Ă��������R��19�l�̎m���̂�����13�l���A����ɑ����ďe�E���ꂽ�B�ނ�͑S���A�@��ł��̈ӎu�ƈӋ`�̐\�����Ă��������Ɗ�]���Ă����B�����ނ�́A�J��̈ꎞ�ԑO�A�R�@��c�@���m�����A���ꂪ���S����J�ŊJ�����̂�m�炳�ꂽ(104)�B �@�ނ�̂قƂ�ǂ́A���̎��̒��O�A�V�c�� �u���v �\�\�V�c�̉i�v�̖����F��\�\�����サ���B�������l���́A���]������ꂽ�F�l�A�����e���ɁA������������������B�u�����̈�̂͋M�a�ɂ��C�����܂��v �ƌ����c�����҂������B�����l�́A �u�����͂������������K���҂�̐[�����Ȃ��肤�v �Ƌ��B�ʂ̎҂́A���̐Â��ɂ��������c�����A�u�V���s����O�ɁA�F���V�c�É��̂��߂ɖ��������Ă���B�䂦�Ɏ������A�V�c�É����A�c�������J��Ԃ��܂��B�v (105) �@�܂��A���̎҂́A���R�Ɋւ��邢����������ȃ��b�Z�[�W���悤�Ǝ��݂��B �u���{�l���c�R�ւ̐�ΓI�M�����������Ƃ������قǁA���̐M���͗�����B���V�A�͒����A�W�A�ł͖��G�ł���A���ꂪ���{�ɔj��������炷�̂��v�B�k�i�h�́A���̓��[�̃E���W�I�X�g�b�N�ւ̂݁A���V�A�U�����l���Ă����B�����̎�v�s�s�Ɣ_�Ɛ��Y�n�т̏����̌�A�T�m�������S�������������āA���V�A�̘e���A�����A�W�A�ɍU������������ׂ��������B��������́A���݂Ȃ��ŏI��낤�Ƃ��Ă����B �@2�E26�����Ɋւ�������Ԑl���e�E�Y�ɏ����ꂽ���A�k��P�\�\�k�i�h�̘V�����_�Ɓ\�\�́A���̋����ԏe�����������Č������B �u����Ȃ���Ȃ��̂��A����Ƃ����̂܂܂ō\���̂��v�B�����ŏe�E�ǂ����炻���Ƃ���ƁA�ނ͋��B�u���点�����̂��B�L���X�g�⍲�q�@��i1645�N�����Y�ɂ��ꂽ�`���j�̂悤�ɂ́A�������Ă����킯�ɂ͂�����̂��ȁv�B �����A�ނ̂��̔���Ɏ���݂��҂͂��炸�A1937�N8��19���A�w�ɒ��ڂ���邱�Ƃ��Ȃ��A�ނ̏��Y�͎��s���ꂽ�B����܂ŁA���{�l�͔ނ̋��̉^���_�̐��_�����L���Ă����B����܂ŁA���{�l�͎�����A�����g��őO�i�����Ă����B�����Ă������āA���{�l�́A�����Ƃ̐푈�J�n���A���ƈꃖ����ɔ��点�Ă����B
http://www.retirementaustralia.net/rk_tr_emperor_50_21_1.htm
http://www.retirementaustralia.net/rk_tr_emperor_50_21_2.htm#kaiketsu |
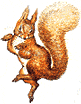
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B