http://www.asyura2.com/09/reki02/msg/566.html
| Tweet |
(回答先: 乃木大将の実像 (八切史観) 投稿者 五月晴郎 日時 2011 年 10 月 16 日 15:29:44)
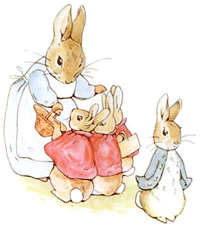
http://www2.odn.ne.jp/~caj52560/seppuku.htm
=転載開始=
【常人には不可解な切腹】
【紹介者・註】
この文は会議室で、乃木大将の切腹と、聖将として定着している通説に疑義を呈した「八切説」を紹介したところ、
ある方から質問があり、それに私が答える形で記したものである。
--------------------------------------------------------------------------------
○○さん今日は。御返事遅くなって済みません。さて、早速私の答えられる範囲でお答えいたしましょう。
>>しかし、酒乱で人を斬ったというのは始めて聞きました。これは、いつ、どこでお
>>こなわれたのでしょうか?
これは乃木大将の(1)で少し触れておりますが、酒乱で酔うと軍刀を抜いて暴れたということです。おそらく料亭で芸者を斬ったのでしょう。勿論こうした大将の神格化に邪魔になる情報は、公式文書に書かれよう筈もありません。
八切先生は終戦の時は満州におり(後で触れますが関東軍将校と切腹しておりますが、その時色々体験や伝聞した事が基礎になっていると思われます)当時の満州国公主嶺の料亭で酒乱の中尉が芸者の生首を叩き斬って、憲兵が来ると「軍神の真似をして何が悪い」と大声で喚いていたのを、先生は見てきた訳で、こうした事は、昭和になっても陸軍部内では「知る人ぞ知る」だったのでしょう。
>>「前線での将としての態度は芳しくなかった」とは、具体的にどういうことを指すの
>>でしょうか?
>>作戦、指揮に問題があったという意味合いなら仰るとおりですが、そうではなく、
>>生活態度に問題があったということでしたら、それは、具体的にはどのような人物の
>>証言や、記録に基づくものなのでしょうか?
>>私の知る限り、旅順攻略戦中の乃木の生活態度に問題ありとした史料はありません。
大将は前線でも「寛永三馬術」「真田軍記」などの講談本ばかり読んでいたということです。そして前線視察には副官を出して、自分は読書三昧では将としては失格です。記録では大将の副官の内一人死亡、一人は重傷とあります。
大将が第三軍司令官として出征するに当たり、白い髭を染める為、染め薬を何箱も持っていったといいます。しかしこうした行動の意味は、自分に背格好のよく似た副官に似せるため、髭を染めたわけで、何のことはない、大将の影武者です。亡くなったり怪我をした副官こそ哀れです。
何処に書いて有る、どんな史料によるのか?とよく聞かれます。これは実証主義(証拠主義)史観の方に多いのですが、
(日本の歴史学会はこの実証主義偏重で、史料や文献証拠がなければ認めないという頑なな態度を取っておりますが、こうした頑迷固陋な態度は学者に固有のもののようです。もっと自由な発想が出来ないものだろうか)
八切史観は伝聞も大切にします。例えば当時の「国民新聞」に載った本堂さんの談話。
「時事新報」に載った白鳥さんの談話。明治芸談こぼれ話、などの提説があります。
そして昭和四十六年当時七十五歳の中野区弥生町に現存していた白鳥模子さんから、大将の最期の様子を聞いて書いて居ります。彼女は当時十六歳で大将に可愛がられ、色々話しも聞いたといいますから、信じてもいいでしょう。
戦略、戦術、作戦この部分に関しては御説の通りです。私が少し問題を広範にし過ぎました。簡素に割り切って「作戦」を問題にするべきだったかも知れません。
>>体的な召集業務を担当していたのは、役所の兵事係ですが?仮に、各連隊で召集
>>業務をやっていたとしも、各師団は師団管区というものがあり、兵員はその中から集
>>められていますから、日本地図は不要です。
役所の兵事係が召集業務を司っていたのは仰る通りです。私の言いたかったことは、召集の段階で部落出身者を優先し、最も消耗の激しい所にさらに彼らを当てたという、差別思想があったということです。
>>乃木の更迭が問題となったのは、旅順要塞陥落後のことです。この時点で、乃木を
>>更迭したところで、兵の損害には影響はありません。
経済で「費用対効果」という言葉がありますが、これは軍事にも当てはまると思います。兵隊の犠牲を最小限に押さえて、目的を達する。
これに尽きると思います。日本の軍隊はこうした思想に欠けていたと思います。
いわば人命軽視の軍隊です。第二次大戦でさえ、機銃の火線の中へ銃剣突撃をしており、目的達成のためなら何人殺ししても可、とはならないでしょう。こうした状況からは最適な成果を得ることが出来るでしょうか?
そんな意味で引用したのですが、適切ではなかったかな?と思っています。
>>前回のレスでも書いたように、江戸時代、既に切腹は、必ず介錯を伴うように変わ
>>っていました。つまり、切腹だけでは死ぬまで時間がかかるので介錯が必要だという
>>ことは、江戸時代には常識となっていたのです。
そうでしょうか?
切腹とはこれはあくまでも武家時代の刑罰にすぎないのです。「勝者が敗者に与えた残酷な処刑、つまり差別感によって発生した階級的制裁」が、本質なのです。自尽、自裁、自害、自殺、屠腹、割腹、腹切、八切、色々の文字がありますが、本質は(自分の手で自分の生命を絶たせる方法)でしかないのです。普通に殺すよりは、より苦しめて死なせようとする、残酷な極めて嗜虐的なものなのです。
「百家説林続編後松記」によれば「およそ死刑は斬罪絞罪の二等しかなかったが、後世になって扶持を与えていた家来に対し、その罪を問う時に当たって、それまでの給与に対する裏切り行為への報復として、賜死の形で切腹は始まった」
として、その起源は足利時代かららしいと説いています。「貞丈雑記」においても、「日本記以下の国史に自殺の記事があるのは、みな縊死か或いは火を放って焼死するという形をとっていて、腹を切って死ぬような記載は見当たらない」と述べています。
ですから古来、切腹をする側が介錯人を同伴して行くなどという事は、作法にも
前例も無いのです。首斬りはもともと切腹させる側が、その証拠品として押収して持っていく必要上切り落すのであって、安楽に死なせようとする為の手助けなどする筈がありません。
早く首を打ち落し首桶へ納めるため、俯伏せになったりひっくり返ってからでは斬首するのが厄介になるので、業務簡素化を計ろうと昔は扇子腹といって、扇子で恰好をつけさせバッサリとやった程のものなのです。
敵味方という言葉は変ですが、切腹人にとって介錯人はあくまで敵の立場にあるもので、苦しむのを見るに見かねた同行者が、やむなく首を落とし楽にさせてやるという話しもないでもないのですが、初めから介錯人同行という事はなく、これはまったく独創的方法でしかありません。「一人口は食えぬが、二人口なら食える」という言葉がありますが、切腹も一人では至難ですが二人ならやれるのです。
>>それなのに、八切氏は、「切腹などで人間死ねるものではない。介錯がなければ出
>>血多量で死に至るまでには、何時間も掛かる。」(#005)ということを、自分が始めて
>>発見したかのように書いています。これは明らかに誤りです。私には単に、八切氏は
>>切腹に関する知識が無かったとしか思えません。
「死に対し同じ立場で向き合える唯一の自由さは、自分も死の中へ飛び込むことでしかない。そうすれば全てが限界を破って可能になるであろうから........」というのはカミユの書いた一節ですが<バーテイザン・レビュー>誌にも、文芸評論家のアルヴァレスが、「自殺のテクニック」という論文を発表していて、これは二十世紀に入ってから小説家の自殺が世界的に激増している点から、あらゆる技術を展開させ、その内なるものと死の方法の結びつきを解明しているものですが、
八切先生は何回かの自殺未遂もしています。前述したように切腹もしています。芝居や映画、講談で流布された誤った切腹の概念のために、つき合いの良いのも考え物ですが、自分で経験して苦しんでいます。
ですから、この時点での先生の「切腹に関する知識が無かった」というのは当たっております。この後自己の体験を踏まえて「切腹論考」をそして「士道論考」を書いたのです。以下にその部分を引用してみましょう。
至上に対し、敗戦のお詫びに関東軍の若手将校達と割腹したのだが、浅く刺して腹筋で左右に開くとは知らず、突き刺しすぎて倒れ、誰も介錯してくれずで首が繋がっていた。そこで北春日小学校の難民収容所の世話をしていた。
日に十体は遺骸となるのを、北陵の日本人墓地まで運べず校庭に穴を掘って埋めていたが、冬は零下三十度にもなる奉天なので地面に積み重ねて、ぐるり屍の砦を作ったが、それでも「救国忠勇軍」と腕章をまいた連中に襲われ、婦女子や子供部屋を庇って木刀で防いだので、脳天をナマクラ青竜刀でやられ今も六センチの傷跡が残っていて秋や冬は痛んで困っている。
「死美人」等という出鱈目を、故江戸川乱歩はよく使ったが、屍となって見られるのはまあいない。男も女も絶息した後は醜悪そのもので「死に化粧」して納棺せねば見られはせぬ。
だから北春日二○○一部隊長としてコロ島より帰国するまで一年半も屍に囲まれて暮らしてきた。(後略)
--------------------------------------------------------------------------------
さて、こうしたわけで、先生は物書きの一人として、普通の人に比べれば遥かに近い距離で死を擬視している人間です。従ってきわめて日本的な死である切腹については関心が強く、前大戦中にアメリカ政府が集めた資料がロスの公共図書館に揃っていると聞いて二週間がかりで文献のコピーもとってきて、これをもとにして発表したのが中央公論社刊の「切腹論考」なのです。
まあ、ここで私があれこれ言ったところで、理解するのは難しいでしょうから、今回の私のコメント部分を予告編又はイントロとして、
『論考・八切史観』の中の「切腹論考」を近日中にUPします。どうぞそちらをお読みになって下さい。切腹の美学とは血の美学です。そして先生の書かれた意図は決して「切腹」の奨励ではないということをお断りしておきます。
戦後四分の一世紀たったのに(注・本書は1975刊行のため1/4世紀といっている)「歴史」というものは案外に解明されていない。
それどころかかえって、もっともらしい仮面の中に収まりかえって、カプセルの儘伝承されて行くような気さえする。だから、それを好まないならば、どうあっても最早、これまでに聞かされた歴史はひとまずこれを一切否定するしかかなく、改めて「常識」というふるいをもってするしか、かっての歴史のあり方というものは考えられないことになる。つまり「真実とは何であるか」という命題を、過去の具象である「歴史」というものの中から、偽りのない視角でこれを補足し直さねばならないのが、これこそ、戦後二十余年の今日では絶対的な一つの義務でもある。
そして、かって嘘を教えた歴史家というものの存在に不信を抱くという事は、これまで伝承されてきた事柄へも疑惑を生じることである。
「ハラキリ」として有名な切腹も、それ自体がこれまでの歴史家の説くような、それは果たして崇高な自殺行為であったかどうか疑問が湧いてくるのである。
さて私は昭和二十年夏、満州の奉天にいた。八月十八日アスファルトの街路遠くから音させ、カタピラを響かせて重戦車の行列が入ってきた。赤いボロ布ともいいたい油と黒い汚染の付いた裂けたような旗がついていた。
クラフチェンコ赤軍司令官の進駐が始まると、奉天駅前から春日町へかけては一斉に満人の暴動が始まった。在留日本人は浪速通りの裏にある北春日小学校へ非難してきた。サーベルを腰に吊った男達も、紛れ込むように一緒に入ってきた。そして彼らは、「俺達は切腹するんだ」と言い出した。
初め彼らは五名いたが、途中で酒を買いに行くと出ていったのが戻ってこなくて、「それでは」と四人の中では年長なのが、真っ先に刀身をぬき手拭いで巻き付けてから「バンザイ」と春日神社の方へ拝礼して「やあッ」と気合いもろとも突き刺した。しかし、(自腹を痛めるのは辛い)というが、腹部の脂肪は強いのか、ゴムのフットボールを突いたみたいに切先が腹の処へ窪みをつけたきりで、刃は跳ね戻ってしまった。「突くものではない。力が倍いる。腹に押し当てて前のめりに身体で押すんだ」肩章はむしってあったが貫禄のあるのが、覗き込んで気合いをかけた。
しかし、その頃になって突いた窪みから血が滲んできたものだから、最初の男はそこへ唾をつけて、「痛いのう」と眉をしかめ上の空だった。「貴様らたるんどるぞ。生きて虜囚の辱めを受けたらどうする」と貫禄のあるのが立ったままで刀を腹に押し当て前え倒れた。これは血みたいな赤黒いものが出た。
小鉢に三杯ぐらいヒュッと音をたて飛んだ。すると他の者は転がった男の側へかがみこみ、刀身がどれくらいまで刺さっているか掌の幅で計ったりした。勿論当人は眼をカアッと見開いているものの気を失っていた。すると他の連中は、「しっかりしろ」と死のうと切腹している最中の人間の背中をさすって声をかけた。「その内に正気づくと、出血多量で死ぬまでは七転八倒の酷い苦しみ方をするぞ。
今ならば、腸を切ったかどうかぐらいだから縫合すれば助かる....医者を呼んで来てやらにゃ」顎髭の黒い男が云った。そこで私も、刺さった刀身から零れだす黒い血潮にあがってしまい、直ぐ飛び出して医者を迎えにいった。
しかし戻ってきた時には三人の男は誰もそこには居なかった。応急手当を受けて晒木綿の腹巻きみたいに包帯した切腹人間も、四日後には私にも黙って何処かへ行ってしまった。
だから、北春日大隊長として在留婦女子二千をコロ島から博多へ引き揚げさせた翌年から、「切腹論」といったものを集めようとしたが、不思議なことに納得出来るものは日本には無い。これまで誰も、まともに書いていないのである。だから、他から借物でないものとしては本稿が「切腹論」としては最初の物だろう。
さて、大正元年九月十五日付「国民新聞」には、当時の赤坂警察署の本堂署長が乃木将軍の切腹に際し行政検視に立ち会った一人として、「十三日午後八時に割腹された将軍の最期に関し誤謬が喧伝されているゆえ真相を語る」と前置きして、
「自分はこれまで多くの自殺を見ているが、これ程武士的な自決は初めてで実に模範的なものである」と断定し、
「二階八畳敷で夫人を左にして将軍は、まず上衣をぬぎシャツのみとなって正座し、腹下左の横腹より軍刀を差し込み、やや斜め右に八寸切りさきグイと右へ廻し上げて居られた。....これは切腹の法則にあい実に見事なものだった。
而して、返しを咽喉笛に当て、軍刀の柄を畳につき身体を前方に被せ首筋を貫通、切先六寸が後の頭筋にで、やや俯伏になって居られた。これに対し夫人は、紋付き正装で七寸の懐剣を持ち咽喉の気管をパッと払い、返しを胸部に当て柄を枕にあて、前ふせりになって心臓を貫き、懐剣の切尖が背部肋骨を斬り、切先は背中の皮膚に現れんとしていた。しかるに膝を崩さず少しも取り乱したる姿もなく、鮮血淋漓たる中に見事なる最期で見る者の襟を正させた」
と、まるで初めから立ち会っていたかのように仔細な描写がなされている。
しかしである。事実が間違いなくそうであるならば、十三日夜の自決が十四日の朝刊新聞に発表されたのに、同日の午後ににはもう「世上にデマがとび」、そこで署長が至急に記者会見し、翌十五日にこうした談話記事が出るのはいったい、何故であろうか。この時のデマというのは、今日では「殉死」とされている夫婦の死が「他殺」と噂を立てられたものである。勿論それなりの裏面史はあるのだが、ここでは命題からそれるから疑問はこれを後回しにし、当時の権力の末端が、模範的と折紙をつけた切腹の方式というものを考察するに止めたい。
一、に下腹に刀身を刺し通して、
二、に右に向かって八寸切りさき、
三、にグイと右へ廻して上げ、
四、は切り上げた刀身を引抜き、
五、はそれを持ち直し襟に当て、
六、で畳の下に柄を何かで固定、
七、で頭を木槌のごとく打ち込む、
各動作を順序よく狂いなく一分ずつやったと見ても、計七分間これでは連続してかかる。さて、現在の法医学の臨床データでは、
「第一の動作つまり異物を皮膚下に突入させた時点に於て八十三例中八十例までは、喪心又は失神状態に陥るものである」とされている。つまり今日私達が乃木将軍を崇拝するのも、この超人的な行為によるものである。なにしろ大正元年以降においても数多くの日本人が、日本刀による切腹をしているがこういう懇切丁寧な実話談話記事もないし、また、「模範」という折紙つきのものも他には知られていないからである。
--------------------------------------------------------------------------------
さて乃木将軍夫妻の記事を具象された型の崇高さから完全な事例として引用したが、これで見ると、死という行為も模範的に遂行しようとすれば、部分的に局部麻酔を施して取り掛かっても常人にはとても不可能である。
ところが戦争の匂いがしてくると、決まって「切腹」というものは、「死を鴻毛の軽き」にさせる為なのか、とかくよく議論されてくる。そして歴史家たちは『保元物語』の源為朝は、柱にもたれて割腹してから、自分の首の骨を後から切った。
『太平記』での新田義貞は、抜き放った太刀を左に持ち自分で首を落とし泥中深く埋めてから、まだ息があったのか、胴体を首の埋まった土の上に庇せて壮烈に死んだ。又、『義経記』では、幼少の頃より秘蔵して身から離さず持っていた三条小鍛冶の鍛えた短刀にて左乳の下から刀を後ろへ通れとかき切って疵の口を三方へ破り、腹中の腸をくりだしてから、刀は大切に衣の袖でおし拭って鞘に納め、ゆっくり死に到るまで休息したなどと、さも勇壮であったように書き、かっての私共はそれで教育されてきたのだが、これは、
「死花を咲かせる」といった供養のつもりだろうが、舞文曲筆どころの騒ぎではない。ただ『義経記』などは筆者が京の六道の辻の者と呼ばれた番衆たちで、彼らの仲間である唱門師が鉦を叩いて歌い歩く門づけ用にと作詞されたことは明らかにされているゆえ、
「これは京の三条小鍛冶で売り廻されていた毛抜きや、みやす針の売り込みのふれ文句」つまり、ひろめ唄だったから、ショッキングにパンチをきかせたものらしいというのが分かる。
が、後の面白可笑しく伝わったものは「戦争遂行協力」の使命に燃えた歴史家が勇壮さを賛美させる為に、かっての私共を戦場で死なせるように意図し教育したのだろう。
また「七生報国」が叫ばれた戦時中は、ゆっくり死なせることも流行した。講談や浪花節では、だからして有名人になるとあっさり死なせてしまっては勿体ないし、それでは客の期待にそわないから、例えば本能寺の信長も、『フロイス日本史』の「カリオン書簡」では、髪毛一本残さず爆薬で吹っ飛んでしまったとあるのを、水増しというか引伸ばしをし、『信長公記』では、信長を白綸子の寝衣のまま弓に矢をつがえてはなち、槍をふるって最期の武勇の程を示し、
肘に怪我をしてやむなく火を放って、おもむろに切腹をしたなどと荒唐無稽に飾って書かれている。つまり、どうせ死ぬにしても「ゆっくり間をもたせて」といった考えが、根本理念にあったがゆえに、即死でない死、つまり何拍子もかかる切腹という死に方を、かっては武士道精神の発露として奨励したものらしい。
また、ここで見逃せぬものに演劇がある。
これも首を吊ったり、刀を襟に当て首を落とすような仕草は演じにくいが、その点、腹を切るという動作は一つずつ節がついて区切れるから、舞台のメリハリがきく。「おのれッ」とまず突きたて、それから「無念」と横に動かして見得が切れる。つまり「見世場」と言う要素がとれるからして、あらゆる歌舞伎にはこの腹切が挿入された。
が、悪人が切腹したのでは観客は同情してくれない。そこで勘平のような二枚目か二枚目半の役柄の切腹というのがどの芝居でも殆ど同じである。つまり切腹の人気というのは、立役者や人気俳優から出たと見るのは、それは誤りであろうか。
また切腹の古語が、張付が一本棒でなされた頃に、「八付」と呼ばれたごとく「八切り」とも謂われていた事も考えたい。八とは、記紀にヤマトタケルノミコトに滅ぼされた八十梟(ヤソタケル)や八わたのおろちの八であり、「土俗八幡」と呼ばれる「八はたの藪知らず」の八である。(今では八幡をハチマン、ヤワタと呼ぶが、五街道図を見ても昔は「八はた」の地名が多い。これは官製の八幡宮に対する村の鎮守の八幡さまのことを区別して そう呼んでいた為である)つまり被征服日本原住民の称号が八であったからして、この切腹という行為は、公家の御方で遊ばされたのは一人の例もなく、みな俘囚の末である地家の者「地家武者」「地家ざむらい」と蔑まれた武家に限定されていた点を、ここで改めて検討しなくてはなるまい。
【名著『武士道』と反響】
今カナダのバンクーバーにその名をとったメモリアルガーデンを残している故新渡戸稲造先生は、日清戦争の四年後にフィラデルフィヤの出版社から『CHIVALRY』(武士道)という英文による不朽の名著を出し、今なお世界各国のパブリック・ライブラリーには、そこのマザーランゲェージに訳されたものが、必ずといってよい程、蔵書されている。
(何故それ程迄にこの本は欧米人向きなのか、私は久しく疑問だったが、バンクーバーでこの本の草稿を見せて貰って初めて判った。タイプライターが無かった頃のものゆえ手書きで、それが女性の書体ゆえ、先生の書かれたものを英国人の夫人が判りやすくリライトれ、それゆえ彼らに判りやすく広まったのかと納得できたのである)その中に「切腹」HARAKIRIと題し種々の引例をつけて、
「武士道は名誉の問題を含む死を以て、多くの多種多様な厄介さを一挙に片づける鍵とされた。これがため功名心とか見栄を張る武士は、自然死を潔しとせず天命を全うするのは、望む処にあらずとして、それが不自然であっても切腹は求められたのだ」といい、
「武士が恥を免れ己の誠実を証明する時、切腹は洗練された自殺方式であり、感情の極度の冷静と態度の沈着なくしては、これは又実行不可能なものでもあった」とわが武士道を説いた。そして新渡戸先生は、それらのことを異邦人にとく説得法として、きわめて近代医学的に、「デカルトは霊魂は松果腺に有るといった。解剖学では、まさか開腹手術をしてもそこから霊魂の摘出は出来ないからventre(腹)というのをcourage(勇気)と同義語にされたり、フランス語では腹を意味するentraillesがamour(愛情)pitie(憐憫)と同義語にもされている。つまり感情の中枢が心臓つまり腹にあるという考えから、日本の切腹は発祥している」と説明し直している。またそれに、
「近世の神経学者は、腹部脳髄、腰部脳髄といい、これらの部分における交感神経中枢は精神作用によって強い刺激を受けるという。この精神生理学が容認されたら切腹の論理は容易に構成されるであろう」とも言っている。
今日でこそ「腹痛は精神障害から」と遅まきながら日本医学もいいだしたが、これを七十年前に言いだし、それをもって、儒教的論理をエスカレートさせたのは、実に立派としかいいようもない。
さて新渡戸説というのは、時あたかも小国の日本が勝って清国から遼東半島や台湾などの割譲、賠償金二億テールの戦果に対し、ロシアがドイツ、フランスを誘って三国干渉をしてきた時代で、その後日露戦争が始まるとドイツのカイゼルは、「黄禍説」まで叫び「日本人とは、何というにんげんであろうか」と世界中がびっくりしていた頃である。
だからして(自腹を切れる気前のよすぎる死を恐れぬ人間)という評価が日本人にはこの時からつけられてしまったものらしい。さて、
「我が国はかくのごとく大勝利を占めた。しかし労農大衆は無益な戦いを欲しなかったから、やがて勝利を放棄した」
とロシア語の大きな説明カードが、真鍮製の機関銃の上に吊され、その下には真黒に埋まって地面も見えない、見渡す限りの日本兵の屍体の大きな写真が、ナホトカの国立博物館の二階には現在でも引き続き掲示されているが、それは、「山川草木うたた荒涼」どころの騒ぎではなく、真黒な服を着て折り重なって倒れている日本兵の屍骸で埋め尽くされ、山川草木なぞ何処にも見えはしない。
関東大震災の被服廠あとの死骸の山よりも、もっとうず高く203高地一杯に広がって死んでいるのである。これは日本では公開されていないが、「この死骸の山を踏み越え突撃し、また共に屍の中に埋没していった当時のあまりにも壮烈な日本兵という人間共」の写真であるが、とても、この勇壮さは異国人には理解も出来なかったろう。
そこで、まるでスフィンクスの謎でも解くように興味をもたれ、『CHIVALRY』はロンドンとニューヨークから再刊され、ハンブルクから独語版、そしてノルウェー語版、チェコ語版、仏訳、露訳と次々と各国版が出た。
だからこれを読んで「ああ日本人とは、かくも偉大な国民であるのか」と感心したのもいるし、またトルーマンごときは、「こんな日本人は危険であるから」と主張して、前大戦ではアトムを落とされるような目にもあわされたのだろう。そして「切腹」それ自体に対しても、ミッドフォードの『古き日本の物語』といったような、感心した好意的なものも、かっては現れたが、やがては『モリセリの自殺論』から引用などし、
「自殺という行為が、最も苦痛なる方法を選び、長時間の苦痛を犠牲にして遂行せられるケースにおいては、百中九十九までそれは狂気、狂信といったcrazyか、病的興奮による精神錯乱の結果によるabnormalでしかない」を論拠として、
「ハラキリ」とは、the idea of the nobility of self-destruction(自己消滅を尊厳とする考え)より発生した一種の特殊すぎる行為としての批判も多く刊行された。
そして、こうした文献は各国人種の坩堝といわれるアメリカのロスアンゼルスに多く集まっていて、ビルトモアホテル裏口正面のパブリック・ライブラリーに揃っている。
私は昭和四十二年五月そこのホテルへ泊まり込み、午前十時の開館から午後四時まで日参した。D・Hモオメントという英国系の歴史学者の『変節体制における自殺』というそこの蔵書では、切腹に対して手厳しい批判をあえてしている。オックスフォードで教鞭をふるったこともある彼は、その説として、
「従来は内科疾患とされ、それは内科医の受持ちであった病気も現在は外科医の領分となった。それまではレントゲン透視や胃カメラに頼って内科医が診察に苦労をしていたことも、今では外科医はメスによって開腹し、患部の処置をするとまた縫合させてしまう。何故かというと、腹部にメスを当てることは、皮下脂肪の層を切り裂くだけで、それ自体においては何ら人体に対し危険視されぬからである。
つまり日本人のハラキリというのは、あれは自殺目的ではなく、そこは切断しても縫合すれば安全であるという考えからして行われたdemonstationではあるまいか」
とさえ極言しているのである。これは、「歴史の追究というのは、それは自分の生きている社会と何らかの摩擦や衝突をした者がその敗北感から立ち直るため ”真実とは何か”と必死になって過去の具象にうちこんで解明するもので、貴族に雇われて御用歴史を書いり、教科書に採用して貰うために国家目的に合致させて著述するものではない」
と言い切って、二十世紀の歴史は、これまでの権力の歴史を放擲し、一般大衆の人間自身の真実の歴史こそ追究せねばならぬと主張するアイザノア・バーリンも、「腹を切る.....何とそれは愚かしき。もし解剖学が進んでいたら、腹と心臓の位置のあり方もはっきりしていたろうに.....ブルータスがシーザーに、わが剣もて逆さまにわが腹を刺せと言ったのだって、その時シーザーはこの世の者ではなく、霊魂
だったからこそ、こうした非現実的ないいかたをしているのだ。なのに日本人がそれをmorality とするのは、その国の歴史に於いてかっての国家主権者がそれを利用することに、価値を認めたせいではなかろうか」といっている。
つまり、かって大日本帝国が華やかであった時は、日本の歴史家によって特殊な栄光に輝いていたものが、敗戦後は、The ritual has provided subject matter(その儀式<切腹>は、何らかの用意された主題目的の存在にある)と言った具合にまでされてしまっている。
【意外に少ない実例】
ところで『貞丈雑記』という江戸時代のものでも、「日本紀以下の国史に、自殺した人の見えたのは、みな縊死や火を放っての焼死で切腹というのは、昔には例が無い」というし、『百家説林』の続編である「後松記」にも、「およそ死刑は、斬、絞の二種であって、自分から刃に伏す形式の切腹は、これは足利時代からではあるまいか」とその起源は明確にしていない。これは、あらゆる戦記物に出てくる武将や勇将が一人の例外も無しに、「最早これまでなりと従容として切腹した」ようになっているから、それに引っかかってのせいだろう。つまり軍国主義の時代に戦場で散華する日本兵は、「いたい」「やられた」とか「お母さん」などと女々しいことは一切これを口に出さず、みんな「バンザイ」と勇ましく絶叫したことにされ、そして護国の鬼と化したと伝えられているのと同じで、例証の出しようがなかった所為だったと思われる。
なにしろ足利時代の切腹の例ではっきりしているのは、永正元年(1504)九月四日。細川政元の被官摂津守護代薬師寺与一が淀城によって、叛いたところ失敗し、「われは一文字好みにて名も与一、名乗りも元一、そこで腹も一文字にこそ切らめ」
と切腹したという話が「舟橋一元院文書」として残っているから、それを確定史料と見てそれ以来切腹は足利時代からという考証になったものらしい。しかし「切腹礼讃」の時代になると、『続日本記』巻十の聖武帝の天平元年二月二十一日の条に「自尽の文字がある」とか、
「『保元物語』巻三にも切腹がある」「『日本霊異記』にもある」と、まるで古来からのようにも伝えられている。しかし確定史料における切腹は、『建内記』の永享十一年二月二日の条に現れてくるものと、それより六十五年後の薬師寺与一のもの位しか確実なものは見当たらぬ。もちろん、『太閤記』『清正公記』などの類には沢山な例があるが、あれは講談本の種本でしかない。
さて乃木将軍のような意志の強い人は、出血多量による死を以て切腹と言う行為をなしとげ得ても、普通はその真似は出来ず介錯といって背後から頸動脈を切断することによって、つまり首をはね落とされて死なされているのである。ところが、古文献の『和訓栞』では違う。
「かいしゃくとは仲介紹。つまり媒妁の意味にて、太平記や旅宿問答などには、取り持ちの意とあり、これは婚礼などの仲立ちのこと」とある。つまり「介錯」というと首を切ることと思われがちだが、戦国時代から江戸初期までの「介錯人」というのは「媒妁人」つまり仲立ち人だったのである。それが変わってきたのは、「徳川四代将軍家綱の延宝年間からである」と昭和九年秋文堂発行の谷川左一の書では考証されるが、切腹が正式になったのは五代将軍綱吉の時代で、これが法制化され実施されだしたのは、元禄十四年の浅野内匠頭の切腹。ついで翌々年の赤穂浪人の賜死からであるらしい。なにしろ、『弾左衛門覚書』によっても、彼の管轄であった江戸伝馬町牢屋敷において、俗に揚屋と呼ばれる士分の囚人に対して「切腹」という判決を下し、これを執行しだしのは、その元禄十六年が始めてだからである。
よく切腹切腹というから幕末まで何人ぐらい腹を切ったかというと、弾左衛門家には手代が六人世襲で居て、その中でこの担当は「首切り浅右衛門」として知名な代々山田浅右の名を世襲する一家であるが、維新後その十八代目浅右が市ヶ谷東京監獄署に転勤した時に綴った手記によると、元禄十六年より慶応三年までの約二百年間に切腹の介錯をしたのは僅か二十人。しかもその半数は、
「安政戌午の難」で捕らえられた志士たちなのであるという。つまり井伊大老の事件さえ無ければ、百年に五人の割合でしか公式には切腹はなかったのが事実のようでなのである。
これは江戸伝馬町牢内だけの話で、各大名家でそれぞれ切腹を仰せつかって屠腹して死んだ者はいるだろうが、それらの公式集計は、妙国寺事件のような国際的なものしか中央には報告されていないので、大公儀直接の記録としてはまことに僅かしか例はない。
それなのに「切腹」は何故に喧伝されたのか。また非公開で催される受刑者の有様が
「砂をまいた上に畳二枚を裏返しに置かれ、その上に白布又は赤毛氈をかけ、浅黄の水色の上下に白衣を着た受刑者が奉書紙に包んだ九寸五分を押し頂き、三宝を持ち上げて後ろへ廻し、おもむろに肩衣をはね腹をひろげる」
と、まるで見聞記のように仔細にあらゆる書に載っているのかというと、これは有り体に言うなら舞台の描写である。本物は二十年に一人の割で、それも他から覗けぬ牢屋敷内だったが、猿若座、市村座などの舞台では、のべつ幕なしに芝居で客寄せに使われていたのに起因する。
そして幕末までの芝居小屋というのは「河原者」として役者や座付き作者も扱われていた関係上、芝居興行の一切は、刑場預りの弾左衛門家の取締まりだったから、「本職が演技指導しとる」とでも思って、その舞台描写をもって切腹作法の本をしかつめらしく書いたものと考えられる。
なにしろ白い砂、赤い毛氈、裏返した黄色い畳裏、水色浅黄の上下と、あまりにもカラフルな絵になりすぎているし、これを演ずるのが人気役者であれば、切腹そのものが又おおいに評判になり有名になるのもやむを得なかったろう。しかし、そうはいっても、
『史料書』の「凶礼式」の部にも、目鼻のない顔で「説腹作法」が図版入りで懇切丁寧に、順序を追って説明されているのは、何故こういうものの必要が、誰の為にあったのだろうかと、今となるとどうしても率直な疑問を抱かざるを得なくなる。
『類聚名物考』等の本にも、図解式で長々と腹の切り方を説明した後で、
「今や泰平の世が百年に及び、人は武備を忘れ故実などを詮索するのを忌々しくさえ思っているが、これは怠慢であって万一の時には恥をかくことにもなる。実に武士の切腹たるや、晴れの業である。時明和九年壬辰正月。俊明これを誌む」など有るのを見ると、
「何の為こういうものが書かれたのか」まったく不思議でならない。これから旅行しようとする者がガイド・ブックを購入するように、さて今から切腹するという人間が、それではとこれらの書の「切腹入門」を求めてきて、はたして読むだろうか。いくら考えても、こうした切腹作法の書は(こうなって腹を切らされるようになってはいけないから、真面目にやるよう心掛けねばならぬ)と脅迫して戒めをしているものとしか思えないような疑惑があるのである。
なにしろ切腹のすすめや作法を書いている人間にしても、経験者でもなんでもなく、(こういう切り方をしたら痛かったから、貴方はこうでない切り方をしたらよい)というような注意も出ていない極めて不親切なもので、「左脇腹から右脇腹へ切尖にて1.5センチ位まず浅く左右に切れ」と、どれにも書いてある。この寸法は皮下脂肪の層だけを先ず切断しろというのである。「蛇の生殺し」というのがあるが、これでは「人間の生殺し」でしかなく、その強要は「武士道における名誉ある死」であるより、「極めて残酷な処刑方法」とも見える。
--------------------------------------------------------------------------------
つまり切腹そのものは、いくら美化され「崇高な死への選択」であると賛美を受け、「自分自身の手をもって行う動作だから、それは自発的な行為であるし、己で己の生命を処分するのだから、名誉ある死」という宣伝的な解釈をなされたとしても、死は、死以外の何物でもあり得ない筈だし数分前まで生きて動いていたものが、一個の物体化してしまう過程の残酷さにおいて「人手に掛かるは潔しとしないから切腹」と言っても、それは何の理屈にもならない。これは小児がパンを路上に誤って落としたとき、土が付いて汚い、もう自分の口へは入れられないと観念したとき、その忌々しさからか、はた又、犬や他の子供が拾ってはとという最期の所有権を示すためにか、自分の足で踏みにじるのと何の差もないのである。
そして自殺というものは、ストラハンの『自殺と狂気』においても、クイック・アンド・イージーこそ正常の自殺と見なされ、
「一刻も早く現実逃避したいという願望から起きるものであって、瞬時に絶命するような方法を誰しも選ぶものである。そうでなけれは天寿を全うせずに死に急ぐ意味合いはないからなのだ」と、これを定義している。
すると、切っても即死しないように皮下脂肪で刃を止め、おもむろに引き抜いた刀身を持ち替えて又突き刺すといった切腹は、「これは急速に死に到らないように、何動作にも区切るという形式からしても、それが狂気による嗜虐性の具象でないのなら.....それは自殺ではなくして、巧みに誘導される他殺への罠でしかない」という結果になる。つまりこうなると、「ハラキリとは自殺ではない」といった解釈もされうるのである。
【方言を誤訳した「腹切り」】
「武士道とは死ぬことと見つけたり」と、葉隠論語にあると、戦時中しきりに教えていた歴史家もいた。そしてそれが「戦陣訓」というパンフレットに挿入されてからは、屠所の羊のように集められた私達はかっての日、「死んでしまえ」と殴られ蹴られ戦地へ持ってゆかれた。私など今でもその時の想念が染み込んでしまっていて、手帖などに時には「死にたいを堪えて今日も生きていき」と、書き込んだり他処への葉書に書きもする。つまり、(死んでしまえば、この訓練の苦しさ、現実の疲労困憊からも脱出できる)というような根本理念、つまり進んで戦死する気構えというか諦観が徹底的に叩きこまれた。
「死のすすめである切腹」に関しては、それが軍の敢死敢闘精神を兵に教育するのを護持する関係上、旧軍部は歴史家を尊重してこれが虚妄を書く者であったとしてもその都合上からして、利用度において、世間の信用をますために、
(歴史とは考えるものではない。国が保証する歴史家の書かれた物なら、そのまま鵜呑みにして棒暗記こそするものである)といった考えからこの国では、歴史は暗記物として教育を強いられた。
しかし、死を薦めるのに明治軍部は、オポチェニストの歴史家を活用したが、これは何も彼らの創案ではない。明治軍部というのは長州人がその上層部をしめ、監督指導をしていたのは、これは周知の事実である。その長州たるや幕末に、「腹切りのすすめ」をしていた所なのである。かって明和四年に藩で偏した、「御家誠」というのを、幕末の安政二年になると、儒臣中村清旭にその判りやすいものを作らせ、それを『大訓衍義』として木版刷りにして藩の子弟の教育の基本とした。この中に、「毛利隆元様御自筆、五月六日、児玉三郎右衛門あて下さるの書」の一項目がある。
「只今の世上には誠に、腹せを切り候えと人に申しかけ候共、否と申し候ものは有るまじく」という一章で、安政版にははっきり冒頭に、
「切腹のこと」と冠詞されている。つまり幕末の毛利家の青少年は一人残らずこれによって、
「隆元(元就の子)様の頃の長州人は”腹せを切れ”といわれたら一人も否応なしに切腹したものである。つまり死を鴻毛の軽きにおいて御家に尽くしたからこそ、毛利家四百年の基礎を固める事ができたのだ。なのに近頃の若い者は何だ。先ず切腹作法の訓練から致せ。いつでも長州人は、ちゃんと腹を切れるようにしておけ」とエデュケイションされた。
(三つ子の魂百まで)というが、これで教育された乃木将軍が、やがて割腹といった
型式で殉死するのも、ここにその起因がある。つまり乃木個人の性癖によってその行為を判断するが如きは、群盲が象をなでるようなものでしかない。そして幕末長州人の上層部は、
(いいか、自分で己の腹に刃をあてるというのは大変な事だ。それで死ぬことの苦労を思えば、まあそれよりは敵に飛び込み、死中に活路を求める方が、まだしも容易である。切腹は始めだしたら死なねばならぬが、身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれて゛勇ましく戦えば命拾いもするぞ)と、下層の子弟を教育し、やがて彼らを率い蛤御門で戦い長州征伐の軍を追払い、ついには「とことん取れな」と江戸幕府を倒し、やがて長州人の天下を作った。
しかし、こういう事を書くと古い歴史家や長州出身者には叱られるだろうが、私は昭和四十三年読売新聞に「毛利は四矢」を連載するに当たって、毛利元就の生まれ育った広島県吉田の多治比へ古史料を蒐集するため赴いて滞在していたところ、
「維新の大業を遂行させた」といわれる、「腹せを切り候えと人に云わば否と申す者なく」という金科玉条の「腹せ切り」を幕末の長州は「腹切り」と単純に解釈してしまっているが、これは元就発祥地の多治比では、「腹背切り」つまり「身を粉にして」とか、「腹背一体二心なく仕える」といった意味で、つまりは安芸の方言なのである。
処が、慶長五年の関ヶ原合戦後、毛利は防長二カ国に押し込められた。つまり元就や隆元の生れ育った安芸地方は、徳川に取り上げられて浅野家の領地となってしまった。だから三百年後の幕末になると毛利家の儒臣は、もはやこの方言が分からず、これを切腹の勧めに用いてしまい、真面目な乃木将軍をして、「腹背をきって」御奉公させたあげく、肉体的にも腹から背まで切らせてしまったものらしい。しかし明治三年に長州人の新政府は、「新律綱領」を立案した時、士族や官吏には「閨刑」として切腹をすすめた。
そして「名例律上」の中の罰則に、「自分から屠腹を致すこと」というのを設けた。しかし長州人は幼時から切腹の仕方を教わり、図式でも習っているが他国人は守りそうではないから、折角奨励しても「結構です」と他殺である斬首の方の希望者が多かったので、これは今で言えばザル法となってしまった。そこで、明治六年の改定律令では切腹刑はもはや廃止されている。
【自己不満の表現と抵抗】
しかし刑罰ではない切腹はその後も「武士道精神の権化」として終戦までは、神がかりの歴史家に推奨された関係上、多くの人々がこの困難な死の方法へ突入し、二十五年前の夏には、阿南陸将を初め多くの軍人や宮城前では集団の男女が、歴史の嘘に瞞されて切腹という苦しい死の中でのたうった。
今日では盲腸手術をしても、昔のように縫合せず、クリップで挟んで自然治癒させるだけだし、腹部は血管があまりないから、一滴の血も出さず行われている。つまり腹を切っても容易に死ねるものではないから、阿南大将は拳銃を、宮城前の男女はもがき苦しみ最期は手榴弾によって自分で自分らの腹切りの始末をつけねばならなかった。ただ
代々木練兵場で、「国うれうやたけ心のきわまりて、静かなるかも神あがるとき」の辞世を残し、壮烈果敢にも、「このたびの敗戦は全く何と天子様に申訳けしたらよいのか、御詫びの言葉もない」と昭和二十年八月十五日に、景山庄平翁以下十四名の大東塾生徒達だけは、同志の者が首をはねて廻ったらしい形跡があるというが、手榴弾も使わずに腹切りで見事に「清く捧ぐる吾ら十四柱の皇魂誓って、無窮に皇城を守らん」と、
死んでいるが、これは希有な例であろう。
つまり真実の切腹ブームを、芝居の人気ではなく本当に作ったのは、それは封建時代ではなく、1945年、今世紀の昭和二十年だったのである。しかし切腹そのものをというより、自殺すらも出来ない人間が多いから、
「敗戦のお詫びを一死をもって償ったのだ」といった表向きだけの評釈がされ、今もそう言われている。だが、私をしていわしむれば、「死んでお詫びする」といったような発想が本当に、人間には有るのだろうかといいたい。芝居の台詞や、言いごととしては放言もする。
しかし本心からそんな感慨は持つものではあり得ない。これは叱られ文句をいわれ、「心を入れ替えます」と口では誓っても、人間の心などというものは、オーバーホールしたりスペアの取替がきくものではないから、そう言って相手に満足感を与えるだけ、唯それのみに過ぎないのと同じことではなかろうか。
死とは、自殺とは「泣き」の変形である。泣きとは、悲哀よりも、口惜しくてなんともならぬ状態における感情の昂揚である。つまり自殺とは、腹立ちや忌々しさを抑圧できなくなった時の衝動的行為といえる。
そしてその自殺を、直接には切断しても致命傷にならない腹部皮下脂肪から始めるハラキリ行為とは、死に近づくという想定のもとに発散させる自己不満の表現でしかない。
言い換えれば切腹というのは単純自殺ではなく、これは protest 以外の何物でもない。大東塾十四烈士の死も「国内政治の腐敗堕落が敗戦の根本原因だった」ということへの抗議の死である。
即死ではなく緩慢な死への道程に身を処して、そこで憤怒と口惜しさとをぶちまけ、こんなザマに誰がしたかと抗議するのが、切腹それ自体の本来の姿でなくてなんであろう。だから人気のある四十七義士が切腹したから、偉大な乃木大将が割腹したからと、「人生は模倣である」とはいえ、
こればっかりは無目的に礼賛など出来はしない。また抗議をするに先立ち、皮下脂肪を切り「死を覚悟」して諫言するのを「諫め腹」ともいうが、これは、「鳥の落ちんとするやその声悲し、人の死なんとするやその声正し」というのを利用してのものだが、これは後幕末のやくざに利用されて、掛合い事をするときに、さあっと横腹に刃を当てがい、横になっている腹筋がそのまま口を開けるのを相手に見せつけ脅しに用いたものである。
腹部には皮下脂肪が溜まっているゆえ腹を切ったら、白い脂肪が覗くだろうと思う人も居るようだが、脂肪が白く凝固するのは死んでからであって、肉屋の店頭のロースや霜降りとは違う。まだ生きている人間の腹の切口は真赤なのである。
清水の次郎長は下腹部に十二本、その舎弟分の「はらきり重蔵」こと石屋の重蔵は二十本の余も腹を切った後があったといわれる。
つまり幕末のやくざが晒木綿を腹にまいていくのは、今とは反対で上から下へと巻いてゆき、下腹部をひろげて刃をあて、横裂きを見せ、話がつくとぐっと腹の力を抜いて晒木綿を下げ、焼酎をぶっかけて消毒し癒着させていたようである。
(やくざが喧嘩仕度の時新しい晒木綿を巻いて行くのは、なにも腹をきりっとさせるためではなく、怪我した時の包帯用にと自分自身で巻いていったのである。だから晒の無い時は、怪我をしないよう古帳面などを水に濡らして、べたべた貼布していったという)
しかし明治十六年の博徒一斉かりこみの時に、やくざに対し、屠腹の真似をするのが恐喝罪を適用されてから、それまで花柳界の起請代りの小指落としが彼らの社会へ入って「指をつめる」等と転用されてしまったのである。
さて刑罰以外の切腹というのは明快にいえば、「本来の自殺行為の目的の前に、抗議つまり自己主張がある」ということ。
裏返せば、
「自己の言い分を通すために、付加的に己の生命を放棄する」という、純粋自殺行為からは全く離脱したものであるのを考え、
「武士道精神による名誉ある死」といったような表現は、新渡戸先生のように外貨獲得の輸出用なら差支えないが、国内向きにはこれは困難すぎるからして慎まねばならぬ。
なにしろ、「ハラキリは絶対に自殺ではない」からである。そして、どうかこれから自決しようと志す人は「かっこよく」などと、惑わされる事無く、自分のことゆえ、もっと確実にして安全な方法をぜひ選ばれたがよかろうとおすすめしたい。
<<終わり>>
【引用参考文献】
八切止夫著「論考・八切史観」(日本シェル出版)
=転載終了=
|
|
|
|
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
|
|
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。