14. 2012”N7Œژ09“ْ 23:47:08
: tCTeyFIUac
پu’n•\پv‚ج‹C‰·‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپA–ˆ“ْ–ˆ“ْ‚جپu“V‹Cپv‚إ•د‚ي‚éپA“V‹C‚ةچ¶‰E‚³‚ê‚éپB ڈ]‚ء‚ؤپAپu’n•\‚ج‹C‰·پv‚ح‚ ‚ـ‚èˆس–،‚ً‚ب‚³‚ب‚¢پB‚؟‚ه‚¤‚ا“dکb’ ‚ج“dکb”شچ†‚ج•½‹د‚ًˆêگ¶Œœ–½ڈo‚·‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚إپA‰½‚ً‹پ‚ك‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©•s–¾پB ’n‹…‹K–ح‚إ”M‚‚ب‚ء‚½‚èپAٹ¦‚‚ب‚ê‚خ‚»‚ê‚ح’n•\‚ة‹y‚ش‚ھپA‚¹‚¢‚؛‚¢گ”ƒJŒژ‚إ‚©‚ي‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚à‚جپB “V‹C‚ةچ¶‰E‚³‚ê‚éپپ•½چt‚إ‚ب‚¢پپ‚à‚ج‚حˆس–،‚ھ‚ب‚¢پB پiڈd—vپIپj ‰·“x‘ھ’è‚جŒ´‘¥‚حپu•½چtپv‚ئپAپuڈًŒڈˆê’èپv‚إ‚·پBپi“V‹C‚ًپAگ°‚ê‚ئ‚©‰J‚ئ‚©پA•—‘¬‚â‹Cˆ³ˆê’è‚إ‘ھ‚ç‚ب‚¢‚ئˆس–،‚ب‚¢پBپj
پu’n•\پv‚ح•½چt“_‚إ‚ب‚پAڈًŒڈ‚à“V‹C‚إ•د‚ي‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پB پu’n‹…‚ج•½‹د‹C‰·پv‚حپA’n‹…‚ج•½چt“_پ—‚T‚T‚O‚O‚چ‚ج•½‹د‹C‰·‚إ‚·پBپiپ|‚P‚Wپژپj پu’n•\‚ج‹C‰·پv‚ً‚¢‚‚çڈW‚ك‚ؤ‚àپAپu’n‹…‚ج•½‹د‹C‰·پvپiپ—‚T‚O‚O‚ˆ‚o‚پپj‚ة‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢پBپi‚؟‚ب‚ف‚ةپu’n•\‚ج•½‹د‹C‰·پv‚ح‚P‚Tپژپ—’n•\پi‚PپC‚T‚چپj پ@پ@پE’n‹…‚ج•½‹د‹C‰·پFپ|‚P‚Wپژپ—‚T‚T‚O‚O‚چپA‚T‚O‚O‚ˆ‚o‚پ
پ@پ@پE’n•\‚ج•½‹د‹C‰·پFپ@‚P‚Tپژپ—’n•\پi‚PپC‚T‚چپA‚P‚O‚P‚R‚ˆ‚o‚پپj
پ@پ@پEگlچH‰qگ¯‚إ‘ھ‚ء‚½’n•\‚ًٹـ‚ق’n‹…‚ج•½‹د‹C‰·پFپ|‚P‚WپD‚Vپژ
پi•â‘«پj
پ@پuŒ¾—tپv‚جˆس–،(’è‹`)‚ً‚ح‚ء‚«‚肳‚¹‚éژ–‚ح‚ ‚ç‚ن‚é‚à‚ج‚ة‚ئ‚ء‚ؤ”ٌڈي‚ةڈd—v‚إ‚·پBپw’n‹…‚ج•½‹د‹C‰·پx‚ئ‚حپA‘ه‹C‚ج–w‚ا‚ھ‚ ‚é‚ئ‚³‚ê‚é‘ه‹C‚ج‘خ—¬Œ—‚ج’†ٹش‚T‚T‚O‚O‚چ‚ ‚½‚è‚ة‚ ‚é‚ج‚إ‚·پB
پ@
‚¾‚©‚çپA‚»‚جƒfپ[ƒ^‚ھ‚ا‚ج‚و‚¤‚ةچى‚ç‚êپA‚ا‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚إ‚ ‚é‚©‚ةٹض‚ي‚炸پA’nڈم‚جأق°ہ‚ً‚¢‚‚çڈW‚ك‚½‚ئ‚±‚ë‚إپAژc”O‚ب‚ھ‚çپw•½‹د‹C‰·پx‚ھڈم‚ھ‚ء‚ؤ‚éƒfپ[ƒ^‚ة‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢‚ح‚¸‚إ‚·پB
پ@
‘ه‹C‚ئ’n•\‚ح”M“I‚ةˆê‘ج‚ج‚à‚ج‚إپAپu”M“Iپv‚ةگط‚è—£‚¹‚ب‚¢‚à‚ج‚ب‚ج‚إ‚·پB‚¢‚ي‚ن‚éƒtƒgƒ“‚ج•”•ھ‚إ‚·پB
پ@‰·ژ؛Œّ‰تک_پE•ْژث•½چtک_‚إ‚حپAƒtƒgƒ“‚ئŒ¾‚¢‚ب‚ھ‚ç–µڈ‚‚ھ‚ ‚ء‚ؤپA’n•\‚ئ‘ه‹C‚ھ–‚–@•r‚ف‚½‚¢‚ةژص’f‚³‚êپu”M“`“±پv‚ب‚ا‚ھ‚ب‚¢‚و‚¤‚¾پB
پ@
–{“–‚ح”M“I‚ةŒq‚ھ‚ء‚ؤ‚é‚ج‚إ•½‹د‚حڈم‹َ‚ة‚¸‚ê‚邵پAگlچH‰qگ¯‚حگ¥‚ً‘ھ‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ة‚ب‚éپBٹî–{“I‚ة‚±‚±‚ھٹشˆل‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·پB پ@‘¾—z‚©‚ç‚ج“ْژث‚ج•ْژثƒGƒlƒ‹ƒMپ[‚ح’n‹…‚ج‘ه‹C’†‚ً’ت‚ء‚ؤ’n•\–ت‚âٹC‚ب‚ا‚ة‹zژû‚³‚ê‚éپB پ@‚½‚ئ‚¦’n•\–ت‚ب‚ا‚ھ‚¢‚‚ç‰ك”M‚³‚ꂽ‚ئ‚µ‚ؤ‚àپA’n•\–ت‚âٹC–ت‚ب‚ا‚حپu”M“`“±پv‚âپu‘خ—¬پv‚ ‚é‚¢‚حپAپuگشٹOگü•ْژثپv(’n‹…•ْژث=•ْژث—â‹p)‚ئŒ¾‚¤Œ`‚إپu”Mپv‚ً•ْڈo‚·‚éپB پ@‚»‚µ‚ؤپAپu‘ه‹Cپv‚âٹC‚ھ”M‚ً‹zژû‚µ’g‚كپAپu•ْژث—â‹pپv‚âپu”M“`“±پvپAپu‘خ—¬پvپAڈِ”پv‚ئŒ¾‚¤Œ`‚إپA‹C‰·‚ً‰؛‚°ˆہ’è‚·‚éپBپiƒGƒ“ƒgƒچƒsپ[‘‘ه‚ج–@‘¥پj
پ@
پ@‚»‚جŒم‚àپA‘ٹŒف‚ة”M‚ح‰e‹؟‚µ‚ ‚ء‚ؤ•½چt‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·پB‚»‚µ‚ؤپu‰·“xچ·پv‚ھˆہ’肵‚ؤپA”M“I‚ة‚حˆê‘ج‚جپu”MŒnپv‚ًچ\گ¬‚µ‚ـ‚·پBپu‰·“xچ·پv‚ھ‚ ‚é‚ئ‚«پAپuژdژ–=‹CڈغŒ»ڈغپv‚ھ‹N‚«‚é‚ج‚إ‚·پB پ@پu’n‹…پv‚ة‚ح‹…‘ج‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ب‚ا‚©‚çپu‰·“xچ·پv‚ھڈي‚ة”گ¶‚µ‚ـ‚·پB‚±‚جپu‰·“xچ·پv‚ً‰ًڈء‚·‚é‘ه‹C‚جپu”Mˆع“®پv‚ھˆظڈي‹Cڈغ‚ًٹـ‚ق‘S‚ؤ‚جپu‹CڈغŒ»ڈغپv‚إ‚·پB
پ@‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤپA‚»‚جپu•½‹د‹C‰·پv‚ئ‚µ‚ؤ‚ح’n•\‚ئ‚حŒہ‚ç‚ب‚¢‚ج‚إ‚·پAپw‘خ—¬Œ—پx‚جڈم‹َ‚ة‚ب‚é‚ج‚إ‚·پB پ@پu’n•\پv‚ح‚¹‚¢‚؛‚¢‚P‚چ‚‚ç‚¢ڈم‚إپAپuƒqپ[ƒgƒAƒCƒ‰ƒ“ƒhپv‚ب‚اپu’n•\پv‚ج‰e‹؟‚ً‹‚ژَ‚¯‚é‚ج‚إپA‘ه‹C‚ًٹـ‚قپu’n‹…پv(=‘ه‹C+’n•\)‘S‘ج‚جپu•½‹د‰·“xپv‚ئ‚ح‚¢‚¦‚ب‚¢پB پi’n‹…‘S‘ج‚ج‚ ‚ç‚ن‚é‹Gگك‚ئژٹش‚ئڈêڈٹ‚جپA’n•\‚ج•½‹د‰·“x‚ب‚اژو‚ê‚ب‚¢‚µپA‚»‚ê‚إ‚ب‚¢Œہ‚èژو‚ء‚ؤ‚ف‚ؤ‚àˆس–،–³‚¢پB‚ـ‚½پA‚P‚O‚O”N‚إ‚O.‰½“x‚ئ‚©‚جŒëچ·‚ج”حˆح‚ًڈW‚ك‚ؤ‚ف‚ؤ‚à‰½‚جˆس–،‚à–³‚¢‚±‚ئپBپj
پEپw’n‹…پx‚ج•½‹د‹C‰·پFپ|18پژپi’n‹…=‘ه‹C+’n•\پj¥¥‚±‚±‚©‚çڈo”‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پB ¥پu’n•\پv‚ج•½‹د‹C‰·پF15پژ‚ئ‚³‚ê‚éپEپEپE‚±‚±‚إ‚ح‚ب‚¢پB
پiپu’n‹…‚ج•½‹د‹C‰·پvپFپ|‚P‚Wپژ‚ئ‚حپA‚T‚T‚O‚O‚چڈم‹َ‚ج‚ ‚½‚è‚إ‚·پBچں‚ê‚ح’n•\‚ئ‘ه‹C‚ًٹـ‚ك‚½•½‹د‹C‰·‚إپAژہچغگlچH‰qگ¯‚©‚ç‘ھ‚ء‚½‰·“x‚ئˆê’v‚µ‚ـ‚·پBپj پ@‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤپA–{“–‚جˆس–،‚إ‚جپAˆس–،‚ج‚ ‚éپw’n‹…‚ج•½‹د‰·“xپx‚جƒfپ[ƒ^‚ئ‚µ
‚ؤ‚حپAژc”O‚ب‚ھ‚ç‚U‚O”N‘مˆبچ~چإ‹كگlچH‰qگ¯‚إ‘ھ’肵‚½‚à‚جˆبٹO‘¶چف‚µ‚ب‚¢‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤پB پ@–{“–‚ةپu’n‹…پv‚ھڈ‹‚‚ب‚ء‚ؤ‚é‚©ٹ¦‚‚ب‚ء‚ؤ‚é‚©‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA’n•\‚ج‰·“x‚¾‚¯‚إ‚ح‚¾‚ك‚إپA‚à‚ء‚ئ’·ٹْٹش‚ة‚ي‚½‚éچ‚‹َ‚جƒfپ[ƒ^‚ھ•K—v‚ئ‚¢‚¦‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚¢‚‚çگlٹش‚ھڈZ‚ٌ‚إ‚é‚©‚ç‚ئ‚¢‚ء‚ؤپAپu’n•\پv‚خ‚©‚èڈW‚ك‚½‚ئ‚±‚ë‚إ‰½‚جˆس–،‚ب‚¢‚ج‚إ‚·پB |
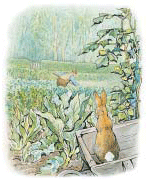
 ƒXƒpƒ€ƒپپ[ƒ‹‚ج’†‚©‚猩‚آ‚¯ڈo‚·‚½‚ك‚ةƒپپ[ƒ‹‚جƒ^ƒCƒgƒ‹‚ة‚ح•K‚¸پuˆ¢ڈC—…‚³‚ٌ‚ضپv‚ئ‹Lڈq‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
ƒXƒpƒ€ƒپپ[ƒ‹‚ج’†‚©‚猩‚آ‚¯ڈo‚·‚½‚ك‚ةƒپپ[ƒ‹‚جƒ^ƒCƒgƒ‹‚ة‚ح•K‚¸پuˆ¢ڈC—…‚³‚ٌ‚ضپv‚ئ‹Lڈq‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB