| Tweet |
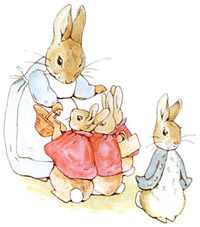
http://moneyzine.jp/article/detail/168961">富裕層のウソとデマにだまされるな お金持ちは決して下流に同情しない:株/FX・投資と経済がよくわかるMONEYzine
お金持ちは平気でウソをつき、お金持ちのタニマチは、本当のようなデマを流す。下流の人たちは疑いもなく信じて、同情さえするが、お金持ちは決して下流には同情もしないし、情けもかけない。そのカラクリを明らかにしよう。(http://moneyzine.jp/article/corner/62/">バックナンバーはこちら)
■「景気が底を打った」というデマ
これまで、富裕層の特集を連載してきたが、「本当に彼らの提唱する論理や言い分は正しいのであろうか?」という疑問がわいてきた。どうも自分たちが有利になったり、自分たちだけが得をする理論を誘導しているのではないか。
そんな疑問の中で、突然にリーマンショックが起こり、国民が苦しんでいる反面、富裕層向けのマーケットは相変わらず盛況を博していた。そして現在、国民経済も大不況からようやく回復しつつあるようだ。
日本政府は、景気について「底を打った」と宣言している。本年6月27日に、与謝野経済財政担当相が、「底打ち宣言」したが、それは正しい判断ではなかった。案の定、その宣言から半月後、6月30日に発表された政府統計では、雇用の状況が一団と悪化していることがわかった。
有効求人倍率は0.44倍と過去最低で、特に「正社員」の求人は、0.24倍と休職者の4人に1人しか求人がない状態である。そのうえ、完全失業率は5.2%となり、過去最低だった5.5%に迫りつつある状況だ。
では、政府はなぜ底打ち宣言をしたのか。与謝野大臣によると、「輸出や生産などのグラフが上がり始めた」からだという。確かに、5月の鉱工業生産指数は3ヵ月連続で上昇して、自動車や電子部品などの生産が持ち直していた。
しかし、その裏側には、いろいろな側面があり、短絡的に景気底打ちの判断ができる状況ではなかったのだ。例えば、2002年2月から始まり、いざなぎ景気を超えたといわれ、2007年10月まで続いたとされる、戦後最大の景気拡大局面では、大企業があのバブル期の2倍以上の儲けを上げたにもかかわらず、労働者の賃金はほとんど増えなかったのである。
利益のカラクリは、正社員を派遣社員に置き換えて、賃金や部品などの単価を抑えることで、輸出企業が大儲けしたというのが実態である。
その後、2008年の秋口には、ご存じの通りリーマンショックが起きて、派遣切りやリストラが横行し、正規非正規にかかわらず労働者を踏み台にして、立ち直ろうとしているのだ。
これは、人件費がグローバル企業の成長の足を引っ張っており、それを削減することで、企業の経営が安定するという経済理論によっている。
経済改革論者(自由経済論者ともいえるが)は常に、国際競争力を保つためには、固定費を最小にして配当をより多くすることで、株主も納得して、企業の国際的な評価も高まり、ますます資金も集めやすくなると説く。こうして、小泉改革など一連の経済改革が断行されてきたのだが、はたしてこれは真実なのだろうか。
■「人件費が経営を圧迫している」というデマ
日本の自動車メーカーを例にとって見てみよう。トヨタやホンダ、日産、スズキの売上高に対する人件費の割合は、ほぼ1割程度である。
この点は、ソニーやパナソニックといった電機メーカーも同様だが、ここで言いたいことは、たとえ人件費が2倍になっても、企業の経費は10%程度増加するだけで、企業の負担自体はそれほど大きくはならないということだ。
では逆に、人件費を大幅に削るとどうなるだろう。
3割カットしたとすると、各従業員の可処分所得は5〜7割も減ってしまうので、消費性向も大きなマイナスになり、商品が売れなくなる可能性が高いわけだ。
企業側からすると、人件費を3割削っても、経費は全体で3%ほどしか削減できないのだが、市場が縮小するという恐れと比較すると、結論は自ずと見えてくるのである。一方で、もし人件費を2倍にしたとすると、消費意欲が大幅に拡大して、市場も大きく広がることが予想できる。
■格差が広がると安物しか売れなくなる
話は少し古くなるが、ここで紹介しておきたい実例がある。
時は90年代前半の米国。日本製のテレビやビデオが、米国の家電量販店でたくさん売られていたが、ビデオデッキは日本に比べて数世代古い、型落ち商品が並べられていた。それでも、大量に売れたのは、貧富の差が大きく、一般市民は型落ち製品しか買えなかったからだ。
当時、ビデオデッキはVHSとベータ、そして米国式との三つ巴の規格戦争の真っ最中で、商品価格もほぼ同じで、だいたい25万円程度であった。
ここで日本の労働者は、ボーナスなど一時金でビデオデッキを購入したのに、貧富の差が大きかった米国の一般市民には手が出なかったのだ。
その結果どうなったかというと、日本の商品が大量に売れることで、コストダウンが図られ、さらに価格が下がり、米国式は敗れ去って規格戦争に勝利することになる。つまり、消費意欲を促進することで、企業間の競争にも勝利することができたのである。
このようにして、米国の製造業が弱体化する中で、いまだに強い産業がある。それは、希少価値を誇り、高額でも購入してくれる顧客がいる業種である。ひとつは航空機関連産業、もうひとつは医療機械関連産業である。
どちらも、労働者が購入するものではなく、限定的な特殊なマーケットである。だからこそ有効なわけで、家電や自動車など一般市民を対象とする産業にはあてはまらない。
労働者の給料が下がり、格差が広がると、安物しか売れなくなるが、逆に給料を保障して、総中流社会にした方が企業の競争力にとっても好影響を与えて、国の経済力もアップするということが、ビデオデッキの例でわかるだろう。
これまで、経済改革論者によって提唱されてきた「人件費がかかると国際競争力が低下して、企業経営を圧迫して、自国の経済も低迷する」という論理は、もともと成り立たない論理であった。
これは、富裕層が富裕層たり得る方便で、自分たちの保有する金融商品を最大化するためのデマであるともいえる。
■「格差のない社会は、悪平等で活力のない社会」というデマ
こんな富裕層に有利なるウソやデマがいかに多いことか。それがまことしやかに語られて、世間の定説や経済の法則のように広がっていくことが、いちばん恐ろしいことなのだ。
例えば、「努力した成功者には、それなりの報酬が必要なので、格差はある程度仕方がない」というものだ。そして、そのあと必ず付け加えられるのが、「格差のない社会は、悪平等で活力のない社会である」というものだ。
小泉元首相や竹中元経済担当大臣は、この論理で改革を推し進めたわけだが、その結果は惨憺たる社会になってしまった。竹中氏がいうには、「まだまだ改革が足りないから、景気が回復しないのだ。もっともっと断行すれば、この不況からどこよりも早く抜け出せるだろう」と、ますます自信も持った声で、持論を正当化している。
これも検証が必要である。米国の著名な経済学者でポール・クルーグマン教授は、2008年にノーベル経済学賞を受賞しているが、ユニークな論理を説く。彼は、現在の米国より、かつての全員が豊かな古き良き時代のほうがよかったといっている。
経済的格差を是正する仕組みとして累進課税制度があるが、この制度がもっとも厳しかった時代が、米国のよりよき時代だったのだ。
■総中流社会のほうが、経済は活性化する
米国の近代をふり返ってみると、1929年に大恐慌が起こったが、この頃のもっとも富裕層にかかる税率は24%程度だったが、33年には公共投資を実施するために、最高税率を67%に引き上げられている。
ここで経済格差が小さくなったのだが、戦争による特需もあり、景気は大きく回復することになった。最高税率を上げたおかげで、一般市民の消費性向が増して、テレビや冷蔵庫、洗濯機、自動車などが売れて、各関連企業が空前の利益を上げたのだった。
つまり貧富の格差が小さく、総中流化した社会のほうが、商品が売れて経済が活性化するということだ。心理学的に見ても、貧富の差が小さい社会のほうが、労働意欲がわき、実績も上がりやすい。
日本でもほんの十数年前までは累進課税が厳しく、会社員の間でも、部長と平社員の給料の差はほんの数万円程度しかなったが、労働意欲は旺盛であった。マラソンでも前方を走る人の背中が見えれば、ますますやる気が出て、追いつき追い越そうと真剣になるものである。
それが、貧富の差が開き、年収にも100倍以上の差ができれば、労働意欲や上昇志向が減退して、いまのままの地位で休暇を取ったり、趣味に時間を割いたほうが楽しいという具合になりかねない。
中には、100倍、1000倍の競争率でも生き残って、ITや金融関連事業で成功者になり、何百億円の資産を手に入れる人もいるが、それは極めて稀な例である。
そのために、詐欺的な手法を用いたり、脱税まがいの会計手法を使ったり、非合法な企業経営に手を染めることになりかねない。
リーマンショック以前に米国経済が好調だったのは、経済格差の給与体系がうまく機能したからではなく、ニューエコノミーの登場によって経済が立ち直ったからだ。
自動車産業のビッグスリーは、経営者と従業員の給与格差が大きく広がったが、年功序列を基本とするトヨタに抜かれてしまった。給与差が大きくなったところから、ますます経営は慢性的に悪化したという。経営陣がいくら高給を取っても、不利な市場を覆すような新車を開発することができなかった。
悪い例ばかりでなく、よい例も存在する。北欧のフィンランドは、IT時代に入っていちばん成長した国といえる。携帯電話で有名なノキアがあり、フリーのOSとして全世界で認知されているリナックスもこの国で開発されている。
各評価機関によると、世界的に一、二を争うほどの国際競争力を有しているが、教育は大学まで無料で、医療費も無料。その一方で、税金がとても高くて、国民の所得と生活水準が平準化しているのが特徴である。つまり、経済格差が少ないが、国際的にも大きな成長をとげているのである。
このように、それなりの地位や肩書きのある人が語る、一見説得力のありそうな論理でも、歴史の中や実際の現場では、まったく違う現象が起きていることが多いのだ。
■「小さな政府はよい政府」というデマ
もうひとつ、富裕層に有利なるデマをあげておこう。
もうひとつのデマは「小さな政府はよい政府」というものだ。
小さな政府というのは、経済改革論者によると「無駄がなく効率的で、民業を圧迫しない」政府ということになるそうだが、本当に正しい理論であろうか?
民間にできることは民間でやったほうが効率的で、競争力も養えるし、経済にも好影響をもたらしてくれるとしていた。しかし、民営化すれば、資本の論理が優先するので、格差は広がり、弱肉強食の社会が浸透してきたのである。
よい例が、民業圧迫といって、人材派遣がすべての業界で認可されたが、その結果、いつでもクビを切ることができるワーキングプアが増加した。一方、新しく人材派遣業を創業して、若い人材を集めて、あらゆる業界に派遣して、給与からいろいろな名目で搾取することで利益を上げて、億万長者になった人間もいる。
また小泉改革のメインテーマであった「郵政改革」が断行された結果、地方の採算の取れない郵便局は閉鎖されて、近所のお年寄りが困ったり、時間外窓口が閉鎖されたり、至るところに弊害が表れている。
効率や採算を重視すると、どうしても弱者のほうにしわ寄せがいってしまい、切り捨てられる人びとが多く出てくるのは避けられない。
■規模の大小ではなく、効率的な国家を目指すべき
何でも「官はダメ」という前提は間違っており、日本が目指すべき道は、政府の規模の大小ではなく、提供するサービスは質が高く、顧客の満足のいく内容でなければならない。北欧のフィンランドにしてもスウェーデンにしても、大きな政府で行政活動を行っているにもからず、国民生活のレベルはより高くなっている。
したがって、大きな政府の中にも、「よい大きな政府」と「ダメな大きな政府」を別々に考えるべきである。警察や消防、そして外交などは国単位で業務を行わなければならないものは除いて、規模の大小ではなく、効率的な国家を目指すことが大切だ。
経済改革論者は、政府による規制は悪だから自由化して競争力を高めるために、セイフティネットまで外してしまったところに大きな間違いがあったのである。おそらく経済改革論者の中では、「政府による規制=セイフティネット=悪」という図式ができていたのだ。
規制緩和で日本に舞い降りた外資系企業は、セイフティネットもない市場を食い荒らして、獲物はすべて自国に持ち帰ってしまった。
同じくおこぼれにあずかった日本の富裕家たちも、このカラクリに気付いていて乗ったに違いない。マスコミに踊らされた一般市民は、いまさら地団駄を踏んでも仕方がないが、目を覚まさない限り、富裕層に有利に、一般人に不利になるばかりである。
参考資料:http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/479667117X/asyuracom-22">『富裕層が日本をダメにした!』(和田秀樹著・宝島社新書),『日経新聞』
|
|
▲このページのTOPへ HOME > ペンネーム登録待ち板2009掲示板
フォローアップ:- 名前登録完了しました 管理(副) 2009/8/29 16:24:21
(0)
|
|
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
|
|
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。
|
|
|
|
|
|
|
|