http://www.asyura2.com/09/iryo03/msg/877.html
| Tweet |
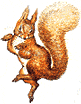
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/39004
ブラック精神科医は、依存性のある抗不安薬や睡眠薬などを大量に処方する
精神医療訴訟の高すぎるハードル
ブラック精神科医たちの驚くべき生態を描いた問題作。読者から絶賛の声が続々と寄せられている
拙著では、継続中の精神医療訴訟を複数取り上げた。今回は、その続報をお伝えする。
第2章「拉致・監禁」で紹介した大阪の民事訴訟は、大阪地裁の判決が確定した。患者に入院を強制できる医療保護入院制度を悪用し、精神疾患ではない60代の女性を大阪府立精神医療センターに強制入院させた元夫が、賠償金を支払うことになったのだ。
女性は2011年1月、突如現れた男たち(民間の救急搬送業者)に拉致され、車で大阪府立精神医療センターに運ばれた。そこで「統合失調症」と誤診され、閉鎖病棟に収容された。対応した2人の精神科医(うち1人は強制入院の必要性を判断できる精神保健指定医)は、「妻には妄想や幻覚がある」などの元夫の作り話や、元夫が提出したウソの病歴書面を真に受け、健康な女性を重い精神疾患と診断し、人身の自由を奪った。
こうした場合、不当な入院は長期化しやすい。強制的に連れて行かれた病院で「私は精神病じゃない」と猛抗議したり、取り囲む医師や看護師を振り切って病院を出ようとしたりすると、それは当然の反応にもかかわらず、「病識(病気という認識)がない」「病的な興奮状態だ」などと決めつけられ、精神疾患の証しにされてしまう。その結果、鎮静の注射や電気ショック(電気けいれん療法)が行われた例もある。
女性は、医師の問いかけに「一切話をするつもりはありません」と返答した。すると案の定、「統合失調症の症状の一つである緘黙(かんもく)、拒絶症」と決めつけられた。離婚訴訟で関わりのあった代理人弁護士が女性の窮状を知り、抗議を行った結果、約6時間後に退院できたのは幸いだった。
裁判長は判決で「元夫が財産分与を免れようと、女性を入院させて離婚訴訟が却下されるのを狙った」と指摘した。救急搬送業者に対しては、訴訟中と知りながら元夫に協力し、抵抗した女性と長女に軽傷を負わせたとして、賠償責任を一部認めた。
健康な人を統合失調症と診断する「精神鑑定の第一人者」
このケースは、本来は医療保護入院の同意者になれない離婚訴訟中の元夫が、これを隠して同意者になったため、不当な強制入院であることは明白だった。だがもし、元夫に同意権があったとすれば、退院は容易ではなかったはずだ。
2014年4月以降、医療保護入院は特定の保護者の同意から、家族(3親等以内)の同意で行えるようになった。これにより、普段は全くつきあいのない親族の一人が、何らかの悪意を持って精神保健指定医にウソを吹き込み、救急搬送業者を使ってターゲットを拉致し、閉鎖病棟に放り込む事件が発生するかもしれない。入退院を巡って家族の意見が対立し、「出す」「出さない」の押し問答で医療現場が混乱する恐れも指摘されている。
大阪のケースでは、強制入院に関わった精神科医2人と大阪府立病院機構に対する損害賠償請求も行われた。だが、大阪地裁は女性の訴えを退け、控訴した大阪高裁は和解を勧めた。
女性は賠償金の額ではなく、安易に病気と決めつけた精神科医の責任を明らかにしたかったのだが、高裁も期待できそうになかった。相手の精神科医の1人が、重大事件の精神鑑定を行うなど、司法や検察の世界で知られた人物だったためだ。
控訴審の途中、女性はこう考えた。
「裁判所が、精神鑑定医に不利な判断をするとは考えにくい。精神鑑定を行う医師の診断力が、実は健康な人を統合失調症と誤診するほどのレベルだったとなれば、この医師がこれまで関わった精神鑑定の精度や、これを採用した裁判所の判決まで疑われることになるでしょうから」
そして女性は「このまま無理に判決に持ち込み負けてしまったら、今後、裁判に訴える被害者にマイナスの判例を残すことになる」と判断し、心ならずも和解に応じた。和解金は、大阪府立病院機構が支払うことになった。
精神医療の被害者は数多い。だが、訴訟を起こすケースはまれだ。不適切な治療を受け続けた被害者は、裁判を起こす体力も気力も残っていないのだ。
司法救済のあまりにも高いハードル
誤診をきっかけに、長く多剤大量投薬に苦しんだ20代の女性の母親は「医師の罪を問いたい。でも娘のことを考えると踏み出せない」と苦しい胸の内を明かす。
女性は、大量の薬を苦しんだ末に断ち、体調が安定して仕事を始めることができた。誤診であったことは、現在の回復ぶりを見れば明らかだ。だが、ここで裁判を起こすと、再びつらい記憶(大量投薬の苦しみや減薬途中の苦しみ、長期入院で受けた心的外傷など)がよみがえり、心身の健康を再び損ねる危険がある。母親も本人も、それを恐れている。精神医療被害者の多くは、こうして泣き寝入りを強いられる。
たとえ、医師や病院を相手に民事訴訟を起こしても、勝訴できる確率は極めて低い。拙著で取り上げた北海道の患者死亡例では、東京地裁が「本件心肺停止は、投与された抗精神病薬の作用によって生じた」と薬の影響を認めた。ところが、大量極まりない抗精神病薬を処方した医師の過失は認められず、両親の損害賠償請求は棄却された。3人の鑑定人(大学病院の精神科医)が「投与量が標準から逸脱しているものの、著しく不適切とはいえない」「医師の裁量の範囲内」などと指摘したことが影響したとみられる。
続く東京高裁では、裁判長が患者差別的な暴言(詳しくは拙著に収録)を吐いた揚げ句、請求を棄却した。両親は上告し、最高裁の判断はまだ示されていない。
元裁判官で、著書の『絶望の裁判所』(講談社現代新書)が注目を集める明治大学法科大学院教授の瀬木比呂志さんは、精神科関連の裁判が特に難航する理由を次のように説明する。
裁判官が医師の処方に疑問を抱いても、精神医療の専門家が「場合によってはありうる」と言えば、それを覆すのは難しいと瀬木氏はいう
「私自身、以前にうつを患った経験があり、精神科の診断の問題や、過剰な投薬の問題は認識しています。薬は適切に使えばうつに有効だと思いますが、私の場合、神経症的な機制を含むうつだったので、処方された強い薬は副作用ばかり出て逆効果でした。結局、森田療法で回復しました。
精神科の民事訴訟では、必要以上の投薬が問題を引き起こしたとみられるケースが確かにあります。しかし、裁判で鑑定を行う精神科医が『症状によってはこうした投薬もありうる』などと、逃げ道のような意見を付け加えると、専門家ではない裁判官は、医師の過失を認定することを躊躇しがちになります。鑑定を行うのは、専門家ではない裁判官が専門家の意見を聞くためですから、精神医療の専門家が『場合によってはありうる』と言えば、やはりその意見を尊重するか、ということになりやすいのです。現代の裁判では、大岡裁きは避けなければなりませんから。
精神科関連の裁判で被害者を救済するためには、精神医療を科学的根拠に基づいた医療に変える必要があります。大量投薬が必要なケースがあるとすれば、それはどのような場合なのか、薬は何ミリグラムまで使えるのか、などの基準を学会が明確に示さなければなりません。医師の裁量権を拡大解釈することに歯止めが効かないような現状では、たとえ良心的な裁判官でも、被害者を救うことは難しい面があります」
精神医療の無秩序ぶりは、医療界の中でも際立っている。未熟な精神科医の思い込み診断や、根拠のない過量投薬が幅をきかせ、患者を追い込んでいる。誤った診断、投薬の影響で患者の心身の状態を著しく悪化させても、彼らが罪を問われることはない。こう言えばすべてチャラになるからだ。
「もとの病気が悪化した」
そして精神医療被害者は増え続ける。
佐藤光展(さとう・みつのぶ)
1967年前橋市生まれ。立命館大学卒。神戸新聞社会部で阪神淡路大震災、神戸連続児童殺傷事件などを取材。2000年元日、読売新聞東京本社に移り、静 岡支局と甲府支局を経て2003年から医療部。『こころの科学増刊 くすりにたよらない精神医学』(日本評論社)、『統合失調症の人が知っておくべきこと』(NPO法人コンボ)などに寄稿。
司法制度の荒廃と腐敗を描き、法曹界に衝撃を与えた「絶望の裁判所」。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4062882507/asyuracom-22
|
|
|
|
|
|
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。