http://www.asyura2.com/09/iryo03/msg/251.html
| Tweet |
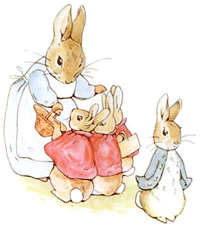
「イモリ」になれなかった人間 - 記者の眼:ITpro
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20100309/345551/
「イモリ」になれなかった人間「トカゲの尻尾切り」などと言われるが、トカゲは尻尾が切られてもまた生えてくる。イモリにいたっては同じ形の手足が生えてくる。人間はなぜそのような再生機能を持っていないのだろうか。言われてみると不思議な話だが、先日、iPS細胞研究の第一人者である京都大学の山中伸弥教授の話を聞いて、目からうろこが落ちる思いだった。
山中氏は、2009年11月23日にNHKが放映した「立花隆 思索ドキュメント がん 生と死の謎に挑む」の中で、立花氏のインタビューに答えてこう語ったのである。
「再生能力というのは、がんになるのと紙一重だと思うんです。高い再生能力を持っているということは、同時にがんがすごくできやすいということなんじゃないか。だからどっちをとるかという究極の選択が進化の過程であった。(その結果)やっぱりがんはだめだと…。(中略)再生能力はなくてもなんとかなるが、がんになれば間違いなく死んでしまう。人間のように50年以上も生きるようになってしまうと、十数歳まで生きないと次の世代に子供を残せない。だからその十数年の間、がんを発生させない必要があって、そのために涙を呑んで再生能力を犠牲にしたのではないか、と一人納得して思っているんですね」。
iPS細胞を実用化するうえでの最大の課題がiPS細胞ががん化してしまう点である。それはまさに「再生能力」と「がん化」のトレードオフの問題であり、進化の歴史そのものに対する挑戦でもあるわけだ。それだけ高いハードルを超えてこそ大きなイノベーションが達成されると言えるが、一方で筆者が興味深かったのが、「iPS細胞」と「がん」はそもそも「同じもの」ではないかという指摘である。
山中氏は、iPS細胞の研究を進めるうちに、iPS細胞をつくるプロセスとガンが起こるプロセスが非常に似ていることに気づく。そもそも、iPS細胞は正常な細胞に四つの遺伝子を導入してつくられたものであり、そのうち二つはがん遺伝子であった。「命」を再生するiPS細胞と患者の命を奪うがんは、一見両極端のように見えるが、いずれもがん遺伝子が関与しているのである。「同じものの表と裏を見ているようなものではないか」と同氏は語る。
がん遺伝子に限らず、がんは、人間が進化の過程で自らの生命維持のために獲得してきた遺伝子を使っていることが次々と明らかになっている。
例えば、「HIF-1」(低酸素誘導因子)という、細胞に対する酸素供給が不足した際に誘導されてくるタンパク質がある。これは、酸素を必要とする生物が進化の過程で獲得した遺伝子によるもので、生命の初期段階で重要な働きをする。胎児の初期段階では酸素が不足した環境にあり、HIF-1がそうした過酷な状況を打開するものであることが分かっている。実際、HIF-1遺伝子がないネズミの胎児は生まれる前に死んでしまう。初期の胎児は血管がないため低酸素状態にあるが、HIF-1が働いて酸素の不足を周りの組織に伝え、血管や神経をつくるのである。この胎児の成長のために不可欠なHIF-1が、がんが転移する際にも使われているという。がんは血液をつくり栄養を得ながら増殖する。しかし、増え続けると中心部には血液が行き届かなくなり、通常なら低酸素の環境では生きられなくなる。そこで、こうした環境の中で生きられるがん細胞だけが淘汰によって生き残るが、そのメカニズムにHIF-1が関係していることが解明されている。
まず、HIF-1は、がん細胞の新陳代謝の仕組みを変えて低酸素環境でも生き残れるようにする。次に、がん細胞が動き出す能力を目覚めさせる。こうして低酸素環境下で生き残ったがん細胞は放射線や抗がん剤に抵抗力を持つより強い細胞となって移動を開始し、浸潤・転移へと進む。
HIF-1は、こうした胎児の成長やがん細胞の転移だけでなく、酸素で生きる生物の生命活動全般に使われていることが分かってきた。例えば、HIF-1は大人になっても酸素を検知するセンサーとして働いている。
生命の歴史とは、海と陸を行き来しながら低酸素という過酷な環境の中で生き抜いてきた歴史でもある。こうした厳しい状況を克服するために生物はHIF-1遺伝子を持ち続けてきた。「ありとあらゆる困難な状況の中で生き抜いてきた生命の歴史そのものの強さが、がんの強さに反映しているのではないか」と立花氏は語る。
この番組は、一昨年、膀胱がんの手術を受けた立花氏が、自らの治療の過程を明らかにしながら、「人類はなぜ、がんという病を克服できないのか?」という本質的な疑問に挑戦したものだが、以上見てきたiPS細胞やHIF-1の話のほか、がん遺伝子のパスウェー(細胞を増やす命令の連絡経路)をブロックしても別のパスウェーが働くメカニズムや、本来がん細胞を攻撃するはずの免疫細胞ががんの成長を助けているなどのがん研究の最先端を紹介していく。そして、各分野の研究者を取材すればするほど、がんとは「生命」と表裏一体であることが明らかになっていく。それはつまり、「半分自分で、半分エイリアン」(立花氏)であるということだ。エイリアンを攻撃しているつもりで、自分を攻撃してしまう−−。そこに、がん克服の難しさがある。
以前に紹介した『ミトコンドリアが進化を決めた』(Tech-On!関連記事)によると、そもそも多細胞生物へと進んだきっかけは単細胞生物であるメタン生成菌がα-プロテオバクテリアという「エイリアン」を取り込んだからという仮説がある。これによって、個々の細胞が自己複製するよりも、複数の細胞が共生した方がより生存のためには有利な条件が生まれた。しかし、各細胞はもともと過去の「自由」な単細胞生物時代の「記憶」を持っているということなのだろう。個体全体の利益ではなく、自分のために猛然と自己複製を始めてしまう。がんとは、細胞が「先祖帰り」したものと言えるのかもしれない。
ということは、がんは、生物が単細胞生物から多細胞生物へと進化する過程で抱え込んだ「宿命」であるとも言える。「多細胞生物が自己の再生産をするという繰り返しが生命の歴史そのもので、その延長線上にわれわれがいるということなのですが、その仕掛けそれ自体ががんを生んだともいえるわけです。その歴史があるからこそ、がんに捕らわれざるをえないという宿命を負っていると感じました」と立花氏は言う。
「がんとは何か」を考えれば考えるほど、がん克服の難しさが浮き彫りになるが、それでもがんという「エイリアン」だけを叩こうという挑戦は続いている。立花氏がインタビューしたがんの研究者達は、50〜100年後にはがんを克服することを目指していた。それは、確たる証拠というよりは「夢」のようであったが、そうした「夢」を追う努力の末には、いつかは完全に克服できる日が来ると信じたい。一方で、現在のがん患者はがんにどう向き合ったらよいのか。番組の最後に同氏が述べた言葉が心に残った。
「取材を通じて確信したことが二つあります。一つは私が生きている間に人類が医学的にがんを克服することはないだろうということ。もう一つは、だからそう遠くない時期に私は確実に死ぬだろうが、そのことが分かったからといってそうジタバタしなくてもすむのではないかということです。つまり、がんとは、しぶとすぎるほどしぶといもので、生命そのものが孕んでいる一つの避けられない運命であるという側面を持っているということです。そうであるなら、すべてのがん患者が、どこかでがんという病気と折り合いをつけなければなりません。私の場合、残り時間の過ごし方はいたずらに頑張ってQOL(人生・生命の質)を下げることではありません。取材で学んだのは、人間はみな死ぬ力を持っているということです。それは、死ぬまで生きる力があるといった方がいいかもしれません。単純な事実ですが、人は誰でも死ぬまで生きられるのです。ジタバタしてもしなくても死ぬまで生きられる。その単純な事実を発見して、死ぬまでちゃんと生きることこそがんを克服するということではないでしょうか」
この記事は「Tech-On!」で連載中の『藤堂安人のイノベーション雑記帳 』から転載したものです。バックナンバーはこちらからご覧いただけます。
(藤堂 安人=電子・機械局主任編集委員) [2010/03/18]
|
|
|
|
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
|
|
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
|
|
|
|
|
|
|
|