| Tweet |
(回答先: オバマ米大統領=「米国消費市場に頼るな」=伯国は自主独立を=危機以前の水準回復は困難=今回はG13の橋渡しか 投稿者 gikou89 日時 2009 年 7 月 23 日 06:44:59)
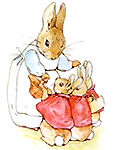
http://www.toyokeizai.net/money/markett2/detail/AC/c18b1d096e2bbb042979b99199f61af0/
上場各社が相次いで「投資単位引き下げに関する考え方及び方針等について」と題する文章を公表している。投資単位とは、株を買うための最低金額のことだが、A4判の紙1枚にタイトルどおり「考え方」を記載しただけで、具体的な内容は何もない。しかし、この中には大幅分割など、今後の株価を左右する重要なヒントが隠れている。
この種の発表文の背景には、東証の意向がある。金融機関は自己資本対策でリスク資産である株を持ちにくく、株の買い手常連だった年金資金は今年度中にも売り手に転じそう。結局、売り物の受け皿は外国人と個人にならざるをえない。東証は政府の要請もあり、個人株主層拡大を目的に、望ましい最低投資金額を5万円から50万円に設定。上場企業に協力を呼びかけ、他取引所も追随してきた。
企業側は株式分割や投資株数の変更で応えてきた。しかし、全企業が必ずしも従っているわけではなく、個人が投資するには敷居の高い企業は今も少なくない。東証、大証、ジャスダックの主要3市場では、約70銘柄の最低投資金額が100万円を超える。このうち200万円超は、600万円台の日本銀行を筆頭に、歌舞伎座、任天堂、ナガセ、エスケー化研など9社もある。
たとえば株価4000円前後の歌舞伎座株を買うには、1000株の代金として400万円必要だ。しかし、10分割か売買単位を100株に変更すれば、最低投資額を40万円に下げることが理屈上は可能だ。
一般に株式分割では、1株配当を分割比率に比例して下げられず、実質増配になることが多い。100万円投資しなければ手に入らなかった優待券が10万円で手に入るようになり、株価が上昇するケースもある。また、投資単位引き下げは流動性向上が評価され、その後の株価は市場平均を上回りやすいという。
このように投資単位引き下げはメリットばかりのようだが、企業にとって無視できないデメリットもある。最も負担の重いのが事務経費の増大だ。年4回の決算報告に加え、株主総会の招集通知などの書類作成費や郵送代で1000円近いコストがかかるという。株主が増えれば、企業への問い合わせも増えるので、相応の陣容を整える必要が出てくる。これとは別に、新会社法適用で監査法人への報酬も重くなった。東証への支払いも決して軽くはない。
資本政策の根幹 笛吹けど踊らず
東証の示すモデルケースの下限である最低投資金額5万円で計算すると、上場維持コストは調達額の2%を軽く超えてしまう。資本の社外流出にほかならず、これでは何のために上場しているかわからない。
そもそも、どんな投資家に株を持ってもらうかは、企業の資本政策の根幹にかかわる大問題。最低投資金額を高めに設定し、富裕層や大口投資家の比率を高めたいとしても、それは個別企業の経営戦略だ。東証と企業の温度差は、対外公表文からにじみ出てくる。株式購入に90万円程度が必要な科研製薬は投資単位引き下げを前向きに評価し、「実施について鋭意検討する」としている。
一方、1000株から100株への株数変更を実施済みのオリエンタルランドは、最低購入額が60万円台。投資単位の引き下げを「個人投資家の拡大、流動性向上に有用な施策のひとつ」と評価しながら、追加策について「慎重に検討」と、見送り宣言に近い態度だ。大日本印刷(最低購入額約130万円)は個人株主拡大の要請には、3万1000名義の株主のうち個人株主が3万人と大半を占める点を指摘し、流動性は確保されているとやんわり拒否している様子。歌舞伎座は株式事務管理費の負担増を指摘。さらに、「株主優待制度への影響や費用対効果を勘案して慎重に検討する」とし、笛吹けども踊らずどころか、反論に等しい。
短期的には、分割や売買単位変更を実施しそうな銘柄に目が向きそうだ。しかし、冷静にコストを計算した結果、政府や証券取引所の号令よりも、既存株主の利益保護を優先させる企業のほうが、長期的な投資対象として頼もしいかもしれない。
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。