| Tweet |

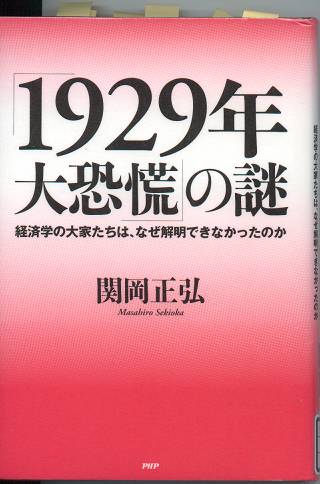
『「1929年大恐慌」の謎:副題:経済学の大家たちはなぜ解明できなかったのか関岡正弘著』を読む。
関岡正弘氏は2002年阿修羅のTORAさんの投稿[http://www.asyura.com/2003/dispute6/msg/109.html / 20世紀石油資源論] ではじめて知りましたが、かくも素晴らしい本を出していたとは知りませんでした。そして、「拒否できない日本」の[http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E5%B2%A1%E8%8B%B1%E4%B9%8B / 関岡英之氏]はその息子さんであったとは知らなかった!
関岡正弘氏は石油有限派であるため、石油問題に関しては多少私と意見が異なり多少批判的に、金融危機後に出版された数多の経済学書と大同小異程度かと読み出したのですが、本書は関岡氏がいかに碩学の学者であるか知らしめる本であった。金本位制1920年代、そして大恐慌がなぜ起きたかをその時代背景とともにわかり易く解説しています。なるほどなるほどと読み進んでいくうちに、「サブプライムローン」問題とかCDOとかCDSなど金融危機の問題に言及していないことに気がつき、最後まで読んで驚いてしまった。「本書は1989年9月にダイアモンド社より出版された『大恐慌の謎の経済学―カジノ社会が崩壊する日』を改訂・改題したものです。
「恐れ入谷の鬼子母神!」本書は20年前、しかも日本がバブルの絶頂期に書かれた本であった、経済に関する新刊は1年もすれば100円で売られることが多いのだが今日読んで古さをまったく感じないどころか、逆に新鮮に感じる驚くべき本だ。本当は20年前に書かれた本だと知らずに読むほうが面白いのだが、「まえがきにかえた」にもちゃんと1989年の本だと書いてあったのだが読み落としていました。
知って読むのも一興でしょう。確かに今思えばバブル時代には何か変だとは思っていましたが、「当時この時代が変だ」と思うことができるのは難しいことのように思えます。残念ながら20代であった私には持ち合わせていませんでした。戦中戦後苦労された世代の方には奇異に思えたのでしょう。逆説的な考えからすると、沈み行く日本の現状はバブル時代にも増して変な時代であると、私は思いたい。
P73~75
{{{++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
一般的な恐慌のメカニズム
ここで、1825年と36年の2回の恐慌についての分析をもとに、
一般的な恐慌のメカニズムをまとめてみよう。
1徐々に富が蓄積されていく。
2なんらかの景気始動要因が働く。
3商品価格が上がり始める。
4生産拡大が始まる。
5原料輸入の増大、工場・機械の増設など実物経済の拡大が始まる。
6その過程で、資金調達のための株式、債券の新規発行が始まる。
7好況が進み、商品価格が一層上昇する。
8商品に対する投機が始まる。
9マネーが忙しく回転し、信用が急速に膨張する。
10投機が過熱する。商品投機のみならず、株式、債券などに対する投機が盛んになる。蓄積されていた富が本格的に動き出す。
11投機ブームによる臨時のキャピタル・ゲイン一あぶく銭一が、実物経済に追加需要をもたらす。
12国内の経済活動の増大、輸入の増大などにより、金貨本位制のもとでは中央銀行の金準備が急激に減少し始める。
13金準備が一定の水準以下へ落ちると、中央銀行は支払不能という事態を避けるため引締め政策を実施する。
14膨張した信用の基盤に水がかけられ、信用の収縮が始まる。
15信用の収縮は、過熱していた投機を一挙に崩壊させる。
16実物経済の消費のうち、臨時のキャピタル・ゲインで支えられていた部分が一挙に消滅する。
17その結果、実物経済で発生した生産の減少、価格の下落、失業などが、タイムラグをもちながら加速度的に、実物経済全体に波及していく。
18実物経済のコントラクション一収縮)は、信用が頼っていた実物的塞盤、担保などの価値を減じ、一層の信用の収縮を招く。
19信用と実物経済の双方の収縮が悪循環し、恐慌を一層激化させる。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++}}}
1920年代の検証
{{{+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
焦点は、なんといっても、1929年10月にアメリカのウォール街で起きた株式市場の大崩壊を、どのように位置づけるかという点にある。なぜなら、それこそが、あらゆる点で時代の転換点になっているからだ。
ここで、これまで検討してきた1920年代の時代的背景を整理しておこう。
1.1870年以降、アメリカとヨーロツパの経済距離が著しく短縮した。木造の帆船から蒸気鋼鉄船に移行して、海上輸送費が革命的に下落一約十分の一へ)したからである。
2.以後アポカ経済は、ヨーロツバヘの輸出を基礎に大発展への道を歩み始める。
3.石油による照明革命は、「知的大衆」という歴史上初めての存在をアメリカ社会に生み出した。
4.巨大株式会社と科学的生産管理技術がアメリカの生産性を飛躍的に高めた。
5.巨大株式会社の誕生は、一方で株式市場という理想的な投機の場を用意したが、過大な水増し株式発行の穴埋めが必要だったため、すぐには投機を誘発しなかつた。
6.第1次大戦は、アメリカに巨大な富をもたらしたが、アメリカの大衆もまた大きな分け前にありついた。
7.アメリカ連邦政府の戦時国債キャンペーンは、大衆に証券投資の味を覚えさせた。
8.石油を燃料とするトラクターによる農業革命は、農業労働者を失業させ、巨大な潜在的余剰労働力を生み出した。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++}}}
以上のような時代背景の歴史的認識なくては経済学のみで、恐慌を理解することは不可能に近い。関岡氏は歴史学者のガルブレイス氏の恐慌の歴史学的観点から読み解いた「大恐慌」をたたき台に関岡氏の碩学な知識を加え、この後金本位制について、非常にわかりやすく解説しています。
今日の金融危機を理解し、資本主義の行き着く先を考察するには絶好のテキストです。
※引用部分は本文の中では引用するほど大事な部分ではなく、目次的な意味合いに近い部分です。
この本で私がブログに転載したいのは以下の部分です。
{{{金為替本位制の弱点―第6章国際金融システムの果たした役割}}}
{{{金本位制の問題点}}}
第一次世界大戦前の金本位制は金貨本位制で実際に金貨が流通していたがその期間は1870年頃~1940年のわずか40年しかないのである。
Ddogがここで気がついたことだが、金本位制が可能となったのは日本の金ではなかったのだろうか?幕末日本から流ない。黄金の国ジパングは存在していたのだった。
1920年代の金本位制は世界経済が一気に拡大し、金不足で第一次世界大戦前の金本位制は復活できなかった。
P180~184
{{{+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ガブルレイスは「マネー」のなかで1867年に主要ヨーロッパ諸国は、パリに会して、金を彼らの通貨に対する基礎的で唯一の準備とし、彼らの間の支払い手段とすることを決定した」と述べている。(略)
イギリス以外、まだ金本位制を採用していた国はなかつた。イギリスだけが、すでに十九
世紀前半、いろいろと試行錯誤を重ねた後、金本位制を確立していたのである。
ところで、真正の金本位制といわれる金貨本位制の成立の要件は、次の三つにあるといわれる。
①金貨鋳造・鋳潰しの自由
②ぺーパー・マネーとの免換の自由
③金貨および金地金の輸出入の自由
(略)要するに、金本位制というのは、すべての商品の「価値ないし価格」を、金の「価値ないし価格」を尺度として決める社会制度なのである。価値と価格の問題については、次章で詳しく述べる。
イギリスでも、ほとんどの国と同じように、昔は銀本位制であった。中世のヨーロッパは金が不足していたし、また商品の流通がそれほど発達していない時代には、金は、日常の取引の価値の尺度としては、あまりにも高価すぎたのである。
その後、十字軍の遠征を契機としてイタリアの商人が勃興すると、1252年にはフローリン金貨が鋳造される。中世ヨーロッパとしては、初めての金貨であった。そしてだんだんと、金と銀が並んで尺度に用いられる金銀複本位制の時代に入る。当時のヨーロッパの辺境、イギリスが金銀複本位制に入るのは、ようやく1666年である。
しかし、両雄並び立たずという諺どおり、複本位制は、不安定で、長続きしない。金も銀も商品であることには変わりはないから、それぞれ需給バランスによって、別個に価格が変動する。したがって、「本位制」で金銀問の交換比率を固定すると、かならずどちらかが割高になったり、割安になったりする。そして、流通するのは割安になったほうの金属であり、割高になったほうは退蔵されてしまう。
さらに、国によって両者の交換比率が違う場合には、より有利な国を求めて、金と銀が反対方向に移動するという問題が生ずる。イギリスは、当時他のヨーロッパ諸国に比べて、金を割高に評価した。銀を虐待したのである。そのため、イギリスから銀が流出し、金が流入した。
偶然かもしれないこの歴史的事実が、イギリスを早い時期から事実上金本位国にしてしまったのである。正確には、1717年の法令が事実上、イギリスを金本位制に移行させたといわれている。
金貨本位制の第二の重要なポイントは、「兌換」という点にある。この兌換という要素は本位制固有のものというより、歴史的な過程において、半ば必然的に金本位制に付け加わったものといえる。
近世ヨーロッパは、「マネー不足」という難問に直面していた。人類は、紀元前数千年も前から金と銀をマネーとすることを決めていた。そうなった最も重要な理由は、この二つの金属の「稀少性」にあった。半面、金と銀をマネーにしたこのそもそもの理由が、問題を発生させた。
稀少性は、「不足している状態」ということでもある。近世ヨーロッパ経済が、テイク.オフして、商品の流通量が増大すると、まず流通手段としてのマネーの不足が深刻な問題となった。
そこで人類は、不足したマネー「金銀」を補うために、「紙」のマネーを発明したのである。ぺーパー・マネーは、いくらでも作れた。その意味では、「不足」を補う手段として理想的であった。半面、その利点が重大な欠点ともなった。人びとは、どんどんぺーパー・マネーを印刷するという誘惑に勝てなかったからである。
ガルブレイスは、アメリカ建国の父の一人、ベンジャミン・フランクリンも、若き日、経営していた新聞社の印刷機を転用しては、ぺーパー・マネーを印刷していたと『マネー』に書いている。植民地時代のアメリカでは、とくに流通手段としてのマネーが不足していたのである。
しかし、マネーも本質的には一種の商品である。印刷されすぎたぺーパー・マネーも、需要と供給の法則の免疫性はもっていない。かくて、近世の資本主義勃興の歴史は、発行され過ぎて無価値となったぺーパー・マネーの実例に満ちあふれている。
このぺーパー・マネー固有の欠点を抑えるためには、ぺーパー・マネーをいつでも必要なときには金と兌換する制度が必要であった。見換の保証によって、ぺーパー・マネーは金と等価になったのである。
兌換制度が確立する過程で、ぺーパー・マネーの二人兄弟のうち「紙幣」は廃れ、「銀行券」が生き残った。紙幣は多くの場合、政府によって、それ自体が法貨(国家が認めた正貨)として発行され、兌換が保証されていなかったのに、銀行券は、本来銀行が発行した約束手形であり、正貨(金)との兌換が保証されていたためである。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++}}}
また、トンでも本の金融の仕組みはロスチャイルドが作ったの批判となるが、この時代の流れは経済学的な必然性があり、陰謀論者が妄想する陰謀説はまったくの無学な連中を洗脳そそのかす危険な本としか思えなくなります。それでは、金本位制について、続きです。
P184~188
{{{+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ぺーパー.マネーの供給の責任は、国家の手から銀行へ移された。イギリスは17世紀末、諸国に先駆けて、イングランド銀行を設立し、銀行券を発行していた。
ここで、重要なのは、兌換の保証といっても、銀行は、発行したすべての銀行券と同額の金を常に準備しておく必要がないという点にある。そんなことをしていたら、金銀の不足を埋めるというぺーパー・マネー本来の目的を果たすことができない。それに人びとは、いっでも金に替えられると信じているかぎり、あえてぺーパー・マネーを金に替えようとはしなかった。重い金よりも、ぺーパー・マネーのほうが扱いやすかったからである。
それは確率の問題であった。銀行は、保有する金以上の銀行券を発行することができた。ここに「準備率」.という概念が生まれた。準備率とは、発行済みの銀行券の総額に対する保有する金銀の比率である。準備率としては、三分の一が経験的に妥当であるという意見が、1830年頃、イングランド銀行のパーマー総裁によって主張された。
1844年のピール銀行条例は、最終的にイギリスの金本位制を確立した法律だが、イングランド銀行に対し、保有する金貨、金銀地金の総額に加えて、1400万ポンドまで銀行券を発行することを許した。逆にいえば、1400万ポンドと決めたのである。これは、以後、ポンドの信用は著しく高まった。
金銀の裏付けのない銀行券の上限を法律でかなり厳しい規定であった。そのせいか、以後ポンドの信用は著しく高まった。
イギリスのパラドックス
1870年以降、イギリス以外の諸国も次々に金本位制を採用する。1872年、普仏戦争に勝ち、フランスから50億フランの賠償金を得たドイツが、まず金本位制に踏み切った。1874年にはオランダが、78年にはフランスが続く。そして79年には、アメリカが一応法的に金本位制に移行する。しかしアメリカの金本位制が確立するのは、ようやく1900年になってからである。1892年にはオーストリア、1897年には、日本とロシアが続いた。
1870年代以降、国際的に金本位制が急速に普及したのは、時代が必要としていたからである。当時、イギリスでは、急速に「過剰流動性」つまり使い道のないマネーが蓄積されていた。一方、遅れて産業革命に入ったイギリス以外の国は、資本主義経済を発展させるための資金をのどから手が出るほど必要としていた。
しかし、ある国から別の国へ、長期貸付けという形でマネーを流してやるためには、為替レートが安定していなければならない。そうでなければ、貸し手は安心して長期の貸付けをすることができない。金本位制は、当時それを実現する唯一の方法であった。第一次大戦前の国際的な金本位制は、イギリスを世界の銀行にするための必要な条件だったといえる。
重要な点は、この時代のイギリスの金の保有高が、意外なほど少ないことである。『文明の血液-貨幣から見た世界史」(湯浅赴男著、新評論)は、1890年代から1922年までのイングランド銀行の保有する金は、2000万ポンドと4000万ポンドの間を上下していたにすぎないという。それに対して、フランスやロシアは1億ポンド以上保有していたという。オーストリア帝国も5000万ポンド保有していた。
金本位制の全盛時代、その宗主国、イギリスの金保有高が意外なほど少なかったという一見して矛盾に思える事実は、しかしじつは、金本位制成立の真の条件を示唆しているのである。
イギリスの金保有量が少なかった事実は、イギリスが積極的に海外へ金を投資していたことを意味する。当時のイギリスの海外投資家は、金利生活者など多数のいわゆる小金持ちから構成されていた。彼らは、国内で資金を運用するよりも海外で運用するほうが金利が高かったから、それを好んだのである。
その上、彼らは海外へ投資することに不安をもっていなかった。19世紀には、イギリスは世界で圧倒的な海軍力をもっており、そして地球上どこへでも、砲艦や兵上たちを送ってイギリスの権益を守ることができたからである。イギリスの海外投資が、多数の比較的小規模な投資家によって行なわれていたことは、その資金のフローを安定化するのに役立っていた。
結局、イギリスあるいはポンドの信用は、単に金の保有高といったハードウェアで裏付けられていたわけではない。数百年の蓄積である「イギリスの世界システム」というソフトウェアによって、その信用が支えられていたのである。パラドックスだが、イギリスが保有する金の量が少なかったという事実は、イギリスの弱さではなく、強さを、そして当時の金本位制の安定性を表わしていたのである。
ここで、金本位制の目的、マネー価値の安定には、犠牲がともなったことに注意しなければならない。よくいわれる金本位制のメカニズムは、次のようなものである。
<なんらかの原因で、ある国で景気がよくなり、所得が増えるとする。商品に対する需要が増え、価格が上昇する。すると輸出が減って、輸入が増える。その結果、金が外国へ流出する。一方、国内の商品流通が増大する結果、金貨の需要が増える。それは中央銀行の手持ちの金貨の流出を意味する。
かくて、国内と国外への二つの流出により、その国の中央銀行が保有する金の量が減り、準備率が下がる。そのため中央銀行は、手持ちの公債を売って銀行券を回収するのである。
この中央銀行の操作を「公開オペレーション」というが、それによって回収される銀行券は、流出した金の準備率の逆数倍(準備率が3分の1であれば3倍)となる。かくて、国内に流通するマネーの量が急激に下がるので、景気が悪化し、物価が下落する。所得も減る。輸入が減って、輸出が増える(物価が下がったため)。
その結果、金が再び外国から流入してくる。国内で流通していた金貨も、中央銀行へ還流してくる。中央銀行の手持ちの金が増大する。準備率が高くなるので・市場から国債を買い上げて、銀行券を増発する。かくて、景気は再び回復に向かう>
国内で流通するマネーを金にリンクしているかぎり、マネーの価値は安定している。上記のプロセスでわかるとおり、インフレーションを防止するメカニズムが経済システムにビルトインされているからだ。これこそ、古典派経済学が理想とする経済システムであった。
半面、それは、実物経済のダイナミズムが、マネー・サイドの事情によって制限されることを意味している。それは、昭和三十年代、四十年代の日本経済を思い出させる。当時は、国際収支の天井があって、少し好況が続くとドル(当時は金と同じと考えてよかつた)不足になるので、泣く泣く不況政策(引締め政策)を採らざるをえなかった。金本位制の場合は、それが政策的にではなく、自律的メカニズムで行なわれたのである。
マネーを安定させるための代償は、「景気」であった。そのせいだろうか、国際的な金本位制が機能していた1870年頃から1890年代の半ば過ぎまでの間、世界は「生産」の増大の一方で、「価格」の長期低落傾向に悩んだ。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++}}}
p189~195
{{{+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
「金為替本位制」
ところで第一次大戦後、ようやく1925年になって、イギリスは金本位制に復帰する。しかし、それは本当の意味の金本位制ではなく、「金地金本位制」という変形であった。金貨は発行されなかった。兌換については、イングランド銀行券は金地金(インゴット)と交換することが一応保証されていた。しかしそれは、たいへん大きな単位でのみ可能だった(イギリスの場合1699ポンド以上)。したがって、一般大衆とは縁のない制度であった。
かくて、金地金本位制は真正の金本位制成立要件のうち、①金貨鋳造・鋳潰しの自由が否定され、②ぺーパー・マネーとの兌換の自由が、事実上制限されていた。
フランス、ドイツをはじめ、ほとんどの国は、1925年から28年にかけて金本位制に復帰する。日本の復帰はさらに遅れた。問題だったのは、これらの国の金本位制は、金地金本位制からさらに縮退した「金為替本位制」だったことである。
これらの国では、金があまりにも不足していたので、金貨を発行できなかったのはむろんのこと、通貨(中央銀行券)発行に必要な準備のための金地金にも不足していた。そこで、ドルおよびポンド建ての外国為替を金の代用とし、通貨発行の準備に加えたのである。ドルは金貨本位制で、ポンドは金地金本位制で、一応金との見換が保証されていた。
そのため、ドル為替とポンド為替を「金為替」と称し、金の代替物と見倣したのである。
その本位制を金為替本位制と呼んだ。
この苦しいやりくりで、金為替本位国の通貨も、間接的に金とリンクしたことになる。
しかし、金為替は、その性格上「両刃のやいば」であった。たとえば、フランスが保有するポンド為替を考えよう。それはフランスにとっては金為替であり、金と等価の資産であった。同時にそれは、フランスにとってはイギリスに対する債権であった。つまり、フランスは、いつでもそれをロンドンヘ送り、イギリスの金本位制を利用して金と交換することができた。
もちろんフランス以外のポンド為替を持つ国も同じことができた。そして、為替である以上、金本位制がうまく機能しないと、一定の枠内とはいえ、その交換レートが変動した。そして、ポンドが安くなり、為替ロスが発生する恐れが生ずると、ポンド為替がイギリスに大量に還流して、もともとぎりぎりの金量で無理に無理を重ねていたイギリスの金本位制を、たちまち危機に陥れたのである。
そればかりではない。イギリスの金本位制は、1925五年に復活した当初から、問題を含んでいた。それは、イギリスがポンドの金価値を戦前の平価に据え置いたことである。
それに対しフランスは、戦前の平価の五分の一の価値しかないフランで金本位制に復帰した。明らかに、ポンドは過大評価で、フランは過小評価であった。そしてこの事実は、フランス商品のポンド価格が、フランス国内のインフレーションを考慮に入れないとすると、五分の一になったことを意味した。割安になったフランス商品の輸出は急増し、割高となったイギリスの商品輸出は低迷した。その結果、海外のイギリスに対する債権、つまりポンド為替はますます増大したのである。
この時期、国際金融をめぐって、はっきり強者と弱者が分かれていた。強者はアメリカとフランス、弱者はイギリスとドイツである。アメリカはともかく、フランスが強い立場にあったのは、フランスが金本位制に戻る前、フランス政府がフランをどんどん下がるにまかせたため、フランスの資本家たちが海外、主としてロンドンヘその資産を待避させていたためである。換言すれば、ポンドの形をとっていたフランスの資産が多かったのである。
これらのフランス資産は、一時的にポンドに避難していたのであり、それでなくてもフランスに帰ろうとしていた。その上、経済の実態から見て、フランがポンドに対して騰貴しそうな情勢になっていたのである。投機家あるいは短期資金の運用者たちは、イギリス人もフランス人も、一斉にポンド為替をフランスヘ持ち込んでフランに換えた。
その結果、フランス銀行(フランスの中央銀行)のポンド為替の保有高が、1926年11月の530万ポンドから27年5月の1億6000万ポンドヘ、たった半年間で30倍も急増した。
フランス銀行は、手持ちのポンド為替をイギリスヘ送って金と交換し始めた。ポンド為替を保有したままにしておくと、フランに対してポンドが下落した場合、損失を生ずるからである。しかし、そのことは、イングランド銀行の保有する金を減少させて、イギリスの金本位制に大きな危機をもたらした。
もちろん、フランスもイギリスの金本位制を破壊することは望まなかった。そこでフランスは、イギリスに金利を上げることを要求した。そうすれば、相対的に高い金利に魅かれて、ポンド資金がイギリスに滞留し、フランスヘ流れて来ないからである。
しかし、当時のイギリスは、政治的に金利を上げることが困難だったのである。なぜならば、当時イギリスの景気は、割高な為替レートのため輸出が伸び悩んだ結果、ただでさえ不況に苦しんでいたからである。そんな情勢では、それ以上景気を悪化させることが確実な、金利の引上げはできなかった。このイギリスとフランスの問の、どうにもならない難問を解決するために乗り出したのが、アメリカであった。
アメリカの金利引下げ
1927年7月初め、イングランド銀行総裁モンタギュー・ノーマン、ライヒスバンク(ドイツ中央銀行)総裁ヒャルマール・シャハトおよびフランス銀行副総裁シャルル・リストという、ヨーロッパ金融界のVIPたちがアメリカヘやって来て、ニューヨーク連邦準備銀行総裁ベンジャミン・ストロングと会議を開いた。その結果、イギリスが金利を上げる代わりに、アメリカが金利を下げることにした。そうすれば、アメリカからイギリスを含むヨーロッパヘ短期資金が流れて、イギリスおよびドイツの窮状を救うことができると考えられたのである。ニューヨーク連邦準備銀行の金利は4%から3.5%へ引き下げられた。
しかし、このときのニューヨーク連邦準備銀行の政策が、どれほど所期の目的を達したか不明である。佳美教授は、「世界大恐慌の発生過程(Ⅲ)」(『経済学論集』50-3)で、アメリカの短期資本移動について、1927年から28年にかけて、アメリカ白身の短期資金の海外流出が12億5000万ドルから2億3000万ドルに減ったこと、また同じ時期に、海外の短期資金のアメリカに対する出入りが、27年の9億3000万ドルの流入一アメリカから見て)から28年の1億2000万ドルの流出に変わったことを示している。
この統計を信用するかぎり、アメリカの金融政策は、アメリカの短期資金よりも、海外(その大部分はヨーロッパ)の資金の動きに大きな影響を与えたことになる。
一方、長期資金の動きでは、最も注目しなければならないのは、アメリカの対外債券投資の推移である。その主体は、外国の政府または企業がアメリカで債券(国債やら社債)を発行して、それをアメリカ人の投資家が買うものである。
このアメリカの対外債券投資は、1926六年の22億ドル、27年の28億ドル、28年の15億ドルと推移したが、29年には7億ドルヘ急減した(『アメリカの大恐慌』1930)。
国際金融システムに与える直接的な影響では、債券投資ほどのインパクトはもたないと思われるが、アメリカの対外直接投資(アメリカ企業の海外投資が主体)は、1926年、27年両年の3億5000万ドルから、28年の5億6000万ドル、29年の6億ドルと増え、1930年には3億ドルヘ急減した。
いずれにせよ、短期資金の場合に比較して、アメリカの公定歩合の0.5%の引下げが、アメリカの対外長期投資に与える影響はそれほど大きなものではなかったろう。長期資金は、短期資金ほどには金利の動きに鋭敏ではないからである。
ここで指摘しておかなければならないのは、アメリカの対外投資、とくにドイツや南米諸国に対する投資は、めぐりめぐって、これらの諸国に対するアメリカの商品輸出を支えていたということである。
第二章で触れた、19世紀のイギリスにおける古典的パターンはここでも見られる。したがって、もしアメリカの対外投資が急減すれば、アメリカの商品輸出も急減せざるをえないという宿命にあった。この点は、最近の日本とアメリカの関係との比較において、重要な意味をもっている。
ところで、問題だったのは、連邦準備銀行の金融緩和政策が、同時にアメリカ国内に大量のイージー.マネーを創出してしまったことである。このイージー・マネーは、結局他に行きどころがなくて、ウォール街へ流れ込んだ。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++}}}
ウォール街へ資金が流れ込んだ後は、ご存知の通りの結果であった。この経済学だけでは理解できない歴史的推移は、今日の金融危機の原因を考察するにあたり、示唆に富む内容であった。
本書は、第7章にて富とは何かの考察を展開する、これもご一読する価値はあるだろう。
そして、第8章において、1989年夏の時点で日本のバブル崩壊と、今日のアメリカ発の金融危機の警告として、大恐慌の再来はあるのかと、考察は予言といってもいいくらいの慧眼である。
関岡氏はクルーグマンより遥か前から警告し予言していた事になる。本書も推薦の一冊です。
【Ddogのプログレッシブな日々】
『「1929年大恐慌」の謎:副題:経済学の大家たちはなぜ解明できなかったのか関岡正弘著』を読む。
その1
http://blogs.yahoo.co.jp/ddogs38/25962973.html
その2
http://blogs.yahoo.co.jp/ddogs38/25994735.html
その3
http://blogs.yahoo.co.jp/ddogs38/25996450.html
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。