http://www.asyura2.com/09/eg02/msg/486.html
| Tweet |
(回答先: 太陽経済かながわ会議 今、始まる。ソーラー革命 年間17兆円が国内にお金が回る方法 (環境ビジネス) 投稿者 蓄電 日時 2011 年 8 月 10 日 16:05:23)
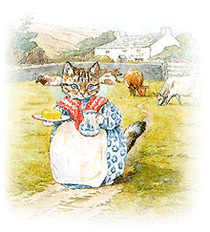

http://www.asahi.com/eco/TKY201011090118.html
電気自動車(EV)のバス普及に向けて、神奈川県と慶応大、いすゞ自動車が開発に取り組んでいる「電動フルフラットバス」の車体デザインが、このほど発表された。エンジンやタイヤのスペースで車内に大きな段差が生まれていた従来の路線バスと違い、EV化で床がほぼ平らになる。試作車は今年度中に完成する見込み。第2次試作車の開発に向け、東芝とJFEエンジニアリングの参加も合わせて発表された。
開発中のEVバスはタイヤの中にモーターを入れる(インホイールモーター)ことで、エンジンのせいで車内に出っ張っている従来バスの座席部分を平らにすることに成功。タイヤもサイズを小さくして、8輪にすることでタイヤボックス上の席もほぼフラットにできた。動力の充電池は、前輪と後輪の間に極力薄くして配置している。ステップの高さは地面から約30センチ。EVの課題である走行距離も、1回の走行距離を路線バスの平均値の120キロを上回る150キロに設定した。
一方、第2次試作車の開発では、慶応大が基本設計、いすゞ自動車が車体設計と試作、東芝が電池開発を担当。JFEが超急速充電器をつくるという。今回の1次試作車は環境省から2カ年で5億円の委託金をもらい行っていたが、それも今年度限り。3年後の完成を目ざす2次試作車は、160億円と試算される巨額の開発費用が課題だ。1次と違い、量産化を目指し複数台作るうえ、より高度な安全性や快適性を求めるため、額が跳ね上がる。松沢成文知事は「国からなんとか金を引き出す。来年度予算に支援を盛り込んでもらうよう働きかける」と意欲を見せている。
県が取り組むEV普及では、バスの他にも、EVタクシーを今後2カ年で県内に100台導入する計画を打ち出している。
【京都市バス】EV(電気)バス実証実験での走行シーン [HD]
http://www.youtube.com/watch?v=dBNTaDyUnBU
【かなマグ.net】次世代EVバスに試乗しました!
http://www.youtube.com/watch?v=xu64VlGeMGU
http://kanamag.net/archives/15012
丸ノ内シャトル デザインライン社マイクロタービンEVバス
http://riversidetraffic.web.infoseek.co.jp/ganbarubus2.html
|
|
|
|
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
|
|
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。