| Tweet |
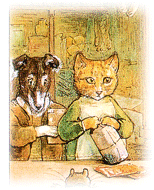
(転送歓迎/ミクシイの日記より)
私は、かつて、厚生省(当時)直轄の病院に勤務して居た事が有ります。
1990年から2000年までの事ですが、その時代、全国の国立病院及び療養所は統廃合の過程に有りました。その中には、実際、経営内容や医療内容に問題の有る病院も有ったと思ひますが、例えば、結核患者用の病棟を持つ病院なども有って、そうした病院を閉鎖した事は、実際、結核医療にマイナスの影響を与えて居ます。
私が居た病院は、比較的経営が良かった事と必要性の大きい分野を取り扱って居た為、統廃合の対象には成りませんでしたが、病棟が縮小された結果、もう永い間使はれなく成った空き病棟が、有りました。赤字を縮小する為の一つの経営手段に、病棟閉鎖と言ふ手法が有り、患者を減らした方が経営が改善すると判断された場合、それまで使はれて居た病棟を閉鎖して入院患者を減らし、赤字を減らす事が出来るからですが、その結果、廃墟の様な空っぽの古い病棟が生まれて居たのです。
そんな、空き倉庫の様な空っぽの病室が、十年以上、全く使用されずに放置されて居たのですが、全国の国立病院が持つそうした空き病棟の数は、相当な数に及ぶのではないでしょうか。
阪神大震災の後、私が思った事は、全国の国立病院、療養所が持つこうした空き病棟を、大地震などの天災やテロ、戦争の際、国が活用するべきではないか?と言ふ事でした。
国立病院は、経営が悪いと言ふ理由で統廃合が進みましたが、災害や戦争の他、新型ウィルスの患者が大量発生した際などに、野戦病院的な場として活用する事が出来る建物や空間を豊富に持って居ます。厚生労働省は、何故、それをしようとしないのか、不思議でなりません。
(まさか、「そう言ふ空き病棟を使ふと、国立病院統廃合のプロセスに支障をきたすから」等と言ふ「官僚的」な思惑による物ではないと思ひますが・・・。)
今回の豚インフルエンザからの新型インフルエンザが何処まで拡大するかは分かりませんが、日本国内にこの新型インフルエンザが広がった場合、旧国立病院の空き病棟を利用する事を考えるべきです。
賛同される方は、私のこの一文を転送、転載しまくって下さい。
2009年4月30日(木)
西岡昌紀(内科医・元厚生省医務官)
-----------------------------------------------------------------
■感染リスクも、「発熱外来」設置機関の確保に課題
(読売新聞 - 04月30日 17:10)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=824293&media_id=20
感染リスクも、「発熱外来」設置機関の確保に課題
(読売新聞 - 04月30日 17:10)
発熱外来用に、新型インフルエンザが疑われる患者をいったん収容するため設置された大津市民病院のテント
新型インフルエンザ(豚インフルエンザ)の警戒水準が「フェーズ5」に引き上げられ、国内での感染者発生の懸念が高まる中、30日午前現在、27都府県が患者発生にそなえて「発熱外来」を設置する医療機関を選定した。
しかし、20道府県では、医療機関と調整中で、「他の患者への感染リスクが高まる」「受け入れスペースがない」など、受け入れ機関の確保には課題が残っていることが分かった。読売新聞が全国47都道府県の担当者に取材した。
国内での患者発生と同時に開設する医療機関の選定を終えた自治体は東京都、京都府、愛知県など27都府県。大阪府、北海道など19道府県は医療機関と交渉を進めており、三重県は30日から交渉に入ったという。
大半の自治体が、発熱外来の設置を依頼する医療機関の選定条件として、「感染症指定機関と大規模な病院」(山口県)を挙げた。
一方、北海道の担当者は「こうした病院には、がんや透析治療を受けて免疫が弱くなっている患者も多数いて、感染リスクが高まる可能性がある」と慎重な姿勢を見せ、選定に向けた協議を続けている。36医療機関と協議中と答えた大阪府も、選定が進まない理由について「二次感染を懸念する声が多い」と打ち明ける。
また、15か所を目標に交渉を続けている和歌山県は「医療機関側に受け入れスペースがない」ことを挙げ、群馬県は「医療機関側の人員不足があり、交渉している」と話す。
「一般の患者と接触しない工夫や、費用面などでハードルが高い」(三重県)として、実際の設置に向けた話し合いが進んでいないという自治体もあった。
一方、発熱外来に選定した医療機関を公表するかどうかについては22県は県のホームページなどで公表するとしたが、17都府県は、「ほかの患者が混乱する」などとして公表しておらず、住民には、まずは近隣の保健所に相談するよう呼びかけていた。ほか8道県は検討していた。
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。