http://www.asyura2.com/09/bun2/msg/650.html
| Tweet | �@ |
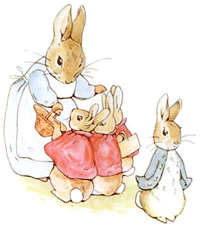
�������R�[�h��Ђɋ߂Ă���1990�N��̏��ߍ�����A���łɁu�N���V�b�N���y�̊�@�v�Ƃ������Ƃ�����Ă����B���̌�����̐��E�ł͐܂ɐG��A�R�A�𐬂��t�@���w�̍���E���������ɂ���ė����B���ƂȂ� �u�������ɂ������I�v �Ƃ͎v�����A������ �u���Ȃ��Ƃ������ɂƂ��Ă���Ȃɂ��ʔ������̂��Ȃ����̐l�ɂƂ��Ė��͓I�ł͂Ȃ��̂��H�v �Ƃ����^������͕��������Ă����B
���R�[�h��Ђ̃N���V�b�N����S���҂Ƃ���18�N�Ԕ��A���y�]�_�ƂƂ��Ė�14�N�ԃN���V�b�N���y�̐��E�Ɋւ�荇���ɂȂ��ė������A���ŋ߂ɂȂ�܂ł��̋^��ɑ��铚����������Ȃ������B�����������w����w�Łu�N���V�b�N���y���_�v�Ƃ������Ƃ�ʂ��āA�w�������Ɂu�N���V�b�N���y�Ƃ͉����H�v�Ƃ��������N���A�f�B�X�J�V�������邤���Ɏ����̍l������������A�悤�₭�������Ȃ̂��������Ă����悤�ȋC������B����Ȓ�����v�����܂܁A���ɕ����ċL���Ă݂����B
���N���V�b�N���y�̒��O�Ƃ��̚n�D
�����v���ɁA�N���V�b�N���y�̐��E�ɂ͋��炭��̃^�C�v�̒��O������̂ł͂Ȃ����낤���B���Ȃ킿
�@ �N���V�b�N���y���ЂƂ̏����ɗǂ��u���{�v�Ƃ��ĂƂ炦�A�u�N���V�b�N���y�ƊE�̉��l�ρv�������͂����ɗǂ��������Ă��邩�����������Q�[�������Ă���l�X�i���Ȃ݂ɂ����ł��� �u�N���V�b�N���y�ƊE�v �̓��R�[�h�A�����A�y���o�ŁA�y�퐻���Ȃǂ̎Y�ƊE�݂̂Ȃ炸�A��ȉƁA���t�Ƃɉ����A���y�W���[�i���X�g�A���y�]�_�ƁA���y���t�A���y�w�҂Ȃǂ��܂߂Č��݂̃N���V�b�N���y�E�S�ʂ��w���j
�A �|�s�����[���y��̗w�ȂȂǂƓ����悤�ɂ����������D��������A�����čD��S�̕����܂܂ɃN���V�b�N���y���l�X�B
�ܘ_�A�P���Ƀ^�C�v�@�̂݁A�^�C�v�A�݂̂Ƃ����l����ł͂Ȃ����낤�B�������A���̐l�̓^�C�v�@�ł͂Ȃ����A�Ǝv���悤�Ȑl���ӊO�Ƃ��̐��E�ɂ͑����B����15���炢�����40�N�ԃN���V�b�N���y���Ă�������ǂ��A���O�Ƃ��Ă̊�{�I�ȃX�^���X�͍ŋ߂ł͂����ς�^�C�v�A�ł���B�u���ԂŘb��ɂȂ��Ă��邩��v �Ƃ��A�u��X�I�ɐ�`����Ă��邩��v�Ƃ������蕶��ɂ��A�u�L�����Ȃ�����v �Ƃ����]���ɂ��قƂ�Nj������Ȃ��B
�u��������100�l�̐l�Ԃ�������100�̚n�D������A����䂦���l�ς̍��ӂȂǂ͎���͂����Ȃ��v�Ƃ����̂����̊�{�I�ȍl�����ŁA�]���D�݂̌X���������N���V�b�N���y�t�@���Ƙb���Ă��Ă��A�����D�����������Ƃ����_�ō��ӂ�����̂͂R���������Ƃ���ł���B�悭�m�荇���̉��t�Ƃɂ��u�X���̐l���牽�ƂȂ��ǂ��Ǝv����悤�ȉ��t�ƂɂȂ낤�Ƃ����A�܂��P���̐l�ɔM���I�Ɏx�������悤�ɂȂ�Ȃ����B���̌セ����Q���A�R���ƍ��߂�悤�ɓw�͂�����ǂ��ł����v�Ƙb���Ă���B
�l���Ă݂�A�N�����������y�Ƃ��D���ɂȂ�Ȃ��Ă͂����Ȃ��A������i���u���ȁv�Ǝv��Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ƃ����v�z�͂ƂĂ��|�����A�댯�ŁA�����B
*�S�Ă�c�����邱�Ƃ̓���A�����T������ʔ���
���������N���V�b�N���y�̗��j��H���čs���Ȃ�e�P���������Ȃ��Ƃ��Ă��A�ꐶ�̊Ԃɒ�����Ȃ��قǖc��ȗʂ̍�i������B
�Ⴆ��18���I�㔼����19���I�����ɂ����Ă̎��ゾ���łP���Ȃ�������Ȃ����݂��Ă���Ƃ����B�������A���̂����ň�ʂɒm���Ă�����̂͂Ƃ����n�C�h���A���[�c�@���g�A�x�[�g�[���F�����炢�ŁA���ڂ����l�ł��T���}���e�B�[�j�A�o�b�n�̑��q�����A�{�b�P���[�j�A�V���^�[�~�b�c�A�f�B�b�^�[�X�h���t�A�N���E�X�c�Ƃ�������ȉƂ̍�i����������x�ł͂Ȃ����B���̎���̌����Ȃ�500�Ȃ��m���Ă����炩�Ȃ�̒ʂł���B
����Ȓ��ň�ʓI�ɒm���Ă����L�R�l�̍�ȉƂ����̍�i�����ł��̎�����\�����ėǂ����̂Ȃ̂��ǂ����H�@�Ђ���Ƃ���Ƃ����ƈ�������l�ς���Ċy���܂��Ă����Ȃ�����̂ł͂Ȃ����c����ȋ^�₪�����������Ă���B
���̂Ƃ���18���I�ȍ~�̍�i�ɂ��ăN���V�b�N���y�̐��E�ň�ʓI�Șb��ɂȂ���̂́A�������钆�̂ق�̕X�R�̈�p�ɉ߂��Ȃ��̂��B�C�O�ł̓}�C�i�[���[�x���𒆐S�ɂ���܂Ŗ�����Ă��Ĉ�ʂɒm���Ă��Ȃ�������i�̊y�����o�ł��A�b�c�^�����铮��������ɂȂ��Ă���B�Ⴆ�i�N�\�X�E���[�x���́u18���I�̌����ȁv�V���[�Y�ł� �u�I���B�f�B�E�X�̓]�g����Ɋ�Â��V���t�H�j�A�W�v���͂��߁A�f�B�b�^�[�X�h���t�̕W����������������Ȃ���������Ă���̂��B
���̈���ŗL�����ȂȂ牽�S�E����Ƃ����^�������̋Ȃɂ��đ��݂���B���̒��ł���ȂɊւ��Ă��Ȃ����ł��D���ȉ��t�ɏo������\���͂ǂ��ł��낤���H�@���t�������̍D�݂ł��邩�ۂ��́A���̋Ȃ��D���ɂȂ�邩�Ȃ�Ȃ����̑傫�ȕ�����ڂɂȂ邾���ɂ���͏d�v�ȃ|�C���g���B�R���N�[���Ƃ������̂��x�z�I�ɂȂ��Ă��������ł́A���t�Ƃ̃X�^�C���͗D���E���܂��邽�߂̗l���ɉ�ꉻ�������̂ō��ق̕��͑傫���Ȃ����A��O��m�������̘^�������ɂ���ƈ�l�ЂƂ�̌������Ȃ�قȂ��Ă��ċ��������B
��͂�A�����i�̎p����������c�����悤�Ǝv���Ȃ�Í������̑�\�I�Ș^����O�O�ɒǂ��Ă��������Ȃ��B�������ςȍ�Ƃ����A�K���Ȃ��ƂɊC�O�̂b�c�ɖڂ�������Ƃ��������ߋ��̘^���A�Ƃ�킯��O�̘^��������^���͂k�o����Ƃ͊r�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��قǐ���ɂȂ��Ă���B�������͍����ł̓T�����T�[���X�A�h�r���b�V�[�A�X�N�����[�r����̎��쎩��������e�ՂɎ�ɂ��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B
���̂悤�ȊC�O�̓�����ǂ������A�����̚n�D�ɒ����ɁA����C�܂܂ɍ�i�E���t��T�����čs���̂͂ƂĂ��ʔ������A�����瑱���Ă��O���Ȃ��B����ǂ��Ƃɂ��������Ǝ�ԉɂ�������B����Ɏc�O�Ȃ��ƂɁA���������ƊE�̈ꉟ���łȂ��悤�ȁA�}�C�i�[������Ă�����̂�T�������̗ǂ����Љ���Ƃ��Ă��A�Ȃ��Ȃ����ꂪ�L�����čs���Ȃ��̂��䂪���̌���Ȃ̂ł���B
���ʂ����ăN���V�b�N���y�ɖ{���́u���T�v�͑��݂���̂��H
�N���V�b�N���y�̐��E�ɂ���ƂЂƂ̂���ڂ̂悤�Ɂu��ȉƂ̈Ӑ}�ɒ����Ɂv�Ƃ������t�����ɂ���B��ȉƂ����ē��ɕ`���A�����������y�����̂܂܂ɍČ����邱�Ƃ�ڎw�����u���T��`�v�Ƃ������t�A���邢�͂��̂��߂ɍ��o���ꂽ�u���T�Łv�y�������l�ł���B
�������A�ʂ����ăN���V�b�N���y�ɖ{���̈Ӗ��ł́u���T�v�ȂǑ��݂���̂��낤���H �����������t�ɐڂ��邽�тɎ��͂��̂��Ƃɋ^��������Ă����B�|�s�����[���y�̐��E�ɂ͑����̏ꍇ�ɖ{���̈Ӗ��ł́u���T�v�����݂���B�Ⴆ�r�[�g���Y�̑�q�b�g�� �u�V�[�E�����Y�E���[�v �� �u���T�v �͉����Ƃ����A�����q�b�g�E�`���[�g�Ƀ����N�E�C�����Ă����V���O���Ղ̉����ł���B�l�X�͂��̉����ɂ���Ă��̍�i�̖��͂ɐڂ��A���̋Ȃ͐��ɍL�܂����̂��B
�Ⴆ�A���Ȃ����u�r�[�g���Y�́s�V�[�E�����Y�E���[�t�����t���Ă��������܂��H�v�Ɨ��܂ꂽ�Ƃ��āA�������̋Ȃ�m��Ȃ�������ǂ������s�����Ƃ邾�낤���H ���炭�قƂ�ǂ̐l�͊y���������O�ɂ܂��ނ�̘^���������Ȃ肵�Ē����̂ł͂Ȃ����낤���H �������邱�Ƃʼn��y�Ƃ͐��Ԃ̐l�X���u���T�v�Ƃ��Ă��̋Ȃɑ��Ď����Ă���u�݂���v�����ۂ̉��Ƃ��Ēm�邱�Ƃ��o����̂��B���Ɋy���͖����Ƃ��܂��͌J��Ԃ������Ă���𐡕���킸�R�s�[���A�������牉�t�ғƎ��̖��t�����l����B
����ɑ��ăN���V�b�N���y�̏ꍇ�͂ǂ����H �قƂ�ǂ̃N���V�b�N�̉��t�Ƃ͂܂��y�����w������B���������������ɂ��邱�Ƃɂ��܂�ϋɓI�ł͂Ȃ��B����͑����̏ꍇ�ɘ^�����ꂽ���̂��u���T�v�ƔF�߂Ă��Ȃ����炾�B���̍ł��傫�ȗ��R�͍�ȉƂ������̍�i�����t���������A���邢�́A��Ȏ҂̈ӎv�𒉎��ɓ`�����ƍl�����鉉�t�Ƃɂ�鉹������X�����ɂ��邱�Ƃ��o����̂͑�̃u���[���X �i1833�|1897�j�A�T�����T�[���X �i1835�|1921�j�����肩���̐���ł����Ȃ����炾�B
���������̎���̍�ȉƂ����̏ꍇ�s�A�m�ȁA�����y�A�̋ȂȂǂɃW�����������肳���B�����̋Z�p�ł͘^������������I�[�P�X�g����i�̂悤�ȑ�K�͂Ȃ��̂͂���ɐ������Ȃ��B����ȑO�̍�ȉƁA�Ⴆ�V���p���̂悤�ɘ^���@�킪��ʉ����锼���I�ȏ���O�ɖS���Ȃ��Ă���P�[�X�ł́A����q�ɂ��^��������c���Ă��Ȃ��B�����肳��ɐ̂̍�ȉƂ����A�o�b�n�A�n�C�h���A���[�c�@���g�A�x�[�g�[���F���A�V���[�x���g�Ɋւ��Ę^���Ƃ��Ắu���T�v�͖]�ނׂ����Ȃ��B
�ł�20���I�O���ɂ͊������t�}�j�m�t�A�����F���A�q�D�V���g���E�X�A�K�[�V���E�B���A�X�g�����B���X�L�[�A�n�`���g�D��������̂悤�Ɏ��쎩���̉��������Ȃ�c���Ă����ȉƂ����̏ꍇ�͂ǂ����낤���H �ӊO�Ȃ��ƂɌ���ł͂��������������������̉��t�Ƃ����ɂ�鉉�t���D��Œ����Ă���l�����Ȃ��Ȃ��B���鉹�y��w�̃s�A�m�ȋ����� �u�����ă��t�}�j�m�t���ăs�A�m�����肾������ł��傤�H�v �ƁA���̍�ȉƂ̎��쎩�����Ȃ����R����������Ƃ����b��m�荇�����畷���āA���̌��疳�p�ɋV�����B
�����܂ō����͂Ȃ��ɂ��Ă��A�u�^�����Â��Ē����Â炢�v�A�u���t�X�^�C�����É߂��ĎQ�l�ɂȂ�Ȃ��v�A�u�ߋ��ƌ���ł͘^���Ƃ����s�ׂ̈Ӗ��Â����Ⴄ�v�Ƃ��������ɓ�Ȃ����Ă����������̂�ے肵������X��������B�����͕�����Ȃ��u���T�v���肤����̂ł���ɂ�������炸�c�c����ƂƂ��ɍ�i�ɂ���Ă͎��쎩���łȂ��Ƃ��̖{���̗ǂ����`����Ă��Ȃ��P�[�X�����Ȃ��Ȃ��B���Ƀ��}���h�`�ߑ�̃s�A�m�̂��߂̐��i�I���i�Ȃǂł́A��Ȏ҂̈Ӑ}����Ƃ��낪�y������͏\�S�ɓǂݎ��Ȃ����Ƃ�����B�V�����E�X�R�b�g�� �u�@�̍��v�A�Z�V���E�V���~�i�[�h�́u�s�G���b�g�v�Ȃǂ̃s�A�m�Ȃ͂����������̂̓T�^�Ƃ����邾�낤�B
�l���Ă݂�Ɖ��t���p�[�g���[�Ɋւ��āA�N���V�b�N���y�E�ł͑����̏ꍇ���̃A�[�e�B�X�g�Ǝ��̍�i�Ƃ����͖̂����A�����̊y�Ȃ����t���邱�Ƃ���{�Ƃ��Ă���B�]���Ă��̋ƊE�́u��������̊y�Ȃ��A�V���ȉ��t�ɂ���čČ���������v���Ƃɂ���Đ������Ă���B���������ړI�̂��߂̊y��������A�o�ŎY�Ƃ�����B���t�Ƃ����āA���t�Ƃ��琬���鋳��Y�Ƃ�����B�R���T�[�g������A���̃}�l�[�W�����g��Ђ����݂���c�c�����N���V�b�N���y�̐��E�Ƀ|�s�����[���y�̂悤�ȁu���Ƃ��Ă̌��T�v�����݂��Ă��܂�����c�o�b�n�A�x�[�g�[���F����V���p���̎��쎩���Ȃǂ���������A���炭�N���V�b�N���y�E�͎Y�ƂƂ��Đ������Ȃ��Ȃ邾�낤�B�Ȃ��Ȃ璮�O�͂��̍�i�̖{������ׂ��p��m�낤�Ǝv�������������������̂�����c�c�u���Ƃ��Ă̌��T�v�����݂��Ȃ����ƁA���邢�͉��ɑ��݂��Ă������F�߂Ȃ����Ƃɂ���āA�N���V�b�N���y�ƊE���������Ă���Ƃ���������̂ł͂Ȃ����낤���H
�ʂȌ���������Ȃ�N���V�b�N���y�́A�u�^���v�����݂��Ȃ���������́u���y�r�W�l�X�݂̍���v�������Ɉ����p���ł��܂��Ă��鉹�y�W�������̓T�^�ƌ��邱�Ƃ��ł��悤�B�����ł͏�ɐV�������y�w�K�ҁA�y���w���ҁA���t�Ƃ������̃��p�[�g���[���Č����邽�߂ɕK�v�Ƃ����B�����āA�V��������鉉�t�ɉ��炩�̉��l�����o���Ȃ��ƋƊE���������čs���Ȃ��Ȃ�B����䂦�ɐV���ɓo�ꂷ��^���ɑ��ĂЂƂ̉��l�ςƂ��āu��Ȏ҂̈Ӑ}�ɒ����ł���v�Ƃ������t�̐������������Ύ咣�����B���̈���ŁA�ߋ��̉��y���L���ȗD�ꂽ�^�����ƊE�S�̂Ƃ��Ă͕s���ɉߏ��]������A�I���ɂ͔p�ՂƂȂ�A�b�c�J�^���O���������A�Y����Ă��܂��̂��B
�Ⴆ��80�N�O�̐��E���l���Ă݂悤�B����̓��W�I������d�C�^���̃��R�[�h���悤�₭���ɏo�Ă�������B�V���p���E�R���N�[�����A�p�\�R�����A�[���b�N�X�E�R�s�[���A�e���r���A���R�̂��ƂȂ���R���r�j�G���X�E�X�g�A�������������ゾ�B�������A�������Ƃ��Ă͎������̎�����̓o�b�n�A���[�c�@���g�A�V���p���̎���ɋ߂������͂����B�����āA���炭���y�̎��Ӗ���������͂���������ȉƂ����̎���ɋ߂������̂ł͂Ȃ����B���̂��Ƃ͑[���Ƃ��Ă��A���̂��Ƃ͔F�߂���Ȃ����낤�B
����80�N�O���Ȃ킿1920�N��㔼�̓t�����X�Ȃ�t�H�[���A�h�r���b�V�[�A�T�����T�[���X�A�T�e�B�炪�S���Ȃ��ĊԂ��Ȃ����A����ɂ̓����F���A�v�[�����N�A�~���[�炪���ۂɊ������Ă�������ł�����B���Ȃ��Ƃ������̍�ȉƂ����̂��Ƃ́A��X��肱�̎���̉��y�Ƃ����̕����悭�������Ă����ƍl����̂����R�ł͂���܂����H ������҂Ƃ��Ď��ɍ�i�ɑ��Ĕے�I�ł������Ƃ��Ă��A�ނ�́u1920�N��㔼�v�Ƃ����g�g�݂̒��ł����ɐڂ��邱�Ƃ��o�����l�X�Ȃ̂��B��ǂ��ł�����̌����鎄�����ɂ͗����ł��Ȃ��悤�ȓ����̈Öق̃��[���A�펯�A���l�ςȂǂ�������ȉƂ����Ƌ��L���邱�Ƃ��ނ�ɂ͂������R�ɏo�����̂��B���Ƃ�������������̉��t�Ƃ����ɂ���Ę^�����ꂽ���̂��A�����̏펯�A���l�ς��ƈ�����Ƃ��Ă��A����͑����ɔے肷��̂ł͂Ȃ��A�����Ƒ��d�����ׂ��ł͂Ȃ����B����䂦�Ɏ������͂�����������́A����ɂ͂����ƌÂ�����̘^���̂��Ƃ�ϋɓI�ɒm�낤�Ƃ���K�v������B
��ɏq�ׂ��悤�ɃN���V�b�N���y�͓�����i�ɑ��đ��l�ȉ��߂����݂����邱�Ƃɂ���ĎY�ƂƂ��đ������Ă���B���������u�݂���v�̒��ŁA�u�������t�Ƃ̂��́v�A�u�V�������́v�̒����獡���I�ȉ��l�����o���A�u��Ȏ҂̈Ӑ}�ɒ����v�Ƃ������z���X�V�������邾���ł́A�N���V�b�N���y�ƊE�͑��ӗ����s���Ȃ��Ȃ�̂��������͏\���ɗ������ׂ����B�����h���ɂ͌Í������̂�����\���̉\���������E�T�������ׂ����낤�B�������������̏d�v�Ȓ��Ƃ��āA�������͉ߋ��̘^����̂�ɂ���̂ł͂Ȃ��A���ꂼ��̍�i�ɂ���19���I�����獡���Ɏ���^���j�A���t�j����������Ɣc������w�͂����邱�Ƃ��������K�v�ł͂Ȃ����H ���̏�Ōl�l���\�\���O�ł��ꉉ�t�Ƃł���A�c��Ȏ�ނ̉��t�̒����玩���̍D�݂̃X�^�C���̂��̂ɃA�N�Z�X���čs�������B��������s�Ɉڂ��̂ɂ͑�ςȎ�ԂƘJ�͂�v���邾�낤�B���K�I�ȕ��S���n���ɂȂ�Ȃ��B����ǂ�����ȑ�ςȋ�J���ۂ����邱�Ƃ̕����܂��y���ɍK���ȏȂ͂����B�N���V�b�N���y�ƊE�̉��I�ȉ��l�ς������t�����錻����́c�c
�b�c�̎���ɂȂ��āA19���I������r�o���㖖����1950�N���܂ł̘^�������E�I�ɑ�ςȐ����ŕ�������Ă���B��������������P�Ȃ�D���Ƃ̃}�j�A�b�N�Ȏ�̕\��ƂƂ炦��ׂ��ł͂Ȃ��B����͕�����Ȃ�����̗v���Ȃ̂�����B
��20���I�̃N���V�b�N���y�Ƃ�
�N���V�b�N���y��20���I���ǂ̂悤�ɍl����̂��H�@��������������ƕs�v�c�Ɏv���Ă�����_���B�R���T�[�g�ʼn��t�����1920�N��ȍ~�̃��p�[�g���[�ɂ͓�̃^�C�v������B�ЂƂ́u�O�q�v��W�Ԃ���悤�ȍ�ȉƂ����̍�i�A�����ЂƂ́u�O�q�v�ɂ͓��ɂ�����炸�����̂������@����g���Ď��R�ɑn�삳�ꂽ��i�B�O�҂́u���㉹�y�v�Ƃ������e�ŃN���V�b�N���y�̐��E�ł͌����B����ɑ��Č�҂͂��̑O�q���̌����ɂ���Ă܂Ƃ��ɕ]���̑ΏۂƂ��Ȃ��Ă��Ȃ��悤�Ɏv����B
�����l�I�ɍD����20���I�̍�ȉƂ����A�A���N�T���f���E�^���X�}���A�}���I�E�J�X�e���k�I�[���H���e�f�X�R�A�}�k�G���E�|���Z�Ƃ������قڂ�����W�������ɂ킽���č�i���₵�Ă�����̂̍����ł͂��̃M�^�[��i�ɂ���ėL���Ȑl�X�A���邢�͊NJy��t�҂ɂƂ��Ċʼn߂ł��Ȃ����݂ł���W�����E�t�����Z�A�E�W�F�[�k�E�{�U�A�W�������~�V�F���E�_�}�[�Y�Ƃ������l�X��20���I�̃N���V�b�N���y�̗��j������ŐϋɓI�ɘb��ɂ���邱�Ƃ͂Ȃ��B����͔ނ炪�O�q�I�ȍ�i�͑����������ɂ��Ă��A���O���ӎ���������Ղ���i�𐔑��������Ă���A����炪���t��Ŋ����Ɏ��グ���Ă��邽�߂ł͂Ȃ����ƍl������B�܂艉�t�̌���Ől�C�����ƂƁA�u���㉹�y�ƊE�v�ŕ]������邱�ƂƂ͑S���������Ă��܂��Ă���̂��B
�{���ɂ���ł����̂��낤���H�@���͑S�̎j�Ƃ��ẴN���V�b�N���y��1920�N��ŏI������ƍl���邱�Ƃɂ��Ă���B���Ȃ킿SP�Ղ̓d�C�^�����o�ꂵ���W�I�������J�n���ꂽ���̎��オ�A 19���I���瑱���Ă����u�y���ˑ��^19���I���y�v�ł���N���V�b�N���y�̑S�̎j�̏I���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂��B1920�N��ȍ~�̃N���V�b�N���y�͍�ȉƌl�X�X�̗��j�̒��Ō����ׂ��؍����̂��̂ł͂Ȃ����B���炭19���I�ȍ~�̃N���V�b�N���y��1960�N�ネ�b�N�̗��j�����r�ׂė��āA���͗��҂ɋ��ʂ�����j�I�W�J������̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B����ɂ��č���͋L���Ă݂����B
���u���y�Y�Ɨ͊w�v �������� �u���}���h�I�W�J�v
����ȑO�̎���͂Ƃ������A19���I�ȍ~�̃N���V�b�N���y�͕s���葽���Ɋy���Ƃ����\�t�g��̔����邱�Ƃɂ���ĉ��y�����V�X�e���ɂȂ������Y�Ɖ������Ƃ����_�ɒ��ڂ��ׂ����낤�B�����āA���̗��j�͂���W�������̉��y�Y�Ƃ̔��W�̖@���i�����Ȃ�� �u���y�Y�Ɨ͊w�v�j�ɏ]���Ă���ƍl����̂������I�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B
�s���葽���̐l�X�Ƀ\�t�g�i�y���ASP���R�[�h�ALP���R�[�h�ACD�ADVD�Ȃǁj�邱�Ƃɂ���Ď�����A���邢�͍�i�̒��쌠�ɂ�������B����͎��19���I�ȍ~�̂����鉹�y�W�������ɂ����č�ȉƂ����E���y�Ƃ����̎������Ƃ��ďd�v�Ȃ��̂ƂȂ����B�����āA���鉹�y�W�����������W���čs���ߒ��ɂ����āA�ЂƂ̌o�ϓI�ȗ͊w�������Ă����ƍl���邱�Ƃ��o����B���̗l���͑�G�c�ɂT�̎���ɕ����čl���邱�Ƃ��ł���B
�@�i�P�j �m�����F���y�W�������Ƃ��Ă̎s�ꐫ���m������
�@�i�Q�j �������F���l���̐����҂�����A�˔\����҂��勓���Ă��̃W�������ɎQ������
�@�i�R�j �c�����F�ߓ��������������Ȃ�A����ɑ��҂Ƃ̍��ق���������X���������ɂȂ�
�@�i�S�j �O�a���F�l�X�Ȏ����I�Ȏ��݂̒��ŐV��ȃA�C�f�B�A������Ɍ͊����s���l�܂�A���̉��y�W�������̍���ɂ���K�肪�j���
�@�i�T�j ���U���F�S�̂Ƃ��Ă̔��W�͍���ƂȂ�A���ꂼ��̌X���̉��y�ɑS�̂����������B�����č�ȉƁE���y�ƌl�̉��y�I�ȗ��j�̒��ŁA�����̌�@���������Ă�������ƂȂ�B�������N���V�b�N���y�̐��E�ɂ����Ă��̎���͈�ʓI�Ɂu�O�q�̌��z�̎���v�Ƃ��Ă̂ݔF���������Ă���B
���Ɂi�Q�j�|�i�S�j���u���}���h�I�W�J�v �ƌĂԂ��Ƃɂ���ƁA�N���V�b�N���y�ɂ����Ă�19���I�O������1920�N���܂ŁA���b�N�ł�1960�N�オ����ɑ�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�S�̂Ƃ��Ă݂��ꍇ�A�Љ�ɉe����^����悤�ȉ��y�W�������͂��̂悤�ȁu���}���h�I�W�J�v�����čs���B
�ł́i�Q�j�|�i�T�j�̂��ꂼ��̎���ɂ��Ă��������ڂ����������Ă݂悤�B
�i�Q�j�������̓N���V�b�N���y�ɂ����Ă̓V���p����X�g�A���邢�̓p�K�j�[�j�̓o��A���b�N�ɂ����Ă̓r�[�g���Y�̓o�ꂪ���Ă͂܂�B�ނ�ɓ��ꎩ�������̂悤�ɂȂ肽���A�ނ�̂悤�Ȑ��������߂����A�l�C�҂ɂȂ肽���Ǝv����҂����𒆐S�ɐl�X���勓���ĎQ�����Ă���B���`�B���x�������������A�N���V�b�N���y�̕����q�b�g�̃T�C�N�����������Ƃ͓��ɓ���Ă����K�v�����邾�낤�B�N���V�b�N�ł͂P���I�����āi�Q�j�|�i�T�j�̃v���Z�X�����������邪�A���b�N�̏ꍇ�ɂ̓}�X���f�B�A�̔��B�̂�������10�N�قǂ̂����ɂ��ꂪ����������ꂽ�B
�i�R�j�c�����͋��炭�ł��d�v�Ȏ������B���̒��ő��҂Ƃ̍��ʉ���}�邽�߂ɍ�ȉƂ����E���y�Ƃ����͌��I�ł��낤�A�l��������X�����������Ƌ����悤�ɂȂ�B���b�N�̐��E�ł��M�^���X�g�̒���Z�I���֎�������A���̃O���[�v���g��Ȃ��y����g���Ă݂���i�V�^�[���A�`�F���o���Ȃǁj�A����ȋȂ�����Ă݂���A����̉ʂĂ͎G����e���r���ӎ����ăR�X�`���[���ɋÂ��Ă݂���i�G�W�v�g�l�̈ߑ��ɐg���T���E�U�E�V�����ƃt�@���I�Y�A�A�����J�Ɨ��푈�����̈ߑ��ʼn��t����|�[���E�����B�A�[�ƃ��C�_�[�X�Ȃǁj�A�O���[�v���ɋÂ�i�����B���E�X�v�[���t���A�X�g���x���[�E�A���[���E�N���b�N�Ȃǁj�悤�Ȑl�X������ė����B�N���V�b�N���y�̐��E�ł���i�K�́i���t���Ԃ��邢�͕Ґ��j�̊g��A���B���g�D�I�W�e�B�̐�s���A������i���w�A���p�Ȃǁj�Ƃ̘A�g�A�����I�ȗv�f�������ꂽ�ٍ���A�p���f�B��̐��ᔻ�Ȃǁc��ȉƂ������l�X�ȐV��Ȏ��݂ɂ���đ��҂Ƃ̈Ⴂ��ϋɓI�Ɏ咣����ł����}���h�I�Ȏ���ł���B
�������Y��Ă͂����Ȃ��B������������̉��y�̗��j�Ƃ����̂͒��O�̚n�D�̑��l���ɕq���ɔ������A�������ɗl�X�ȃ^�C�v�̍�i���������Ă���̂��B�����y���ɐ�삯�Ă�����́A����̗��s�ɑ��Ė��S�Ȃ��́A���ɕێ�I�ȌX���̂��́c�����āA�����������l�����������̎���̉��y����ɖ��͓I�Ȃ��̂ɂ��Ă���̂ł���B���݂�60�N��̃��b�N�ɂ����ăV���O���Ւ��S����A���o���Ƃ��ẴR���Z�v�g��������LP�ՂւƏ��X�ɕ\���̋K�͂��g�債�čs�������Ƃ́A�N���V�b�N���y�̐��E�ł̍�i�K�͂̊g��X���Ƃ����v����B
�ƊE���`������邱�Ƃɂ���Ă���ɊW�����}�X�R�~�����B����̂����̎���B�₪�ă}�X�R�~�͉��l���f�ɂ��d�v�Ȗ������ʂ����悤�ɂȂ�A���j�ς����悤�ɂȂ�B�����Đi���I�Ȃ��́A�����I�Ȃ��̂�i�삷��X��������ɋ����Ȃ�B
�i�S�j�O�a���͉��y�Ƃ����̃W�������ɂ�����\���̌��E��͍����n�߂�B�����ł͓���I�Ȃ��̂���̗��E�A���l�ԓI�Ȃ��̂ւ̓���A���ɕK�������S�n�悭�Ȃ����̗̂��p�c�Ƃ������X���������B�ꍇ�ɂ���Ă͖Ȃǂɂ���Ĉ����N�������u���z������ԁv�����y�ɂ���ĕ\������҂������B���̂悤�ɂ��Ăǂ��炩�Ƃ����Ǝ��ȕ\���̂��߂ɒ��O�Ɍ}�����Ȃ��X���������ɂȂ�A�����������̂�O�q�̊��U�������}�X���f�B�A���i�삷��Ƃ����}���Ŏ��オ�i��ōs���B���傤�ǃN���V�b�N���y�ł̓��O�l���Y���A�t�����L�X�g�̉��y�A�������ێ�`�ȂǁA���b�N�ɂ�����T�C�P�f���X�������̎����̎���l���ƍl���邱�Ƃ��ł���B
�������āu���}���h�I�W�J�v���I���A�i�T�j���U���ɂ����Ē��O�̑命�������͂₻��ȏ�́u�O�q�v��]�܂Ȃ����ԂɊׂ�ƁA��ȉƌl�X�X�̗��j�ɃX�|�b�g���C�g��������悤�ɂȂ�A�S�̂Ƃ��Ă̂��̉��y�W�������̗��j�͂��͂����Ȃ��Ȃ�B�����̂������@���g���Ăǂ̂悤�ɌX�̉��y�Ƃ��n�삵�Ă�����������鎞�オ��������B���邢�͂ЂƂ̌X���ɓ����������y�̗��j�����ꂼ��ɐV�����W�������Ƃ��Č����悤�ɂȂ��čs���B���b�N�ł�1960�N�㖖����1970�N�㏉���ɂ����āA�v���O���b�V���E���b�N�ւƂ���Ɂu�������v�����߂��O���[�v�����������̂́A�T�C�P�f���X���ɌX�|���������̃O���[�v����������t�H�[�N�A�u���[�X�A�J���g���[���E�G�X�^���̉e�����ɁA����ɂ̓v���~�e�B���ȃ��b�N�����[���ɉ�A���čs�������Ƃɂ�����Ă���B�₪�ă��b�N�̗��j�̓v���O���b�V���B�A�n�[�h�E���b�N�A�w���B�[�E���^���A�p���N�̂悤�ȐV�����W���������ɁA���邢�̓A�[�e�B�X�g�P�ʂŌ���čs���悤�ɂȂ�B
����N���V�b�N���y�̐��E�ł�1920�N��ȍ~�ɂ��u�O�q�I�ȑn��v�𑱂��čs�����l�X������B�������Ȃ��瑽���̍�ȉƂ����͂����������̂���������Łi�����ɂ͑O�q�I�Ȃ��͈̂�؏����Ȃ��l�����邪�c�j�f�批�y�A�q���̂��߂̃s�A�m�ȁA�����ȁA���t�y�̂��߂̍�i�A���p���y�Ȃǂɂ������߂Ă���̂�����Ȃ̂��B�ЂƂ̗��R�Ƃ��Č��㉹�y�ƊE�����́u�O�q���y�v�͈�ʎ���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A��{�I�Ȑ���������̂ɓK���Ȃ�����������B���ɂ̓N���V�b�N���y�ƊE�͑O�q�Ɏu�������n�삾�����u���㉹�y�v�Ƃ��Č��`���邱�Ƃɂ���āA���̑S�̎j�����������Ă��邩�̂悤�ɋU�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����ĂȂ�Ȃ��B
���̂悤��20���I�̃N���V�b�N���y�j�͕\�ʏ�u�O�q�̌p���v�����A�����I�ɂ́u���U���v�A�u�l�j�̎���v�ɓ˓����Ă���ƍl����̂����R�A�Ǝ��͍l����B�܂������l���������N���V�b�N���y�̌��݂͂�葽�l�ŁA�e���݈Ղ��A�y�������̂ɂȂ�̂͌����܂ł��Ȃ��B�q�����������t���铒�R���́u���َq�̐��E�v���A20���I�̓��{���Y�s�A�m�Ȃ̍ō�����Ƃ��Č����悤�ȁc����Ȓ��O�̖{���ʼn��y���d�������鎞�オ�������ė~�������̂��B
�����y�]�_�͂ǂ�����ׂ���
����͎��̃N���V�b�N���y�\�t�g�̏N�W�ƁA���y�]�_�ƂƂ��Ă̊�������A�N���V�b�N���y�E�̖��_�ɂ��ď����Ă݂����B
�l���Ă݂�Ύ��͏��w���̍����烍�b�N�̃��R�[�h�̏N�W���n�߁A���[�����O�E�X�g�[���Y�A�L���N�X�A���[�h�o�[�Y�A�t�[�A�s���N�E�t���C�h�A�h�A�[�Y�A�A�C�A���E�o�^�t���C�Ȃǂ̉��y�ɐe����ł����B����ǂ��T�C�P�f���b�N�E�~���[�W�b�N�̃��[�������g�����ɂȂ���1969�N���Ƀ��b�N���̂����߁A�ǂ������N���V�b�N���y���悤�ɂȂ����B����ȗ��A���ꂱ��40�N�ȏ���N���V�b�N���y�\�t�g�̏N�W�Ƃł���B���������1976�N����18�N���̊ԃ��R�[�h��ЂŊC�O�Ճ\�t�g�Ɋ�������d�l�k�o�E�b�c�̐���E��`�E�ҏW��ƂɎ��g�B������1994�N�Ƀ��R�[�h��Ђ����߂Ă���16�N�ԁA�����́u���R�[�h�]�_�Ɓv�A���݂� �u���y�]�_�Ɓv �Ƃ����������Ŏ��M���������Ă���B
�Ȃ��ŏ��Ɂu���R�[�h�]�_�Ɓv�Ƃ����������ɂ������Ƃ����A�����̎��̓��R�[�h���W�ƁA���R�[�h��Ђ̕Ґ��E�ҏW�E��`�Ɩ��S���Ƃ��Ă̌o���͏\���ɂ����āA���R�[�h�̗ǂ������ɂ��Ă͂���������Ȃ�ɔ��f���邾���̃m�E�n�E�������Ă������炾�B����ɑ��ăR���T�[�g�̌���ɂ��Ă̒m���ɂ͌����Ă���̂ŁA�Œ�ł� 1,000�ȏ�̃R���T�[�g�ɒʂ��܂Łu���R�[�h�]�_�Ɓv�̂܂܂ł��悤�ƐS�Ɍ��߂Ă����B�R���T�[�g�ʂ��͔N�� 250��ȏ�̃y�[�X�ő����A�������� 4,000�̑��ɏ��B�܂��A�����ł��������̃R���T�[�g����Â���Ȃǂ��āA������̋ƊE�̎d�g�݂Ɋւ��Ă�������x�̂��Ƃ������Ȃ�ɗ����ł����B����䂦�ŋ߂ł́u���y�]�_�Ɓv�����̂���̂Ɉ�a�����o���Ȃ��Ȃ��ė��Ă���B
����ǂ����́u���y�]�_�Ɓv�Ƃ����E�Ƃɑ���t�@���̕��X�́A���ɃR���T�[�g���ł����Ί�����킹��悤�ȃw���B�[�E�R���T�[�g�E�S�[�A�[�̕��X�̖ڂ͌������B����͉��̂Ȃ̂��낤���H�@�ȒP�Ɍ����Ȃ����͉��y�ɑ��鈤��̉��x���������ł͂Ȃ����B��ʋ��{�̃r�W�l�X�Ƃ��Ẳ��y�]�_�Ƃ݂̍���ƁA�l�̎�Ƃ��Ẵt�@���݂̍���̈Ⴂ�������������x���������N�����̂��B�����āA�N���V�b�N���y�ƊE�̉��l�ς����l�����Ȃ������̂ЂƂ́u���y�]�_�Ɓv���u�l�̎�v�ł͂Ȃ��A�u��ʋ��{�̃r�W�l�X�v�Ɋ�Ĉׂ����悤�ɂȂ��Ă��܂������ƂɋN������̂ł͂Ȃ����B����Ɠ����ɁA�ƊE�S�̂Ɍ�����ҏW�Ɩ��̗����������X�����������Ă���v�����낤�B�ł͉��y�]�_�Ƃɂ͈�̉����K�v�Ȃ̂��H�@����͂����������_�������̌o���܂��ċL���Ă݂����B
�i�P�j�����̏��������̂ɐӔC������
���y�]�_�ƂɌ���Ȃ����A���y���C�^�[�ł���A�W���[�i���X�g�ł���A�`���V��v���O�����Ȃǂɐ��E�����������悤�Ȑl�������̃R���T�[�g�ɗ��Ă��Ȃ��Ƃ����P�[�X�ɂ����Α�������B���͊�{�I�ɂ����������Ƃ����͖����悤�ɂ��Ă���B�����I�Ɏ����ōs���Ȃ��悤�ȃR���T�[�g�𑼐l�ɑE�߂邱�Ƃ͂��Ȃ����A���E���͈����Ȃ��B���ӏ��ŊJ�Â̏ꍇ�ɂ͎�s���Œ����Ȃ��Ă����������K�����̂ǂ����Œ����悤�ɂ��Ă���B�u�Ȃ̗~��������̑��l�Ɏ{���Ȃ���v�A����͂����鉹�y�]�_�Ƃ̊�{�|���V�[�ł����ė~�����Ǝ��͊���Ă���B�܂��A����������������Ă���悤�ȕ]�_�ƁA�W���[�i���X�g�̏������Ƃ͐M�p����悤�ɂ��Ă���B���l�ɑE�߂��R���T�[�g�Ɏ���o�����邱�Ƃɂ���Ă��̐ӔC���ʂ����B�ʂɃR���T�[�g�����������ꍇ�ɒ��O�ɑ��ēy��������Ƃ����̂ł͂Ȃ��B���������ꍇ�ɂ͔��Ȃ��A�ǂ������ꍇ�ɂ͎����̊����Ɏ��M�������ċA������̂��B���������m�F��Ƃ̐ςݏd�˂����O�̐M���邽�߂̗B�ꖳ��̕��@�Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���H
�����܂ő��l�ɉ����t���悤�Ƃ͎v��Ȃ����A�l�I�ɂ͋Ȗډ�����������������̂ł����Ă����̃R���T�[�g�ɂ͍s���悤�ɂ��Ă���B����͎��������e�����������ɓ��ɕ`�������̂ƁA���ۂɃR���T�[�g���ŋ��������y�ɂ͂����Ɛ������������������m�F���邽�߂��B����Ǝ��͎������{���ɍD���ł��Ȃ��悤�ȋȖڂ̉���͏����Ȃ����Ƃɂ��Ă���̂ŁA���ʂƂ��ċȖڂɊւ��Ă������ɂƂ��āu�����v�̃R���T�[�g�ɂȂ邩�炾�B
������ɂ���ǎ҂ɑ���Œ���̐ӔC�Ƃ��Đ��E�����������悤�ȃR���T�[�g�ɂ͕K���o�����āA���O�Ƃ��Ĉꏏ�Ɏ��Ԃ��߂����Ƃ������[���͎�肽�����̂��B
�i�Q�j����ҁE���O�Ƃ��āA�����̍D��S�E�~���ɒ����ɍs������
���y���D�ƁE����҂Ƃ��Ă̎����ɗ����Ԃ鎞�A�������ƂĂ��D���ȃA�[�e�B�X�g���i�ɂ��Ă���ɑ�������������������Ȃ����͂ɐڂ��邱�ƂقǕ������������Ƃ͂Ȃ��B���t��]�ł��A�b�c�̏Љ�E��]�ł��������B�����v���̂��������ɂƂ��ċ����̖����A�[�e�B�X�g�A�����̗N���Ȃ���i�ɂ��ď����Ƃ��̂悤�Ȍ��ʂɂȂ邱�Ƃ������B�����Ď�����18�N���̃��R�[�h��Ђɂ�����ҏW�҂Ƃ��Ă̌o�����猾���A���������P�[�X�̐ӔC�̔����͎��M�ҁA�����͕ҏW�҂ɂ���B
���͊�{�I�Ɏ������ǂ��Ǝv�����R���T�[�g��b�c�Ɋւ��Ă������e�������Ȃ��悤�ɐS�����Ă���B�s���Ă܂�Ȃ������R���T�[�g�A�����Ėʔ����Ȃ������b�c�ɂ��ď����Ă�����͎��ʂ̖��ʂ̂悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ����炾�B����ɂ��̘A�ڂ̒��ł����łɋL�������l�Ԃ̚n�D�͏\�l�\�F�B�����͂����łȂ��Ă����̃A�[�e�B�X�g��Ȗڂɂ��čD���Ȑl�͕K������͂��ŁA���������l�����������̂��B���͌��e���˗����ꂽ���ɁA���ĕҏW�҂̒[����ł����������̗ǐS�Ƃ��āu�ނ��낱�̃A�[�e�B�X�g�A�ȖڂȂ灛������̕����������ǂ����e��������̂ł͂Ȃ��ł����H�v�Ɠ����Ă��܂����Ƃ������B���������Ή����u�������v�A�u���ӋC���v�ȂǂƕҏW�҂̕��X����ᔻ����邱�Ƃ�����̂ɂ͋����Ă��܂��B�������A�܂��͂��̃R���T�[�g��b�c�Ɋւ��錴�e�ɐڂ���ǎ҂̂��Ƃ���ɍl����̂��ł͂Ȃ����낤���H
�|�낵���̂́A���������l��F�߂����̂ɂ��Ă��������Ȃ��Ƃ����ԓx�ʼn��y�]�_�������s���Ă����ƁA��ʓI�ȓǎ҂́u���̐l�͉��ł��ق߂�l���v�Ƃ������Ɍ�����Ă��܂����Ƃ��B���Ԃ��A���ꂭ�炢�R���T�[�g��b�c�ɂ��Đ��߂��C�����ŏ����Ă��錴�e�A����Ɍ��������͂����Ă���Ƃ������ƂȂ̂��낤�B
�i�R�j�ƊE�̍L�����ł���O�Ɂu���[�U�[�Ƃ��ĉ��y�]�_�Ɓv�ł��邱��
����̓N���V�b�N���y�����Ɍ������b�ł͂Ȃ���������Ȃ����c�傫�Ȑ�`�\�Z���t���悤�ȃA�[�e�B�X�g��v���W�F�N�g�ɊS����������A�ւ�荇���ɂȂ���������葽���̎����ɂȂ��邵�A�I�o�̑傫�ȃ��f�B�A�ɓo�ꂷ��̂ʼn��y�]�_�ƂƂ��ăX�e�[�^�X���オ��B���̂��߉��y�]�_�Ƃ͎����̖{���̎�E�n�D�͑[���āA�ǂ����Ă��}�X�R�~�Ō��ɘb��ɂȂ��Ă���悤�ȉ��t�ƁA��ȉƁA��i�𒆐S�ɒ������蒲�ׂ��肷��Ƃ����X���������Ȃ�B�ƊE�Ɋ֘A�������f�B�A������A�ǂ�Ȗ₢���������Ă�����Ȃ�ɖ���ȓ������Ԃ��Ă���悤�Ȗ��\�]�_�Ƃ��]�܂�Ă���悤���B�������ҏW���鑤���炷��Ƃ��������l�̕����g�����肪�ǂ��Ɍ��܂��Ă���B
����A�ˑR�A����}�̂̕�����u���N�̃T�C�g�E�E�L�l���E�t�F�X�e�B�o���ŁA���V�����̑���Łs�T�����t���w���������F���o�[�ɂ��Ăǂ��v���܂����H�v�Ƃ�����|�̎���̓d�b���������Ă����B���́u�\�������܂����̓T�C�g�E�E�L�l���E�I�[�P�X�g���ɂ͋���������܂���v�Ɠ������B���������ǂ����Ď��ɂ���ȓd�b���˂����Ă���̂��H�@���̓����̌����i�Ⴆ�� �u�R���T�[�g�Ȃсv�ɖ����A�ڂ��Ă���u���̃R���T�[�g���������I�v�j�������ł��m���Ă���Ȃ�A������y�E�����y�𒆐S�ɒ����A�I�[�P�X�g���͂����ς狦�t�Ȃ����߂ɍs���悤�Ȑl�Ԃł��邱�Ƃ��e�Ղɔ��肻���Ȃ��̂����c �������S�̖������ƂɎ��Ԃ��₵�Ă���ɂ͎��ɂ͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ玄�������̃N���V�b�N���y�ɂ�������T�����邽�߂Ɉꐶ�͗]��ɂ��Z���A�����˂Ȃ�Ȃ��R���T�[�g��\�t�g�͗]��ɂ���������Ǝv���Ă��邩�炾�B����Ɏ��͈�ʋ��{�Ƃ��ẴN���V�b�N���y�ƊE�̏펯�≿�l�ς����߂����Ƃ͑S���v���Ă��Ȃ��B
�l�X�ȕ]�_�Ƃɂ���đ��l�Ȍ����E���������A��������������R���Z���T�X���`������Ă����K�v������B10�l��10�l�ƊE�i���y�w�҂̋ƊE���܂߁j�̉��l�ς��ق��Ĕ�������̂ł���Ε]�_�Ƃ͒N������Ă��������ƂɂȂ邵�A���O�̑��l�ȉ��l�ςɃN���V�b�N���y�ƊE�Ƃ��ď_��ɑΉ��ł��Ȃ��Ȃ�B�ƊE�̉��l�ς��ق���̂ł͂Ȃ��A��ɓƗ������l�̉��l�ρE���ӎ��������ĉ��y����邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂��B
�i�S�j��ɃR�X�g�̈ӎ�������
���ԏ펯�Ƃ��āA���̂̒l�i�Ƃ����̂͂��̃R���T�[�g���邢��CD�̉��l�ƃ����N���Ă���ׂ��ł͂Ȃ����H�@�U���~�̃`�P�b�g�����R���T�[�g�̊����́A�T��~�̃R���T�[�g�̊��������y���ɑ傫�Ȃ��̂łȂ���Β��낪����Ȃ��ƍl����̂����R���B����ǂ����̂悤�ɉ��i�Ƃ�������b��ɂ���͕̂i�̂Ȃ����ƁA���������N���V�b�N���y�̉��l��`������s�ׂł��邩�̂悤�Ɍ����ƊE�l�����Ȃ��Ȃ��B�܂����y�]�_�Ƃ����҂ł���R���T�[�g�ɍs���Ă���ƁA�`�P�b�g�̊z�ʉ��i��������ł��邩��Y��Ă��܂��A��ÂȔ�]�����Ă��܂����Ƃ���������B���Ҏ҂̓^�_�ŖႦ��v���O���������O�͂������Ĕ����Ă��邱�Ƃ�F�����ēǂނׂ����낤�B����҂ł��邱�ƁA�t�@���̗���ɗ����ĉ��l�]������C�����͈ꐶ�Y�ꂽ���Ȃ����̂��B�K���s�K�����̏ꍇ�ɂ͍s�������R���T�[�g�ł����҂�����̂͂R�����x�Ȃ̂ŁA����҂Ƃ��Ă̎�����Y��邱�Ƃ��o���Ȃ���Ԃɂ���B
���̈���ŁA���ꗿ���������Ƃɂ���Ĕ�������l�X�Ȗ��_�ɂ��Ă��A�������������ȃR���T�[�g�ɏo�����l���Ă݂�ׂ����낤�B�����ȃR���T�[�g�ł́A�����Ƃ������R�����ŕʒi�����������̂ɗ������O������ɕs�K�v�ȕ����𗧂Ă�g���u�������Ȃ��Ȃ��B�܂��v���O���������܂�ɂ��e���ł�������A�{������ׂ��������ȖڂɊւ������Ȃǂ̃C���t�H���[�V���������������肷��B����A�b�c���������ɂȂ����ꍇ�ɂ͕ҏW�Ɩ����m������肷�邱�Ƃ����X����B�������������܂��āA�������Ƃ͗ǂ����Ƃ��ƒP���ɍl����̂ł͂Ȃ��A���ꂪ�{���R�X�g�������Đ�������Ă���ꍇ�Ɋr�ׂė��_���Ȃ������l�@����K�v������B
�i�T�j���{�̃N���V�b�N���y�E�̌���ɂ��ĔF����[�߁A���͂���
�O���̉��y�ƁA�Ƃ�킯�z�ʉ��i�̍����I�y����I�[�P�X�g���̃R���T�[�g�ɒʂ����Ƃ����̃X�e�[�^�X���A�ƍl���Ă���N���V�b�N���y�t�@�������Ȃ��Ȃ��B�����ċƊE�W�҂≹�y�]�_�Ƃ̒��ɂ������������̂ɐ���������o�����Ƃ��A�����̃X�e�[�^�X�Ɗ��Ⴂ���Ă���悤�Ȑl�������Ό�������B���͎v���A���{�̃N���V�b�N���y�ƊE�W�ҁA���y�]�_�Ƃ͂����Ƃ����Ɠ��{�l�̃A�[�e�B�X�g�ɂ�������Ē����K�v��������̂ł͂Ȃ����ƁB���͓��Ɏv�z�I�ɉE���ł͂Ȃ��B�ނ���o�ϓI�Ȋϓ_���炻����l���Ă���B���Ȃ킿�����N�I���e�B�̉��y�Ƃł���Γ��{�ɍݏZ���Ă���҂̕����������ɗD�ꂽ���y������Œ��Ă����\�����������炾�B�����Ȃ�Ή��y�ɂ�����u�n�Y�n���v�̍l�����ł���B����ɊO���̃A�[�e�B�X�g�����Ɋւ��Ă͂��ꂼ��̍��̉��y�]�_�Ƃ��ӔC�������ĕ]����������B��X���{�l�͂܂����{�l�̉��t�Ƃɒ��ڂ��ׂ��ł͂Ȃ����H�@�u�n���K�͂ōl���A�n��I�ɍs������v�Ƃ����G�R���W�[�̃X���[�K���͉��y�]�_�����Ɋւ��Ă������ł���B
�ԈႢ�Ȃ������邱�Ƃ͏��Ȃ��Ƃ����J�j�b�N�̕����Ɋւ��ē��{�l�A�[�e�B�X�g��20�N�O�Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǂɍ����Ȃ��ė��Ă���B�C�O�̐l�X�Ɍނ��Ă���Ă����邾���̎��͎͂����Ă��鉹�y�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B������������ł���ɂ�������炸�C�O�Ɋr�ׂē��{�̃A�[�e�B�X�g�����Ƃ����̂ł���A����͉��y�ƌX�̖��Ƃ��������䂪���̃N���V�b�N���y�ƊE�̃V�X�e���A���邢�͉��y����݂̍���Ȃǂɖ�肪����ƍl����ׂ����낤�B
�i�U�j�������E�߂��A�[�e�B�X�g��������
�����̏��������ƂɐӔC�����͓̂��R�����A���݊������̃A�[�e�B�X�g�E�c�̂Ȃǂɂ��ċL�������̂Ɋւ��Ă͌��e�̏ܖ�����������Ƃ������Ƃ��Y��Ă͂����Ȃ��B���y�]�_�Ƃ͓����A�[�e�B�X�g�������邱�Ƃɂ���Ă��̌����c�����čs���̂����A���N�A�P�N�Ȃ�܂������A�Q�N�A�R�N�Ǝ����o�Ƃ��̃A�[�e�B�X�g�̉��t���傫���ω����邱�Ƃ����蓾��B�ǂ������ɕω����Ă����̂͊��}�����A���������Ė��͂������Ă����v�f���S�������Ă��܂��Ƃ������Ƃ�����B���邢�͂��Ă��̒c�̂̎�ÃR���T�[�g�͑f���炵���������A�ŋ߂ł͂�������R���T�[�g���e��ҏW�Ɩ��̎��������A�����g���u�����������Ă���Ƃ����悤�ȃP�[�X������B���������ėl�X�ȃA�[�e�B�X�g��c�̂̊����͌p���I�ɒ����m�F����K�v������B�܂��ǎ҂̓A�[�e�B�X�g�̐�`���ɔ�]�����p����Ă���ꍇ�ɂ͂��ꂪ���̎��_�ŏ����ꂽ���̂Ȃ̂��A���Ӑ[���`�F�b�N����K�v������B�Ɠ����ɁA���y�]�_�Ƃ̉��y�ɑ���p�����Q�N���o�ĂΕς���Ă��邱�Ƃ�����̂ŁA�������M������l���̏����Ă��邱�Ƃ�M������ɑ��邩�ǂ����܂ɐG��`�F�b�N���ׂ����낤�B
���y�]�_�Ƃ������̍D���ȃA�[�e�B�X�g�ɂ�������Ē������Ƃ̕K�R���A����͌���̂悤�ȁu�V�l�A�[�e�B�X�g�̎g���̂Ă̎���v�ɂ����Ă܂��܂��d�v�ł͂Ȃ����Ǝ��͍l����B�Ƃ������{�ł̓R���N�[�����ܗ���b�萫���d�v������A20��O��̉��t�Ƃ��₽��Ƃ��Ă͂₳�ꑛ�����B�������Ȃ���S�A�T�N���o�Ƃ��̌�ɓo�ꂷ��V���Ȑl�X�̉A�ɒǂ�����A���̃A�[�e�B�X�g�ɂ��Ă̌��y���}���Ɍ����Ă����B���y�]�_�Ƃ͂��������ƊE�̐����Ƃ͊W�����ɁA�������ǂ��Ǝv�����A�[�e�B�X�g���p���I�ɒ��ڂ������邱�Ƃ��d�v�ł͂Ȃ����Ǝ��͍l����B�V�l�����S����c������͕̂s�\�����A���ꂼ��̕]�_�Ƃ����̉��t�Ɏ����Ȃ�̈��������Ă�悤�ȉ��y�Ƃ�I�����Ēǂ��čs���悤�ɂ���A���Ȃ�̐l�͂���ŋ~����͂����B�����Ȃ�Ή��t�Ƃ̎d������Ƃł���B
�i�V�j���̃R���T�[�g��\�t�g���N���V�b�N���y�̉��t�j�̒��łǂ̂悤�ȈӖ������̂���܂ɐG��čl�@����
�R���T�[�g���b�c���A�[�e�B�X�g��Ȗڂƒ��O�Ƃ̏o��̏�ł���B���y�]�_�Ƃ͂����i�̎�e�̗��j�ɊS�������A���̒��œ��Y�̃R���T�[�g��b�c�ɂ����鉉�t���ǂ̂悤�Ȉʒu�t���������Ă���̂����l����K�v������B���̂��߂ɂ͂����i����e����^������ė������j��܂ɂӂꌤ�����Ȃ��Ă͂����Ȃ��B�K���Ȃ��ƂɊC�O�ł�20���I������A19���I���ɘ^���@�킪�a�����Ĉȍ~�̋M�d�Ș^���̕������ڊo���������Ői��ł���B�Ƃɂ����������S�̂����i�E�W�������ɂ��Ă͍ł��Â��������炱�����������Ղ�O��I�Ƀ��T�[�`���Ă������Ƃ�����B�ЂƂC���������̂́A�l���畷������A�{��ǂ肵�ē����m���͉��y�]�_�ƂɂƂ��Ă͒P�Ȃ�`���ɉ߂����A���ۂɉ��t�≹�����ē����m�����{���̒m���Ȃ̂ł���B����Ȃ��Ƃ͓�����O�����ď����K�v���Ȃ����ƂȂ̂����A�����ď����˂Ȃ�Ȃ�����������̂��B
�������ĕ]�_�Ƃɖ{���K�v�Ǝv����p������ׂčs���ƁA�����玞�Ԃ������Ă�����Ȃ��d�����Ƃ������Ƃ��e�Ղɗ�������邾�낤�B����͉����ʂɐ�Ƃ̎d���������Ă��̕Ў�Ԃɂł���悤�Ȏd���ł͂Ȃ��B����ǂ���Ƃʼn��y�]�_�ƂƂ����d���Ɍg������ꍇ�ł��A����Ɍ����������̎�����������\���͂���߂ĒႢ�B�u���Ȃ��͂���Ȃ��Ƃ��̂����ɏ����܂����A�N����������̂ł����H�v ���������Ď������ӂ��鉹�y�]�_�Ƃ����邩������Ȃ��B����ǂ����͊����ē��������B����������邱�Ƃ̏o����l���܂���������Ȃ����A�ƁB
���l�̌o�����猾���A���y���ɓ������čł�������Ƃ́u����ς�r���āA���S�ɒ����v�Ƃ������ƁB���ɓ���̂́u�����̊��z�𐳒��Ɍ����v���ƁB�R�Ԗڂɓ���̂́u����҂Ƃ��Ď����̐S�ɐ����ɃR���T�[�g��b�c��I������v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ����B���R�̂��ƂȂ���]�_�Ƃ̎d���͉��ɑ��Ă����ՂɃR�����g���ǂ�Ȃ��Ƃł������邱�Ƃł͂Ȃ��B�ꍇ�ɂ���Ắu�����������v�A�u����Ȃ��v�A�u�m��Ȃ��v�ƃn�b�L���\�����邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł���B
���^���̑��݁`�N���V�b�N���y�������I�ɕ����閵��
���̘A�ڂ̑�S��ڂ������I���Ă���R���T�[�g�ɒʂ��Ă��邤���ɁA�ӂƂR�N�قǑO�ɕp�ɂɎ��ɂ����ЂƂ̌��t���܂ɐG�ꓪ�ɕ�����ŗ���悤�ɂȂ����B����̓A�����J�̋��Z�@�ւɊւ��Ĕ�����ꂽ�u�傫�����Ĕj�]�������Ȃ��v�Ƃ������t�B�Ђ���Ƃ��ăN���V�b�N���y�ƊE���u�j�]�������ς��v�Ƃ����h�q�{�\���ƊE�S�̂Ƃ��ď�ɓ����悤�ɏo���Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����^�₪�����������ė����̂��B
���������N���V�b�N���y�Ƃ������̂́A�ȑO�ɂ��L�����悤��19���I�h�C�c�ꌗ�𒆐S�ɁA�y����̔����A���t�҂����炵�A�R���T�[�g�����s����Ƃ����R�{���Ő��������Y�Ƃł������B�����19���I�̊Ԃɏ����ɐ����𑱂��čs�����B�����ĕ����푈�Ńv���C�Z���Ƀt�����X��������ƁA�N���V�b�N���y�̐U���ɔs��̗J���ڂ𖡂�����t�����X���͂��߁A���ꂼ��̍��̕x�T�w�A�M���A���A���{�Ȃǂ��ϋɓI�Ɋ֗^����悤�ɂȂ萬���ɔ��Ԃ����������B
�������قǂȂ��傫�Ȗ�肪�N�������B19���I���Ƀ��R�[�h�i�^���j���o�����A20���I�����ɂ̓s�A�m�E���[���̂悤�Ȏ������t�y��܂ł��o�ꂵ�����Ƃł���B��q�̒ʂ�A�N���V�b�N���y�̑O��ł��鉹�y���Č����邽�߂̂R�_�Z�b�g�\�\�y���̔��A���t����A�R���T�[�g���ȗ����āA���y���Ƃɋ��Ȃ���ɂ��Ċy���ނ��Ƃ̏o����V�X�e���������Ɋm�����Ă��܂����̂��B
���������̘X�ǘ^����A�R�[�X�e�B�b�N�^����SP�Ղ͉����n�ゾ�������߂ɑ傫�ȋ��ЂƂ͂Ȃ蓾�Ȃ�������������Ȃ����E�E�E�������d�C�^����SP�ՁA���m����LP�A�X�e���ILP�A�f�W�^���^��LP�A�����Ăb�c�Ƃ������R�[�h���B�̗���̒��ŁA���Ђ͒m�炸�m�炸�̂����ɑ傫���Ȃ��Ă��܂����̂��B
�S�Ă̐l�ɂƂ��Ă����ł͂Ȃ����낤���A���Ȃ��Ƃ����̂悤�Ɏ����Ŋy������t������̂����肵�Ȃ��l�ԂɂƂ��ẮA���̃��R�[�h�̓o��ɂ���ĉ��y���y���ގ��R�����ٓI�ɍL���������Ƃ̈Ӗ��͑傫���B
�������ă��R�[�h�̓o��̓N���V�b�N���y�̎Y�ƂƂ��Ắu�݂���v�ɖ������������̂��B�|�낵���Ǝv���̂͑����̃N���V�b�N���y�W�҂����̃��R�[�h�̑��݂ɉ��̖����������Ă��Ȃ��_�B�����̃��R�[�h�𐧍삷��ɓ������Ă���͎����̃R���T�[�g�����̂��߂̃v�����[�V�����E�c�[���Ƃ��čl���Ă���l�����Ȃ��Ȃ��B
�u���₠�A�����͌����Ă��R���T�[�g�ł̎����Ƃk�o��b�c�ł̊ӏ܂Ƃł͉��̃��A�������S���Ⴂ�܂���E�E�E�v�A�Ƃ������Ɍ���������N���V�b�N���y�ƊE�W�҂͑����B�������Ȃ��玄�͂��̌����ɂ͈٘_������B
�����鉹�y�ɂ����Ē�����ɉ����������炷�̂͊�{�I�ɂ͂��̉��̃��A�����ł���B�܂��Ă�N���V�b�N���y�̂悤�ɏ��@���k�������敿�̉��y�ł́A�ו������Ăɒ������邱�Ƃ���i����щ��t�𗝉������ł̏d�v�ȃ|�C���g�ł���B����䂦�s�A�m�Ƒt��̋ȁA���K�͂Ȏ����y�Ƃ����������ȕҐ��̂��̂͏����ȉ��ɂ����Ċԋ߂Œ����̂��ł��S�n�悢�B
�����������̂��u�i�N���V�b�N�j���y��p�z�[���v�ƌĂ��c���ߑ��̃R���T�[�g���̕��䂩�牓���ȂŒ������炢�Ȃ�A�Ƃłb�c������DVD�����������قǃ��A���ɉ��y���ӏ܂ł���̂��B�����������ł͕��䂩��̎����͋q�Ȃɓ`���ԂɁA�����˂����c��������������₵�������ɂȂ��Ă��܂��B���傤�Lj߂̌����V�n����z������Ηǂ����낤�B
���������u���y��p�z�[���v�Œ����Ȃ�A����Ƃ̋������߂��őO��Ƃ��̋ߕӂ��o���R�j�[�̕���ɋ߂��Ȃ��x�X�g���Ǝ��͍l���Ă���B���ۂɃw���B�[�E�R���T�[�g�E�S�[�A�[�̕��قǍőO��ɂ�������ă`�P�b�g���������ɂȂ��Ă���X���������͓̂��R�����A��������������{���j�Ń`�P�b�g���w�����Ă���B
�������ɃI�[�P�X�g���̏ꍇ�ɂ͎c���̑����u���y��p�z�[���v�͕K�v��������Ȃ��B�I�[�P�X�g�����ЂƂ̊y��Ɍ����Ă�A���̉����݂��ɗZ�����邽�߂̎c���͕K�v�ł���A�z�[�������̖������ʂ����B�z�[�����̂��y��̈ꕔ�ɂȂ�̂��B����̓I���K���̏ꍇ�����l���B�Ɠ����ɃI�[�P�X�g���Ƃ͓d�C�����Ƃ����Z�p��������������ɁA�傫�ȉ��ő����̒��O�Ɍ����悭���y�����V�X�e���Ƃ��Ĕ��W�����Ƃ��l������B���̂��߂Ɂu�c���v�Ƃ����d�C�Ɉ˂�Ȃ����̑����ɂ���������Ƃ����������o���邾�낤�B
�ŋߎv���̂����N���V�b�N���y�ƊE�̐l�X����уt�@�������Ƃ���I�[�P�X�g���ɂ�����闝�R�́A���y��p�z�[���ɂ����Ď����Œ������Ƃ̃����b�g���ł�����̂̓I�[�P�X�g���ł��邩��ł͂Ȃ����H�@���̂��Ǝ��̂͑S���\��Ȃ��̂����A���̕��Y���Ƃ��� �u�c���M�v ���N���V�b�N���y�ƊE�ɍ���������͖̂��ł͂Ȃ����낤���H�@
�܂�z�[���̗p�r�A�傫���ɊW�Ȃ��c���̑�����ꂪ�ǂ��R���T�[�g�z�[�����Ƃ����M�ł���B���ꂼ��̉��y�W�������ɂ͂��ꂼ��ɓK�����c��������̂��A�Ƃ���������O�̂��Ƃ����āA�c�����������łȂ���N���V�b�N���y�͂����Ȃ��Ƃ����ӖړI�ȐM���B
�����ЂƂ����̐l�X�������ł��Ă��Ȃ��̂͂�����u���y��p�z�[���v�ɂ����ẮA�����ł̉��̒��������͋q�Ȃł̂��̂Ƃ͑傫���قȂ�Ƃ������ƁB�Ⴆ�s�A�m�̏ꍇ�Ȃnj��ʂĂ��߂��A���������z�[���ł͉������牓���Ȃ�Ȃ�قǎc���̈߂��������Ȃ�A���̃��A�����������čs���B����䂦�ꗬ�̃s�A�j�X�g�����͂�����������Ƌq�ȂƂ̉��̈Ⴂ���\���Ɍv�Z���ăz�[���c���ɍ��킹�����t�����邵�A���̂��Ƃ���ɂ��Ȃ��B����ǂ����ꂪ�o���Ȃ��l����������B�s�A�m�Ƃ����y��̐��\�𑶕��ɔ����ł�����Ƃ��ẮA�ߏ�Ȏc���ɂ���ĉ��t�𐧌�����Ȃ��R���T�[�g�z�[�����]�܂����̂ł͂Ȃ����H�@�l�I�ɂ͎�s���̒��K�̓z�[���ł͓���������ُ��z�[���A���邢�͒Óc�z�[�����s�A�m�E���T�C�^���ɂ̓x�X�g�Ǝv���Ă���B
�����������玄�̓N���V�b�N���y�ƊE�Ɍ����ȁu�����M�v�A�}�C�N���t�H���i�d�C�����Ƃ����v���Z�X�j��ʂ��Ɖ��y�̔����Ȗ������Ȃ���Ƃ����咣�ɂ͂�����������������̂ł͂Ȃ����A�ƍl����B���̑z���͕p�ɂɃR���T�[�g�ʂ�������悤�ɂȂ��Ă����w�����Ȃ����B�傫�ȏW�c�̉����K�͂̑傫�ȉ��y��p�z�[���Œ����I�[�P�X�g����ʂƂ���A�������ŗǂ̏����Œ������Ƃ̏o��������������邱�Ƃ͍����ł͍���ɂȂ����B�ꗬ�̉��t�Ƃ̎������ԋ߂Œ������Ƃ�������Ԃ��ґ�Ȃ̂����A������������邽�߂ɏ����ȃz�[�����g���ɂ̓A�[�e�B�X�g�̃M�������������߂��Ă���B�c���������Ă������ȉ������������Ȃ��ȂŒ������炢�Ȃ�Ƃłb�c���������]���܂��Ȃ̂��B
�������Ƃ̏o���郌�p�[�g���[�̖L�x���A�A�N�Z�X�\�ȉ��t�̖c�傳�Ƃ����_�ł����R�[�h�͗y���Ɏ��������D�ʂɗ����Ă���B������R���T�[�g�̂悤�ɓ������ԁE�ꏊ�ɒ��O���W�߂�K�v�������B�������ɂ��̕��A�̔�����\�t�g���ǂ����ɍɂ��Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ƃ�������������B������������l�b�g�̔��̋����A����ɂ̓_�E�����[�g�E�T�[�r�X�̎��I����ő��Ӊ�������̂ł͂Ȃ����B����������肪�N���A�[�����Έ�ʓI�ł͂Ȃ��ȂɊS�������O�𐢊E������W�߂�2,000�����鎖���\���B����̃R���T�[�g�œ������ԁE����2,000�l�W�߂Ē������邱�Ƃ��l����ƁA���ꂪ�ǂ�Ȃɑ�ςȂ��ƂȂ̂��͗e�Ղɑz���������낤�B�܂����y�\�t�g��19���I�����獡���Ɏ���܂ŊԒf�Ȃ��ǂ�ǂ�~�ς���ė��Ă���A���ꂩ������ꂪ���X�Ƒ����čs���B
�ܘ_�A���R�[�h�ɂ����_�͂���B�^�������̕ҏW��Ƃ��\�Ȃ��Ƃ��B����͈�ʂɂ̓e�[�v�^���ȍ~�̘^���̒����ƍl�����Ă���B�������Ȃ��炻��͏��n�̌����B�������ɂЂƂ̉��t����芮���Ȃ��̂Ƃ��Ďd�グ�邱�Ƃ��\�ɂ������ŁA���y�Ƃ̂���̂܂܂̎p��`����@�\�����̂��߂ɑj�Q����Ă��܂����Ƃ����邩�炾�B
�ȑO���R�[�h��Ђɋ߂Ă���������Ȃ��Ƃ��������B����M���^�C�v�̉��y�ƂɊւ��C�O�̐���S���҂Ƙb���Ă��� �u�ǂ����ă��C���^���ɂ��Ĕނ̉��t�̔��M��`���Ȃ��̂��v �Ɛu�˂��Ƃ���A�u����͈�x�����ɂ͂������A�J��Ԃ������ƖO���Ă���v �Ƃ̓����������B�������A��x�����ăC���p�N�g�̖������̂��ʂ����ď���҂͔������낤���H�@�����ČJ��Ԃ��������낤���H�@�����̔��M���`���Ȃ����ǂ������A�e���V�����̒Ⴓ�A�����͉��x�����x���ҏW���ꂽ���͂����炯�̂��̂�����邱�Ƃɑ傫�Ȍ���������̂ł͂Ȃ����B���͂���ȋ^������������Ă���B�ܘ_����̓v���f���[�X���鑤�̃|���V�[�̈Ⴂ�������T�ɂ͌����Ȃ����낤�B�ҏW���ɗ͏��Ȃ����ĉ��y�̎��R�ȗ�����ɂ��悤�Ƃ�������҂����邾�낤���A�^���ɍۂ��ĕҏW�ɂ������ł͕s�\�Ȃ��Ƃ���������Ƃ������m�ȖړI�ӎ������݂���ꍇ���������邾�낤�B
������ɂ��捡���ł͌o�ό������]��ɂ��D�悳��߂��Ă��āA�ȑO�̂悤�Ɏ��Ԃ������Ă�������Ƙ^�����Ď�ԉɂ����ėǂ����̂���낤�Ƃ����ӎ����ł���ꍇ�����Ȃ��Ȃ��悤�Ɏ��ɂ͎v���ĂȂ�Ȃ��B��������ԉɂ����邽�߂̌o��S����ɂ̓��R�[�h�i�b�c�j�͂��̉��i�����̕����̏㏸�Ɏ��c��������Ȃ�߂��Ă��܂����̂ł͂Ȃ����B��������������w�i�ɂ����Ă��i����͎��̏���Ȏv�����݂Ȃ̂�������Ȃ����E�E�E�j�A�ŋ߂ł͓��ɃI�[�P�X�g���̘^���ɂ����ă��C�����^�ɂ��b�c�����삳��邱�Ƃ������Ȃ��Ă���i���̏ꍇ�ł��Q�l�v���A�ꍇ�ɂ���Ă̓��n�[�T�����^�����Ă��ĕҏW��Ƃ͂���̂��낤���E�E�E�j�B������W�������ɂ����Ă��������X��������w�i�݁A����܂łɐ������̘^�����₳��Ă���悤�ȗL�����Ȃ̎s�̗p�b�c�̘^���ł́A�g���u���������Ă��\��Ȃ����烉�C���̈ꔭ�^��ɋ߂����̂��Ƃ�������������{�ɂȂ�����̂����E�E�E�Ǝ��͐S�����Ɋ���Ă���B
���|�ւ��̂Ȃ��^����Y�̕ۑ��̕K�v��
������T��̌��e�������I����Ă���40���قǂ��ē����{��k�Ђ����������B���̎��A���͐�����̎���ɋ����B�x�����H���߂��̈��H�X�ōς܂��ĉƂɋA��A�c�u�c���ς悤�ƃf�B�X�N����ꂽ�u�Ԃɗh��������n�߂��B�ŏ��̂����A�ア���h����������̂� �u����͉����n�k��������v�A10�b������Ύ��܂�v �Ɣ��R�Ǝv���Ă����B�������ǂ�ǂ�h�ꂪ�傫���Ȃ�B���������܂�C�z�������B�S�z�ɂȂ��Ďd�������ɍs���ƁA�{�I�̏�Ƀu�b�N�G���h�Ŏx�����ׂĂ������k�o�����X�Ɨ����n�߂Ă����B�ׂ̕����ł̓X���C�h���{�I�̏�Ƀ|���v���r�������̃L�����[�{�b�N�X�ɓ���ĕۑ����Ă����R���T�[�g�E�v���O�����������Ɨ����A��j���Ă��đ��̓��ݏ��������ԁB�|���Ȃ��ċ��Ԃɖ߂�A�h�ꂪ���܂������_�Ńe���r���m�g�j�j���[�X�ɐ�ւ����B
���ꂩ���͓����ŁA����ɂ��ē����{��k�Ђ�̌����ꂽ�����̕��X�Ɠ��l�ɗ]�k�ɋ����Ȃ���A�Ôg�̖҈Ђ�`����������ׂ��f��������������R�ƌ��߂Ă����B����Ȃ��Ƃ��{���ɋN�����Ă��܂��Ƃ́c���߂ē����{��k�Ђŋ]���ɂȂ������X�̂����������F�肷��ƂƂ��ɁA���N�ȏ�o���Ă��x�X�Ƃ��Đi�܂Ȃ���������Ў҂̕��X�̈ӌ����\���Ɏ������`�ŃX�s�[�h�A�b�v���čs�����Ƃ��F�炸�ɂ͂����Ȃ��B
��k�Ђ̂��̓��̂����Ɏ��̓L�����[�{�b�N�X�������āA�قƂ�ǐ����������Ƀv���O�����ނ����[���A�u�b�N�G���h�Ŏ~�߂Ă��������̂k�o���R�[�h���A���x�͊ȒP�ɂ͓����Ȃ��悤�ɂ��邽�ߔ��ɋl�߂Ď��d���d�����Č��̈ʒu�ɖ߂����B���ڂɎ��ł��Ȃ��Ɨ]�k�łǂ����Ȃ�̂ł́c����Ȃ��Ƃ��l���čs�������̂������B����ɂ��Ă��k�x�U����悤�Ȓn�k�������玄�̉Ƃɕۊǂ��Ă��邩�Ȃ�̗ʂ̉��y�W�̃\�t�g��y���A���ЂȂǂ͂ǂ��Ȃ��Ă��܂��̂��낤���H�@���ł��s���Ŏd���Ȃ��B�䂪�Ƃł͖{���Ȃ�Q���ɂȂ��Ă���͂��̓��������ɏ��ɂƉ����Ă���B�X���C�h���{�I�ɖ{�Ƃb�c���т�����Ƌl�܂�ǂ̑S�Ă��́B���ꂾ���ł͑��肸�ɕ����̒����ɂ������{�I�������Ă���B���Ԃɂ��A�N���[�[�b�g�̒��ɂ��y���A������f���̃\�t�g�A���y�W�̏��Ђ������Ă���L�l���B�\���Ȑk�Б���u����ɂ͗]��ɂ��ۗL���Ă��鎑���ނ���������̂��B
����Ȃɑ����̂��̎����Ă��Ĉ�̂ǂ�����̂ł����A�K�v�Ȃ��̂͗l�X�Ȑ}���قȂǂœ���������̂ł͂Ȃ��ł����H�@�Ƌ^��Ɏv���l�����邩������Ȃ��B�����������̑����͎����ɂƂ��Ċ|�ւ��̂Ȃ������Ȃ̂��B�������ɉ��y��w�Ȃǂ̐}���ق��͂��ߗl�X�Ȏ{�݂ɉ��y�W�̐}����\�t�g����������������Ă���B����ǂ������������͕̂s���葽���̐l�X�ɂƂ��ďd�v�Ǝ{�ݑ��Ŕ��f����x�[�V�b�N�Ȃ��́A�����I�ȕ]�����m�肵�Ă���悤�ȍ�ȉƁA��i�A���t�ƂɊւ�����̂��唼�ł���B�����玄�͊y���⏑�ЂɊւ��Ă͎��������ɋ����S�������Ă��錮�Չ��y�E�����y�𒆐S�ɁA��ʂɂ͒m���Ă��Ȃ���i�𒆐S�ɏN�W���Ă���B���͂ǂ��̐}���قɂł����肻���ȗL���ȋȂɊւ��Ă͎d���ŕK�v�ȍŏ����ɂ��A�ȃX�y�[�X�ɂ���w�߂Ă���B�Ƃɂ�����ʂɒm��ꂴ����́A�S�̒Ⴂ���̂ɂ��Ă͌l�I�ɏN�W���邵����y�ɃA�N�Z�X����L���ȕ��@�������̂��������B
���̃R���N�V�����Ŏ������d�v�ƍl���Ă�����̂̂ЂƂ͂�͂��ʓI�ɒm���Ă��Ȃ���ȉƁE��i�̊y���Ƃ����Ɋ֘A�������ЁB�Ⴆ�Ύ��̓X�y�C���W�̊y���⏑�Ђ��T���S�T�i�X�y�C���j�̏��X���甃���Ă��邪�A�����������̂��ǂ�ʁA�䂪���ɂ͗A������}���قȂǂɏ�������Ă���̂����������Ȃ��B���炭�قƂ�ǖ�������Ă���̂ł͂Ȃ����낤���H
�������ɍŋ߂ł͒��쌠��̊y����d�q�����A���R�Ƀ_�E�����[�h�ł���悤�ɂȂ��Ă���z�[���y�[�W������B���͍ŋ߂��̑��݂ɋC�t�����̂�������͂ƂĂ��֗����B��ʂ̐l���Â��y���������i�o�c�e���j���ē��e���Ă���P�[�X�������̂����A���[���b�p�̐}���َ��̂��Â�������d�q�����Č��J���Ă�����̂�������B�܂茻�n�ɍs���Ȃ��Ă�����ɋ��Ȃ���ɂ��ď����̎�e���Ȃǂ����邱�Ƃ��ł���̂��B�������ɂ������������Ă���18���I�̍�ȉƂł̓h�C�c�̍�ȉƃN���X�g�t�E�O���E�v�i�[��A�|���g�K���̍�ȉƃJ�����X�E�Z�C�V���X�̎�e���Ȃǂڌ��邱�Ƃ��o���đ�Ϗd�Ă���B����ǂ����E�e�n�̂�����}���ق�����������Ƃ�ϋɓI�ɐi�߂Ă���킯�ł͂Ȃ��B�܂�����͂����܂ł����쌠��̊y���Ɋւ��Ă݂̂ł���B�Ȃ�����i�Ƃ��Ă̒��쌠�͐�Ă��Ă��V���ɍZ�����ꂽ�łŏo�ł���Ă�����̂��A�������������T�C�g��ʂ��ă_�E�����[�h�͓��R�̂��ƂȂ���o���Ȃ��B�L���̃T�[�r�X�܂Ŋ��p�����Ƃ��Ă��C���^�[�l�b�g����̃_�E�����[�h�ł͓���ł��Ȃ����̂͑����B�f���}�[�N�̃_���E�t�H�O�Ƃ������Êy���X����N�ɐ����Ă��钆�Êy���̃��X�g������� �u���A����Ȃ��̂��������̂��I�v �Ƃ�����i���ڂ��Ă��āA���炪�y�����N�W����K�R�������߂Ď������Ă��܂��B�܂��܂��d�q�����ꂽ�y���͏\���Ƃ͂����Ȃ��̂��B
����������ʓI�ł͂Ȃ���i�̉����i�b�c�A�k�o�A�c�u�c�j�Ɋւ��Ă͂ǂ����H�@�Ⴆ�b�c�ɂ���ă|�[�����h�̉��y�̗��j�ɂ��Ēm�낤�Ǝv������A�N�g�E�v���A���u����c�t�w�A�X�y�C���̉��y�̗��j�ɂ��Ēm����[�߂悤�Ƃ���Ȃ�X�y�C�����y�w��A���E�}�E�f�E�M�h���͂��߂Ƃ���}�C�i�[�E���[�x���̉������N�W���čs���Ȃ��Ə\���Ȃ��̂��������Ȃ��B�����ɂ͐��E�ŗB��^������Ă���y�ȂȂǂ����Ȃ��Ȃ����炾�B�����������̂͗A���Ǝ҂�ʂ��č����s��ɗ��ʂ͂��邾�낤����ǂ��A����炪�����̐}���قɌp���I�ɔ���������Ă���\���͂قƂ�ǖ������낤�B��������������r�I�ŋ߂ɏo�ł��ꂽ���̂Ɋւ��ẮA������x�̎��Ԃ����������Ƃ��Ă��������̉�ЂɃA�N�Z�X����Ή��炩�̕��@�œ��肷�邱�Ƃ͉\��������Ȃ��B�������A��������̃��R�[�h��Ђ����݂��Ă���̘b�ł���B
���͎��������̃R���N�V�����ōł���ƍl���Ă���̂́A�������܂�ڂ݂��Ȃ��ߋ��̗l�X�ȉ��t�Ƃ����̘^���̐��X�A���ɌÂ��k�o���R�[�h���B�����������̂̒��ɂ͈�x�����Ă��܂����������x�Ɠ���ł��Ȃ��\����������́A�ł���Ƃ��Ă��c��Ȏ�Ԍ����������Ă��܂��ł��낤���̂����Ȃ��炸����B�����I�ȕ]���͒Ⴂ��������Ȃ������t�j�̗����ǂ��Ă�����ł͌������Ȃ������Ƃ������̂��ƂĂ������B
�Ⴆ��1970�N�ォ��80�N��ɂ����ă|���g�K���� A VOZ DO DONO�i�g�l�u�j ���[�x�����甭������Ă��� �gLVSITANA MVSICA�h �Ƃ����V���[�Y��10���̂k�o�̓��l�T���X�`�o���b�N���̃|���g�K�����y�����̐�삯�ƂȂ�����Ϗd�v�ȃV���[�Y�ł���A�����t�������Ă����̂����c�O�Ȃ���b�c��������Ă��Ȃ��B�����������̂͋��炭�|���g�K�������̐}���قȂǂɂ͏�������Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���邪�A�ʂ����ē��{�����ł͂ǂ����낤���H
�����������A�E�A�C�e���łȂ��Ƃ����y��w�̐}���قȂǂł��k�o���R�[�h�̕ۑ��ɂ͍����Ă���Ƃ��낪���Ȃ��Ȃ��悤���B�b�c�Ɋr�ׂĊ��p�����p�x�����Ȃ����Ƃ��������������̒u���ꂽ���������Ă���B�}���ق��牓�����ꂽ�q�ɂɕʓr�ۑ����ꂽ��A�ꍇ�ɂ���Ă͔��p����Ă��܂����Ƃ�������悤���B��������Ƃ�͂薜����̏ꍇ�ɂ͔������̃��R�[�h��Ђ��Ō�̗��݂̍j�Ƃ������ƂɂȂ�B
����ǂ��������̃��R�[�h��Ђ������Ȃ��Ă��܂�����A���邢�͂ǂ����̉�Ђɋz����������Ă��܂�����ǂ��Ȃ�̂��H�@�����̏ꍇ�������������͎��Y�Ƃ��Ĕ��p���ꂽ��A�ʂ̃��R�[�h��Ђ̃J�^���O�ɉ�����ꂽ�肷��B����ǂ����ۂ̐���҂ł͂Ȃ����l�̎�ɂ��̔��������ڍs���������Ƃ����͈̂ꕔ�̔���̂��̂�ʂƂ���A�傫�ȊS�������ꂸ�A��W�Ȉ�������\���������B�܂��V�����^�����s���Ă���悤�ȉ�Ђł͐V�����̏��i�ɗ͂����Đ�`���邵�A���܂ɃJ�^���O���W���I�ɍĔ�������悤�Ȋ�悪�����Ă��A����͉ߋ��̔���グ���т���]���̊m�肵�Ă�����̂ɕ��Ă��܂����Ƃ������B���̌��ʁA�N���V�b�N���y�̐��E�ł͖c��ȃJ�^���O������ɂ�������炸�����̂قƂ�ǂ������Ă��܂����ʂɂȂ��Ă���B
���̒��ɂ͂ǂ��ł������悤�Ȃ��̂����Ȃ��炸���邱�Ƃ��낤�B����ǂ������ɁA��ʂɂ͒m���Ă��Ȃ�����ǂ��|�ւ��̂Ȃ����Ղ�������Ă��邱�Ƃ����X����̂��B���W���[�E���[�x���ł͂��������J�^���O�̈ꕔ��ʂȕ������̉�ЂɌ�����ݗ^���čĔ��������A��Ŏ�����Ƃ���������u���Ă���P�[�X�������B�������A�����������̂������Ă���X���e�ՂɃA�N�Z�X�ł���͉̂ߋ��ɘ^�����ꂽ�c��ȃJ�^���O�S�̂̂ق�̕X�R�̈�p�ɉ߂��Ȃ��̂��B
�����̏ꍇ�A�Â��]���ʓI�ł͂Ȃ������Ƃ����̂́A���̖�����o�܂��悤�ȉ����ȒT���S�����������҂ɏo���Ȃ��Ɩ�����Ă��܂��P�[�X�����|�I���B����18�N���ɂ킽�背�R�[�h��ЂŊC�O�̃��R�[�h��Ђ��甭������Ă���k�o��b�c�������Չ������ƂɌg����ė����B����Ȓ��łƂ�킯��������������Ă��܂��Ă��鉹���̖�����o�܂��悤�ȍ�ƂɔM�S�Ɏ��g��ł����Ǝ������Ă���B���y�]�_�ƂɂȂ��Ă�����ߋ��̖Y����Ă��܂���������Ă��Ȃ��D�ꂽ�����ɂ��ĐϋɓI�ɋL���悤�ɂ��Ă���B�܂��D�ꂽ�����ՂɊւ��Ă��\�Ȍ�����グ��悤�ɂ��Ă���B
����ɂ��Ă��f�B�X�N���j�I���Ȃǂ̒��Ã��R�[�h�X�ɍs���ƁA�����ɂ��̑��݂�����m��Ȃ������k�o���R�[�h�ɑ������邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B������t�����X�̖��w���҃A���Q���u���V���g���U�����O���[�O �u�y�[���E�M�����g�g�ȁv �i�����j��25cm�Ղ����A�Q�ĂĔ������߂��B���̎��_�ł͂��ꂪ�ǂ�ȉ��t�Ȃ̂��͒��������Ƃ��Ȃ��̂Ŕ���Ȃ������B����ǂ��A���Q���u���V���g��1880�N���܂�ł���A�h�r���b�V�[�Ɛe�������肱�̍�ȉƂӂƂ��Ă����w���҂��B�������ߔN���Ăł̓O���[�O���h�r���b�V�[�ɗ^�����e���Ɋւ��Č������i�߂��Ă���B�܂��A���Q���u���V���g�̓h���[�t���X�����ɍۂ��ăO���[�O���h���[�t���X�h�ł��邱�Ƃ�\�����A�������o�b�V���O�������Ƃ�������҂Ƃ��Ēm���Ă����͂����B������������Ȃ�����̂��Ƃ��̂k�o�ɂ͋���������B������ɂ��掩���̍D���ȋȂɊւ��A�ߋ��ɂǂ�ȃA�[�e�B�X�g�ɂ��ǂ�ȉ��t���������̂���m��w�͂����邱�Ƃ́A���̉��y������ŏ�ɏd�v�Ȃ��Ƃł͂Ȃ����낤���H
�N���V�b�N���y�͏�ɉߋ����Q�Ƃ��Ȃ���A���̗��j��H��V�������̂�n�����čs�����̂��Ƃ������Ɏ��͔F�����Ă���B����ǂ��N���V�b�N���y�ƊE�̎Y�Ƃ̈ꕔ��Ƃ��ă��R�[�h��Ђ̃N���V�b�N���傪�ʒu�Â����Ă��錻��ł́A�ǂ����Ă������̃A�[�e�B�X�g�A�V�����^�����`���邱�ƂɃN���V�b�N���y�S���҂̖ڂ��s���������B����䂦�ɂȂ�����̂��Ɖ��y�]�_�Ƃ����͗D�ꂽ�ߋ��̘^����Y����Ɍ������A�p���I�ɃN���V�b�N���y�t�@���ɑ��Č[�ւ��Ă������Ƃ�����Ǝ��͍l����B���Ƃ����ꂪ�g�K����ĂȂ�����ԉɂ������銄�ɕ���Ȃ����Ƃł������Ƃ��Ă��c
�����́A���́u�m��ꂴ���i���L�߂��v����Â���̂�
���Z���̍��A��������i��ŃN���V�b�N���y�̐��E�Ɏ��˂��������獡���Ɏ���܂Ŗ�45�N���o�����B���̊ԂɎ����ɂƂ��āu���A���ꂪ�{���ɖ��ȂȂ́H�v�Ǝv���Ă��܂��悤�Ȃ��̋ƊE�̃X�^���_�[�h���ȂɎ��͐��������������B�m���Ɍ����ɍ\������Ă����i�Ȃ̂��낤�������I�Ȗ��͂ɖR����������A�Ȃ����߂��Ė���Ȃ������肵�ĕ����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B�����̑ΏۂƂ��ĕ��͂���̂ɂ͖ʔ����̂�������Ȃ����A�A�[�e�B�X�g�E�T�C�h�͊����ɉ��t����ΒB������������̂��낤�B�܂�������̗��ꂩ�炷��u������Ȃ������o�����v�Ƃ����������ɐZ��邩������Ȃ��B��������������������i��\���I�ɒ����������Ƃ����ΑS���H�w�������Ȃ��B���炭�]���̍˔\�����������t�҂Ɍb�܂�Ȃ���A���ɂƂ��ĐS�Ƃ��߂��悤�Ȋy�Ȃɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��̂��B
���̈���ŃN���V�b�N���y�t�@���Ƙb���Ă��Ă�����̒m��Ȃ��悤�ȍ�i�����ɂƂ��čň��̂��̂ł��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B�|�[�����h���a���̏���哝�̂ɂ��Ȃ����s�A�j�X�g�E��ȉƃC�O�i�c�E�����E�p�f���t�X�L�i1860�|1941�j�́u�s�A�m���t�ȃC�Z��op.17�v�̓O���[�O�A�T�����T�[���X�̑�Q�A�T�ԂƂƂ��Ɏ��ɂƂ��čň��̃s�A�m���t�Ȃ̂ЂƂB�|�[�����h�̃A�[�e�B�X�g�ɂ����̂𒆐S�ɘ^���������ď��Ȃ��Ȃ����͉�����10��ދ߂������Ă���B����ǂ����ۂ̃R���T�[�g�Œ��������Ƃ͈�x�������B�܂��قƂ�ǂ̃N���V�b�N���y�t�@���͂��̋Ȃ������Ƃ������悤���B�܂������Љ�l�ɂȂ肽�Ă�����1970�N��㔼�ɂ̓��V�A�̍�ȉƃA���g���E�A�����X�L�[�i1861�|1906�j�́u�s�A�m�O�d�t�ȑ�1�ԃj�Z��op.32�v�͑S���Ƃ����Ă����قǒm���Ă��Ȃ���i�������B 1980�N�㖖�̂b�c�u�[���Ń��[���b�p�̗l�X�ȃ}�C�i�[���[�x�������̋Ȃ�^������悤�ɂȂ��ď��X�ɗL���ȍ�i�ɂȂ��ė������c ����ł����̂悤�ɌÍ������̃s�A�m�O�d�t�Ȃ̒��̍ō�����ɋ�����l�͂܂����Ȃ��̂ł͂Ȃ����H�@�킸��19�Ś�������X�y�C���̍�ȉƃt�A���E�N���\�X�g���E�A���A�[�K�i1806�|26�j�́u���y�l�d�t�ȑ�1�ԃj�Z���v���܂�������B�����ꂳ��������Ȃ�̐l���b�c���Ă݂悤�Ǝv����i�ł���ɂ��ւ�炸���O���A�N�Z�X�o����@��ƂĂ����Ȃ��̂��B���͂���܂Ŏ����ł͂Q�x�������������Ƃ��Ȃ��B
�������D���ȍ�ȉƁE��i�ň�ʓI�ɒm���Ă��Ȃ���i�̖��͂𐢂ɒm�炵�߂邱�ƁA����̓��R�[�h��Ђł�18�N���A�����ĉ��y�]�_�ƂɂȂ��Ă����18�N�ԂŎ����I�n��ю��g��ł����e�[�}�ł���B���l���K���⎩���̋C�ɓ�����̂ɃA�N�Z�X�o����悤�ɋƊE�̉��l�ς̑��l���𑣐i���邱�Ƃ������A�N���V�b�N���y��{���̖��͓I�Ȃ��̂ɂ��邱�Ƃɂ��Ȃ���̂��Ƃ����M�O���炻�����Ă���B�u�������̂�N�����ǂ��Ǝv��Ȃ��Ă͂����Ȃ��v�Ƃ������l�ς̉�ꉻ�≟���t���̓N���V�b�N���y�𐊑ނ����錴���ɑ��Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������Ƃ����͎������g�̌o������ǂ��m���Ă���B����ǂ����̂悤�ȍl�����͂��̐��E�ł͏����h���B�ЂƂ̑傫�Ȍ����Ƃ��ċƊE�̑����̐l���u����͈�ʓI�ł͂Ȃ���ȉƁE��i�Ȃ̂ŃR���T�[�g�Ŏ��グ�Ă��W�q�Ɍq���炸�A�`�P�b�g������Ȃ��v�Ƃ������ɔ��f�������ȌX��������B����ɍ��������Ƃɉ��y�]�_�Ƃ͂���������i�ɂ��Č��y���Ă����e���̃l�^�ɂȂ邱�Ƃ����Ȃ�����A����I�ɂ��������m��ꂴ���i�ɑ��ĐϋɓI�ɃA�N�Z�X���悤�Ƃ��Ȃ��Ȃ�B����Ȃ��Ƃ����邭�炢�Ȃ�ނ���p�ɂɎ��グ�����i�Ɋւ��đ��ʓI�ɒm����[�߂Ă��������������ɂȂ�A�ƍl�������Ȃ�̂��B����ɗL���ȍ�i�ɂ��Ă͍����O�̕��������E�y���E�������A�N�Z�X���e�Ղ����A�m��ꂴ���i�Ɋւ��Ă͂��Ȃ�̍�������B�������ԉɂ�������������L���łȂ���ȉƁE��i�Ɋւ��̂͑��Ƃ������ƂɂȂ�B����Ӗ��Łu�}�j�A�b�N�v�Ƃ������t�ň�ʓI�łȂ����̂�ے肷�邱�Ƃ̓N���V�b�N���y�́u��������̔ے�v�A�u���l���̔ے�v�Ɍq�����Ă���̂��B
���́u�N���V�b�N���y�̐��E�ō�i�ɑ��鉿�l�ς̑��l������������v�Ƃ����M�O����������ׂ��A�u�m��ꂴ���i���L�߂��v�𗧂��グ���̂�2002�N�̂��ƁB����܂łV�̃R���T�[�g�E�V���[�Y��g�݁A21�̃R���T�[�g�������������B���̉�̖ړI�́u�L���E�������킸�A�D�ꂽ���t�Ƃ̕��X�ɂ����͂��������A�m��ꂴ���ȉƂ����̖Y����Ă��܂�����i�̉��l��������x�A���ۂ̉��t��ʂ��Ĕ��f���Ă����������v�Ƃ������́B�Ⴆ�ΐ�q�̃A�����X�L�[��2006�N�ɖv��100�N�̋L�O�N�������̂����A���̖����ɓ�����Q��25���ɂ͔ނ̍�i����������Ղ�S���Ԃ����ē��W�����R���T�[�g���g�b�p���z�[���ōÂ����B
���͂R��24���ߌ�R������Óc�z�[���ŃR���T�[�g���s���B�������̘A�ڂ̌�������Ă��鏬�ї���̊��A�����āu�m��ꂴ���i���L�߂��v�i�Ƃ͂���������͎��j����Â���`�ł̊J�ÁB�V���p���A���X�g�A�O�m�[�A�x�����I�[�Y�A�T�����T�[���X�A�t�H�[���Ƃ�����������̍�ȉƂ����ɑ���ȉe����^�����t�����X�̏����̎�E��ȉƁA�|���[�k�E���B�A���h�i1821�|1910�j�̍�i�𒆐S�Ƃ����R���T�[�g���B�ߔN�A���E�I�ȃ��]�\�v���m�A�`�F�`���A�E�o���g�[�����͂��߂Ƃ��ă��B�A���h�̉̋Ȃ����グ��l���o�Ă��Ă���B�������܂��܂����ɂ���@��͏��Ȃ����A�����ɒ��������Ƃ̂Ȃ��Ȃ̕������|�I�ɑ����B������グ��ޏ��̃s�A�m�ȁA�A�e�ȂȂǂ͂قƂ�Ǐ��т���N���Ƀp���܂ŏo�����Ċy������肵�ė������̂ŁA�b�c�ł��������Ƃ̏o���Ȃ���i����B�����Ă������N�A�����邲�Ƃɒm�荇���̉��y�Ƃ����ɉ��t�����߂Ă��郔�@�C�I�����ƃs�A�m�̂��߂� �u�U�̏��i�v�����グ��B�Ƃɂ����ޏ��̉̐S�ƃR���T�[�g�̌��ꊴ�o�Ɉ�ꂽ�y������i��傢�Ɋy���݂����B
��̂����ЂƂ̖ڕW�͎�ÃR���T�[�g�Ŏ��グ���ȉƂ���э�i�̐�`���s���Ƃ������ƁB���̂��߂ɂ`�R��܂�̍�ȉƂ̗��N���Ȃǂ��ڂ����ڍׂȃ`���V���쐬���A�l�X�ȃR���T�[�g�̉��ȂǂŖ�Q���S�疇�z�z���Ă���B�܂����̃`���V�ɂ͎Q�l�����A��v�f�B�X�R�O���t�B�Ƃ�������{�f�[�^���ڂ��ċ������������l������ɒm����[�߂�̂��菕������悤�ɂ��Ă���B�i���Q�l�܂łɖ{�e�̍Ō�Ƀ`���V�̂S�y�[�W���f�ڂ����Ă����������j
����Ɠ����Ɏ��͏�X�R���T�[�g����悷��l�Ԃ́A���������t���˗�����A�[�e�B�X�g�Ɋւ��Ă��̋N�p���闝�R������ł��Ȃ��Ă͂����Ȃ��ƍl���Ă���B�]���ăR���T�[�g�̃`���V�ɂ̓A�[�e�B�X�g�̑���������v���t�B�[�������̂܂܍ڂ��čς܂���̂ł͂Ȃ��A�K�����̉��t�Ƃ̃Z�[���X�|�C���g�����Ȃ̂��A���邢�͉��̂��̐l��I�̂����R�������Ȃ�̌��t�ŋL���悤�ɂ��Ă���B�`���V��ǂ܂����X�ւ̐����ӔC�Ƃł����������c
���͂���܂ł����ƃ|�s�����[���y�Ɠ����悤�Ɂu�ЂƂ̎�Ƃ��āv�N���V�b�N���y���ė����B�u��ʋ��{�v�A�u�㗬�K���̕����v�A�u�����Ȍ|�p�v�Ƃ��Ē������Ǝv�������Ƃ͂قƂ�ǖ����B�Ђ����玩���̋C�ɓ�����̂L���A�[���T���������Ă����B�����疲���ɂȂ��Ē����ė���ꂽ���A�O���邱�Ƃ����������B�������{���ɍD���Ȃ��̂⋻���̂�����̂��������A���̌��ʂƂ��ċC�ɓ��������̂�T���������A����𑼐l�ɑE�߂�ׂ��M�������ė����B��N�͓����{��k�Ђ̉e���͂��������̂̃g�[�^����272�̃R���T�[�g�ɒʂ����B
���������u2011�R���T�[�g�E�x�X�g�e���v�Ƃ����L��������G���p�ɏ������̂����ҏW���̓s���Ń{�c�ɂ���Ă��܂����B���̋L���̓x�X�g�e����I�ё�P�ʂɑI�R���T�[�g�ɂ��ẴR�����g�������Ƃ������́B��N�Ȃ�u�܂��d���Ȃ��v�ƒ��߂��̂�������Ȃ����A2011�N�͓����{��k�Ђƕ�����ꌴ�����̂�������ʂȔN���B�����ĉ��y�]�_�ƂƂ��Ă̎Љ�I�ӔC�Ƃ����_�Ɋӂ݂đ�P�ʂɑI�R���T�[�g�Ɋւ��Ă͂ǂ����Ă������̈ӌ���\�������������B����䂦�Ƀ{�c�ɂ����G���ҏW���ɂ͌��e���̎x���������ۂ��A�{�c�ɂ��ꂽ���e�����R�Ɏg�킹�Ă��炤���Ƃɂ����B�����đ�P�ʂ̃R�����g�͈ꕔ�����������ŁA�����V���P���V�������́u�����v���ɓ��e���̗p���ꂽ�B���̌l�I�Ȏ�̕\���Ƃ��Ďc��̂X���܂߁A�x�X�g�e���ɑI�R���T�[�g�����߂Ă����ɂ��Љ���Ă��������B
�k��P�ʁl
����v��ȉƁE����@�g���^�����S�[�A�E�N�@���e�b�g�A�R�c���F�i�s�A�m�j�A�ق��@�m11��12���^��v��w���ԗ���p�� �u�����فv�i��c�s�j�n
�ȉ��A�J�Ó���
���͑����q�i�s�A�m�j�̎����y�^�����r��(���@�C�I����)�A��؍N�_�i���B�I���j�A�ق��@�m�P��13���^JT�z�[���n
���|�V���q���@�C�I�������T�C�^���^�]����i�s�A�m�j�@�m�Q��14���^���c�s���z�[���n
���ؗ�Ȃ�����^�쎇���i���@�C�I�����j�A�e�r�m�q�i�s�A�m�j�@�m�R��13���^�A�[�g�X�y�[�X�E�I�[�i���c�j�n
�����{���[�c�@���g�����527����^�O�c��Y�i�s�A�m�j�@�m�R��16���^����������ُ��z�[���n
�������{��k�Д�Ўҋ~������̂��߂̃}���\���E�R���T�[�g�@�m�S���X���^�E�B���O��剪�Q�K�K�[�f���E�R�[�g�i���l�s�j�n
�����H�Y�̑��Ձ^��X�˕�(�`�F��)�A��c�����i�s�A�m�j�A���엳��w���������y�c�@�m�U��24���^�U�E�V���t�H�j�[�z�[���i���j�n
�����R���t�b�A�R����j�w�����t�B���k���t�}�j�m�t�F�s�A�m���t�ȑ�Q�ԁl�@�m10���Q���^���s�N�����Z���^�[�n
������t�s�A�m�Ƒt��@�m10���U���^�l���{�����z�[���n
���q���N�C�G���̏W���r2011�^�n�C�����b�q�E�V���b�c�����c�E�����@�m11��18���^�����J�e�h�������}���A�吹���n
�@����̃g���u�����o�����Ă��Â��v�����B���y�]�_�Ƃ͎������g�̉��l�ς𐳒��ɕ\�����Ă������y�]�_�Ƃ��肤��̂ł͂Ȃ����A�ƁB�����łȂ��Ƃ����猴�q�͑��̒��ŋƊE�̓s���̂����悤�ɐ�����t���邱�Ƃ��d���ł��邩�̂悤�ȁA���q�͈��S�ۈ��@�⌴�q�͈��S�ψ���Ƒ卷�Ȃ��̂ł͂Ȃ����H�@���n�t����^���邱�Ƃ̐ӔC�A����̓N���V�b�N���y�ƊE�ɂ����Ă�������Ɖʂ�����Ă���̂ł��낤���H�@���̂��Ƃ̓R���T�[�g�S�[�A�[�̕��X�A�b�c�̏���҂̕��X����ԗǂ������m�ł͂Ȃ����Ǝv���B�����R���T�[�g�A�܂�ʂb�c��E�߂�ꂽ���Ƃւ̍��݂͎������g���������₵�Ă݂Ȃ��Ɣ���Ȃ��̂��B�K���s�K�����y�ւ̍D��S�̉����Ȏ��͖����ɏd�Ăȏ���҂ł��葱���Ă���B
�����{��k�Јȍ~�A���{�͒n�k�����������Ȏ���ɓ������B�����ĕ�����ꌴ�����̂ɂ����˔\�����̎��Ԃ͍��㏙�X�ɖ��炩�ɂȂ��Ă���̂ł��낤�B����Ȓ��ŁA�c�菭�Ȃ���������Ȃ��l���̒��Ŏ������S�ꈤ����A�����ċ����̎��Ă鉹�y�E���t��S���Ē����čs�����Ǝv����V���ɂ��鎄�ł���B
���{���ɂ��q�l�͐_�l���H
���̂Ƃ��������Y���w�}�X�R�~�͂Ȃ��u�}�X�S�~�v�ƌĂ��̂��H�x ���͂��߂Ƃ��āA�����}�X�R�~�̍����ɂ�����݂�����e�[�}�ɂ����{���������ǂ�ł���B�j���[���[�N�E�^�C���Y�̓����x�ǒ��}�[�e�B���E�t�@�N���[���w�u�{���̂��Ɓv��`���Ȃ����{�̐V���x�A�疢�ʒ��w���{�͕K���R�����x�ȂǂȂǁc�B�����̎����ҁE�ǎ҂͏���ł̑��ŁA�I�X�v���C�̔z���A�����̍ĉғ�����ѐV�݂ȂǁA�]��ł��Ȃ��̂ɂ�������������i�삷��悤�ȃ}�X�R�~���Ȃ����B�ϋɓI�ɗi�삵�Ȃ��Ƃ��Ă��A�u���̒��͂����Ȃ��Ă���̂�������߂Ȃ����v�ƌ�������̖��ӔC���ŋq�ϕ������B���̌���̔w�i�ɂ��闠�����������邱�Ƃɂ���Ď��������̓L�`���Ǝ�ނ��A�}�X�R�~�Ƃ��Ă̐E����S�����Ă���Ǝv������ł���B
�Ƃɂ����u�o�ρv�A�u���ē����v�Ƃ������t���o���A�ǂ�ȗ��s�s�Ȑ��{����ł����Ă����������x�����邩�̂悤�Ȏp�����A�ŋ߂̃}�X�R�~�̐�������͋�����������B��������щ���̐l�X�����܉���]�݁A�����l���Ă���̂��͔M�S�ɕ��ꂸ�A�A�����J�A�����A���Ƃ̊������v��i�삷�邽�߂̐��{�A�����A���E�l�A��p�L���ҁE�w�҂Ȃǂ̔������ł��d�v�Ő��������̂悤�ɓ`�����Ă���B�u�Љ�̖ؑ��v�ȂǂƂ����@�\�͂Ƃ��̐̂ɑ����̃}�X���f�B�A����͖����Ȃ��Ă���̂��낤�B�D�ނƍD�܂���Ƃɂ�����炸�A�l�b�g�̏��ɗ���Ȃ��Ă͖]�ނ悤�Ȍ��_�A���m�ȏ��͓����Ȃ�����ɂȂ��Ă��܂��Ă���̂�������Ȃ��B����ǂ������ɂ��܂��u�K���v���������悤�Ƃ��Ă���Ƃ����̂�����{���ɕ|�낵�����̒��ɂȂ������̂��B
��q�̓�������̖{��ǂ�ł��Ă����ЂƂ����v�����̂́A�}�X�R�~�ƊE�ɂƂ��ēǎҁE�����҂ւ̐ӔC�����ǂ�ǂ�Ă��邱�ƁB����}�X�R�~�}�̂ɂƂ��ď����A�L���o�e��Ȃǂ̈ӂɉ������Ƃ��A�w�Ǘ����M�����ǎҁA�����҂����d�v�ƍl�����Ă���̂�������Ȃ��B����Ȃ瑽���̃}�X�R�~�����������悤�Ɂu�o�ρv��u���ē����v�𐺍��ɋ��Ԏp���ɂ����_���s���B�������ɍŋ߂̐����Ȃǂ����Ă��Ė��Ɏv���̂́A�ǎҁA�����҂̗��v�̂��߂̕�咣���}�X�R�~�}�̂ɂ���ė]��ɂ��Ȃ�����ɂ���Ă���_���B�W���[�i���Y���Ɋւ��l�Ԃ����肵�������A����ҁi�܂�ǎҁA�����ҁj�Ƃ��Čl�I�ə��[�����Ă�����邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����H
�U��Ԃ��ăN���V�b�N���y�ƊE���l���Ă݂Ă�����Ҏ匠�A�u���q�l�͐_�l�v�Ƃ����l�����͂��Ȃ�̂悤�Ɋ�������B�悭�N���V�b�N���y�E�̕]�_�ƁA�W���[�i���X�g�A�w�҂Ȃǂ̒��ɂ́u���y�]�_�Ƃ͏����ɉ��y���ꎩ�̂Ɖ��t�ɂ��Č��ׂ����́v�Ƃ������ɑ�������������Ȃ��Ȃ��B�������R���T�[�g�̏ꍇ�ɂ͇@���̎��d��A�A�v���O��������̎��A�B���O�̎��A�C���̓����A�D���ꗿ���̐ݒ�Ɣ̔����@�ȂǁA���y�\�t�g�̏ꍇ�Ȃ�@���̉��i�ݒ�A�A���C�i�[�m�[�g����ѕҏW�Ɩ��̎��A�B�S�̂̃A�[�g���[�N�A�C����̓�Փx�Ȃǂ��S�Ă���]�̑ΏۂƂȂ�B�Ȃ��Ȃ�����������X�̗v�f���R���T�[�g�≹�y�\�t�g�̈ꕔ�����炾�B����̓R���T�[�g�ɕt��������_�̂����̂������ɐG��Ă݂����B
�܂��͒��O�̖��B���̂Ƃ���N���V�b�N�̃R���T�[�g�ɍs���ĕs���ȋC���ɂȂ邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B���Ȃ킿�A�u�{���ɂ��̐l�����͒��������ė��Ă���̂��낤���H�v �Ƌ^��Ɏv���Ă��܂��悤�Ȃ��q���A�R���T�[�g�̊ӏ܂�W�Q����悤�Ȏ��Ԃ��N����̂��B���t���ɁA�g�ѓd�b�̃X�C�b�`���Y��Ė�o������A�A����������ۂ��Ȃ����̂ň����r�߂悤�ƂȂ��Ȃ��J���Ȃ��܂�����o�����Ƃ��ĉ��𗧂Ă���A�߂��̒m�荇���Ƃ�������n�߂���A�܂�Ȃ��Ȃ��ē��ꎞ�ɔz�z���ꂽ�`���V�̑���傫�ȉ��𗧂ĂȂ��猩�n�߂���A�����ė������̂̓��������W�܂����������T���ĉ��𗧂Ă���A�q�����ދ����ĕ����𗧂Ă���e�ɘb����������c
���ɕ|�낵���̂̓g���u�������o���҂̉Ƒ��A�e�މ��ҁA�F�l�A�e�̉�Ђ̎Ј��ł������肷��P�[�X�B�V�l���t�����̃\���E���T�C�^���Ȃǂł����Ζڂɂ�����i���B���⑧�q�̐��ꕑ������������Ƃ��A�q�Ȃ��₵�����牽�Ƃ����߂Ȃ��Ă͂Ƃ��A���������������ɃR���T�[�g���y���݂����̂ł͂Ȃ��A������������ꂽ�l�X������悤�Ȏ��̓g���u�����N����₷���B�܂��}�X���f�B�A�̗l�X�ȓǎ҃T�[�r�X�Ȃǂɂ��u�������ҁv�Ƃ����̂��v���ӂ��B�^�_�����A�ɂ����狳�{��[�߂邽�߂ɍs���Ă݂悤���Ƃ������ƂȂ̂��낤�B����ǂ�����͕ʂȈӖ��Łu�^�_�قǕ|�����̂͂Ȃ��v�Ȃ̂ł���B
�����������O�̃g���u���́A�N���V�b�N���y����ʋ��{�Ƃ��čl�����Ă��邱�ƂɋN������P�[�X�������悤�Ɏv����B���Ȃ킿�A�u���{��[�߂邽�߂ɃN���V�b�N���y�ł������Ă������v�Ƃ� �u�q���̏����ɃN���V�b�N���y���ǂ������Ȃ̂ŁA�������Ȃ��Ă͂Ɓc�v�Ƃ��������ՂȔ��z�ŁA���ɒ����������Ȃ��̂ɗ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����B���������Ȃ̂����A�����ɂƂ��ċ�����S�̖������̂��̂͑����̏ꍇ�ɂ����đދ��ŔE�ϗ͂�K�v�Ƃ���B����͓��R�̂��ƂȂ����ɂ��B�����N���V�b�N�E�R���T�[�g�ɒʂ�����Ă���̂ŁA���Ƃ������Ȃ���Ȗڂ≉�t�҂����҂͂��ꂾ�����肵�đދ����Ă��Ă��A���̒��O�ɔz�����ĉ\�Ȍ��蕨���𗧂ĂȂ��悤�ɓw�͂��Ă���B����ǂ�����Ȃ��Ƃ��A�قƂ�ǃN���V�b�N�̃R���T�[�g�ɗ������Ƃ̂Ȃ��l��A��������������o���Ă��Ȃ��q���ɋ��v����̂͂ǂ��l���Ă�����������B���������l�X�̓R���T�[�g��I��ōs���ׂ����B
�Ⴆ�A����s�����u�O����̃R���T�[�g�v�ł͒��O�̑唼���c���Ƃ��̕�e�Ƃ����ŁA�ׂ̂܂��Ȃ��Ɏq���͋����A�����肵�A�������Ƃ����ŃK�T�K�T���Ă����B����������͌���肻����������O��Ƃ��Ă���R���T�[�g�ł���A���t�҂����O���[�������̂��ƂȂ̂œ��ɖ��͖����B����͋ɒ[�ȗႩ������Ȃ��B���������̓}�i�[��������x���i�Ɏ�邱�Ƃ��K�v�Ȉ���ŁA���������Â��łȂ��q�Ȃ��O��̃R���T�[�g�������Ƃ���ׂ��ł͂Ȃ����ƍl������̂��B���������̂悤�ȃR���T�[�g�Ɋւ��Ă͉��t���̓��ꐫ�̓`���V�ȂǂɃn�b�L���ƋL�����ׂ����낤�B
�悭���t�҂ɑ��Ď���Ƃ������ƂŁu������v����ɂ���l�����邪�A���͓��ɖ��ɂ͂��Ȃ��B����͎~�ނȂ����Ƃ����炾�B�����ꍂ��������肷��ꍇ�ɂ͋߂��̐l���y������@���Ȃ肵�ċN�����Ă�����Ηǂ������̂��ƁB�N���Ă��ĕςɕ����𗧂Ă邭�炢�Ȃ�܂��Q�Ă���ق����܂��Ȃ̂��B���ɂ����x�ƂȂ��o�������邪�A���Ƃ��ăR���T�[�g���ɍ��������ɏP���邱�Ƃ�����B�悭�u�������t�Ȃ̂Ŗ����Ȃ�̂��v�Ƃ������ɐ�����������l�������邪�A���Ȃ��Ƃ����ɂƂ��Ă͈Ⴄ�B�ł������Ȃ�̂́A���ԓI�ȉ��l�ς��猾���Η��h�Ȃ̂�����ǂ��A�����̎�ɂ͍��v���Ȃ����t�̏ꍇ���B���J�j�b�N�����炩�ɕs�\���������肷�邢����u����ȉ��t�v�͒����Ă��ĐS�n�ǂ��Ȃ�����p���Ė���Ȃ����̂ł���B
�ŋ߂̃R���T�[�g�œ��ɕ������̂́u�u�����H�[������v�B�Ȃ��I���ƊԔ����ꂸ�Ɂu�u�����H�[�v�����ԁB�\���ɗ]�C���y���݂����Â��ɏI���Ȃł��A����ȂɌ��o�������t�łȂ��Ă��A���\���Ȃ��ɉ��t�҂��Ō�̉���t���I�����u�Ԃɋ��ԁB�I�y���Ȃ炢�����炸�I�[�P�X�g���̉��t��A�����y���y�̃��T�C�^���ł���������Ɩ{���ɋ����߂��B��{�I�Ɂu�u�����H�[�v�͖����̔����˂��j���ċ��Ԃ���J�b�R�������A���܂ɂȂ�̂ł���B���������u�T�N���v�̂��ƂȂǗ��j�I�Ȕw�i������Ă���u�u�����H�[�v�͋��тȂ����ƌ��������Ȃ�B��x��Ñ��̒S���҂ɕ������������A�u�A�[�e�B�X�g�̒��ɂ͂��������u�����H�[���D�ޕ�����������Ⴂ�܂�����c�v�Ɠ�����ꈠ�R�Ƃ������Ƃ��������B�Ђ���Ƃ��Ă���͎�Î҂��ق����T�N���������̂��H�@�Ȃ�����Ǝ��̗ǂ��T�N����I��ŗ~�������̂��B�������̂��ƋƊE��ÂŃu�����H�[������̕i�]��Ƃ������͂��������낤���H
�����������O���̃g���u���A��Îґ��Ƃ��Ắu�������ē��ꂵ�����q�����瑽���̂��Ƃ͑�ڂɌ��āc�v�u�����ł����N���V�b�N���y�ƊE�͏W�q�ɋ�J���Ă���̂����痈�ĉ����邾���ł��肪�����v�Ƃ����ӎ�������̂�������Ȃ��B�������Ȃ�����f���鑤�̂��q��������������ꂵ�Ă���̂��B���������g���u���ɖڂ��Ԃ邱�Ƃ́A�R�A�ȃN���V�b�N���y�t�@���w�����R���T�[�g�ɍs�������Ƃ����ӗ~���킮���ʂɂȂ��Ă��܂�Ȃ����낤���H�@���͉��y�]�_�ƂȂ̂ŁA���������g���u�����܂߂ăR���T�[�g��_���闧��ɂ���A�ƍl���Ă���B
�{���Ȃ�A���������g���u���ɂ��Ă̓R���T�[�g�E�S�[�A�[�����̎G���Ȃǂł����ƐϋɓI�ɖ�肪����A���ӂ����N����Ă�����ׂ����̂ł͂Ȃ����H�@�����������������f�B�A�ɂƂ��ĉ�������ȁu�W�q�v�Ɉ��e�����o�邱�Ƃ�����Ă��A���邢�͎�Îґ��̊Ǘ��ӔC�̕��S����q���m�̃g���u���ɔz�����Ă��A���W��g��ŔM�S�Ɏ�舵���Ă͂��Ȃ��悤�Ɏ��ɂ͎v����B�������Ɂu���q�l�ɏo���邾�������W�܂��ė~�����v�Ƃ������z�͓��R�̂��ƁB�������W�߂����q�������������Ǘ����邱�Ƃ��܂����q����̂��߂ł͂Ȃ��̂��H�@����A�����V�e�B�E�t�B���̃R���T�[�g�ɍs������v���O�����ɋ��܂ꂽ���ɔ���̃^�C�~���O�ɂ��Ă̒��ӏ������������B�܂��ʂ̃I�[�P�X�g���ł́u����Ȃǂ͎w���҂��w���_�����낵�Ă��炨�肢���܂��v�Ƃ����A�i�E���X���������B����Ɏq���������͏��S�҂�z�肵���A�R���T�[�g�ł̃}�i�[�ɂ��Ē��ӂ����N�������̎����v���O�����ɋ��܂�Ă���P�[�X���ŋ߂������������B���������w�͂��ܘ_������A�ƊE�Ƃ��Ă̔��{�I�ȑ]�܂��B
���Ƀz�[�����̖̂����������B�܂��w������̌X�����傫�����Ȃ̖��B����͍���S�n���ǂ��̂ŁA�ǂ������Ɏv����B�Ƃ��낪�֎q�̔w���傫���X���Ă���Ƒ������R�ɑO�ɐL����������Ȃ��Ȃ�B���̂��ߍ��Ȃ̔w�̌X�ƐL�т����̕������ʂŁA�O��̋q�ȊԂ̕����ƂĂ������Ȃ��Ă��܂��B�l�������Ă����Ԃł��̑O��ʂ��ė�̓����̐Ȃɓ��낤�Ƃ���Ƒ�ςȋ�J�����邱�ƂɂȂ�B�����炱���������Ȃ̏ꍇ�ɂ͑O��̗�̊Ԋu���\���ɍL�����Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂�����ǂ��A��������Ƌq�Ȑ��������Ă��܂��̂ŏ\���ɍL���Ȃ����Ƃ������B
���X�^��Ɏv���̂́A�z�[����v����l�̓R���T�[�g�ɒx��ė��āA��̓����̍��Ȃɍ���l���K������̂��Ƃ������Ƃ𗝉����Ă���̂��ǂ����Ƃ������ƁB���������c�_������ƋƊE�W�҂̒��ɂ́u�C�O�̗R������z�[���ɂ͂����Ƌq�Ȃ̑O��̕���������������܂��v�Ƃ��������_�_�Ŕ��_���ė���l�����邾�낤�B����ǂ����������q����̗���ɂȂ��Ă݂�A�Ȃւ̃A�N�Z�X���e�ՂŁA�Ȃ����������ƍ����ɉz�������Ƃ͂Ȃ��̂͂����ɔ��肻���Ȃ��̂����c �����������R����z�[���Œ����t�߂̍��Ȃ̃`�P�b�g���Ȃ�őO���I������̂������B�����Ȃ�ꕔ�̗�O�����������������ޏ�̔ς킵���Ƃ͖��������炾�B
�r���̍����K�ɂ���G���x�[�^�[�ł����s���Ȃ��z�[���Ƃ����̂���肪�����B�ꎞ�ɒ��O���G���x�[�^�[�z�[���ɎE������I����̍��G�����ɂȂ�B��ɗp�����T���Ă���ꍇ�ȂNJK�i�ō~��Ăł��}���Œn��ɍ~�肽���̂����A�K�i�͎g�p�֎~�Ƃ����ꍇ�����Ȃ��Ȃ��B����g�p���Ă��Ȃ����K�i�����Ȃ�������A�r���̒��ɑ��̉�Ђ������Ă��Ėh�Ə�̗��R����g���Ȃ�������A�K�i�ɃA�N�Z�X����r���Ɋy������������c���炩�̗��R�Ŏg���Ȃ��̂��B���ԓI�ɂ�Ƃ肪�����ꍇ�A���������z�[���ł̓A���R�[���̔�������������ɑގU����̂��x�X�g�B�����Ĉ�ڎU�ɃG���x�[�^�[�z�[���ւƌ������̂��B���̂悤�ȃz�[���͒n�k��Ђ̏ꍇ�ɉʂ����đ��v�Ȃ̂�����ƐS�z�ɂȂ�B
�z�[���́u�i���R�[�i�[�v�̖��ɂ����ڂ��Ăق����B���Ȃǂ̓R���T�[�g���n�V�S���邱�Ƃ���������イ�Ȃ̂ŁA�z�[���̋i���R�[�i�[�Ōy�H��i�����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B�Ƃ��낪����Ăɂ��čs���Ɖc�Ƃ��Ă��Ȃ����Ƃ���������B���ɍx�O�̌����z�[���ł��������i���R�[�i�[���c�Ƃ��Ă����肢�Ȃ�������Ƃ������Ƃ������B���������z�[���ł̓z�[����Ì����Ƒ݂��قƂ��Ă̌����Ƃō��ʉ����Ă���̂��낤�B���Ȃ킿��Ì����ł͂��q����̕X���l���ċi���R�[�i�[���J�����A�݂��ق̏ꍇ�ɂ͂��̃T�[�r�X�͎��Ȃ��̂��B����ǂ��l���Ă݂���q����ɂƂ��Ă͂��̌������z�[���̎�Âł��邩�ǂ����Ƃ������Ƃ͊W�Ȃ����ƁB���Ȃ��Ƃ����q����ɂ����������j�m�Ɏ������߂ɂ��A�u�z�[����Ì����ȊO�ł͕��v �Ƌi���R�[�i�[�ɂ͏�Ɍf�����Ă����ׂ��ł͂Ȃ����B
�������A������u���y�Ձv�̂悤�ɁA�R���T�[�g�Ԃɂǂ�����Ď��Ԃ�ׂ����������ΔY�ނ悤�ȍÂ����ł́A���q��������̃z�[�����ӂ̐H�ו�������K�C�h�͕K�{���B����2007�N�W���ɐ�������̏��z�[���ƃO�����h�T�������g���A�T���Ԃɂ킽���Ē���12�������琬��u������ȉƉ��y��2007�v���s�������ɁA�H�ו�������K�C�h��������B�������邽�߂Ƀz�[���߂��̈��H�X�ɑ��ɂ��ʂ��A��x���A�c�Ǝ��ԁA�։��Ȃ̗L���A�X�̂a�f�l�͉����Ȃǂׂ���ŃK�C�h�ɋL�������̂������B���������w�͂������Ȃ炱���������̂�����ƕ֗����낤�Ƃ����R���T�[�g�E�S�[�A�[�Ƃ��Ă̌o�����Ɋ�Ă̂��Ƃ��B
�����������́u������ȉƉ��y��2007�v�̎��ɂ́A����������z�[���̍��Ȃ����d���̂ŁA���s�̓c�����i���݂͐�����j����\���̕����܂߂ď����z�c��240����194�̍��Ȃ̏�ɕ��ׂ����̂������B�z�[�����Ɂu�I���������܂��v�ƒ�Ă����̂������ۂ��ꂽ�̂ŁA�Ō�̃R���T�[�g�ɗ���ꂽ���q����ɂ������A�肢���������Ƃɂ����B�ŏ��͂��q�������A��Ȃ�������ǂ����悤���ƍl���A�m�荇���̃f�C�P�A�E�Z���^�[�Ɏc��������S�Ĉ�������ĖႤ�悤�ɘb�����Ă������B�K���Ȃ��Ƃɏ����z�c�͑�ύD�]�ŁA�l�ɂ���Ă͂����K�ɕ~���̂ł͂Ȃ�����w�ɓ��ĂĎg���l�������B�����Ď��̐S�z�͞X�J�ɏI������B�Ō�̃R���T�[�g���I��������ɑS�Ă̍��Ȃ̏����z�c�����ꂢ�ɖ����Ȃ��Ă����B�l�ɂ���Ă͂R�S���Ă邾���������ċA�����l�������B���ł����X�R���T�[�g�ł��̎��̂��q����u���̏����z�c�𖢂��Ɉ��p���Ă��܂��v�Ɛ�����������B�d���֎q�Œ����ԍ����Ă���̂͂���ǂ��A�Ƃ����ߋ��̌o�������Ƃɂ������������Ė{���ɗǂ������Ǝv���Ă���B
���Â��v���B�u�Ȃ̗~�����邱�Ƒ��l�Ɏ{���Ȃ���v�B����҂̐S�𗝉�����ɂ͎��炪����҂Ƃ��Ă̍s�����d�ˁA�ǂ�����������ƐS�n�ǂ������l�@������������̂��ƂȂ̂ł���B�ܘ_�A�R���T�[�g�ł悭������킹�M���ł���l�Ɠ����R���T�[�g�E�S�[�A�[�Ƃ��Ė{���̕����Řb����Ȃ�A�����������Ƃ��Ă�����_�ɂ��C�t���̂ł����Ɨǂ��̂����c�����͂܂�����B
�����E�{���ɂ��q�l�͐_�l���H
�O��̓R���T�[�g�ɊW�������_�̂������O�A�z�[�����̂ɂ��ċL�����B����͎�Îґ��̃g���u���ɂ��ċL���Ă݂悤�B
�����o�������g���u���ōŋߑ����Ă���̂��R���T�[�g�{�Ԓ��̎ʐ^�B�e�B�M�����Ȃ����Ƃ����A��Î҂��z�[�����Ŏʐ^�B�e���s�Ȃ����̉������邳���̂��B�B�e�p�̕����������Ă������炷��Ƃ����̂ł͂Ȃ��q�Ȃ̒ʘH����B��I ���R�̂��ƂȂ���V���b�^�[�����J�V���J�V�����Ĕς��B�ǂ����Ă���Ȃɂ����_�o�ɂȂ��̂��낤���H
�F�X�ȏ��𑍍�����ƁA�ŋ߂ł̓z�[���̐�`�p���q��z�[���y�[�W�ȂǂɗՏꊴ�Ɉ�ꂽ�ʐ^���ڂ��悤�Ƃ��Ă��������؍s������y�������Ă���悤���B�������l���Ă݂����͕ςȘb���B���O�ɉ��ɑ���}�i�[�̏�������߂Ă����Î҂����炻�̃��[����j���Ă���̂�����c�B
����m�l�̃J�����}���Ɂu�V���b�^�[���������ĎB�e�ł���J�����͖����̂ł����v�Ɛu�˂����A����Ȃ��͖̂����Ƃ̓����������B�Չ����邽�߂ɃJ�����������ŃO���O�������ɂ��ĎB�e����l�����邪�]����ʓI�ł͂Ȃ��悤���B�܂Ƃ��Ȏ�Î҂̊��o�ł͉��t���i�̎B�e�̓��n�[�T�����ɂ�����̂��B�߂�ǂ�������ǂ����t�҂ɃX�e�[�W�ߑ��𒅂Ă�����ĎB��B�Տꊴ�̂���X�i�b�v�ʐ^�������O�ɂ����K�ȉ���Ԃ���邱�Ƃ̕�����Î҂Ƃ��ē��R�̋`���ł͂Ȃ����낤���H
���Ȃ݂Ɏ��������������������P�[�X�͑S���̂Ǒf�l����Â��Ă�����̂ł͂Ȃ��z�[����Â̂��̂ł�������A���邢�͉��y�Ɩ{�l����Â��Ă̌����������肷�邩������Ă��܂��B
�����ǎ҂����������g���u���ɑ��������牓���Ȃ���Î҂ɃN���[�������Ă������������B�R���T�[�g�͎ʐ^���B�e�����ł͂Ȃ����y���ӏ܂��邽�߂̏�Ȃ̂�����c�B
���ɃT�C����ł̎�Î҂̑Ή��ɂ��āB�R���T�[�g���I����Ăb�c�A�{�A�֘A�O�b�Y�Ȃǂ��ăT�C�������߂钮�O�����ւ̗������Ă���B����ɂ�������炸�A�[�e�B�X�g���Ȃ��Ȃ��z���C�G�ɓ��݂��ꂽ�T�C�����Ɍ���Ȃ��A�Ƃ����g���u���ɂ����Α�������B
�F�X�ȃP�[�X���l�����邪�A�y���ɋƊE�W�҂����������Ē��b�����Ă��܂��t�@����҂����Ă���Ƃ����p�^�[�������Ȃ��Ȃ��B
��Î҂̑Ή��ŕs���Ɏv���̂͋ƊE�W�ҁi���R�[�h��Ђ̒S���ҁA���y�]�_�ƁA�R���T�[�g���ҁA�Ƒ��A�F�l�A��q�ȂǂȂǁj�̖ʉ�͌�ɂ����āA�R���T�[�g���I�������^����ɃT�C�����ɃA�[�e�B�X�g�������킹��ׂ����Ƃ��������������Ύ���Ă��Ȃ����ƁB����͗������đ҂��Ă���t�@���ɑ��ĂƂĂ����炾�Ǝv���̂����c�����ɋƊE�W�҂͂Ƃɂ����A�[�e�B�X�g�{�l�̂��߂ɂ��A�܂��͂��q����ւ̃T�C����D�悳���Ă����悤�Ƃ����z��������̂��{���̈���ł͂Ȃ����Ǝ��͎v���̂��B
���͉��y�]�_�ƂɂȂ��Ă���ƊE�W�҂̏I����̎d���́u�҂��Ɓv�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B�T�C����I���܂Ŏ��͂��̗l�q��������ꏊ�ő҂��Ă��邱�Ƃ������B���̃A�[�e�B�X�g���T�C�������Ȃ����𐬂��t�@���̕��X���ǂ̂悤�ɎJ���čs���̂��A�ǂ�Ȃ��Ƃ������̂����ώ@����̂��B�������邱�ƂŔށE�ޏ����ǂ�ȃA�[�e�B�X�g�Ȃ̂��������Ă��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B���̐l���ł�������A���[���A�̃Z���X�ł�������A���ɂ͓{��̃c�{�ł�������c
�����ΗL���Ȑ搶�����ւ̗�𐬂��t�@���̐l�����������̂��ăA�[�e�B�X�g�Ɩʉ��Ƃ����P�[�X�ɂ��������邪�A���Ă��Č����ċC�����������̂ł͂Ȃ��B�u�������̐l�͂�͂肱�̃��x���̐l�ԂȂ̂��I�v�ƌ��X���h�̔O�Ȃǎ����Ă��Ȃ��Ă����߂Ĕ[�����Ă��܂��B���͊�{�I�Ɏ�Î҂��犩�߂��Ă��������Ō�܂ő҂悤�ɂ��Ă���B�ǂ����Ă����A���Ȃ��Ă͂����Ȃ��ĂȂ����オ�����Ă���悤�ȏꍇ�ɂ́A�b�c���Ƃ��玝���čs���ăT�C����̗�ɕ��Ԃ悤�ɂ��Ă���B���������̓N���V�b�N���y�ƊE�l�ł���A��ʂ̃t�@�����̓A�[�e�B�X�g�ɂƂ��ďd�v�ȑ��݂Ȃ̂��A�Ƃ������v���オ��قnj��ꂵ�����̂͂Ȃ��B����҂����ẴN���V�b�N���y�ƊE�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ����͖Y�ꂽ���Ȃ����̂��B
����ɂ��������W�҂͑����̏ꍇ�A���̃A�[�e�B�X�g�ɑ��ĉ��炩�̘A�����@�������Ă���̂�����A�������g���Č�قǃR�~���j�P�[�g��������̂��B���邢�͉���������U���Ėڗ炷�邭�炢�ɂ��ċA������̂ł���B�I���タ���Ƃ����A���Ȃ��������Ƃ͓d�b�Ȃ胁�[���Ȃ�ŁA�����ƒ��J�ɂȂ�莆�ł��l�т�������B
���ꂩ��x�O��n���̃z�[���ő����̂����t�҂ɑ���g�[�N�̋��v�̖��B���̋ƊE�ɂ���Ɓu�N���V�b�N���y�̕~����Ⴍ����v�Ƃ�������ڂ����������B�܂�u�N���V�b�N���y�͈�ʂɂ͉���Â炢���̂�����A���炩�̕��@�Őe���݈Ղ��������H�v�����悤�v�Ƃ������Ƃ炵���B���̂��߂ɃR���T�[�g�ɂ����ĉ��t�҂ɋȂ̍��ԂɃg�[�N���邱�Ƃ����߂�ꂽ�肷��B�����肪���蕨�́A���邢�͏��Ȃ��Ƃ����ӂȉ��t�ƂȂ炢�����A�����ł͂Ȃ��A�[�e�B�X�g�����Ȃ��炸����B
�����ꍇ�ɂ͓����ɂȂ��ċ}�ɏo���҂��Ȗډ�����܂߂��g�[�N������悤�Ɉ˗�����邱�Ƃ��炠��̂��B�l�I�Șb���b�����炢�Ȃ�܂��������A���O�ɏ\���ȉ����ׂ����Ȃ��ō�i�ɂ��Ă̘b���}�ɂ���̂͂ǂ��l���Ă�����������B����ɂ͒��ӂ������������B�q�Ȃɂ͂����ȉƁE��i�Ɋւ��ă}�j�A�b�N�ɏڂ������O�����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��̂��B
���ĉ䂪���̃o���b�N���y�̍ō����Ђ����������K�O�搶�́A���郌�R�[�h�X�ōÂ��ꂽ�Êy�n�V���[�x���̐�����̐܂ɁA�����܂��삯�o���̃��R�[�h��Ђ̕ҏW�҂���������⼌����ꂽ���̂������B�u�����ăt�@���̊F������Ă͂����܂����B�D���ŏW�܂��Ă������X�̒��ɂ͖{���ɏڂ���������R��������Ⴂ�܂�����v�B���N���h���ė����搶�̌����Ȏp���ɂ͊����������A���̌��t�͍��̃N���V�b�N���y�ƊE�ł͂܂��܂��d�݂𑝂��Ă���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B
����ɏo���҂ɂ��g�[�N�͈ꌩ�ǂ��t�@���E�T�[�r�X�̂悤�Ɏv���邪�A�����ɂ͎�Î҂̑S���ʂȈӐ}������ꍇ�����Ȃ��Ȃ��B���Ȃ킿�ʓ|�ȕҏW�Ɩ��̕����ł���B�g�[�N���v�������R���T�[�g�ł̓v���O�����ɋȖڂ̉�����ڂ��Ă��Ȃ����Ƃ������B���t�҂��Ȗڂ�������Ă���邱�Ƃ�D�荞��ł��邩�炾�낤�B�����������R����g�[�N�ɌŎ������Î҂͗ǂ��l����ׂ����낤�B
�{���ɂ��q����ɃN���V�b�N���y�̒m�����������莩���̂��̂Ƃ����A�R���T�[�g�̃��s�[�^�[�ɂ��邱�Ƃ�ڎw���Ȃ�A���̏�ŏI����Ă��܂��g�[�N����������A�v���O�����ɕ����Ƃ��č�i�����ڂ��������͂邩�ɐe���Ƃ������Ƃ��B�v���O�����ɋȖډ������������ڂ�����ʼn��t�҂ɃR�����g�����߂�̂��{���̃t�@���E�T�[�r�X�Ƃ������̂��낤�B�g�[�N�͈ꎞ�̂��́A�Ȗډ���͏��Ȃ��Ƃ��v���O������ۑ����Ă�����ł��J��Ԃ��ǂނ��Ƃ��o����̂��B���ꂪ�ǂ̒��x�̂��̂��͂��Ă����Ƃ��Ă��c�B
����ɂ��Ă����̂Ƃ���ҏW�Ɩ��̐��ނ��N���V�b�N���y�ƊE�S�̂Ői��ł���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B�b�c�u�b�N���b�g�A�R���T�[�g�E�v���O�����̋Ȗڈꗗ��C�i�[�m�[�g�Ɍ�肪�������肷��B�܂��ǂ�ł����̃A�[�e�B�X�g���ȉƁE��i�ɑ��鏑����̈���`����ė��Ȃ��u�P�ɋȖډ���̃X�y�[�X�߂܂����v�Ƃ����悤�Ȍ��e�����Ȃ��Ȃ��B
���ۂ̂Ƃ��날����x���̎��ɂ������ƕҏW�Ɩ��͂ƂĂ��ʓ|���B�܂����M���˗����鑊������߂�̂���ς��B�ǂ�ȕM�҂����āA���̐l�͂ǂ��������y�I�Ȏ�������Ă��āA���e���̑���͂����炩�A���M�̃X�s�[�h�͂ǂ��Ȃ̂��A�˗�����Ƃǂ�ȃ����b�g�E�f�����b�g������̂��c����Ȃ��Ƃ��c���ł��Ă��Ȃ��Ǝ��M�˗��o���Ȃ��B�܂����e��\��ʂ�Ɏ��̂���ς��B���������M�҂Ȃ炢�����A�Ȃ��Ȃ����M�҂����e�������Ȃ��ꍇ�ɂ͖��B�ŋ߂͍����̖����l�����Č��e�����e�ł����ҏW��Ƃ�r���ŕ������Ă��܂��S���҂���������Ƃ����B�ҏW�҂����M�҂������l�Ԃł���A�ƊE�����L�����Q���������Ă���B���ɂ͜������A���ɂ͂Ȃ��߂������c���e�̎旧�ĂŒm�b���i��̂���ȋƖ��̂ЂƂ��B
�ꍇ�ɂ���Ă͕ҏW�Ҏ��g���������̌��e�����A����ɐԓ�������Ă��炢���e���d�グ�邱�Ƃ�����B���̈ʂ̂��Ƃ��o���Ȃ��ƕҏW�҂͖��܂�Ȃ��B���������ҏW��Ƃ̖ʔ������ǂ����Ĕ���Ȃ��̂��Ǝ��Ȃǂ͎v���Ă��܂����c�ǂ����e�Ƃ����͓̂ǂݎ肪��ȉƁE��i�E���t�ƁA���邢�͊y��ɑ��ĕ���������X�ɑ������Ă����B�Ƃ�킯���e�I�ɐ��m�ŁA�V�����m���E���_��ǎ҂ɗ^���Ă����Ȃ�\�����Ȃ��B����䂦�ɕҏW�҂͍�ȉƁA�W�������A���t�ƂƂ������e�[�}���ɁA��������S���Ă���悤�ȕM�҂���Ƀ`�F�b�N���Ă���K�v������B����Ȓ��ŁA�������R�[�h��ЂŕҏW�Ɩ���S�����Ă������̓p�\�R���ȂǕ��y���Ă��Ȃ��������Ƃ�����A�l�X�Ȏ��M�҂̕��X�Ǝ��ۂɉ���Ă��b������@������Ă��͎̂����̍��Y���Ǝv���Ă���B
���������ɕҏW�Ɩ��ɂ�����肪�Ȃ���A����ȓw�͂�����������̗ǂ��A�C�S�̒m�ꂽ�A�g������̗ǂ��M�҂ɔC���������������ɋC�͊y���B�u�ƊE�̉��l�ς����L���A�������̂Ȃ����e�߂Ă�����������ł����v�Ƃ����l����Ȃ�ҏW�Ɩ��͈ӊO�ƊȒP��������Ȃ��B����������w�i�ɉ�����e�͂��̓��e�]�X�͂��Ă����ꕔ�̕M�҂̊������Ɖ�����P�[�X����������悤���B
�Ƃ͂����������R�[�h��Ђɋ߂Ă������ォ�炷�łɊC�O�̃��[�x���̏d�����`�S���҂���u���{��ʼn���̕ҏW�Ɩ���M�S�ɂ���ɂ���������ꖇ�ł������b�c�邽�߂̃v�����[�V�����ɂ����Ɛ����o���v�ƁA�������������ꂽ���Ƃ����x���������B����҂������Ă݂Ȃ�����̗ǂ�����������Ȃ��b�c�u�b�N���b�g��A�R���T�[�g�ɍs���Ȃ���Γ���ł��Ȃ��v���O�����̂��߂̕ҏW��Ƃ́A���̉��l���Z�[���X�ɒ��������]������Â炢�̂�������Ȃ��B�������C�O�̃}�C�i�[���[�x���ɂ͕ҏW��Ƃō��ł��������Ă����Ђ����Ȃ��Ȃ��B�Ƃ�킯��ʓI�ł͂Ȃ����p�[�g���[��A�[�e�B�X�g�Ɋւ��āA�u�b�N���b�g��ǂ�ł���ƒʏ�̉��y�j���⎖�T���ł͌����čڂ��Ă��Ȃ��悤�ȋM�d�ȏ�����邱�Ƃ������̂��B
�������A���{�̃N���V�b�N���y�ƊE�̂قƂ�ǂ��������ƌ�������͖ѓ��Ȃ����A�ҏW�Ɩ��̐��ނ͖��炩�ɐi��ł���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B���ꂾ���ɍŋ߂ł̓R���T�[�g�̃v���O�����⍑���Ղb�c�̃u�b�N���b�g�ŕM�҂̗͂̓��������e��A���J�ȁu�ҏW��Ɓv�ɏo�����Ƃ܂�ŕł����������悤�Ɋ������Ȃ��Ă��܂��B
��������������������
http://www.news-pj.net/npj/kobayashi-midori/index.html
�@
���̋L����ǂl�͂���ȋL�����ǂ�ł��܂��i�\���܂�20�b���x���Ԃ�������܂��B�j
�@
�����̃y�[�W�̂s�n�o���@�@�@�@�@ �����C���� > ����2�f����
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B���ׂẴy�[�W�����p�A�]�ځA�����N���������܂��B�m�F���[���͕s�v�ł��B���p�������N��\�����Ă��������B