| Tweet |
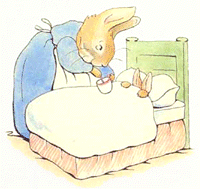
2009-12-21 15:36:02 受験競争と企業戦士を育てる日本の教育システムに反発していた18歳の飛幡祐規(たかはた・ゆうき)さん、ある日、仏語専門学校の留学案内を見て、「地方の人が東京の大学に出るのと同じ感覚ではないか」とフランス行きを決意した。「母親だけが賛成してくれました」。以来、在仏三十年以上、ジャーナリスト、作家、翻訳家として活躍中。その飛幡祐規さんが、「パリの窓から」なる連載通信記事をレーバーネットに寄せている。 <参照> ======================================== 第7回・09年12月15日 この作品は、フランス人にまじって生活をつづけながら、ユダヤ人の立場から迫害の現実を描いた史料として価値が高いうえに、序文で作家のパトリック・モディアノが指摘しているように、文学性にもすぐれている。1942年の4月から始まる日記の最初の部分は、21歳のパリジェンヌのみずみずしい生命力と幸福感に溢れているが、彼女の生活はユダヤ人迫害という不気味な影に急速に覆われていく。その年の6月以降、フランスのユダヤ系の人々は「黄色い星」を着用しなければならなくなった。それから2週間たらずでエレーヌの父親は逮捕され、パリの北郊外ドランシーにある収容所に拘禁される。ユダヤ人迫害の現実を日々、具体的に認識する一方、ソルボンヌで知り合った青年ジャンに対するエレーヌの恋心は高まり、やがて恋愛の歓びに包まれたのも束の間、彼はフランス解放軍に参加するためにパリを去ってしまう。 この恋愛によって日記にはたぐいまれな悲劇性と美がもたらされるが、恋愛はエレーヌが日記を書きつづけるための大きな原動力ともなった。1943年の秋以降、日記の後半でエレーヌは、ユダヤ人迫害の事実を後世に残すために記すとともに、老人や子どもまで強制移送する信じがたい迫害の意味を問い、キリストの教えやユダヤ教、戦争について考察する。彼女は、自分の考えたことを愛するジャンに知ってもらわずに消えたくないと、ジャンに宛てて、自分の魂をこめた文章を綴った。身に迫る危険と恋人や親友の不在という大きな孤独のなか、共感するキーツやシェリーの詩、『チボー家の人々』エピローグのアントワーヌの日記を引用し、哲学的な思索を深めるエレーヌの精神性の高さと人類愛に、読者は心を打たれずにはいられないだろう。 エレーヌは、家族や愛する人を失ったユダヤ人、拘禁され、殺されていく人々全員の苦悩を思って心を痛め、ごく少数の例外をのぞく「他の人たち」(ユダヤ人以外のフランス人)がそれを知らないこと、知っていても理解できないことに悩む。大多数の人間は、身近な人の不幸にしか心を動かされず、哀れみや同情を示しても、真の共感を抱くことはできないーーエレーヌのこの指摘は、ユダヤ人迫害にかぎらず、他者への真の共感(連帯感)、友愛とは何かという本質的で普遍的な問いかけだと思う。日記で絶えず繰り返されるこの問いかけを、多くの人に考えてもらいたいと願いながら、わたしはこの本を訳した。 この作品はまた、ナチスに積極的に協力したヴィシー政権時代のフランスの様子が、個人の体験・見聞をとおして描かれている点でも貴重だ。文学的・芸術的な感受性だけでなく、明晰な思考力も備えていたエレーヌは、つとめて冷静にユダヤ人迫害の現実や人々の反応を記した。それらの描写によって、これまで抽象的にしかとらえられなかった事象、たとえば「黄色い星」を着用させられたユダヤ人の心の葛藤やまわりの人々の反応が、具体的に読者にせまってくる。そして、フランスでのユダヤ人迫害と死の強制収容所への大量移送が自国の警察と憲兵の加担によってなされたこと、大多数の人々の無為・無関心がそれを許したということが、この日記を読むとよくわかる。ユダヤ人をかくまい、援助した人々ももちろん出てくるが、エレーヌが記したように、キリスト教会をはじめ大勢の国民が初めからヴィシー政府のユダヤ人差別法に反対していたら、大量のユダヤ人の逮捕、拘禁と強制移送はできなかったはずなのだ(フランスから強制移送されたユダヤ人は約76000人、国内での死者も入れると8万人以上。戦前フランスに住んでいたユダヤ人の約4分の1にあたる)。その証拠に、ナチス・ドイツの要求するユダヤ人強制移送に政府、聖職者、国民の大多数が反対したデンマーク、フィンランド、ブルガリアでは、ユダヤ人絶滅計画の犠牲者はほとんどいなかったのである。 レジスタンス運動とド・ゴール将軍が率いたフランス解放軍によって戦勝国になったフランスでは、国民の大多数がレジスタンスに参加したという神話がつくられ、戦後四半世紀近く、ヴィシー政権時代について語ることはほとんどタブーだった。しかし、1970年代以降はこの時代についての歴史学者や市民の研究・調査が進み、暗い過去にもきちんと向き合おうとする動きが高まった。1995年、シラク大統領はユダヤ人迫害と大虐殺におけるフランス国家の罪を初めて認める演説を行い、現在ではこの歴史認識が(一部の歴史修正主義者をのぞけば)深まっている。 暗い過去を直視する歴史認識をもつことは、現在の民主主義の危機を感知し、防ぐ行為につながるかもしれない。たとえば、11月中旬からフランスの政府は「国(民)のアイデンティティについての討論」なるものを全国的に組織しようとしているが、政府主導のナショナリズムが臭う似非「討論」に対して、哲学者や歴史学者などからたちまち批判の声があがった。この「討論」をオーガナイズしているのは、サルコジが大統領になってすぐ、2007年に新設した「国(民)のアイデンティティ・移民省」だ。設置に際しても、「国(民)のアイデンティティ」と「移民」を結びつけるのは、移民を問題視・敵視する危険な考え方だと批判されたが、この省は実際、「サン・パピエ」と呼ばれる滞在許可証をもたない外国人の国外追放(年に27000人)を目標に掲げている。 この省が各県知事に「討論」開催のために送った通達(質問のお膳立て)には、「フランス人のアイデンティティはこれだ」という作成者の見え透いた前提と、外国人を問題視する偏見が溢れているため、11月24日付けのル・モンド紙で「国(民)のアイデンティティ:外国人嫌悪の表現をとおして設定された討論を拒もう」と題する声明文が発表され、法学者、社会学者、NPOの責任者、聖職者、今年のゴンクール賞を受賞した作家のマリー・ンディアイなどが署名した。12 月2日には、インターネット新聞メディアパールのサイトで「私たちは討論に参加しない」と題する署名運動が始まった。「この討論は、政府が質問を提出して回答を統制するものだから自由がなく、私たちの国の多様性を一つのアイデンティティに縮減しているから複数性に欠け、いたずらに分断をもたらして外国人を非難するものだから有益でもない。国家が私たちの代わりに何が私たちのものであるかを定義するのを受け入れたら、専制と服従への道を開くことになる」という内容の声明文に、学者や文化人、政治家(主に左翼だが保守の元ドヴィルパン首相も)、俳優、その他さまざまな職業の市民200人が連名し、12月14日現在、既に37000人以上が署名している。 つづいて12月4日付のリベラシオン紙上では、哲学者のエチエンヌ・バリバール、社会学者のリュック・ボルタンスキー、歴史学者のツヴェタン・トドロフなど20人の学者が、「国(民)のアイデンティティと移民省」の撤廃を要求する声明を発表した。この省が推進するサン・パピエの国外追放の目標数を達成するために、警察はメトロの出口などでサン・パピエを狙った「一斉検挙」を行い、子どもまで不法滞在者用収容施設に閉じこめ、「外国人らしき」面相の人に対して頻繁に身分証明書検査を行い、アフガニスタンなど戦争中の国にも亡命者を追放している。声明文は、政府が進める「国家という観念の民族主義による拉致」に対して、共和国の基盤をなす普遍的な理想を再び主張しなければならないと述べ、民主主義を危うくする「国(民)のアイデンティティと移民省」の撤廃を強く要求している。 サルコジは前保守政権で二度内務大臣をつとめたときから一貫して、移民規制をどんどん強化する政策を進めてきた。それに対して、従来の人権擁護や外国人援助の団体に加え、サン・パピエの子どもたちを庇護する「RESF国境なき教育網」という市民運動網が2004年につくられ、外国人の子どもや彼らの親が国外追放されるのを阻止しようとしている。すべての子どもが教育を受け、人間らしい暮らしができるようにという「子どもの権利条約」の倫理にのっとり、彼らは子どもたちを「法を犯してでも庇護する」と宣言している。 民族大虐殺につながったユダヤ人迫害と現在のサン・パピエたちの困難には大きな差異があるが、文化人類学者のエマニュエル・テレは、フランス行政の態度に焦点をしぼると、収容施設への拘禁や検挙などの手段や、追放後の人間の運命に全く無関心な非人間性など、類似点を見ずにはいられないと言う。エレーヌ・ベールは日記に綴っている。「乳母にあずけられた二歳の赤ちゃんを、収容所に入れるために逮捕しに行けという命令にしたがった憲兵たち。これこそ愚鈍に陥り、道徳意識を完全に失ったわたしたちの状況を示す、もっとも嘆かわしい証拠ではないか。(……)良心とは無関係に、正義、善意、慈悲とは無関係に義務というものを考えるようになったなんて、それはわたしたちのいわゆる「文明」が空虚である証拠だ。」 「民主主義国家でも不当な法律がつくられることは、歴史が示している」と声明文に記した「国境なき教育網」の市民たちには、ヴィシー政権時代のユダヤ人迫害だけでなく、フランス軍がアルジェリア戦争の際に行った拷問や、アメリカ合衆国の人種差別法などの歴史認識がある。「そうした時代、耐え難い迫害を目の前にして、ひとりひとりは選択をしなくてはならなかった。そして、選択しないことは黙認することだった。(……)私たちの名のもとに卑劣な行為がなされることを許してはならない」。 2009.12.14 飛幡祐規(たかはたゆうき) ======================================== 【関連記事】 Student's diary tells of occupied Paris(USA TODAY) France's Own Anne Frank Hélène Berr, l'autre Anne Frank(lepoint.fr)
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10416209840.html から転載。
gataro-cloneの投稿
パリの窓から〜エレーヌ・ベールの問いかけ【レイバーネット】
テーマ:人権の歴史
パリ通信/飛幡祐規
連載「飛幡祐規 パリの窓から」第7回/エレーヌ・ベールの問いかけ 10月の末に『エレーヌ・ベールの日記』という訳本を上梓した(岩波書店)。第二次大戦中、ナチス・ドイツ占領下のパリで、ユダヤ系の若いフランス女性が綴った日記の翻訳である。ソルボンヌ大学で英文学を学んでいたエレーヌ・ベールは、ユダヤ人に対する迫害が強まってもパリにとどまり、家族を失ったユダヤ系子どもたちの世話や、彼らをかくまわせる活動をしていたが、1944年の3月、両親と共に自宅で逮捕され、アウシュヴィッツの強制収容所に送られた。両親が殺された後も彼女は生きのびて、ドイツのベルゲン=ベルゼン収容所に移送されるが、1945年の4月初め、この収容所が解放される数日前に24歳で非業の死を遂げた。
10月の末に『エレーヌ・ベールの日記』という訳本を上梓した(岩波書店)。第二次大戦中、ナチス・ドイツ占領下のパリで、ユダヤ系の若いフランス女性が綴った日記の翻訳である。ソルボンヌ大学で英文学を学んでいたエレーヌ・ベールは、ユダヤ人に対する迫害が強まってもパリにとどまり、家族を失ったユダヤ系子どもたちの世話や、彼らをかくまわせる活動をしていたが、1944年の3月、両親と共に自宅で逮捕され、アウシュヴィッツの強制収容所に送られた。両親が殺された後も彼女は生きのびて、ドイツのベルゲン=ベルゼン収容所に移送されるが、1945年の4月初め、この収容所が解放される数日前に24歳で非業の死を遂げた。
(クリックすると画像拡大)
Helene Berr's Holocaust Diary Flies Off the Shelves(SPIEGEL)
|
|
|
|
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
|
|
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。
|
|
|
|
|
|
|
|