| Tweet |
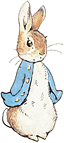
【帝国の衰退について】-----(ル・モンド・ディプロマティーク日本語・電子版2008年11月号)
エリック・ホブズボーム(Eric Hobsbawm)
歴史家
訳:三浦礼恒
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
16世紀にはスペインが、17世紀にはオランダが、強力な帝国を築き上げた。
だが、グローバル化した帝国、すなわち世界中に散らばった資源を支えに、軍事基地網を張りめぐらせ、国際的な野心を誇示することのできる帝国の事例は、18世紀から20世紀半ばまでの英国と、20世紀半ば以降の米国の2つしかない。
英国の力の源泉は海軍力の優越性であり、米国のそれは爆撃による破壊能力である。
とはいえ、軍事的な勝利だけで帝国の長期的存続が保障された事例はひとつもない。(・・・)
英国と米国はいずれも、もうひとつの切り札を持っていた。
それは、グローバル化した経済という枠組の中でしかありえないものだ。
すなわち世界の産業の支配である。
まず、大規模な生産機構を備えていたことで、両国は「世界の工場」となる。
1920年代を通じて、それから第二次世界大戦の後、全世界の工業生産の約40%を米国が占めるようになった。
今日においても、この比率は22%から25%の間で推移している。
2つの帝国は、他国が模倣しようとする手本でもあった。
両国は国際貿易の要となり、その予算や金融、通商に関わる決定は、国際貿易の内容、物量、方向を左右した。
さらに、英語の使用の途方もない拡大などを通じて、度はずれの文化的影響力を行使した。(・・・)
両国の間には、こうした共通点以上に、数多くの相違点がある。
最も明白なものは国土の面積である。
英国は島国であって大陸ではないから、米国的な意味における国境を持ったことがない。
様々なヨーロッパの帝国の一部になったことはある。
ローマ時代や、ノルマンディー公による征服後、そして短期間ながら1554年にテューダー朝のメアリー1世がスペインのフェリペ2世と結婚した際のことだ。
だが、英国はそれらの帝国の中心の座を占めたわけではない。
国内の人口が過剰になると、国外への移住や植民地の建設が開始され、ブリテン諸島は移民の一大輩出地となった。
逆に米国は、本質的に移民の受け入れ地である。
その広大な領土は、国内人口の増加と、移民の大波によって満たされた。
移民の中心は1880年代までは西ヨーロッパの出身者だった。
米国はロシアと並んで、ディアスポラを形成することのなかった唯一の帝国である。(・・・)
国土と大陸がほぼ一致していることを基本とした拡張の論理的帰結、それが米帝国である。
高い人口密度に慣れていたヨーロッパからの移民の目には、アメリカは無限かつ無住の地と映ったに違いない。
入植者が持ち込んだ病気が、故意によるものかはいざ知らず、広がったことで現地民がほとんど壊滅したために、そうした印象はいっそう強められた。(・・・)
とはいえヨーロッパ人が、この地を神から与えられたという確信をさておいても、自己流の経済システムと集約農業を強行するために、遊牧民族を端的に一掃することは必然のなりゆきだった。
したがって、米国憲法は、「自由の恩恵にあずかる自然権」を享受する人々からなる政治体から、先住民を明示的に排除している。(・・・)
英国およびヨーロッパ全般とのもうひとつの相違点は、米国が、同等の勢力を持つ国々からなる国際システムの一員だという認識を持っていないことだ。
植民地という概念も、米国の見解とは相容れない。
カナダを含む北米大陸全土はいずれひとつの国になるべきものだからだ。
それゆえ、ハワイを別として、それまで人が住んでいなかった地域や、既にアングロサクソンが入植していたプエルトリコやキューバ、太平洋の諸島のような地域を、米国が本気で自国に組み入れようとはしたことはない。
大陸国家たる米国の海外における覇権が、大英帝国あるいは英連邦のような形をとることはありえなかった。
世界中に入植者を送り出すこともなかったから、現地民の参加あるいは排除の下に、次第に自治権を獲得した白人植民地、つまりカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカのような自治領を作ることもなかった。
南北戦争における北軍の勝利以降、合衆国からの分離独立は、法的、政治的に、またイデオロギー的にも考えられなくなった。
国境を越えた米国の勢力の表出は、衛星国あるいは従属国のシステムという形をとることになる。
【イデオロギー的な自己規定】
英国との第二の根本的な相違点は、米国の源流が、おそらくは啓蒙の世紀の希望に突き動かされた一連の革命にもまして、長期にわたって続いた革命にあることだ。
米国の帝国化が必然だったとすれば、その出発点は、自分たちの「自由」な社会が他のあらゆる社会より優れており、したがって世界中の手本になるべきものだという救世主的な信念にある。
アレクシス・ド・トクヴィルが理解したように、そのような企図は政治的にはポピュリズム、反エリート主義の方向に向かわざるをえない。
英国でも、16世紀と17世紀にイングランドとスコットランドが革命を経験している。
だが、これらの革命は長続きしなかった。
革命を経て生まれたのは、近代化を志向しつつも極めて階級的で不平等な資本主義体制であり、地主の名家による統治が20世紀まで続いた。
英国は当然ながら、他国の社会に対する優越性を確信していたが、救世主的な信念を持たず、異国の民に対し自国流の統治方式はおろか、プロテスタント信仰への改宗も迫るつもりはなかった。
大英帝国は宣教師によって築かれたわけでも、宣教師のために築かれたわけでもない。
第三の相違点は、11世紀にドゥームズデイ・ブック(1)を作成して以来、イングランド王国(1707年以降はグレートブリテン)が、極めて中央集権的な司法システムと政府を中核として、ヨーロッパ最古の国家を形成したことだ。
自由を重んずる米国では、中央政府はもとより、あらゆる国家機関が敵視され、権力分立による機能不全が意図的に仕組まれている。(・・・)
もう一点、忘れてはならない根本的な相違点は、両国の年齢である。
国民国家には国旗や国歌に加え、自己の歴史の中に見出すべき建国神話が必要だ。
だが、米国には、イングランドや革命を経験したフランス、あるいはソ連などとは異なり、まだ神話を汲み出すほどの歴史がない。
清教徒たちは自らを先住民とは異なる存在であると規定した。
建国の父祖が謳った「人民」からは、そもそも先住民は奴隷とともに除外されている。
したがって、アメリカには最初に入植した英国人よりも古い先人がいない。(・・・)
さらに、米国は、英国を相手どった革命戦争を通じて自己を規定した。
かつての祖国との唯一受け入れられるつながりは、言語だけに限られるようになった。
それゆえ、非アングロサクソン系移民が大量に流入する以前でさえ、米国の国民意識が英国と共通の過去から構築されることはありえなかった。
米国の国民意識を構築したのは、その革命的イデオロギーと共和主義的な新機構にほかならない。
ヨーロッパ諸国の多くは、隣国や敵国との関係において自己を定義した。
南北戦争以外に存亡の危機に見舞われたことのない米国は、敵を歴史的な観点から規定することができ
ず、イデオロギーの観点からしか規定できない。
つまり、米国の生活様式を拒絶する人々を敵と見なす。
両国の相違点は、帝国となった場合でも国家の場合と変わらない。(・・・)
英国にとって、厳密な意味における帝国、あるいは非公式な帝国という形態は、経済的な成長と国際的な勢力の要素をなすものだった。
米国においては全く異なる。
米国が下した最も重要な決断は、諸国家のうちのひとつになるのではなく、大陸規模の大国になることだった。
海洋ではなく、陸地こそが、米国の発展に重要な役割を果たした。
米国は常に拡張主義的ではあったが、本国の規模のつつましさゆえに拡張主義に走った16世紀のカスティーリャやポルトガル、17世紀のオランダ、あるいは英国のような海洋帝国の拡張主義とは流儀を異にした。
米国はこれらの国よりもロシアに似ている。
ロシアもまた平原を通じて、バルト海から黒海、太平洋の間に、「ひとつの海から別の海まで」広がる平原を通じて、自国の影響力を広げていった。
たとえ帝国の領域がないとしても、米国は西半球で最大、世界でも第3の人口大国である。
逆に、帝国の領域を除いた英国は、世界人口の4分の1を統治していた頃から十二分に自覚していた通り、中規模経済の諸国のひとつにすぎない。
【大英帝国の教訓】
さらに重要な点がある。英国経済が国際貿易の大半に関わり合っていたことだ。
この帝国は19世紀の世界経済の発展の中心的要素だった。
1950年代まで、英国による巨額の投資のうち、少なくとも4分の3が発展途上国に向けられていた。
両大戦間期には、輸出の半分以上が勢力圏内の地域に向けられていた。
ヨーロッパと米国の工業化が進むにつれ、英国は世界の工場ではなくなったが、国際輸送網の盟主の座を保ち、世界の仲買人、世界の銀行家、最大の資本輸出国であり続けた。(・・・)
米国経済は、世界経済との間にこれほど象徴的なつながりを持ったことがない。
だが、突出した世界最大の工業国であり、巨大な国内市場ひとつとっても、大きな影響力がある。
技術革新や労働の組織化の分野で上げた成果によって、米国は1870年代以降、とりわけ世界最大の大量消費社会となった20世紀には、手本として仰がれるようになった。
両大戦間期まで、極めて厚く保護されていた米国経済は、主に自国資源と国内市場によって発展していった。(・・・)
旧世界に対する新世界の経済的支配は、冷戦期に確立した。それが今後もずっと続くと言明できる根拠はない。(・・・)
既に工業化が広く進展し、また依然として最大の資本輸出国だったヴィクトリア時代の英国は、ヨーロッパと米国の工業化への対処策として、投資先を帝国の勢力圏内へと大きく転換した。
21世紀の米国には同様の可能性はない。(・・・)
グローバル化した世界において、米国の文化的支配と経済的支配は同義でなくなりつつある。
米国はスーパーマーケットの発祥国だが、ラテンアメリカと中国を征服したのはフランスのカルフール・グループだ。
英国との決定的な違いの結果、米帝国は自国経済を支えるために、常に腕力を振るわなければならなかった。
仮に、冷戦の要請に従う「自由世界」という条件がなかったとしたら、米国はその
経済規模だけで世界の手本となりえていただろうか。
米国の金融格付機関や会計基準、ビジネス法の支配を確立できていただろうか。
国際通貨基金(IMF)と世界銀行の金科玉条である「ワシントン・コンセンサス」を規定できていただろうか。
大いに疑わしい。
以上に挙げた一連の理由により、大英帝国は、米国の覇権構想を理解するためのモデルと見なしうるものではない。
しかも、英国は自らの限界、特に軍事力の限界を知っていた。
世界の新興盟主の中の世界王者というタイトルを永遠に防衛できないことを知っていた中堅国の英国には、他のいかなる国も持ったことがなく、これからも持つことのないだろう広大な帝国領域があった。
だが英国は、全世界を支配することは不可能だと知っており、支配しようと試みたこともない。
英国は逆に、世界を安定化による繁栄に導こうと試み、自らの意向を世界各地に押しつけようとはしなかった。
20世紀半ば、海洋帝国の時代が終わりを告げた時、英国は他の植民地大国に先駆けて風向きの変化を感じ取った。
その経済力を軍事力ではなく貿易に依存していた英国は、帝国の喪失という事態にも、諸大国に比べて円滑に順応した。
かつて、史上最大の凶事となったアメリカ植民地の喪失に、やがて順応したのと同様である。
米国はこの教訓を理解するだろうか。
それとも、政治力と軍事力だけでグローバルな支配を維持しようとし、いっそうの無秩序と紛争、蛮行を生み出していくのだろうか。
* 本稿は、Eric Hobsbawm, Globalisation, democracy and terrorism, Little,
Brown, 2007 の仏訳書(2009年初頭にアンドレ・ヴェルサイユ出版とル・モンド・ディプロマティークの共同で刊行予定)からの抜粋である。
(1) ウィリアム征服王が作成し、1086年に完成した土地台帳のこと。王税の算定基準として用いられたと考えられる。
(ル・モンド・ディプロマティーク日本語・電子版2008年11月号)
All rights reserved, 2008, Le Monde diplomatique + Miura Noritsune
+ Okabayashi Yuko + Saito Kagumi
----------------------------------------------------------------------------
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。