| Tweet |
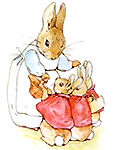
| 二年ほど前。ある大手新聞社の主催する会合に招かれて出席した。文か・教育・出版関係者などを主として、五百人近くも集まったはずである。 開会に当たって、主催者側から発言があり、「皇太子御夫妻が臨席されるので、一同起立してお迎え下さい」という。 突然で、しかも初めての経験なので、多少戸惑ったけれど、天皇と異なり、憲法上何の地位もない(つまり、ただの人)皇太子ではあっても、まあ客人を迎えるのの立って挨拶するというのならそれも礼儀というものだろうかと思い、私は人々に倣って起立した。 皇太子夫妻の入場が終わり、一同着席して式典が始まった。ある章の授与式である。主催者の開会の辞があり、次いで「皇太子のおことばをいただく」という司会の紹介があって、ふたたび、一同ご起立下さいという。 周囲の人々は、ためらうことなくもう一度椅子から立った。この瞬間、私の裡に嵐のごとき同様が襲った。立つべきであろうか。いや、立つ必要はない。立たなくては。ノウ、いけない、いけない。私も対等な客人の一人のはずである。 びっしり椅子の詰まった会場である。前にも、左右にも、人々はみな立っていて、もちろん座っている私に、講堂内の様子を見渡すことはできない。混乱し狼狽する目には、前に立つ人の灰色の背広の裾が、ぼうっと霞むように迫るだけである。 前方に声がして、もちろん皇太子が何事か読み上げているのだ。 私の胸はいっそうざわめきつづける。おれは立っていない。座っている。人々は立っている、おそらくひとり残らず。ただひとり、おれは座っている。立ったひとり、立つことを拒んで‥・・・。 「なぜ立たんのか。貴様は!」 私は、背中に浴びせかけられる罵声を、ぎゅっと固くした全身で待った。いま、いま、その声が頭上に落ちてくる。そら、いまだぞ。「非国民、立て!」 すべての毛穴が恐怖を吸い込み、ぶざまに沸き返る胸が、凍りつくようなおののき。 左の人も立っている。右の人も立っている。その隣もその隣も、前の列も、その前の列も、ずっとずっと、人々は立っている。 ああ、立とうとして腰を浮かしたとしても、恐らく私は立つことができなかったにちがいない。背後からの視線が、無数の憤怒と非難の矢となって私を刺し貫いているのだ。内から凍りつき、外からは架刑、私の五体。 小学校の校庭、中学校の講堂。私の記憶はいつも鮮やかだ。 白手袋をつけた校長の捧げ持つ白いものは、もちろん天皇の詔勅である。私たちは首をうなだれて、それを朗読する校長の緊張しきった音声を聞かねばならない。異様に作られたこの静寂の、いつ果てるとも思えぬ時間の中で、それが冬ならば、次々と洟をすする音だけが断続し、自分は何時洟をすするべきか、そのタイミングを、ともかくもできるだけと、耐えながら量りつづけ、ついに我慢できなくなってすすり上げ、ほっと息をぬすんだあの時間。 ・・・ カカッテ汝等青少年学徒ノ双肩ニアリ ・・・ 校長の声が、ときどき耳に入ってきて、「御名御璽」という最後の結びが、どんなに待ち遠しいものであったことか。 コツ、コツ、コツ、コツ。先ほど、同じように仰々しい態度で桐箱に入った紙筒を運んだ副校長が、もう一度壇上に立って、白布に包まれ、さらにその上を紫の袱紗で覆った詔勅を三宝に載せ、相互の交わされる最敬礼の後に校長から押しいただき、頭上に高く掲げたまま、一歩一歩後しざってゆく。 長い長い作為の時間が、廊下に副校長の足音が遠ざかってゆくにつれて溶け始め、足音が完全に消えたところで、吐息や、咳や、今度は大っぴらにすする洟の音が一挙に講堂を満たす‥・・・。 それは、中学校でのある式典のの日だった。式終了後そのまま、私たち四年生全員が講堂に残ることを命じられて。教師からさんざんに締め上げられたことがある。 一生徒が。来賓祝辞の最中、席にあって本を開いていたのだ。彼は最前列に引きずり出され、その本でなぐられ、平手でなぐられ、土下座して詫びさせられた。お前ら全員が腐っているのだと、予備役軍曹の軍事教練の教師は、一時間余りにもわたって私たちを怒鳴り立てた。 漸く解放されて教室に帰っていた私に呼び出しがかかった。林幹也というその生徒が開いていたいたのは、私が兄の本棚から抜いて彼に貸していた本だった。和辻哲郎『偶像再興』、岩波書店。 教練と体操の教員室に、林と私は立たされて、さまざまな追求に耐えねばならなかった。林の頬は赤くはれ、涙がそれを濡らしていた。 「何だ、これは。え、漫談哲学か-------」 たいそう教師が私に言ったことばは、意地悪くねちゃついた抑揚に乗って、私の耳に今も消えることがない。そしてそれを思い出す度に私は顔が赤らむ。 当時私は、国や社会のことについて何一つ疑いを持つ者ではなかった。勤労動員先の軍の施設では、天皇のため、勝つために。最も忠実な作業員たらんと努めていた平凡な一生徒に過ぎなかったのである。 皇太子のことばは終わり、私はことなきを得た。生き延びた---------。そんな実感が、人々の着席するざわめきの中で私の体の力を解き放ってくれた。しかし、背骨の髄のところは、永くしこったままだった。いまも、あの時間を反芻するたびに、凍りつく背筋の感覚が甦る。この怖しさを、どのように人に伝え得るのか、私にはわからない。 被害妄想と、人々は笑うにちがいない。しかし被害に気づくのにも、時間というものが必要だと私が悟ったのは、敗戦以後、飢餓や寒さの冬を、天皇という憑きもの落ちて虚脱した精神の冬とともに、いくたびか経た後のことであった。 あれらの日々から三十年の余を経ている。十年一昔、既に大昔のことではないか。 そうではないのだ。皇太子のことばの前に人々の立ったのは今日のことである。従って昨日のことであり、明日のことでもあるのだ。 私は夢を見ているのだろうか。天皇の呪縛を解かれた戦後の三十年というのは、ほんの一晩の浅い夢であったのか。私はそれを林幹也に聞きたい。私の同級生たちに聞きたい。すべて、三十年前を生きた人々に聞きたい。 |
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。