| Tweet |
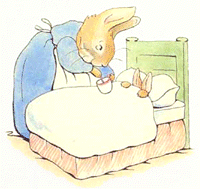
http://money.mag2.com/invest/kokusai/2008/06/post_67.html
米国勢を襲う「時価会計の爆発」が、サブプライム問題とどめの一波に?
時限爆弾としての「時価会計」
主に米国からの圧力によって日本にも導入された会計原則の1つに「時価会計」がある。平たく言えば、ある企業が持っている資産や負債を、計算するタイミングできっちり算定すべし、という原則だ。
一見したところ当たり前のように思えるこの時価会計であるが、実は“当たり前”では決してなかった。日本の大企業たちは、90年代までグループ企業の株式を相互に持ち合っていた。いわゆる「持ち合い株」である。日本においては、株式を取得した段階での株価がベースとなる会計処理を行えば良いとされていた。そのため、グループ企業の株価が下がったとしても、これをマーケットで売りさばくまでは、その株を持っている企業自身の財務体質が「悪化した」とは言われることはなかったのである。
ところが時価会計が外圧によって導入され、事情は一変する。なぜなら、持っているグループ企業の株価が暴落したら、その分だけ正直に“実態としての損失が生じた”と公表しなければならなくなったからである。事実、「小泉構造改革」の中、強烈な株価下落に見舞われた日本の大企業たちは、時価会計に悶絶するかのように、続々と持ち合い株の解消を行い始めた。その結果、投売りが投売りを呼ぶ展開になったことは記憶に新しいことであろう。
時価会計が導入された当時、“これは米国からの仕掛けだ”といった議論が横行した。何を隠そう、私自身もこの議論を支持してきた経緯がある(拙著『騙すアメリカ 騙される日本(ちくま新書)』参照)。
しかし、今、この時価会計という大原則がその提唱者であったはずの米国、そして欧州のファンドや投資銀行といった「越境する投資主体」たちを飲み込もうとしつつあるのだ。その様子は金融資本主義の中に密かにセットされた“時限爆弾”にも似ている。
なぜなら、一度は時価会計を日本等に無理強いして「勝ち組」を気取った欧米の「越境する投資主体」たちであるが、今度は自らがその餌食となりつつあるからである。そこに仕込まれた仕掛けは余りにも密やかであり、巧妙なものであるが、確実に今あるシステムを炸裂させ、大転換させる威力を持つものだ。
19世紀後半にドイツで大混乱を巻き起こした「時価会計」
具体的にご説明しよう。私が率いる研究所が去る2日に発売を開始した「IISIAマンスリー・レポート」2008年6月号においても詳細に記したのであるが、今年6月後半以降、7月末から8月初旬までの間に、マーケットは米国発の「瓦落(がら)」を迎える可能性が高い。なぜなら、米系の「越境する投資主体」たちが、4月11日にワシントンで行われたG7会合の結果を踏まえ、“本音の赤字”を提示しなくてはならなくなる公算が高まっているからだ。
このG7ワシントン会合で定められた原理原則の内、もっとも中心に据えられているのが、他ならぬ「時価会計の徹底」である。実のところ米国勢は日本勢など他人に対しては時価会計の徹底を大声で求めつつ、米国の国内では、投資目的で作られた子会社の決算は、時価会計にしたがって連結決算で公表しなくても良いなど、手前勝手なルールを運用してきている。
「そのおかげでサブプライム・ショックは乗り切った」などといった議論もあったのだが、こうした手前勝手なルールがもはや適応できなくなれば、話は全く異なってくる。“乗り切った”どころか、“真実の時(moment of truth)”はむしろこれからということになるのだ。そしてそれが、2008年2月〜5月期の決算を「米系越境する投資主体」たちが続々と発表する6月後半にやってくる可能性が高いというわけなのである。
余り知られていないことであるが、ちなみにこの「時価会計」、米国の発明ではないことをご存知だろうか?実は国家統一に向けて法典整備を急いでいたドイツにおいて、今からさかのぼること147年前の1861年に導入されたのである。確かにいかにも「きっちり計算する」のが好きなドイツ人が考えそうなことではある。しかし、この原則、その直後より大変な大混乱をドイツ経済で巻き起こすことになる。
私も言論人であると同時に、独立系シンクタンクという私企業の経営者であるので日々体感していることなのだが、日々のマネーのやり取りは決して取引の瞬間に全てが完結するものではないのである。入金が前後したり、支払いを延ばしてもらったりと、「時価」では説明がつかないのが企業経営なのである。当時のドイツでも事情は全く同じであり、この「時価会計」は1884年に廃止された。そして、この流れを受け継いだ日本でも当然「時価会計」を知らない企業会計原則が作られていったというわけなのである。
ところが今度は米国が圧力をかける形で世界中に「時価会計」が植えつけられた。なぜなら、そうすることによって本来であれば何ら問題のなかった企業会計に対して「巨額の損失」という風穴を開け、ひいてはファンドや投資銀行、監査法人といった「破壊ビジネス」の立役者たちが大立ち回りを演ずることができたからである。
正に「歴史は繰り返す」である。今、米系の「越境する投資主体」たちこそが「時価会計」の徹底という要求で絶体絶命のピンチにある。その一方でどうやら欧州勢もスネに傷が無いわけではないようだ。「『時価会計』は逃避なのか?それとも救いなのか?」といった声が、たとえばスイスから上がり始めている(5月31日付「ノイエ・チューリッヒャー」新聞参照)。「時価会計」に対しては大いに批判的な論調だ。欧州勢としても、これを徹底されてしまっては巨額の損失を明らかにせざるをえなくなるというわけなのだろう。
「時価会計」という時限爆弾は、150年の時を超え、いよいよ炸裂寸前になっているのだ。
歴史を学ぶことで生き残りの戦術を探る
時空を超えて連鎖反応を起こしつつある「時価会計」。この問題も含め、これから始まるシステムの大転換について、私は6月28日に神戸・大阪、7月5・6日に東京・千葉でそれぞれ開催するIISIAスタート・セミナー(完全無料)でじっくりお話できればと考えている。
私がこのコラムで「金融インテリジェンス」の最前線についてご紹介するのに対し、「紹介される事例が欧州、特にドイツに由来するものが多いのはなぜか」という声を頂くことがたまにある。時には「たとえば英国の有名経済紙を読んでいれば事は足りるのではないか。ドイツ事情を知る必要など全く無い」といった“暴言”まで聞こえてくることすらある。
しかし、考えてみていただきたい。たとえば「越境する投資主体」の典型であるゴールドマンサックスは、そもそもドイツ系移民が19世紀に米国で設立した企業なのだ。つまり、その頃、資本主義は米国へと“移植”されたのであって、その本家本元であるドイツにおける事情をつぶさに知らなければ、金融資本主義の今を本当に理解することはできないのである。
ところが、そうした「真実」を私たち=日本の個人投資家に知られては困るのであろう、欧米を股にかけた金融資本主義の真の歴史について記した研究、もっといえば、分かりやすく、かつ「それではどういった戦略で今のマーケットに臨めばよいのか」という切実な要望に応える書籍は日本にはほとんど無いのである。
だが、この「時価会計」をめぐる歴史からもお分かりいただけるとおり、歴史を学ぶものだけが今を生き残るための戦術を会得することも出来るのではなかろうか。このコラムでも引き続き、こうした観点からの探求を読者と共に行っていきたいと考えている。なぜなら、それは「遠い道のり」のように見えて、マーケットの“潮目”を乗りこなすにあたって最も「近道」であるように感じられてならないからだ。
2 81 +−
▲このページのTOPへ HOME > 政治・選挙・NHK51掲示板
フォローアップ:
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。