| Tweet |
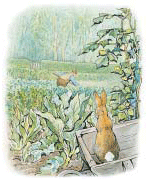
フランス労働法、世紀の改悪ジェラール・フィロッシュ(Gerard Filoche)労働監査官訳・日本語版編集部経営陣の法的責任はどんどん軽くなり、従業員はますます保護されなくなる。これがフランス政府の決めた変化の方向だ。たとえば、2月中旬に法相に提出された報告書では、ビジネス関連の不正行為(業務上横領など)を刑事罰の対象から外すことが提唱されている。こうした流れの中で、雇用契約をかつての随意契約の形に戻し、労働組合が勝ち取ってきた保護規定を無に帰せしめる新労働法典が、よりによって5月1日という日に施行を予定されている。[フランス語版編集部] フランス企業運動(MEDEF)のローランス・パリゾ会長は率直だ。「労働法典が始まるところで、思想の自由は停止する(1)」。別の言い方をすれば、「人生も健康も愛情も、不安定なものだ。労働がこの法則に従わない理由があるだろうか(2)」ということだ。フランスでは最近、労働法を「定常化」して簡素化するものだと称する「抜本改正」が実施された。上記のパリゾ発言が、いかに本人が否認しようと、為政者を動かしたことは言うまでもない。 9巻からなっていた労働法典は、全面的に8部構成に組み替えられた。文字数は10%減ったが、細目の数は271から1890に、条文の数は1891から3652に増えた。すべての条文が切り刻まれ、4ケタの新しい番号に付け替えられた。この新法典によって、過去の進歩的な判例の見直しへの道筋が開かれた。こうしたリライトは、労働法典の理論と実践の本質にかかわるものだ。500件の法律規定の全文または一部が、政令規定に格下げされている。 「法典再編」の原則は、2004年12月9日の法律によって打ち出された。続く2005年2月16日、法典再編高等委員会の中に、ラルシェ労働関係担当相が5人の識者(3)、労働組合の代表(各組織から2人ずつ)、経営者団体の代表からなる関係部会を特設した。MEDEF寄りの弁護士事務所の代表が最後まで審議を続けたのに対し、労組の代表は次第に疎外され、不満を募らせていった(4)。官僚が実務を担い、協議もなく、強行突破された法典リライトの責任者は、ド=ヴィルパン首相とサルコジ国務大臣(いずれも当時)である。2007年2月、5大労組は一致して、新法典の公布をやめろという「要求」を突き付けたが、なんの効果も得られなかった。同年3月7日、大統領選の真っ最中、報道がまったくないまま、964ページものオルドナンス(国会追認を要する政府立法)が閣議決定され、同12日の官報に掲載された。 あらゆる法律文書の中でも、労働法典はことに機微に触れるものだ。そこには130年間にわたる労使の力関係の変化が刻まれている。労働法典は、汗と涙と血の結晶である。条項、政令規定、大臣命令の一つ一つが、闘争や厳しい交渉、細部に至るまでの合意形成、賛否の割れた国会表決から生まれたものだ。多くの文言が、句読点の打ち方一つに至るまで入念に書き上げられてきた。労働法典の役割は、あらゆる雇用契約につきものの「雇用主への恒常的な法的従属関係」を補償することにある(6)。ひとたび会社の門をくぐると、雇用主が決定し、従業員はそれに従う。自分の労働時間を「自由」にできる従業員はいない。残業や休日出勤は「自発的行為」などではない。労働法には、そんなものは存在しない。 かわりに労働法典が規定しているのは、雇用主が従業員の生産活動そのものに対価を払うだけでなく、生産活動を可能にするもの一切の費用を負担するという義務だ。休憩時間、有給休暇、住宅手当、交通費、業務研修、失業保険、労働災害、健康保険、老齢年金などだ。法典は、スト権、従業員代表制度、組合権、労働監査、労働審判所など、労使関係を律する一連の法律規定を置いている。額面上の賃金と手取りの賃金、つまり労働力の対価を決定する一助にもなる。法典は、民間企業の従業員とそれに準ずる労働者1600万人の集団的、個人的権利の集約であり、自覚の有無にかかわらず、彼らの日々の生活を規定している。労働法は学ぶ機会が少なく、あまり知られておらず、報道も稀で、他の分野より違反が多い法律だ。それを遵守させ、強化し、あるいは弱体化させるべく、労使は恒常的な対決を繰り広げている。賃金労働者の人数が増え、労働力人口に占める割合が1945年の60%から2005年には90%超へと達しているだけに、この対決は多くの人にかかわっている。 労使の抗争において、MEDEFは言葉をめぐる闘争を繰り広げ、社会保険の「負担」を「掛け金」に、「解雇権」を「離職可能性」に、「賃金労働者」を「協力者」に、「有給休暇」を「タイム・アカウント」に、「パートタイム」を「選択時間制」に、「早期退職者」を「シニア社員」に、といった置き換えを進めようとしている。MEDEFの望みは、社会的公序を縮小させ、組合権を狭め、従業員代表委員の数を減らし、労働審判員の数を抑え、労働監査の機会を減らし、労働刑法の範囲を狭めることだ。そして、政府による労働法典の変更は、奇しくもすべて、そうした方向に沿っている。2007年のオルドナンスを概説した論文によれば、「長期的な展望」の下で、「EU法」に準拠した「新しい規定を取り入れる」ためのものだという(7)。 1つ目のポイントは労働時間「再編」の1つ目のポイントは、労働時間である。それも道理だ。労働法典は、誕生した時から、この基本問題を中心に据えていたからだ。法典誕生のきっかけは、1840年にルイ=ルネ・ヴィレルメ医師の報告書が、(1日14時間労働で働く)工場労働者、女性、子供の健康状態のひどさを指摘したことにある。報告書が奨励したのは「もっと働く」ではなく「少なく働く」ことだった(9)。労働法典は、この処方箋を守らせるために生まれ、次第に内容が充実し、詳細になっていったものだ。1892年には労働監査制度が創設され、1906年には労働省が設置された。同じ時期に、1日あたり14時間だった労働時間は、最長10時間と定められた。20世紀初頭、労働者は8時間の労働、8時間の休息、8時間の余暇という「8時間かける3の制度」を要求した。法定の基準労働時間は、1936年に週40時間、1982年に39時間、そして2002年には35時間(最長でも48時間)に引き下げられた。この70年間の経験が証明したのは、労働時間の短縮と並行して、賃金と生産性の向上も実現させるのは可能だということだ。 労働時間の規定は、労働者に必要な休息という観点から、従来の法典では労働条件に関する第2巻に入れられていた。新法典では、賃金の部に入れ込まれている。この変更は、「戸棚の棚板を入れ替える」ようなものではない。構成の変更の裏にあるのは、原理そのものの変更である。つまり、1日または週あたりの労働時間は、健康や生活条件、仕事のつらさといった観点ではなく、コストの観点からのみ顧慮されるということだ。この原理の下では、「もっと働く」ことは「健康を差し出してカネを受け取る」ことにすぎない。 労働法典の「再編委員」は、労働時間の監督を困難にする規定を導入した。従来の法典には、雇用主が「拘束時間およびそれに対応する報酬を列挙した」書類を従業員に渡すことを義務付ける法律規定があった。リライト法典からはこの規定が消え、実際の労働時間の記録台帳や、変則勤務、パートタイム勤務におけるシフト待機時間の制限(最長2時間)、基幹社員の年間労働日数制の監督に関する規定もなくなった。 「法典再編」の大きな変更点の2つ目は、過去1世紀にわたる流れを反転させたことだ。同一の労働法典に、様々な産業部門の賃金労働者に関する規定を集約するという従来の流れに対し、2007年3月12日のオルドナンスは、ある種の賃金労働者に関する規定をまるごと他の法典に移してしまった。中にはまだ作られていない法典さえある。農業賃金労働者、つまり農場労働者、農作業会社従業員、庭師、庭番、農業会議所・農業組合・互助組合・協同組合の職員、それにクレディ・アグリコルの従業員までもが、農事法典の中に戻された。大きな後退である。農業最低保障賃金(SMAG)が全産業一律最低保障賃金(SMIG)に統合されたのは1968年にすぎず、1936年に導入された週40時間が農業部門に適用されたのは1974年、衛生と安全に関する一般規定が農業に適用されたのは1976年でしかなかったのだから。 複数の法典への分散という状態に舞い戻ることで、数百万人にのぼる賃金労働者の権利は、以降は足並みが揃わないことになる。たとえば、増加の一途をたどる育児支援労働者、家庭教育労働者や家事労働者は社会扶助・家族扶助法典、船員は海上労働法典、港湾労働者は港湾法典、わずかに残る鉱山労働者は鉱山法典の適用を受けることになる。運送会社の従業員は新設予定の運送法典、電力・ガスの公社・民間企業の従業員は新設予定のエネルギー法典、私立高等教育機関の非常勤講師は教育法典だ。これらすべての賃金労働者を合計すると、数百万人にのぼる。現在の「法典再編」作戦は、まず民間部門を攻略し、それから公務員の身分規定に取りかかる手はずである。公務員法典が化粧直しを施される日は近い。 「法典再編」の細工師たちは、付属の小細工も見事に仕立て上げた。たとえば、これまで雇用契約の関連で規定されていた労働実習契約は、「職業訓練」関連に移された。労働実習者は、雇用契約による諸々の保証を受けない「研修生」と位置付けられている。雇用契約の締結において、団体協約を打ち砕き、商事契約に類する随意契約に逆戻りさせるという経営者の夢、それを実現させるためには、全賃金労働者に共通した身分規定を爆破しなくてはならないのだ。 「雇用主の義務」と「賃金労働者の義務」「法の定常化」に伴う第3の変更点は、労働条件に関するものだ。新法典では、まるで経営者と労働者が「協力者」であるかのごとく同列に置かれている。従来の法典では、雇用主が従業員の健康、衛生、安全を守る義務を免れる余地はなかった。新法典では、「雇用主の義務」と完全に対になる形で「賃金労働者の義務」という1章が設けられ(11)、労働条件の捉え方が一変した。たとえば、L.4122-1条2項は、与えた指示が守られなかったと雇用主が主張すれば、従業員の側が責任を問われるという解釈を許すものだ。指示は文書によらなくともよい。「ああ、でも私は安全靴を履くようにと言ったんですから、彼が足に怪我をしたのは私の責任ではありません」というわけだ。従業員は、安全靴が足りなかった、古すぎた、業務に合わないものだった、見えるところに置かれていなかった、あるいは、出された命令は実行不可能な状況だった、所定の時間内では実行不可能だった、といったことの立証責任をこれまで以上に負うことになる。今でさえ当たり前になされている「私は指示を与えていた」という雇用主側の抗弁に、さらに新たな法的根拠が加わることになる。判例の抜本的な変更を実現し、雇用主責任を軽減するには、あとは裁判所のダメ押しがあればよい。 「法典再編」により激変した4つ目の分野は、司法と労働監査に関する規定である。「労働監査官」の語が新法典では「行政機関」に、「労働審判所」が「司法機関」に置き換えられた。この置き換えは、系統的でもなければ、根拠のあるものでもない。かなりの個所は、MEDEFの意向とダチ法相の決定に完璧に沿っている。MEDEFは労働審判所をなくしたいと望んでおり、ダチ法相は全部で237あった労働審判所のうち63カ所の閉鎖を決定している。従来の法典では、労働審判所の設置または閉鎖には、県議会、当該審判所、控訴院裁判長、労働組合、職業団体の意見を求める必要があったのに、新法典ではその必要がなくなった。労働審判員から「司法判事」への置き換えは、中立的なことではない。たとえば、頻発する「過大な残業または不十分な残業手当をめぐる紛争」は、労働審判員ではなく司法判事の管轄となる。 荒療治は労働監査官にも及んでいる。「再編委員」の手により、労働監査官は「所轄の行政機関」に書き換えられた。この書き換えによって、現場の監査官の業務の一部が、中央政府の任命する県局長(県局長ポストが廃止された場合は地域圏局長)、つまり監査官ではない者に移管される道が開かれた。これは些末なことではない。政府からの独立性が国際労働機関(ILO)第81号条約によって定められ、「時の政府に賃金労働者の境遇について通報する」という労働監査の仕事が、新法典の下では労働行政と為政者に委ねられるということなのだ。監査官の権限と対象分野(農業、運輸、海上、国家機関、土建業あぶれ手当金庫)は、法律規定から政令規定に移された。 政令「格下げ」で何が起こるか法典再編の5つ目のポイントは、法律規定から政令規定への噴飯すべき「格下げ」だ。国会議員は目隠し状態でオルドナンスを追認せざるを得なかった。ごっそり削除された500件の法律規定がどうなるのかは、いまだに不明だ。それに代わる政令規定の公布期限が5月1日になっているからだ。一般論として、国会で可決された法律の方が、単なる内閣政令よりも労働者を強く保護するものになる。国会では公開で、法案の審議、修正、表決を行う。労働組合は情報収集し、対応するだけの時間がある。もし初採用契約(CPE)が政令の形で作られていたならば、国会で2カ月がかりで審議されることもなく、2006年春の反対運動が拡大する前に発せられていたことだろう。「格下げ」により、何十件もの「細かい権利」が停止、廃止、変更された。たとえば、女性の授乳権だ。従業員300人以上の企業で設置することになっていた授乳室が、実質的になくなっているのは事実である。それでも従来の法典では、雇用主の同意があれば、毎日1回か2回、1時間の授乳休憩を1年にわたり有給で取れるとの規定が活きていた。新法典の政令規定ではどういうことになってしまうのだろうか。 同様に、「雇用主は労使委員会に通知するものとする」といった命令規定が、「雇用主は企業委員会に通知する」といった奨励規定に変更された。命令規定の拘束力に争いの余地がないことは誰にもわかることだ。この点についても、労働組合がそろって反対したにもかかわらず、政府は既定方針を貫いた。新法典の法律規定から、金額、水準、パーセンテージといった数字がすべて、リライトの天才たちによって取り除かれたことは明らかだ。 その一例が解雇手当に関する規定である。MEDEFのパリゾ会長はほくそ笑んでいるに違いない。彼女は解雇を「離職可能性」に置き換えることを望んでいる。2002年にジョスパン首相によって勤続月数の2割分の月給に引き上げられた法定解雇手当(12)を免れる余地ができるからだ。きたるべき政令規定で、どれくらいの水準が示されることだろうか。 従来の法典では、重量物の取り扱いは1人25キロに制限されていた。新法典の政令規定ではどうなるだろうか。職業上の男女平等からしても、この問題は重要だ。重量物の取り扱いは、すでに女性の場合も男性と同じ規定を適用されているからだ。また、労働法上の基準となる企業規模、従業員数の計算、従業員代表委員の人数といったことも、すべて未公布の政令規定に回された。すでにフランス中小企業連合(CGPME)が動き出しており、従業員代表委員の設置を義務付けられる企業規模について、現行の従業員11人から25人への引き上げを求めている。MEDEFもずいぶん昔から基準規模の引き上げを望んでおり、ジャック・アタリの報告書も(13)、労使委員会の設置基準を現行の従業員50人から100人に引き上げるよう提唱している。 従業員代表委員を務める組合活動家、弁護士、法律家、労働監査官、労働監督官、労働審判員らは、「再編委員」による「膨大」な作業結果に少しずつ取り組みはじめており、実質的な変更点をひっきりなしに見つけ出している。それでも、「定常化」されたという労働法典のすべての「秘密」を見抜くにはほど遠い。 労働法典は「情熱が注ぎ込まれたものであり、普通の法典とは違う」というのが、再編作業の中心となった労働・社会関係・連帯省のジャン=ドニ・コンブレクセル労働局長の心情だ(14)。問題は、注がれた情熱がどのようなものかということだ。経営者のためなのか、従業員のためなのか。 (2) Le Figaro, Paris, 30 August 2005. (ル・モンド・ディプロマティーク日本語・電子版2008年3月号) All rights reserved, 2008, Le Monde diplomatique + Okabayashi Yuko + Hiroi Junnichi + Saito Kagumi |
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。