| Tweet |
(回答先: 諸悪の根源は現在の資本主義のあり方にあるのでは。 投稿者 sunflowers 日時 2008 年 5 月 11 日 16:47:59)
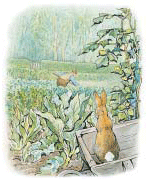
>現在の資本主義のあり方
をイメージするのは、たけ(tk)には難しいですね。
苦:《問題点》を指摘する。
集:《問題の原因》を見極める
滅:《我々の採りうる手段》には何があるか、を検討する。
道:《実行する》。
というような手順で考えて行く必要はあると思いますが、《問題の原因》としての「現代の経済システムのあり方」をイメージするところまでいっておりません。
下のスレッドで「国際競争力」という言葉が出てきたので、「現在の資本主義のあり方」との関係で野口旭さんの論文を引用しておきたいと思います。
>資源/食料輸入国の日本が国際競争力を失うということは
>http://www.asyura2.com/08/idletalk31/msg/383.html
>投稿者 佐藤巧 日時 2008 年 5 月 11 日 09:40:42: GXLHmgxmIOPfo
>(回答先: 労働ダンピングを止めれば、為替で調整できる 投稿者 最大多数の最大幸福 日時 2008 年 5 月 10 日 23:34:08)
>誰も食べていけなくなるということですよ。
>そこまで考えておっしゃっていますか?
以下の論文によると
(1)「国際競争力」という概念それ自体が、標準的な国際経済学の中には存在しない。
(2)「国際競争力」という考え方に基づく推論のほとんどは、人々を矛盾にみちた無内容な結論へと導く。
(3)多くの人々は、企業同士の間での競争という現実をあまりに日常的に経験しているということである。そして、その現実から得られた推論を、誤って国家間に援用しがちである。しかし、企業間とは異なり、国家と国家は、貿易を通じて相互依存はしていても、競争をしているわけではない。
だそうです。
−−−−
http://www.rengo-soken.or.jp/dio/no166/k_hokoku..htm
なぜ「国際競争力」にとらわれてはいけないのか
専修大学教授 野 口 旭
本稿は、連合総研「活力ある安心社会のための基本政策研究員会(主査:栗林世連合総研所長)」の論議にあたり、野口旭専修大学教授よりご示唆頂いた内容を、編集部の責任において転載したものである。
はじめに
最近、「日本の国際競争力の低下」という言葉を聞くことが、きわめて多くなってきた。同様な文脈の話は、以前から、グローバル競争とかメガコンペティション(大競争)という言葉によって語られてはいたが、最近のそれは、日本経済にとっての悲観的な含意がより一層強まっているように思われる。
メガコンペティション論とは、冷戦終了と新興工業国(Emerging Economies)の登場による「グローバルな競争の激化」を提示する議論である。最近ではそれに加えて、「中国に追い越される日本」といったような「中国脅威論」が付け加わることが多い。
この種のメガコンペティション論は、「日本の構造問題=日本的システムの疲弊=国際競争力の低下」といった図式を強調する多くの論者やマスメディアが好んで語る主題ではあるが、その焦点は必ずしも明確なわけではない。日本の国際競争力低下による「空洞化」をそれに結びつける主張もあれば、そこから「日本の高コスト構造の是正=物価の国際的収斂」といった「良いデフレ論」あるいはデフレ必然論を展開する議論もある。
その意味では、メガコンペティション論とは、経済学的仮説というよりは、日本的システムの機能不全、産業構造の調整不良、国際競争力低下、高コスト構造、産業空洞化等々といった「構造問題らしきもの」を雑然とくくり合わせるためのキャッチ・フレーズというようなものであろう。とはいえ、その現実的な影響力は、単にキャッチ・フレーズと侮っていてはすまされない段階になってきている。
私見によれば、この「メガコンペティション下における日本の国際競争力低下」というう図式や、それに結びついた「良いデフレ論」のような考えは、ミクロ経済学的にもマクロ経済学的にも、まったく誤っている。しかし、野口悠紀雄氏、竹中平蔵氏、斎藤精一郎氏、香西泰氏、池尾和人氏とういった、メディアにおいてきわめて有力な論者が、同様な見方を繰り返し表明している。そうしたことから、このような考えの社会一般への影響力は、とみに増大しているよう思われる。最近に出版された書籍の中では、ベストセラーとなった野口悠紀雄氏の『日本経済企業からの革命?大組織から小組織へ』(日本経済新聞社)が、その典型である。
もちろん、いくら誤った見方であっても、単にお話として語られているだけであれば何も問題はない。ところが実際には、こうした見解の流布が、明らかに、日本にとって真に必要なマクロ経済政策の実現への障害となっている。また、「国際競争が厳しいから、組合には賃下げを呑んでもらうしかない」といったように、「国際競争」という言葉が労使交渉において悪用されることも多いようである。
そこで以下では、「日本の国際競争力の低下」について一般的に論じられている考え方のどこが誤りなのかを、論点ごとのコメントの形で整理しておきたい。
(1)日本の「国際競争力」は低下しているか。
その答えはイエスでもノーでもない。というのは、そもそも「国際競争力」という概念それ自体が、標準的な国際経済学の中には存在しないからである。国際経済学の多くの教科書で論じられているように、国際貿易において最も重要なのは、「比較優位」という概念である。そして、この概念はまさに、「国際競争力」というような一般的通念が何の根拠もないことを示すものである。
多くの人々はしばしば、一国の生産性が他国に比較して低いことが「国際競争力」が低いことと考えがちである。しかし、これは誤りである。たとえば、仮に日本の自動車の生産性が中国のそれよりも低かったとして、その生産性の低さの「程度」が他の産業よりはましだとすれば、日本は中国に自動車を輸出することになる。これが比較優位の考え方である。
一般に、生産性が低いことは、その国の経済的厚生が低いことを意味する。しかしそれは、その国に輸出できるものがないことを意味しないのである。
(2)日本の「国際競争力」が低下すると、日本は損失をこうむるか。
「国際競争力」という概念が定義できない以上、これも返答不能な問いである。そこで、この「国際競争力」を「生産性」に置き換えて考え直してみよう。というのは、多くの人々は、「日本の各産業の生産性上昇率が相対的に他国(たとえば中国)よりも低くなってきた」ことをもって「国際競争力の低下」と考えているようだからである。
そのように置き換えると、上記の命題は明らかに誤りであるということが分かる。というのは、「日本が損失を被る」ということは、「日本の貿易利益が減る」ということであるが、日本の貿易相手国の生産性の上昇は、通常は日本の貿易利益を減らすよりも増やすことが多いからである。
たとえば、中国の日本への輸出品である繊維製品の生産性が上昇したとしよう。その場合、中国製の繊維製品は通常、相対的により安価になる。だとすれば、日本は、これまでと同じ輸出量によって、より多くの中国製繊維製品を輸入できるようになる。つまり、日本の交易条件(輸出財一単位によって得られる輸入財の量)は改善する。したがって、日本の貿易利益は、減るのではなく増えているのである。
もちろん、こうしたことで、中国製品と競合する日本の繊維産業は、一時的に打撃を受けるであろう。しかしそれは、産業構造調整によって解消していくしかない問題である。実際、一九六〇年代の貿易自由化以来、日本経済はこうした産業構造調整を進めつつ経済成長を遂げてきたのである。
(3)「国際競争力」を失った国の労働者の賃金は低下していくか。
ここでもまた、「国際競争力」を「生産性」と置き換えておこう。そうすると、以下の正しい命題が得られる。それは、「生産性の低い国の労働者の賃金は、それが高い国の労働者の賃金よりも低くなければならない」ということである。たとえば、日本と中国が同じ品質の鉄鋼を生産し、それを同じ価格で他国(たとえばアメリカ)に輸出しているとしよう。この場合、もし日本の生産性が中国よりも低ければ、日本の労働者の賃金が中国よりも低くなるのは当然である。というのは、生産性が低いのに賃金が同じでは、同じ価格にはできないからである。
以上は、「各国の平均的な賃金には、その生産性水準に即した妥当な水準がある」ということを意味する。したがって、生産性上昇率の相対的に高い国は、通常は賃金の上昇率も高くなる傾向がある。
重要なのは、こうした調整は、例外的な状況を除き、「それ以外の国の賃金の低下」によって実現されるわけではないということである。もしそうなら、生産性上昇率の相対的に低い国の賃金は常に低下しているはずであるが、そうはなっていない。
つまり、現実に生じているのは、生産性上昇率の高い国の賃金上昇であって、生産性上昇率の低い国の賃金低下ではないのである。
(4)「国際競争力」の維持のためには、「高コスト構造=高賃金」の是正が必要であるか。
「日本と中国が同じ品質の鉄鋼を生産し、同じ価格でアメリカに輸出している」という上記の例を踏襲しよう。ここで、仮に中国に比較した日本の賃金が、上記の意味での「本来あるべき水準」よりも高すぎる場合にはどうなるのかを考えてみよう。というのは、「日本の高コスト構造=高賃金」に言及する人々が念頭においているのは、主にこうした状況であるように思われるからである。
その場合には確かに、日本の鉄鋼は、高賃金=高コストによって、中国の鉄鋼よりも割高になる。したがって、そのままでは、アメリカに輸出できない。
注意すべきは、この状況でも、「日本の名目賃金の引き下げ」は必ずしも必要ないということである。というのは、日本の賃金が一定でも、為替レートが低下すれば(すなわち円安になれば)、日本の対中国での賃金は低下するからである。
つまり、為替レートが一定のもとでの日本の賃金の低下と、賃金が一定のもとでの日本の為替レートの低下は、基本的に同一の結果をもたらす。ただし、賃金を一斉に切り下げるのに要する調整コストは膨大なものになるのに対して、為替レートの調整は一瞬ですむ。どちらが望ましいのかは自明であろう。
(5)円安による調整は、日本に損失をもたらすか。
野口悠紀雄氏は、上掲の著作の中で、金融緩和によって円安が生じることを認めながらも、「円安によって人々の実質所得が低下するするので、円安は日本を貧しくする」と述べて、金融緩和を通じた円安の「弊害」を指摘している。
確かに、日本および諸外国の物価が一定のもとで円安が進めば、日本の交易条件は悪化し、貿易利益は減少し、日本の実質所得は低下する。だからといって、円高であればあるほどいいというわけではない。上記の推論から明らかなように、為替レートが一定のもとので「分不相応な高賃金」と、賃金が一定のもとでの「分不相応な円高」は、基本的には同じことである。というのも、両者とも、輸出の困難と、その結果としての失業増加をもたらすからである。つまり、過度な円高は、貿易利益の若干の増加とひきかえに、国内経済の停滞=失業の増加をもたらす。いわゆる「円高不況」である。
逆にいえば、国内経済が不完全雇用の状態にあるかぎり、円安はむしろ望ましい結果をもたらす。その場合には、円高を維持することで、わずかばかりの貿易利益とひきかえに大量の失業を放置しておくのは、まさに愚の骨頂という以外にはないのである。
(6)日本の「高コスト構造」の打破のためには、デフレが必要であるか。
日本の高コスト構造といった場合に、賃金コストとともに言及されることが多いのが、運輸、通信、電力などの産業インフラを利用するコストの高さである。まず明確にしておく必要があるのは、仮にこうしたサービスの価格が国際的にみて「割高」だとしても、それは「国際競争力」を低下させる要因にはならないという点である。もし、「産業インフラ利用のコストが割高なために、それを用いている財の価格が国際的に高くなっていて、輸出が困難になっている」というのが問題なのであれば、それは円安になれば解消される。
実は、こうした産業インフラは、国際貿易のできない「非貿易財」であるという点で、国境を越えた移動が不可能な労働力と似た性質を持っている。したがって、賃金についていえるのと同様なことが、ほぼそのまま産業インフラの価格についてもいえる。つまり、円安になれば名目賃金の切り下げは無用になるのと同様に、円安になればそれらの価格の引き下げは無用になるのである。
もちろん、こうした産業インフラの「高コスト」が、政府規制などの存在による低生産性によるのであれば、規制緩和などによってそれが解消されることは、国内経済厚生の面では望ましい。とはいえ、そこで必要なのは、こうした産業インフラの相対価格(他の財サービスと比較した価格)の低下であって、デフレすなわち全般的物価水準の低下ではない。特定分野に生産性上昇が生じたからといって、経済全体がデフレになる必然性はまったくないのである。
(7)日本の「高コスト構造」は、政府規制による低生産性が原因であるか。
非貿易財産業の低生産性は、その価格を国際的にみて割高にする傾向を持つのは確かである。しかし、「高コスト」だからといって、常にその産業の生産性が低いとは限らない。たとえば日本の散髪サービスのコストが中国よりも高かったとしても、必ずしも日本の床屋の生産性が中国よりも低いわけではない。
実は、「高コスト構造」論には、見落とされがちな点が一つある。それは、仮に非貿易財産業の生産性が他国を上回っていても、輸出財産業の平均的生産性がそれ以上に他国を上回っている場合には、非貿易財の価格は必ず他国よりも高くなるという事実である。
(3)で説明したように、輸出財産業の平均的生産性が他国よりも高い国は、賃金も他国より高くなる。その高い賃金は、一国の非貿易財産業にも適用されるから、その価格は必ず他国のそれよりも高くなる。したがって、この場合には、他国に比較した非貿易財の「高コスト」が観察されたとしても、それはその国の非貿易財産業の生産性の低さの現れではなく、輸出財産業の生産性の高さからくる高賃金の現れなのである。
床屋の生産性は、あるいは日本が中国を上回っているかもしれないが、日本の賃金が中国のそれを大きく上回る以上、日本の散髪サービスは中国のそれよりも「高コスト」になっても当然ということである。
(8)日本の「国際競争力」を守るためには、「高付加価値産業」の創出が必要か。
一九七〇年代前半くらいまでの日本は、産業政策と呼ばれる、重要産業(将来の高収益が期待できる産業?)の保護育成政策を実行していた。しかしそれは、多くの経済学者に批判され、現在ではまったく省みられていない。なぜなら、政府が民間の企業家以上に正しく「将来の高収益が期待できる産業」を見つけることができるという保証はどこにもないからである。
本来、「高付加価値」とか「高収益」というのは、産業が固有に持つ特性ではない。ハイテク産業が常に「高付加価値」であって、農業が常に「低付加価値」であるわけではないのである。それぞれ産業の付加価値は、自然的ないし人為的な参入制限によるレント(収益)が存在しない限り、需要に対する供給の調整によって、長期的には適切な水準に落ち着く。
野口悠紀雄氏は、前述の著作の中で、中国が台頭しつつある中で日本の実質賃金の低下を避けるためには、「日本が経済構造を改革し、中国で生産できないものを生産するようになる」必要があると主張している。中国の台頭が日本の実質賃金低下に結びつくものではないことは、既に述べた。後半の主張も、貿易に関するありがちな誤解である。「他国が生産できないものを生産する」のは、貿易の本質ではない。国内で生産できるものでも、比較劣位である限り、自国で生産するかわりに輸入したほうが利益となり、それは相手も同じというのが、あらゆる貿易論の基礎である比較生産費説の基本原理なのである。
◆結語――――
結論としていえるのは、「国際競争力」という考え方に基づく推論のほとんどは、人々を矛盾にみちた無内容な結論へと導くいうことである。にもかかわらず、その言葉は、メディア上においてもビジネスの現場においても、頻繁に用いられている。それはなぜなのであろうか。
その理由の一つは、多くの人々は、企業同士の間での競争という現実をあまりに日常的に経験しているということである。そして、その現実から得られた推論を、誤って国家間に援用しがちである。しかし、企業間とは異なり、国家と国家は、貿易を通じて相互依存はしていても、競争をしているわけではない。
もちろん、同一業種の企業と企業とは、日本国内であれ、海外企業との間であれ、文字通りの競争を行っている。そして、そうした状況に直面した企業経営者が、「国際競争」を口実にコスト削減=賃金切り下げを図ろうとするのは、とりわけ不況下においては、やむをえない面もある。
留意すべきは、経営者がそうした行動をとる背景には、それなりのマクロ経済状況があるということである。景気が拡大して人手不足になっている状況では、いくら競争が厳しいといっても、企業はむやみに賃下げはできない。逆に、現在の日本のようなデフレ不況下では、企業は否が応でもリストラや賃下げに追い込まれざるをえない。同じことは、円高に直面した輸出産業についてもいえる。
重要なのは、デフレにせよ円高にせよ、企業の経営努力によってどうにかできる問題ではないということである。一部の企業は、リストラによってそれに何とか対応できるかもしれない。しかし、すべての企業がデフレや円高に対応することはできない。そして、企業がどのような経営努力を積み重ねても、デフレや円高を止めることはできない。それをできるのは、政府および日銀による適切なマクロ経済政策のみなのである。
以 上
|
|
- Re: なぜ「国際競争力」にとらわれてはいけないのか【野口旭】 sunflowers 2008/5/11 21:17:14
(3)
- 一言で言えば「国際競争力」は、使えば混乱するだけのバズワード(インチキ用語)だということでしょう。 tk 2008/5/11 23:21:01
(2)
- しかしそのインチキ言葉に我々が勝てていないというのが実情と思います。 sunflowers 2008/5/13 00:09:20
(1)
- 自分で自分の思考停止に気づきました(苦笑) sunflowers 2008/5/13 01:25:55
(0)
- 自分で自分の思考停止に気づきました(苦笑) sunflowers 2008/5/13 01:25:55
(0)
- しかしそのインチキ言葉に我々が勝てていないというのが実情と思います。 sunflowers 2008/5/13 00:09:20
(1)
- 一言で言えば「国際競争力」は、使えば混乱するだけのバズワード(インチキ用語)だということでしょう。 tk 2008/5/11 23:21:01
(2)
|
|
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
|
|
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。
|
|
|
|
|
|
|
|