| Tweet |
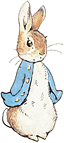
--「アウシュヴィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか」--
第4章 「証言」の問題
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
イスラエルのガザ空爆・侵攻から2か月が経とうとして居ます。
報道は減りましたが、医療状況の悪化をはじめとする現地ガザの民生の状況には、深い憂慮を抱かずに居られません。
--報道の減少は、逆に、国際社会の関心の低下を招くのではないかと憂慮して居ます。
イスラエルのガザ侵攻と、それによって生じたおびただしい民間人の被害に対する私の抗議として、特に、何の罪も
無い子供たちの被害に対する私の講義として、私の著作である 『アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか』
(日新報道・1997年)の一部(第一章)の全文をお送りします。
コピペによる転送、転載を歓迎します。以下の文章の一部分でも全体でも、自由に御利用下さい。ただし、文章の変更は
お断り致します。文献参照、写真、グラフ、図、などは、労力の問題と技術的理由から、割愛させて頂きましたので、
御覧になりたい方は、本の実物で御覧下さい。
イスラエルのプロパガンダである「ナチのガス室」をまだ信じて居る御友人、御知人などにメールとして転送される事や、
各種掲示板に貼り付けて下さる様、お願い申し上げます。--イスラエルがガザで行なった民間人殺戮への抗議活動として、
そして、民生状況の劣悪化への抗議として、御協力をお願ひ申し上げます。
これは、私のインティファーダです。
http://spn05738.co.hontsuna.com/article/1059522.html
(この本についてのサイトです)
2009年2月23日(月)
西岡昌紀
(以下本文/転送・転載歓迎)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(第3章 「ガス室」は実在したか の続きです)
第4章 「証言」の問題
--この本をここまで読んでこられた方たちが、今一番、戸惑っておられることは、それでは、「ガス室」の「目撃証言」をどう考えたらいいのか、という問題だと思われます。即ち、仮に何の証拠がないとしても、「ガス室」の「目撃証言」はあるではないか、ということです。
その問いに答える前に、先ず、繰り返しますが、私は、ナチスドイツがユダヤ人を収容所に収容したことや、様々な形でユダヤ人を差別迫害したことは否定など全くしていません。ですから、言うまでもなく、そうしたドイツのユダヤ人迫害に関する証言全てを否定するつもりなど毛頭ありません。当然、アウシュヴィッツをはじめとする収容所に関する証言全てを否定する意図なども、全くありません。こんあことは言うまでもないことですが、あえて、もう一度申し上げておきます。
しかしながら、私は、ドイツがユダヤ人を「絶滅」しようとまでしたという主張と、その手段として「ガス室」で人を殺した、という二点については、「納得」していません。ですから、この二点に関係した「証言」については、当然、これから述べるような検証を加えなければなりません。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)160ページより)
--そこで、その「証言」ですが、私が疑問を提出しているこの二点(「ユダヤ人絶滅計画」と「ガス室」)の内、「証言」の問題がより大きな意味を持っているのは、明らかに、「ガス室」の方でしょう。即ち、二つの論点の内、「ユダヤ人絶滅計画」があったかどうかというのは、あくまでも政策に関する議論です。そのような政策が当時のドイツ政府にあったか否かが議論の焦点なのですから、これは、収容所に入れられていたユダヤ人の証言よりも、当時のドイツ政府文書の検討によって判断されることになります。「絶滅計画」については、「証言」が無関係だとまでは言いませんが、議論のおもな対象は、あくまでも文書であるはずです。そして、その点についての私の立場は既に第2章でお話しした通りですが、戦後、ニュールンベルク裁判などで語られたドイツ人の「証言」の一部は政策の問題に関係がありますので、後で触れることとします。
これに対して、「ガス室」の存在については、当然「目撃証言」の検討が重要となります。前章の終わりで私が述べたように、ここまで私の話を読んでこられた方の多くが、「『ガス室大量殺人』に物証と呼べるものが存在しないとしても、その目撃証言はあるではないか。例えば、ガス室で人が殺されるのを見た、というような証言はウソだと言うのか?」といったような疑問を今抱いておられるのではないかと思います。
そうした疑問に答えるのが、この章の目的です。詳しくお話ししますが、その前に、論より証拠です。そうした「ガス室」の「目撃証言」の一つを読んでみようではありませんか。これは、『ショアー』(クロード・ランズマン著 高橋武智訳 作品社)という「定説」側のバイブルのような本に収められている「ガス室目撃証言」の一つですが、とにかくお読み下さい。その後で、「ガス室」に関する「証言」全般に関するお話をしたいと思います。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)160~162ページより)
--以下に私が引用、要約するのは、前述の『ショアー』という本に収められている、アブラハム・ボンバ(Abraham Bomba)という人物の「証言」です。この『ショアー』という本は、フランスのドキュメンタリー作家クロード・ランズマン(Claude Lanzmann)監督の同題の映画の内容を収録したもので、「ホロコースト」に関係した「証言」といった内容のものです。(「ショアー(Shoah)」とは、ヘブライ語で「絶滅」を意味し、欧米では「ホロコースト」の別名としてしばしば使われている単語です)
この「ドキュメンタリー映画」には、大戦中ナチスの収容所に入れられていた人々をはじめとする多くの人々が登場し、質問に答える形で、当時、自分が見聞きしたこと、または見聞きしたと主張することを語ります。そうした「証言」の一つが、以下に引用するアブラハム・ボンバ氏の証言です。ボンバ氏は、ポーランド系ユダヤ人であり、戦後イスラエルに移住していますが、氏によると、彼は戦争中、ポーランド東部のトレブリンカ(Treblinka)収容所に収容されていたそうです。そして、床屋であったため、「ガス室」で殺される女性たちの髪を、その「ガス室」の中で、彼女たちが殺される直前に刈る仕事をさせられていた、と証言しています。当然、ボンバ氏は、トレブリンカ収容所の「ガス室」を自分の目で見ていると主張するわけですが、そのボンバ氏の証言の一部を引用しますので、お読み頂きたいと思います。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)162~163ページより)
--「或る種の仕事のために、床屋を運び出せ、という命令が、ドイツ兵から出されました。(中略)私は相当長いこと、床屋をしていたんです。(中略)いっしょに、次の命令を待っていますと、連中、つまりドイツ兵と一緒に来い、という命令が出ました。トレブリンカ収容所の第二地区にあるガス室まで、護送されたんです。」(クロード・ランズマン著 高橋武智訳『ショアー』252~253ページ[アブラハム・ボンバの証言]より)
これが、ボンバ氏が、トレブリンカ収容所でドイツ人に命じられ、処刑直前の女性たちの髪を「ガス室」の中で刈るようになった経緯だそうです。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)163ページより)
--氏の証言を続けて読みましょう。
「ガス室の中に連中[西岡注:ドイツ人たちを指す]は、女たちが腰かけられるように、ベンチを置きました。それはまた、これがこの世で最後の歩みだとか、最後の瞬間だとか、最後の呼吸だなどということを、彼女たちに気付かせないため、すぐあとに起こることを、勘付かせないためでもあったのです。」
(同書253~254ページ)--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)163ページより)
--では、「ガス室」がどのくらいの大きさだったのかと言うと--「大きな部屋じゃなく、そうですねえ、4メートル平方くらいでした。けれども、そんな部屋に、連中[西岡注:ドイツ人のこと]は、あまり大勢、女性を詰め込んだので、ほとんど重なり合うくらいでした。」(同書254ページ)と言うのです。この大きさにご注目下さい。その「ガス室」は、「4平方メートルくらい」だったと、言うのです。ところが、問題は次の部分です。その「ガス室」の中に鏡があったかという質問に答えて、ボンバ氏はこう「証言」しているのです。
「いや、ありませんでした。ベンチだけで、椅子もなかった。ただベンチと、床屋が16人か、17人だけしかいないのに(中略)、女性の数は、あまりにも多かった!一人のカットに、二分ほどかけましたが、それ以上は無理でした」(同書257ページ)
つまり、「4平方メートルくらい」の「ガス室」の内部にベンチがあり、そこに床屋だけでも「16人か、17人」がいた、というのです。その上、その狭い「ガス室」の中にこれから殺される女性もたくさんいたことを思い出して頂きたいと思います。ボンバ氏は、一回に何人の女性を刈ったかという問いに答えて、こう「証言」するのです。
「一度に(中略)、おおよそ(中略)、60人か70人でしたか」
(同書258ページ)
--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)164ページより)
--そして、次にはこう「証言」します。
「いや、第一集団が終わると、次のグループが入ってくる。あわせて、女性140人としか、150人になりますかね。この人たちのカットが、全部すむと、連中(西岡注:ドイツ人たち)から命令が出て、われわれは、約5分の間に、ガス室を出なければなりません。それから、ガスを送り込み、女性を窒息死させたのです。」(同書258~259ページ)
お分かりでしょうか?つまり、その「4平方メートルくらい」の「ガス室」内部には、先ずベンチがあり、床屋が16人か17人いて、その上、何と「あわせて140人か150人」の(殺される)女性がいた(!)と、ボンバ氏は「証言」しているのです。「4平方メートルくらい」の「ガス室」にこんなに大勢の人間が入ったのでしょうか?
これが、「定説」側のベストセラーに収録されている「ガス室」の「目撃証言」の一つなのです。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)164~165ページより)
(参考サイト:クリックしてお読み下さい)
↓
http://www.jca.apc.org/~altmedka/aus-27.html
(木村愛二著『アウシュヴィッツの争点』より)
--数が多いか少ないかは別として、「ガス室大量殺人」を見た、という証言は勿論、存在します。そして、それらは、戦後、半世紀以上の間、マスメディアなどで繰り返し取り上げられてきました。ですから、皆さんが、そうした「証言」をどう考えるか、とお尋ねになるのは全く当然のことです。しかし、その疑問に対して、先ず、私は逆にお尋ねしたいと思います。収容所で戦後を迎えた多数の生存者の中に、ウソの「証言」をした人は一人もいなかったのでしょうか?私のこの問いを、冷静に考えてみて下さい。一つの収容所だけで何万人も収容されていた場合もあるのに、そのように大勢いた被収容者の中に、ウソの証言をした人は一人もいなかったのでしょうか?或いは、有名になりたいいう気持ちから、ニュールンベルク裁判やマスメディアが語っているのと同じことを自分も目撃したと語った人は、一人もいなかったのでしょうか?または、政治的な動機から、例えばソ連に対する忠誠心などから、そのソ連の敵であったドイツ人の残虐行為を実際以上に誇張して語った「証人」は、一人もいなかったのでしょうか?--では、今引用したアブラハム・ボンバ氏の「証言」などは、どう考えればいいのでしょうか?--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)165~166ページより)
--ナチスの被害者の中にウソの「証言」をした人がいたなどとは、私も信じたくありません。しかし、逆に、「証言があるのだから、ガス室はあったのだ」と言う方は、ウソの「証言」をした元被収容者が一人もいなかった、と断言なさるのでしょうか?そして、もう一つ。これが重要な事ですが、ナチスの収容所に入れられていたユダヤ人や政治犯、その他の元被収容者の中には、皆さんが信じておられるかも知れないのとは違い、「ガス室」の存在に全く否定的な証言をする人々が、実は、多数いるのです。そうした人々の証言は、マスメディアなどでは決して大きく取り上げられませんが、後で引用するように、現に存在し、「定説」側の出版物の中からすら見つけることができるのです。それも、アウシュヴィッツ(ビルケナウ)やトレブリンカに永くいたユダヤ人他の被収容者の証言の中にです。「証言があるのだから、ガス室はあったのだ」と言う方は、それでは、そうした「ガス室」に否定的な証言をするユダヤ人他の生き証人がいることは、どうお考えになるのでしょうか?そして、ウソの「ガス室目撃証言」をした元被収容者が一人もいなかったと、とお考えになる方は、例えば、今、ご紹介したアブラハム・ボンバ氏の「証言」は、どのように説明なさるのでしょうか?(他にも、この種の「証言」を挙げることは容易です)--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)166~167ページより)
--このことに関連して、ここで非常に重要なことをお話ししたいと思います。既に述べているように、この「ガス室大量殺人」には、物証と呼べるものはありません。テレビの資料映像には、ベルゲン・ベルゼンなどで撮影された病死者が、まるで、「ガス室」の犠牲者ででもあるかのように映し出されますが、「ガス室」で殺された死体は一体も確認されていません。また、処刑用ガス室の設計図も結局、発見されていません。それに、「ユダヤ人絶滅」の命令書も存在しなければ、そのための予算も計上されていないのです(既述)。それにも拘らず、「定説」側は「ガス室」があったと言うのですが、その「根拠」が何かと言えば、つまるところ、「証言」なのです。先ほど引用したアブラハム・ボンバの「証言」もそうした「証言」の一つですが、それはともかく、ここで、非常に重要なことをお話ししたいと思います。それは、こうした「証言」に基ずいて成立しているその「定説」側の説明が、実は、何度も変わっているということなのです。即ち、「ガス室」の話を中心とした「定説」側の語る「ホロコースト」の内容は、実は、戦後、何度も変わっているのです。皆さんは、このことに気付いておられるでしょうか?--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)167~168ページより)
--一例を挙げましょう。前にお話ししたベルゲン・ベルゼン収容所はドイツ北部にあった収容所で、戦争末期にイギリス軍によって解放されています。この収容所は戦争末期にチフスが大発生したことで有名で、そのことは、「定説」側の本でも、また医学論文にも明記されています。そして、この収容所に「ガス室」がなかったことは、前述のように、「定説」側の著作にはっきりと書かれています。当然、このベルゲン・ベルゼン収容所は、「定説」側の著作においても、アウシュヴィッツやマイダネックやトレブリンカのような「絶滅収容所」には分類されていません。
ところが、戦争直後には、ある歴史家は、その「ガス室」などなかったはずのベルゲン・ベルゼン収容所について、こんな「歴史」を書いていたのです。
「ベルゼンでは、クレーマー[西岡注:同収容所司令官]が、子供たちが母親から引き離され、生きたまま焼かれるのを眺める間、オーケストラにウィーン風の音楽を彼のために弾かせ続けた。ガス室で、毎日、何千人もの人々が殺されていたのである」(訳:西岡 原文は以下の通り)
In Belsen, Kramer kept an orchestra to play him Vienese music while he watched children torn from their mothers to be burned alive. Gas chambers disposed of thousands of persons daily(Francis.T.Miller“ A Hostory of World WarⅡ”, 1945 p.868)
おかしいとはお思いにならないでしょうか?今日では「定説」側論者たち自身が「ガス室はなかった」と言っているベルゲン・ベルゼン収容所について、戦争直後には、こんなことが書かれていたのです。「ガス室で、毎日、何千人もの人々が殺されていたのである」などと・・・。つまり、話が変わっているのです。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)168~169ページより)
--ベルゲン・ベルゼンだけではありません。例えば、ドイツ南西部に在って、アメリカ軍によって解放されたダッハウ(Dachau)収容所に関しても、同様に、話が変わっているのです。即ち、このダッハウ収容所についても、今日、「定説」側歴史家は、戦争中そこで「ガス室大量殺人」が行われていたとは言いません。「ダッハウのガス室は未完成だった」などと言って、そこで「ガス室」が使われていたとは言わないのです。ところが、このダッハウ収容所についても、戦争直後には、処刑用ガス室があり、多くの人々が「ガス室」で殺されていた、という話が堂々と語られていたのです。
ベルゲン・ベルゼンについては、そこに「ガス室」があったと書いた前述の「定説」側歴史家ミラーは、自分が根拠とした証言を明記していません。しかし、このダッハウについては、フランツ・ブラーハ(Franz Blaha)という、チェコ人の医師で同収容所に収容されていた人物が、そこには処刑用のガス室があり、大勢の人々が殺されていた、と「証言」しています。しかも、そのブラーハという人物は、戦後の戦犯裁判に「証人」として登場し、その「ガス室」で殺された人々の死体を自分が「ガス室」内で検屍した、とまで「証言」しているのです。
皆さんは、これをおかしいとはお思いにならないでしょうか?こんな具体的な「証言」が裁判という場で語られていたのに、今日、「定説」側の歴史家たちは、何故、「ダッハウのガス室は未完成だった」等と言うのでしょうか?rすまり、そこで戦争中「ガス室」による処刑が行われていたという説を自ら否定しているのですが、それならば、ダッハウでは実際に「ガス室処刑」が行なわれ、その死体を自分が検屍した、とまで語ったブラーハの「証言」とは、一体何だったのでしょうか?--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)169~171ページより)
--これだけではありません。その他にも、例えばドイツ中部に在ったブーヒェンヴァルト収容所などでも、かつては、そこに「ガス室」があったという「目撃証言」が語られていたのです。しかし、そのブーヒェンヴァルト収容所についても、今日では、「定説」側論者自身が、「ガス室」があったとは言わないのです。そこでも、「ガス室を見た」という「証言」があったにも拘らず、です。
皆さんは、こうした「定説」側の変化を不思議には思われないでしょうか?このように、終戦後しばらくの間は、今日では「定説」側論者自身が「ガス室大量殺人」は行われていなかったと認める収容所で、「ガス室大量殺人」を目撃したという「証言」が堂々と語られていたのです。そして、それらの「証言」やそれに依拠した著述を反映する形で、戦後しばらくの間は、その「ダッハウのガス室」などが、本や映画に堂々と登場していたのです。そのため、戦後しばらくのそうした時期には、こうした状況を反映して、「ナチのガス室」といえば、ポーランドのアウシュヴィッツやマイダネックといった収容所よりも、ダッハウをはじめとする、ドイツ本国の収容所の方が、その代名詞として語られていたくらいだったのです(このことは、「定説」側の本も認めています)。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)171~172ページより)
--このことは、こうした「証言」が、単に個人による「証言」として存在していたのみならず、欧米のマスメディアによって、「真実」として認知されていたことを意味します。例えば、『ニュールンベルク裁判』という、リチャード・ウィドマークやバート・ランカスターが登場する、文字通り、ニュールンベルク裁判を題材にしたアメリカの劇映画がありました。劇映画としては良く出来た作品ですが、例えば、この映画などにも、「ダッハウのガス室」は堂々と登場していたのです。それほど、「ダッハウのガス室」が当たり前に語られていた時期があったということです。つまり、それらの「ガス室」は消えたようなものですが、これがどういうことなのか、不思議に思うのは、私だけではないはずです。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)172ページより)
--考えてもみて下さい。例えば、フランツ・ブラーハが語った「ダッハウのガス室」に関する「目撃証言」がもし本当だったとしたら、「定説」側歴史家たちは、なにも「ダッハウのガス室で大量殺人が行われた」という命題を否定する必要などなかったはずです。ところが、それを今日彼ら自身が否定しているのは一体何故なのか。それは、彼ら自身が、この「証言」を信用していなかったからではないでしょうか?・・・皆さんは、これでも、ウソの「ガス室目撃証言」はなかったとお考えになるでしょうか?--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)172~173ページより)
--このことに関連して、思いだして頂きたいことがあります。それは、前章で指摘したように、「定説」側論者たちが、今日、何故か、「絶滅収容所」はドイツ本国にはなかった、といっているということです。即ち、前にも述べた通り、今日、「定説」側論者たちは、アウシュヴィッツをはじめとするポーランドにあった収容所の幾つかを「絶滅収容所」と呼んでも、ドイツ国内にあった収容所を「絶滅収容所」とは呼びません。当然、今日、「定説」側論者たちは、今お話ししているこれらの収容所、即ち、ダッハウやベルゲン・ベルゼン、ブーヒャンヴァルトなどの収容所も、「絶滅収容所」とは呼ばないわけですが、そのことは、このように、これらの収容所から「ガス室」が消えて行ったことと無関係なことだったのでしょうか?--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)173ページより)
--この点については、ドイツの「定説」側歴史家マーティン・ブロサット(Maartin Broszat)博士が、1960年8月に、ドイツの新聞Die Zeitに寄せた注目すべき投書があります。同博士はその投書の中で、ダッハウやベルゲン・ベルゼン、ブーヒェンヴァルト等における「ガス室大量殺人」を事実上、否定する見解を述べているのですが、ブロサット博士のこの投書をもって、ドイツ本国での「ガス室大量殺人」に関する「定説」側の見解が大きく変更されたと見るのが、妥当と思われます。即ち、これは、ドイツ本国に在ったこれらの収容所での「ガス室目撃証言」を「定説」側が、事実上、自ら否定したということなのですが、これが、彼ら自身が、それらの収容所における「目撃証言」を信用していないことの現われでなくて何だと言うのでしょうか?いずれにせよ、「定説」側の見解が、これらドイツ本国の収容所の「ガス室」について戦後、変化したことだけは確かです。そして、その変化の後、「絶滅収容所」は、ポーランドという、ソ連の支配下に在って、西側の人間が自由に調査できない国にのみ在ったことになったわけですが、これは、単なる「偶然」だったのでしょうか?--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)173~174ページより)
--このように、ドイツ本国の収容所であるダッハウなどでは、「ガス室殺人」の「目撃証言」が、「定説」側の歴史家自身によって否定されるに至っています。しかし、おかしいのは、ダッハウなどでの「ガス室目撃証言」だけだったのでしょうか?そうではないのです。今日「定説」側が「ガス室」があった収容所の代表としているアウシュヴィッツ(ビルケナウを含む)での「証言」についても、おかしなことは、多々、指摘できるのです。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)174ページより)
--例えば「定説」側の出版物によく登場する話の一つに、このような話があります。第二アウシュヴィッツ(ビルケナウ)収容所では、特に1944年になると、毎日、大勢の人々が、「ガス室」で殺され、焼却されたことになっています。
その主張に符合するかのように、「定説」側の出版物やドキュメンタリーなどには、そのビルケナウで、死体焼却棟の煙突から煙がのぼっているのを見た、という「証言」や「体験談」がしばしば引用されています。殺されるユダヤ人他の犠牲者が多かったので、「ガス室」のみならず、「ガス室」に隣接する焼却棟がフル稼働していた、というなのでしょう。この話は特に、その44年の目撃談として、こうした「定説」側の本や雑誌記事などに、非常によく登場します。
ところが、こうした「死体を焼く煙」の「目撃証言」に疑問を投げかける、ある客観資料があるのです。それは、航空写真です。即ち、この44年になると、アメリカやイギリスはしばしばポーランド上空にまで偵察機を飛ばし、軍需工場が多かったこのアウシュヴィッツ=ビルケナウ周辺で多数の航空写真を撮っていたのです。
そうした航空写真が79年にCIAによって公開されたのですが、その一枚をここにお見せしたいと思います。驚くほど鮮明に、当時のアウシュヴィッツ=ビルケナウの様子が映し出されていることが、お分かり頂けると思います。こんな写真が、当時の連合軍機によって、その44年に多数、撮影されていたのです。
ところが、こうした44年のアウシュヴィッツ=ビルケナウの航空写真のどれを見ても、多くの「目撃者」が「証言」する、「死体焼却炉の煙突から上がる煙」は、全く確認することができないのです。また、当時のアウシュヴィッツ=ビルケナウ及びその周辺では死体を野焼きした、というような「証言」もありますが、そんな「死体の山」も、「野焼き」の様子も、多数撮影された連合軍機撮影の航空写真には全く写っていないのです。その「肢体を焼く煙」は、多くの「証言」によって語られてきたものです。そして、それは、アウシュヴィッツを取り上げた多くの記事やドキュメンタリーにおいても、繰り返し、語られてきたものです。それなのに、その煙がこれらの航空写真に写っていないのは、一体どうしてなのでしょうか?--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)174~177ページより)
--それから、こういう問題もあります。それは、「ガス室大量殺人」に関する「目撃証言」がお互いに矛盾している場合があるということです。それも、救いようがないまでにです。
例えば、こういう例があります。アウシュヴィッツで最初に青酸ガスによる大量殺人が行われた時の状況については、幾つも、「目撃証言」があります。それらによると、それは、第一アウシュヴィッツの第11棟という建物の内部で、チクロンBによる大量処刑が実験的に行われた時だった、ということになっています。ところが、それに関する複数の「証言」を注意深く観察すると、その日付けも、所要時間も、建物の中の場所も、処刑の方法も、救いようがないまでに食い違っていることを、見直し論者の一人であるイタリアの研究者カルロ・マットーニョ(Carlo Mattogno)は指摘しています。例えば、日付けについては、41年の7月から12月まで、6か月もの間に「証言」が食い違っています。また、犠牲者たちが死ぬまでの時間は、「即死」から一晩まで。そして、その場所は、その第一アウシュヴィッツの第11棟の地下室というものの他、その廊下など。中には第11棟の外の「ガス室」だった、というものすらあるというのです。「思い違い」で説明するには、それぞれの「証言」はあまりにも「リアル」で「具体的」過ぎるのが不思議です。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)177~178ページより)
--こうした事例は、まだまだたくさん挙げることができます。しかし、それよりも、ある意味では、もっと決定的な事実があるのです。それは、「証言」内容を追及されて、それまで語り続けてきた自分の「目撃証言」を、「実は人から聞いた話だった」等と、事実上、撤回した人間が少なからずいるという事実です。しかも、それらの中には、前述のドキュメンタリー『ショアー』に登場する「生き証人」を含めて、マスメディアなどで、「アウシュヴィッツの生き証人」として持ち上げられてきた人々もが、含まれているのです。
例えば、ある有名な「目撃証人」は、永年、アウシュヴィッツで「ガス室大量殺人」の現場を自分の目で見た、と「証言」してきました。ところが、ある裁判でその内容を追及されると、途端に「それは、実は人から聞いた話だった」等と言って、そんな事柄を目撃していなかったことを認めているのです。それも、法廷においてです。
この「目撃証人」が、「ガス室大量殺人」の「目撃証人」として大変有名だったために、この出来事は外国の新聞では大きく報道されています。しかし、日本では何故か、こういう事実の存在が全く知られていません。それどころか、「ガス室目撃証人」の言葉といえば、何か絶対の真理ででもあるかのような思い込みが存在し、それを疑ったり、検証することなど思いもよらない、といった空気が、特にマスメディアを支配しています。「マルコポーロ」廃刊事件の際、私を取材しに来た新聞記者たちの多くが、「証言があるじゃないですか」等と言い、その「証言」を検証しよう などとは全く考えていなかったことは、その一例です。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)178~179ページより)
--このように、ウソの「証言」はあった、としか考えようがありません。考えたくないことですが、そうとしか、考えようがないのです。ただし、ここで言っておきますが、私は、意図してウソの「証言」をした人々は、大勢いた被収容者たちのごく一部に過ぎなかっただろうと考えています(後述)。問題は、むしろ、そうした虚偽の「証言」が、何故、マスメディアなどで大きく取り上げられてきたかということです。即ち、「証言」とは選ばれるものであり、選ぶ側が公正な存在でなければ、真実を語った百の証言よりも、虚偽を語った一つの「証言」の方が大きく扱われることもある、ということです。私は、皆さんに、このことに気付いて頂きたいのです。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)179ページより)
--特に、虚偽の証言が一人歩きする時には、そうした「証言」を選ぶ側の問題が大きいことは、過去の冤罪事件が教える教訓です。実際、冤罪事件の経過を調べると、「証言」を集める側が都合のよい証言ばかり拾っていたり、逆に都合の悪い証言は取り上げていなかったりした事例の多いことが、容易に分かります。 すぐ後でお話ししますが、ニュールンベルク裁判をはじめとする連合国による戦後の裁判や、戦後のマスメディアは、この問題について、決して公平公正な裁判、報道を行なってはきませんでした。ですから、そのニュールンベルク裁判や戦後のマスメディアが「証言」を選んできた基準が一体どのようなものであったかを考えず、ただ「証言がある」といっても事の真相には到底迫れないと思うのですが、違うでしょうか?
例えば、これはほんの一例ですが、皆さんは、そうした「証言」を選んだ連合国が、戦後の幾つかの戦犯裁判の裏で、ドイツ人被疑者に拷問を加えて自白調書を作成していたことを、ご存知でしょうか?(後述)これは、その拷問に関する調査を行なったアメリカの議会記録に詳細に記録されていることなのですが、このようなことが裏で行われていた裁判で採用された「目撃証言」や「自白」をそのまま信じて良いものなのでしょうか?「ガス室大量殺人」について、「証言があるのだから」と言う人に限って、こういうことを知らないのは、偶然ではないような気がします。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)180ページより)
--この「ガス室」の問題は、ユダヤ人迫害に関わるテーマだけに、「目撃証言」を疑ったり、その不合理、矛盾を指摘したりすると、感情的な反応を生むのは、ある意味では仕方のないことなのかも知れません。私自身、「マルコポーロ」廃刊事件の際、一番聞かれたのはこの「証言」の問題でしたし、その際、かなり感情的なことを言う人もいたことが、印象に残っています。そこに、この「証言」の問題が持つ独特の性格があるのだと思います。
しかし、私はここで皆さんに、ちょっと冷静に考えて頂きたいのです。歴史上の様々な出来事について、或いは社会の大きな事件などについて、有名になりたいとか、或いはその他の動機から、見てもいないことを「証言」したり、事実を著しく誇張、歪曲する「証人」が現われることは、考えてみれば、全く珍しいことではないのです。特に、この問題のように、大変な数の関係者がおり、その中にドイツ人に憎悪を持つ人々が多数含まれている場合、そうした現象がより顕著に出現することは、容易に想像できると言えるでしょう。問題は、先ほど申し上げた通り、そうしたウソの「証言」が、何故選ばれ、大きく取り上げられるのか、という点にあるのです。
もう一度言いますが、この「ガス室」に関して、「証言」を選んできたのは、連合国の政府であり、それに追随した欧米のマスメディアでした。そうした「ガス室目撃証言」の選び手たちは、果たして本当に公正に証言を収集していたのでしょうか?--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)181~182ページより)
--このことに関連して、前にも名の出たフランスの見直し論者(リビジョニスト)ロベール・フォーリソン博士は、ある重要な事実を指摘しています。それは、戦後、ドイツ人戦犯を対象にして開かれたどの戦犯裁判でも、「ガス室目撃証人」に対する交差訊問(cross examinaion)が全く行なわれていなかったという、驚くべき事実です。
ご説明するまでもないとは思いますが、ここでいう「交差訊問」とは、弁護側が検察側の証人に質問をし、検事が被告側証人に質問をすることです。つまり、「反対訊問」と同じことですが、その「交差訊問」が、戦後どの裁判でも、「ガス室目撃証人」に対しては、何故か一度も行なわれていなかったという、驚くべき事実です。
あの有名なニュールンベルク裁判を含めて、ドイツ人戦犯を対象にした戦犯裁判は、ダッハウ裁判、アウシュヴィッツ裁判、トレブリンカ裁判など幾つも開かれてきました。イスラエルで開かれた、あのアイヒマン裁判もその一つに数えることができますが、それらの裁判記録を読むと、他の事柄はともかく、こと「ガス室」に関してだけは、法廷で、「目撃証人」に対して、弁護側(ドイツ人側)の弁護士がその「証言」を問い正すということが一度もなかったと、フォーリソン教授は指摘しているのです。
これが何を意味するか、考えて頂きたいと思います。そうです。これは、これらの裁判で偽証が野放しだったことを意味しているのです。少なくとも、結果的にはです。
しかも、フォーリソン教授によると、これは、別にそうすることが禁じられていたとかいうことでは毛頭なく、ただ単に被告(ドイツ人側)の弁護士たちが「ガス室目撃証人」たちに質問しようとしなかった、というだけのことだというのです。だからこそ、これは驚くべきことだと言えます。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)182~183ページより)
--このように、弁護側から「ガス室目撃証人」に対して交差訊問が全く行なわれなかった理由は、つまるところ想像するしかないわけですが、このことを指摘するフォーリソン教授は、これが何故なのかを疑問に思い、そうした戦犯裁判の弁護士の一人に、どうして「ガス室目撃証人」には質問しなかったのか?と聞いたことがあるそうです。すると、この弁護士は、次のように答えたというのです。--もし、「ガス室」の「目撃証人」が言うことに疑問など投じたら、自分が弁護している被告が「ガス室大量殺人」に関係あるような印象を与える可能性があった。他のことはともかく、自分が弁護する被告が「ガス室」にだけは無関係だと法廷に印象付けるためには、「ガス室」については質問しないことが一番良いと考えた。--もっともな答えです。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)183~184ページより)
--この「ガス室目撃証人」に対する交差訊問の問題は、戦後のドイツ戦犯裁判がどのようなものであったかを考えさせる上で、大きな示唆を与えていると、私は思います。先ず、「ガス室目撃証人」に対する交差訊問が行われていなかったということは、今述べたように、これらの裁判において、偽証が横行していたことの状況証拠と言って、言いすぎではありません(現に「偽証」としか考えようのない「証言」はあります)。
そして、このことは、これらの裁判の雰囲気が一体どのようなものかであったかを語っているとも言えるでしょう。即ち、ドイツ人側の弁護士が、「ガス室大量殺人」に質問するだけで、被告が「ガス室大量殺人」に関与していたかのような印象を生みかねなかった、というのがこれらの裁判の雰囲気だった、ということなのですから。
既にお話ししていることですが、これら戦後の戦犯裁判の一部で、連合国側の取調べ官たちが、ドイツ人被疑者に拷問を加えて「自白調書」を作成していたことが、アメリカの議会記録に明記されています(この記録は、日本の国会図書館にもあります)
また、アウシュヴィッツ収容所の司令官だったルドルフ・ヘス(Rudolf Hoess)という人物は、戦後イギリスに捕らえられ、ニュールンベルク裁判に出廷した後、ソ連支配下のポーランドに身柄を移され、処刑されていますが、そのヘスがニュールンベルク裁判に出廷した際、イギリスは、彼の「自白調書(Affidative)」を提出しています。[このヘス(Hoess)は、戦争中イギリスに飛行したヘス(Hess)とは全くの別人]
この「自白調書」は短いものですが、その中には例えば、ヘスが、アウシュヴィッツでチクロンBによる大量殺人を開始させたのは自分だ、と「告白」している個所などがあり、事実なら、大変な証言ということになります。そのため、当然と言うべきでしょう、この文書は、アウシュヴィッツ収容所の司令官がアウシュヴィッツでの「ガス室大量殺人」について「自白」した文書として、「定説」側歴史家によって非常に重要視されてきました。
ところが、そのヘスを占領下のドイツで逮捕した際、彼を取り調べて、この「自白調書」を作成したイギリスの軍人バーナード・クラークは、後年、ヘスの取り調べを回想したインタビューの中で、何と、ヘスを逮捕した際、彼に激しい暴力を加えたことを自慢するように語り、その「自白調書」が拷問の産物であったことを暗示しているのです。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)184~185ページより)
--拷問で自白調書を得るなど、法的にも人道的にも許されないことは言うまでもありません。たとえ相手が何者であろうとも、です。しかし、私がここで皆さんに考えて頂きたいことは、現にそのようなことが行われた裁判で「認定」された事柄を、検証もせず、「事実」として鵜呑みにしてよいのか、という問題なのです。言い換えれば、拷問によって書かれた「歴史」を私たちは検証もせずに受け入れるべきか、という問いを、皆さん一人一人に、私は考えて頂きたいのです。何故なら、それは、私たちの自由に関わる問題だからです。
象徴的な言い方をしますが、拷問によって書かれた歴史を信じる事を強制され、それに異をはさむことが許されない社会が、民主主義社会であるわけがありません。私は、そのような社会に生きたいとは思わないのです。そんな社会こそは「ネオナチ」の社会だと思いますし、そんな歴史を信じろと言う人々が、自由を愛する人々だとも、信じられません。
拷問によって書かれた「自白」だけでなく、交差訊問も受けずに語られた「証言」や後には、「証言」の主自身が撤回した「証言」までをそのまま鵜呑みにし、「歴史」を語るということは、事実という神聖なものに対する冒涜であると私は思います。そして、事実が尊重されないところに、自由や民主主義が存在するわけがないと、私は思うのです。
これは、ナチスや第二次世界大戦に関する道徳的議論とは全く別の次元の問題であり、もし、私のこの問いかけを「ナチスの弁護」などと呼ぶ方がいたとしたら、その方こそは、その「ナチス」に最も近い方ではないかと、私は思います。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)185~186ページより)
--こうしたことをふまえた上で、次の事実に注目して頂きたいと思います。アウシュヴィッツ=ビルケナウやトレブリンカといった、「ガス室」があったとされる収容所に入れられていたユダヤ人他の人々の中には、実は「ガス室」の存在に否定的な証言をする人々がいるのです。それも、そこに永く収容されていた人々です。皆さんの中には、ユダヤ人たちは皆、「ガス室」があったと言っているような錯覚を抱いている方が少なくないと思いますが、実はそうではないのです。言うまでもなく、これは極めて重要な事実ですが、多くの方は、それを知りません。それは、これら「ガス室」に否定的な証言が、何故か戦後の戦犯裁判においても、マスメディアにおいても、不当に無視され続けてきたからだと思われます。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)187ページより)
--例えば、戦後、西ドイツ(ドイツ連邦共和国)で開かれた戦犯裁判の一つにトレブリンカ裁判という裁判がありました。これは、戦争中、ポーランドのトレブリンカで起きたとされる出来事を「証言」に依存して裁いた裁判です。
既に述べているように、このトレブリンカ収容所という収容所は「定説」によれば「絶滅収容所」で、ワルシャワの東方にあったこの小さな収容所では多くのユダヤ人が「ガス室」で殺された、と説明されています。先にご紹介したアブラハム・ボンバ氏が、そこに在った「ガス室」で女性の髪を刈らされたと語っていたのも、このトレブリンカ収容所とされています。
ところが、この裁判の初期に、注目すべきことが起きているのです。即ち、この時、トレブリンカの元被収容者たちの中から、自分はトレブリンカにいたけれど、「ガス室」など見たことも聞いたこともなかった、と証言する人々が幾人も現れたのです。(「ガス室に否定的な証言」とは、こうした証言、或いはそれに類似した趣旨の証言を指します)。
ところが、この裁判を開いた西ドイツの司法当局は、何故か、これらの証言を全て無視しています。そして、「ガス室」があったとする趣旨の「証言」ばかりを採用し、トレブリンカ収容所がどんな収容所で、どんな「ガス室」があったか、というような「事実認定」を行なっているのです。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)187~188ページより)
--当然ですが、このトレブリンカ収容所が認定した「事実」は、「定説」側歴史家たちのトレブリンカに関する記述にも影響を与えています。例えば、ここにお見せするのは、コゴン(Kogon)という「定説」側歴史家の編集による著作に載っている、トレブリンカ収容所の見取図ですが、これはまさしく、そのトレブリンカ裁判で採用された「証言」に基ずいて、法廷が「認定」した「事実」の一つとされているわけです。
この見取図については後で触れますが、「定説」側論者によると、このトレブリンカ収容所には「ディーゼル・エンジンで一酸化炭素を発生させるガス室」があったということになっています。しかし、ディーゼル・エンジンの工学的特性の一つは、一酸化炭素を極く微量しか排出しないことなのです。
ですから、この「ディーゼル・エンジンで一酸化炭素を発生させるガス室」というものは、不可能ではないかも知れませんが、驚くほど不合理な方法なのです。しかし、その点については次章で論じるとして、その「ガス室」の実物は、ともかく、今日、トレブリンカの収容所跡には現存しないのです。「ドイツが隠滅したから」なのだそうですが、「ガス室」のみならず、この収容所そのものが、今日、完全に消失しているのです(ドイツが、「定説」側論者が主張するように「隠滅」を企図して収容所を破壊した証拠はありません)。
こういうことですから、私たちは残念ながら、この「ディーゼル・エンジンで一酸化炭素を発生させるガス室」の実物を見ることもできません。あるのは、ただ「証言」だけなのです。しかし、その「証言」の一つが、4平方メートルの「ガス室」に百数十人もの人間が入ったと語った、あのボンバ氏の「証言」であることは、記憶すべきことに違いありません。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)188~190ページより)
--では、そうした「ガス室」に否定的な証言を無視して、「ガス室」に肯定的な証言ばかりを採用した、そのトレブリンカ裁判の「事実認定」が信頼できるものだったかと言うと、例えば、こんな不思議なことがあるのです。戦争中、連合軍が、アウシュヴィッツの航空写真を多数撮影していたことは既に述べましたが、このトレブリンカについては、ドイツ軍が撮影した航空写真が残っています。ただし、このドイツ軍の航空写真は、戦後、アメリカが押収して保管していたもので、89年になってようやく公開されたものです。
ですから、60年代に西ドイツでトレブリンカ裁判が開かれていた時には全く知られていなかったものなのですが、その航空写真を見ると、60年代に西ドイツで行われたこのトレブリンカ裁判の「事実認定」とは大きく食い違う事実が幾つも見て取れるのです。例えば、この収容所の敷地の形は、トレブリンカ裁判によれば、189ページにお見せしたように、長方形をしていたことになっています。それは、もう一度言いますが、この裁判で採用された「証言」が、トレブリンカ収容所の敷地はそんな形をしていたと述べているからです。ところが、89年に公開された航空写真を見ると、トレブリンカ収容所の敷地は長方形ではなく、扇形をしていたことが一目瞭然なのです。
また、この航空写真を見ると、トレブリンカ収容所で採用された「目撃証言」が「ガス室」があったという場所に建物は写っていなませんが、これは、「隠滅」されたからなのでしょうか?それに、トレブリンカ裁判が採用した「証言」では、トレブリンカ収容所は二重の鉄条網で囲まれていたと「証言」されているのに、そうではなかったことも、この航空写真からは明らかなのです(この航空写真と、189ページでお見せした、トレブリンカ裁判が「認定」した見取図とを見較べて下さい)。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)190~192ページより)
--そして、もう一つ、トレブリンカ裁判で採用された「目撃証言」の信憑性に疑問を投じる事柄があります。それは、80年代後半から90年代初めにかけて、アメリカ、ソ連、西ドイツ、そしてイスラエルを巻き込む形で発生した、ある冤罪事件が投げかける疑問です。即ち、80年代に、ジョン・デムジャンジュク(John Demjanjuk)氏というウクライナ系アメリカ人が、ソ連からアメリカへの「通報」によって、戦争中トレブリンカで「ガス室」を運転していた、という嫌疑をかけられ、アメリカからイスラエルに身柄を移された後、一旦は、死刑の判決を受けたという事件です。この冤罪事件について詳しくお話しする余裕はありませんが、同被告が93年にイスラエルの最高裁で無罪を勝ち得たことは、氏がトレブリンカで「ガス室」を運転していた等というソ連発の「情報」がいい加減なものであったことを証明しています。そして、この冤罪事件の過程で、トレブリンカの元被収容者と名乗る人物が複数登場したのですが、彼らの「証言」の虚構がこの裁判の中で露呈した結果、今お話ししているトレブリンカ裁判が実はいい加減に「証言」を採用していたことが、間接的に暴露される結果となっているのです。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)192~193ページより)
--ここにお見せするのは、このデムジャンジュク氏の裁判の結末を報じた日本の新聞記事ですが(「読売新聞」1993年7月30日。同紙ではデミャニュク氏)、このように、冤罪事件は、トレブリンカのみならず、トレブリンカのみならず、「ガス室大量殺人」の「目撃証言」全般に疑問を投じさせる結果を招いてしまったと言って、決して間違いではありません。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【エルサレム29日 村上大介】イスラエル最高裁は二十九日、第二次大戦中、ナチ占領下のポーランドにあったトレブリンカ・ユダヤ人強制収容所の残虐な看守「イワン雷帝」だったとして起訴されたウクライナ出身の元ソ連兵イワン・デミャニュク被告(七三)に対し無罪を言い渡した。判決は五人の判事の全員一致で、被告が「雷帝」とは別人であると疑う合理的な理由があると述べ、一審特別法廷の死刑判決を覆した。
--「ユダヤ人虐殺」容疑に無罪--
--生存者証言覆し「被告は別人」 イスラエル最高裁--
ソ連兵だった「雷帝」は、ドイツ軍の捕虜になった後、志願してナチに協力。一九四二年から二年間にユダヤ人八十五万人が虐殺された同収容所のガス室で働き、残虐の限りを尽くしたとされる。
被告は戦後、難民として米国に渡り、自動車工として働いていたが、七九年、移民の際に虚偽の申告をしたとして起訴され、八六年にイスラエルに引き渡された。一審特別法廷で、同被告は「戦争中はナチの捕虜だった」と主張したが、トレブリンカの生存者の証言が死刑判決の決め手となった。
しかし、弁護側は一審判決後、ソ連崩壊の過程で国家保安委員会(KGB)によるナチ協力者に対する尋問調書を入手。トレブリンカで看守をしていた複数の元ソ連兵が「雷帝の本名はイワン・マルチェンコだった」と供述していたことが判明した。
これに対し、検察側は、同被告がポーランドの別の収容所(ソビボール)で看守だったことを示唆するナチ文書を提出、「被告がナチに協力していた事実だけで有罪とするに十分」と主張した。
これまでホロコーストをめぐるナチ戦犯裁判では、生存者の証言が疑われることはほとんどなかったが、デミャニュク裁判で、それが大きく揺らいだ。
[写真:判決を聞くためヘッドホンをつけてもらうデミャニュク被告(ロイター)]
(読売新聞 1993年7月30日)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)193~194ページより)
--「ガス室」の存在に否定的な証言を無視して「事実認定」を行なったトレブリンカ裁判は、結局このようなものだったということです。しかし、「ガス室」に否定的な証言がユダヤ人他の元被収容者の側から為されているのは、トレブリンカだけではありません。アウシュヴィッツ=ビルケナウにつても、そこにいたユダヤ人他の元被収容者から同様に、「ガス室」の存在について否定的な証言が為されているのです。
例えば、既に何度か取り上げている、クロード・ランズマン監督の『ショアー』にすら、そのような証言は載っています。この本は、前述のように、アウシュヴィッツ=ビルケナウやトレブリンカの元被収容者たちの「証言」を「定説」側論者たち、或いは、シオニストの立場から集めたものですが、そのような出版物にすら、次のような証言が収められているのです。
「私たちは、B2Bブロック、または『家族用収容所』とも呼ばれる区画に連れていかれました。子供も、男も、女も、皆いっしょで、前もって選別されることはありませんでした。『男性用収容所』の囚人が、私たちのところにやって来て、アウシュヴィッツは絶滅収容所で、ここで人々を焼き殺すのだ、と言いました。私たちはそれを信じませんでした。B2Bブロックには、私たちより三か月前の、九月に、テレジン収容所を発った移送組がちゃんといたからです。先着組も、そんな事は信じていませんでした。というのも、私たち全員が再会したからです。だれ一人、連れ去られた者はいなかったし、だれ一人焼き殺された者もありませんでした。だから、私たちは、そんな事を信じなかったのです。」
(クロード・ランズマン著 高橋武智訳『ショアー』338~339ページ:ユダヤ人女性ルース・エーリアスの証言より)
この証言は、「ガス室」そのものについては何も断定していません。しかし、この証言の内容が、毎日、大勢の人々が「ガス室」で殺されていったとする、「定説」側論者たちが語る「アウシュヴィッツ」とかけ離れたものであることは、お分かり頂けると思います。その意味で、この証言は「ガス室」に否定的な証言と呼べると思いますが、こうした証言をする人々が何人もいるのです。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)194~195ページより)
--「定説」側論者たちがこうした証言について言うことは、分かりきっています。このルース・エーリアスのような証人は、たまたま知らなかった、たまたま見なかっただけだ、と言うのです。しかし、この論法なら、誰でもあらゆることを「目撃者がいる」というだけで「証明」できりことになってしまいます。考えてもみて下さい。仮に、誰かが「私は湖で恐竜を見た」と言ったら、「そんなものは見たことがない」という証言は、たとてそれが、ずっと湖畔に住んでいた住民のものであっても、論証もせず、一方的に無視してしまってよいのでしょうか?それならば、ネッシーも存在することになると思いますが、「定説」側論者の「目撃証言があるのだから、ガス室はあったのだ」という論法は、これとどれだけ違うものでしょうか?--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)195~196ページより)
--このように、「ガス室」の存在に否定的な証言は、ユダヤ人からも、そしてドイツ人からも提出されていたのですが、戦後の司法当局やマスコミは、それらを不当に無視してきました。そればかりか、ドイツなどでは、こうしたことに加えて、何と政府が、「ガス室大量殺人」に疑いをはさむような言論を法律で規制しているのです。
ですから、たとえユダヤ人でも、「ガス室」の存在に否定的な証言を発表し、「ガス室」の存在に異論を提出することは困難ですし、ましてやドイツ人の場合は、たとえ戦争中アウシュヴィッツにいたような人でも、こうした証言をするには、社会的な危険を覚悟しなければなりません。例えば、こうしたことを証言した場合、それだけで年金を剥奪される可能性もあると言われているのです。こうした状況が戦後ずっと続いているのですから、「ガス室」については、その存在を「確認」するような言論ばかりがはびこり、少しでもそれに疑問を投じるような証言や発言は、容易に発表できないのです。しかし、そうした「ガス室大量殺人」に否定的な証言し、発表されています。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)196~197ページより)
--そうした証言をするドイツ人の一人に、ウィルヘルム・シュテークリッヒ(Wilhelm Staeglich)博士という、ドイツの元判事が挙げられます。このシュテークリッヒ博士は、ドイツ連邦共和国(西ドイツ)で永年に渡り判事を務めた人ですが、若い頃、軍務でアウシュヴィッツを訪れたことがありました。
ところが、そこで若き日のシュテークリッヒ博士が見たものは、戦後語られ、信じられているような「アウシュヴィッツ」とは全く違ったものであったと、博士は67年以来、証言しています。それによると、博士は、44年に、第12防空部隊の将校として、アウシュヴィッツ近くのオシエク(Osiek)という村に滞在しながら、アウシュヴィッツの収容所を何度も訪れたということです。しかし、そのいずれの訪問においても、被収容者が死や虐待におびえているような様子は全く見られなかったと、博士は述べています。
これは、「ガス室」そのものに言及した証言ではありませんが、アウシュヴィッツが言われているような「絶滅収容所」とはかけ離れた場所であったということを意味します。つまりそこは、確かに強制収容所えはあったが、不必要な虐待が日常茶飯事に横行しているような場所ではなかった、というのが、博士が、アウシュヴィッツに何度も足を運んだ者として証言していることなのです。こうした自分自身の体験に加えて、博士は、アウシュヴィッツに関するそれまでの「証言」を裁判官の目で徹底的に再検討し、79年に発表した自身の研究書の中で、アウシュヴィッツにおける「ガス室大量殺人」の話に正面から異論を提出しています。
その結果、博士は何と、自身の博士号を剥奪されるという政治的迫害を受けています。言論弾圧としか言いようのないことですが、このようなことがドイツでは起きているのです。しかも、シュテークリッヒ博士に対するこのような決定は、この問題を巡る言論弾圧の一例に過ぎません。それどころか、欧米では、「ガス室」に疑いを投じる人々に対するテロすら起きているのです。
こうした事柄については後で触れますが、読者の皆さんは、このような社会的状況下で、当時を知る生き証人たちが本当に自由にものを言えたとお考えになるでしょうか?そして、欧米のこうした状況下で、マスメディアがアウシュヴィッツなどに関する証言を公正に伝えてきたとお思いになるでしょうか?「証言」の問題というものは、このように、誰が証言を選んでいるか、という問題に収束されるように思われます。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)197~198ページより)
--こうしたことからお分かり頂ける通り、「証言があるから、ガス室はあったのだ」等というのは、何も知らない人の言うことなのです。しかし、現実にはそうした「証言」だけに依拠して、何も物証のない「ガス室大量殺人」が、疑うようのない事実であるかのように語られてきました。ところが、その「証言」には、前述したように、虚偽としか考えようのないものが多数含まれています。大部分の人々は、このことに気付いていません。その一方では「ガス室」の存在に否定的な証言が、戦後、不当に無視され、伝えられずにきたため、多くの人々はそうした証言の存在にすら気付かない、という状況も続いてきました。ですから今日、半世紀に及ぶこうした思い込みに支配された人々にこうした論争の概要を理解して頂くのは、はっきり言って、心理的に大変な抵抗に出会うことを覚悟しないとできることではありません。特に、「証言」の問題は、そうした心理的抵抗が非常に強くつきまとう問題に違いありません。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)199ページより)
--もう一度くり返しますが、ウソの証言はありました。これは、ナチスの被害者の中にウソの「証言」をした人々がいたとは考えたくはありませんが、そうとしか考えようがないのです。ただし、私は、「ガス室を見た」と主張する生き証人たちの全てが、故意にそうした証言をしたなどとは全く思いません。「証言」そのものは無数にあり得るわけですが、あえて最後に想像を付け加えたいと思います。
私は、特にアウシュヴィッツの元被収容者の中には、全くの善意から、「ガス室ではないものを「ガス室」だったと勘違いして証言している人が相当いるのではないかと思っています。何故なら、既にお話しした通り、アウシュヴィッツ=ビルケナウでは、火葬場の建物の地下や内部に「ガス室」があったと説明されているからです。つまり、そうした火葬場の建物を見た人々が、戦争中そこにいた時はそのようには全く考えていなかったのに、戦後、マスメディアなどでそれらの建物の地下や内部に「ガス室」があったと聞かされ、「そうか、あの時は知らなかったが、あの建物はガス室の建物だったのか」と思い込む例がかなりあるのではないか、と思うのです。こうしたことは、大きな犯罪事件などでは、現にしょっちゅう起こっています。即ち、事件の現場にいた人が、事件後聞かされた情報によって自分の記憶を再解釈し、事実とかけ離れた証言をしてしまうことなどです。こういうことは、心理学の本にも書かれている、非常にありふれた現象で、現に多くの冤罪事件が、こうした集団心理学的な現象によってくり返されています。ですから、もし、「証言」だけで「ガス室大量殺人」を語ろうというなら、当然、こうしたことをも考慮し、「証言」を一つ一つ検証することが、「ガス室大量殺人」があったと主張する側には課せられることになります。言うまでもないことですが、全ての出来事は、それがあったと主張する側に挙証責任があります。ところが、これまでお話しした通り、「ガス室」の存在を主張する論者たちは、その責任を全く果たしていないのです。
そのようにして、「証言」だけで成る事柄を「事実」と主張しながら、その「証言」をも検証しようとしないなら、最早、信じろと言う方が無理ではありませんか。
「マルコポーロ」廃刊事件の際、新聞記者たちが私にした質問は、この「証言があるのだから、ガス室はあったのではありませんか」というものばかりでしたが、彼らは、「ガス室」があったと主張するなら、主張する人々には挙証責任があることを完全に忘れているように思えました。こういう彼らの報道が、あの松本サリン事件の場合のように、冤罪を生み出しているのは偶然ではないと、私は思います。--
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)199~201ページより)
--最後に一つ、興味深いお話を紹介して、この章を終えたいと思います。数年前、私は、この「ホロコースト」に関する研究会を何度か続けて開いたことがありました。そこには、私の意見に好意的な方も批判的な方も共に参加されましたが、そうした参加者の一人に、731部隊の研究で最高の権威とされる、ある高名な大学教授が来ておられたのです。大変尊敬している方なので、緊張してお話をしたのですが、その際、「ガス室大量殺人」に関する「証言」についても当然、議論が行なわれました。ところが、その際、その731部隊の研究家は、ご自身の経験として次のようなことをお話し下さったのです。
その教授は、731部隊の諸行為を実証的に解明し、発表してきた立派な方ですが、そうした研究の過程で、戦争中、731部隊のことを知っていたとか、彼らの行動を目撃した、などという多くの人々に会い、その証言に接してきたという体験の持主なのです。それで、そうした証言の問題については、ご自身、色々な体験をしておられるのですが、その教授がそうした731部隊に関する証言を収集する過程で気ずいたことは、思い違いによる証言というものが、非常に多い事だった、というのです。
誤解のないように申し上げておきますが、私はもちろん、人体実験をはじめとして、731部隊が多くの非人間的行為を行なったことを疑ってなどいません。ましてや、その教授はそうした諸事実を研究発表してきた方なのです。ところが、その教授が、そういうことを述懐しているのです。例えば、「私は、生体実験を見ました」と言う人に会って話を聞くと、どうも話がおかしい。それで、詳しく聞いていくと、その人はウソなどはついていないのだけれど、その人が見たのは、「生体実験」などではなく、通常の病理解剖だったらしい。しかし、その人は、それを「生体実験」だと固く思い込んでいて、善意からそれを話して聞かせてくれた、というような例が多々あった、というのです。このエピソードも、証言の問題は、詰まるところ、誰が証言を選ぶかという問題に収束されることの一例とはいえないでしょうか?--(第4章 終はり)
(西岡昌紀「アウシュウィッツ『ガス室』の真実/本当の悲劇は何だったのか?」(日新報道・1997年)201~202ページより)
(続きはここで読めます)
↓
http://www.asyura2.com/08/holocaust5/msg/190.html
(クリックして下さい)
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。