| Tweet |
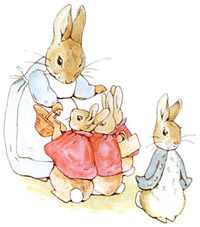
http://melma.com/contents/moneyfeature/081208.html
チベットを“売った”と揶揄される英国勢
2008/12/8
私たち=日本の個人投資家・ビジネスマンはマーケットとそれを取り巻く国内外情勢を見る際、「地政学リスク」というとどうしても地球の裏側のことばかり考えてしまいがちだ。しかし、地図の上をよく見ると、不安定な地域として掲げるべき筆頭格はむしろ日本を取り巻くアジアであることに気付く。日本についても、“北方領土”“尖閣諸島”“竹島”など、未だに「紛争」となっている事案に取り囲まれているのである。
そのような懸案事項の中で、戦後アジアにおける最大の問題の一つに「チベット問題」がある。ダライ・ラマ14世に率いられた亡命政府が世界中に対し、中国政府による“人権侵害”を訴えるのに対し、中国政府はというとこれを国内問題であるとし、諸外国からの批判を一切受け付けない態度に終始してきた。米国をはじめとする西側各国はいずれもこれを深刻な問題であるととらえ、中国に対して問題の解決を求めてきている。だが、中国はといえばこれをいわば対中関係における“踏み絵”としてとらえ、最近でもEU議長国であるフランスのサルコジ大統領がEU中国首脳会談を申し込んだのに対し、「フランスがチベットの肩を持った」と糾弾、会談自身をキャンセルしたくらいである。
実はこのように中国が勢いづいていることには理由がある。―――こともあろうに西側諸国の雄であるはずの英国が、ここにきて完全に中国寄りの姿勢を持つに至ったのである。具体的には、ミリバンド首相がここにきて「英国は、チベットに対する領有権を中国が持っていると考えている」と中国側に伝達したのだ(11月1日付ウォールストリート・ジャーナル(米国)参照)。これに対し、米国勢は猛反発。「英国はチベットを“売った”」と糾弾する論調すら現れる展開になっている。日本ではしばしば“アングロ・サクソン”と十把一絡げにされがちな米英だが、実はその間で今、激しい火花が散り始めているのである。
もっとも、このような中国大陸をめぐる米英の確執という構図は、金融資本主義の歴史を紐解くと繰り返し現れてくるものであることに気付かなければならないだろう。この点について、日本におけるアカデミックな研究として金字塔とも呼べる論文と目されているのが、三谷太一郎「ウォール・ストリートと満蒙」(細谷千博他編「ワシントン体制と日米関係」東京大学出版会所収)だ。
この論文によれば、米英のこうした確執がもっとも見て取れたのが、他ならぬ日本が展開したプロジェクト「満州」(現在の中国東北部)なのだという。日本は1931年以降、一気にこれを押し進め、それがやがて日中戦争、そして第二次世界大戦へと連鎖していく。1945年に待ち受けていた「敗戦」という冷厳な現実だけを後から学ぶと、あたかも共に連合軍であった米英が最初から結託して日本を抑え込みにかかったかのようにも見えてしまう。
しかし、実際には全く異なるのである。日本はプロジェクト「満州」を実現すべく、ひとつには南満州鉄道(満鉄)の外債を大量に発行した。ところがこれらはいずれも英国のポンド建だったのであり、すなわち英国勢の支援を受けて発行されたものだったのである。その背景には「英国にとっては“Manchuria”は中国における勢力圏の外にあり、日露戦争後ロシアの南下が止った後は、直接に国家的利益に関係する地域ではなかった」(前掲論文)からだ。
ところが、「米国にとっては、“Manchuria”は、1899年以来の門戸開放政策を象徴する意味をもっていた。・・・(中略)・・・とくに満州および中国北部の「門戸開放」を含意していた」(前掲論文)であった。そのため、利回りの良い日本勢の外債であっても、満鉄外債には協力はしなかったというわけなのである。実際、満鉄外債が米ドル建で、NYにおいて発行されたことはなかったのだ。
これだけを読んでも、自称「評論家」「国際問題専門家」たちがしばしば口にする“アングロ・サクソン”という表現が虚構に満ちたものであることがおわかりいただけるであろう。そもそも、米英はそれぞれ異なる勢力なのであり、抱えている利益関係は各々の歴史に基づき異なっているのである。そのことを踏まえ、これまで東アジアの“現場”で展開されてきた確執を知らなければ、今起きている「チベット問題」をはじめとして、マーケットとそれを取り巻く国内外情勢について正しい予測分析をすることはできないのである。
こうした論点も含め、今後、激動が想定される“マーケットとそれを取り巻く国内外情勢”と、その背景にありながら私たち=日本の個人投資家が知ることのなかった歴史上の“真実”について、私は、12月20・21日に東京、横浜でそれぞれ開催するIISIAスタート・セミナー(完全無料)で詳しくお話できればと考えている。ご関心のある向きは是非ともお集まりいただければ幸いである。
ちなみに、英国勢による突然の「中国のチベット領有確認発言」は、どこぞの島国の閣僚にありがちな“失言”などでは全く無いことは、その周到さからもわかるのである。インターネット化の進んだ現在、対外情報工作機関にとって最も重要なのは動画サイトを通じた世論工作になりつつある。そのような観点をも踏まえつつネット上を探すと、実は英国勢はかのYoutubeを使用し、あらかじめ「“チベット”なる存在を支えてきたのは米国の情報工作機関であった」というドキュメンタリー・フィルムを公開すらしているのである。
一般に日本では全く問題視されていないが、日本語字幕のフィルムまでもがアップされていることに注目すべきだろう。このことを通じ、英国勢は重要なメッセージ、すなわち「アジア、とりわけ東アジアを米国から取り戻す」というメッセージを発している可能性があるからである。
つまり、歴史の針は1840年代の“アヘン戦争”のころに戻った感があるのである。日本ではその後、幕末となり、明治維新となったことを思い起こしながら、「今、すぐそこまで迫った世界システムの大転換」に向け、隠された「潮目」の予兆をしっかりと読みこなしていくことこそ、私たち=日本の個人投資家・ビジネスマンに課せられた最大の課題なのである。その私たちが大転換の時代をいかに生き抜き、いかなる新たな「日本」を築き上げていくべきかという点については、来年(2009年)1月に開催する「新刊記念講演会」で私なりの考えをお話するつもりである。ご関心の向きはご来場いただければ幸いである。
[新世紀人コメント]
これは「オバマ政権」の奥に潜む本質を探る上でも重要な視点であろう。
この様に書くといささか離れた事柄を引っ張り出して来た様に見えるが実はそうではない。
オバマ政権にも米英の利害関係の対立は潜んでいる筈だ。
2 81 +−
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。