| Tweet |
(回答先: WTO年内合意を誓約=金融危機克服へ政策協調−APEC首脳が特別声明【時事ドットコム】 投稿者 ワヤクチャ 日時 2008 年 11 月 23 日 16:51:46)
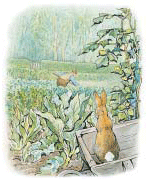
スーザン・ジョージ『WTO徹底批判!』から WTOについて 後編
http://tama9-jo.at.webry.info/200607/article_4.html
<< 作成日時 : 2006/07/23 16:14 >>
トラックバック 0 / コメント 0
前回の続きとして、今回はWTOという組織について考えてみたい。前回の最後に述べたとおり、WTOの国際会議の際に世界各地で起こる大規模な批判デモというのは、必ずしも偏狭なナショナリストや保護貿易主義者のみによって行なわれるわけではない。むしろ「持続可能な開発sustainable development」や南北問題(先進国と途上国の経済格差)などを視野に入れた、より公正な貿易ルールを求める人々によるWTOへの抗議が中心であるともいえる。WTOの抱える問題と米国産牛肉輸入再開との問題と関連付けながら、この問題を考えていきたい。
こうしたWTO批判において、以前このブログで紹介したスーザン・ジョージがその中心的な理論家の一人となっている。彼女の『WTO徹底批判!』(作品社、2002年)を軸に、何故WTOが問題なのかを見ていこう。そうすればおのずと、米国産牛肉の輸入再開の論理が、WTO体制の下では「正当」とされる現実を知ることができるからである。ちなみに同書は、農産物の貿易だけでなく他の様々な分野、特にサービス貿易に関するGATSという協定などの問題点もわかりやすく説明している。以前紹介した『オルター・グローバリゼーション・宣言』より分量も少ないので、こちらを先に呼んだほうが彼女の問題意識は分かりやすいかとも思う。
『WTO徹底批判!』の中でスーザン・ジョージが述べていることのうちの重要な点のひとつは、WTOという国際組織は、国際連合と何ら直接的な関係を持たないものであるということである。このことは決定的に重要である。引用を見よう。
例えば、あなたがWTOの加盟国に属していて、二つのサッカーボール ―ひとつは衛生的・エコロジー的にとてつもない条件のなかで子どもによってつくられたボール、もうひとつは組合加盟している大人の労働者によって作られたボール― の前に輸入者として立ちあっていると仮定してみよう。WTOの規則に従うなら、あなたはこの二つのボールの違いを考慮して、どちらかを優位においてはならない。なぜなら、一方のボールは他方のボールと「同種」のものだからである。(26ページ)
WTOはその組織下で作る国際協定内において、独自の拘束力を持つ国際的慣習を成立させる。その際上の引用が示していることは他でもない、国連体制の国際法の体系においては本来遵守されるべき国際人権規約や子どもの権利条約などの諸人権基準が、WTOの貿易ルールが適応される範囲においては無視されるわけである。ILOにおける労働基準などでは違法となるべき児童労働や劣悪な労働環境で作られた製品と、きちんとした労働基準を守って作られた同一種類の製品を同じ条件下で売買しなければならないのがWTOのルールであることを、上の引用は述べているのだ。そうなれば、労働力の取り換えのききやすい現在の国際労働市場では劣悪な環境の企業の方が安い製品を作れることになるわけで、非人道的な企業、およびそうした企業を野放しにする国家が繁栄し、その国の弱者(=賃金労働者)や、国連のルールを守ろうとする企業や国家は馬鹿を見ることになってしまう。
こうしたルールが理不尽なものであると感じる方であれば、BSE問題に関してのアメリカ牛肉の輸入再開にも納得がいかないのではないだろうか。しかしそれが通ってしまう状況だからこそ、WTO体制が問題なのである。とある途上国が劣悪な雇用条件を許容しているとする。この国が本気で長期的に産業を発展させようと思えば、本当は児童労働などせず、教育に力を入れて質の高い労働者や技術者を育てる必要がある。しかしWTO体制の下では、労働条件や環境対策の切下げ競争が起こるので児童の保護や教育環境の整備が困難となり、その途上国は途上国という立場から抜けられない。
このようなルールが当たり前のものとなっていくと、今回の日米間で起きた牛肉の件などもあたりまえとなってしまう。WTO体制におけるTBT(技術的貿易障壁に関する協定)とSPS(衛生植物検疫措置に関する協定)という協定を通してスーザン・ジョージが書いていることを見るとそのことがよくわかると思う。
このいずれの協定も、生産物の無害性に疑いがある場合、無害性を証明する責任は買い手=輸入者にはないという、予防原則の適用を非常に困難なものにする。したがって、危険に直面した政府は、絶対的な科学的根拠がなくても、人間・動物・植物の健康と安全を保護するために行動する決断を下さねばならない。こうした予防原則は、健康や環境といった領域―こうした領域では、生産物や生産方法の有害性は具体的に顕在化するのに長い時間がかかり、手遅れになるのが多いのは周知のところである―においては不可欠のものである。(32ページ)
BSEのような、非常に不透明な、悪い影響を与えうるものも、その害の可能性が現在の科学でははっきりわかっていなければ、輸出側に責任がない。更には、輸入側も健康や環境という観点からその製品の輸入をストップすることが出来ない。こうした構造こそ現行のWTO体制が作りつつあるものである、ということを考えるならば、地球環境や人間の健康な生活を守るために、WTOとは異なる国際貿易のルールを模索していく必要があるのではないか。
- 諸悪の根源=WTOを批判 ワヤクチャ 2008/11/23 17:29:07
(0)
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。