| Tweet |
(回答先: Re: 30年間、「市場は万能」 ・・ アングロサクソンモデル <-- 自由、経済、数学 投稿者 健奘 日時 2008 年 10 月 09 日 15:35:21)
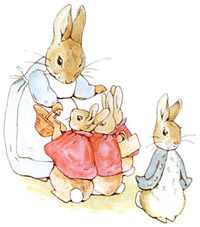
第二章 グローバリゼーションはユートピアを実現するか?
http://d.hatena.ne.jp/rainbowring-abe/20050831#1125416516
■世界を「売り物」にする多国籍企業−企業という名の精神病質者− 00:41
ヨーロッパのナンバーワン実業家と讃えられた元ABB社(電力とオートメーション技術に関するスイスとスウェーデン合併の多国籍企業。世界100ヶ国に進出している)社長のパーシー・バーネヴィック氏がグローバリゼーションについて正直で率直な定義をしています。
「私はグローバリゼーションを次のように定義する。つまり、私のグループ企業が望むときに望むところに自由に投資できる自由、そして、私のグループ企業が生産したいものを生産し、買いたいと思うところから買い、売りたいと思うところで売り、しかも労働法規や社会慣行による制御を可能な限り、撤廃する。そういった自由を享受することである。」
なんとも身勝手な考え方であると個人的には思いますが、そもそも企業とは利己的な存在のようです。
企業=営利の目的で継続的・計画的に同種の経済行為を行う組織体。また、その活動。(三省堂「大辞林」より)
そして、現在、資本主義国家にある多くの企業、多国籍企業のほとんどは株式会社です。
株式会社=構成員の地位が細分化された株式という形式をとり、株式の自由譲渡性、および構成員たる株主の有限責任などを特色とする企業形態。機関としては株主総会・取締役会・代表取締役などがある。物的会社の典型的なもの。(三省堂「大辞林」より)
ブリティッシュ・コロンビア大学の法学教授ベイカン・ジョエル氏は『ザ・コーポレーション−わたしたちの社会は「企業」に支配されている−』(早川書房)の中で、企業の持つ精神病質 的な性質について言及しています。
企業とは機関であり、一連の強い原則の集まりであって、その原則が企業人の行動を規定します。その原則とは「営利の追求」です。また、株式会社において会社の所有者は「株主」です。法人 として企業に定められた使命は「株主」に利益をもたらすこと。法的には、経営者および従業員は「株主」に最大限の利益をもたらすための"手段"でしかありません。したがって、株主に利益をもたらさなければ、経営者や従業員は解雇されて当然な存在なのです。
法律で企業とその所有者が別扱いとなったことで、企業は地域社会に対する責任から解放されました。企業は「法人」として個人に与えられる法的な権利を享受していながら、個人が負ういかなる道徳的義務も負わなくてよいのです。株主の責任も「有限責任」であり、出資した額以上の損失がないように保護されていますから、必然的に企業は無責任になりがちです。最近、企業の社会的責任について盛んに言われていますが、ジョエル氏は、新古典派経済学の第一人者といわれるミルトン・フリードマン氏の「経営者の唯一の社会的責任は、株主のために多額の金を儲ける事、これが道徳的な義務だ。社会や環境上の目標を利益に優先する(道徳的に振舞おうとする)経営者は、非道徳的だ。企業の社会的責任が容認されるのは、それが利益追求の方便である時のみで、偽善が収益に寄与すれば良く、道徳的善意も収益に繋がらなければ非道徳だ。」という発言を紹介し、その限界を指摘しています。そして、燃料タンクが炎上する危険を知りながらも訴訟された際の費用と安全策をとった場合の費用対効果では訴訟された場合の費用のほうが安くつくという理由でそれを放置したGMの例や、予算削減、リストラ等で安全性、環境汚染を犠牲にし、その結果、爆発事故を起こしたBP(ブリティッシュ・ペトロリアム)等の実際に起きた事例を数多く提示しています。
社会的責任と株主の利益が一致していればよいのですが、社会的責任を果たすと、その結果、株主の利益を損なうようなことがあれば、経営者は株主の利益をとらざるを得ません。他者への思いやりは「株主への背任」とみなされてしまうのです。また、利益を上げ続けなければならないという宿命は、経営者から人間的・道徳的な判断を奪っていきます。
このような企業の「機関」としての性格を、心理学者であり、精神異常の専門家であるロバート・ヘア博士に診断してもらったところ「精神病質に極めて近い」という結果になったそうです。ヘア博士の診断結果をみてみましょう。
人々が企業経営者として取る態度や行動の多くは精神病質であるといえます。その理由は「競争相手を叩き潰そうとし、あれこれ策を弄して出し抜こうとし、商品を買ってくれる限り、大衆のことなどたいして気にはしていない」からです。
また、企業は無責任であるとし、その理由は「自らの目標を追求する上で、他のいかなることも危険にさらしてしまう」こと。
企業は「すべてを操ろうとし、世論でさえ、その例外ではなく」常にもったいぶっていて、絶え間なく「われわれが一番だ。われわれがもっとも優れている」と言い立てている。
ヘア博士は、共感を欠き、非社会的である傾向も企業の特徴だといいます。
「企業の行動は、犠牲者のことを心から気にかけていないことを示しています」
そして、企業はしばしば自らの行動の責任を取ることを拒み、良心の咎めも持っていない。
「企業は違法行為が発覚したら高い罰金を支払い…また性懲りもなく同じことを繰り返すのです。そして実際、たいていの場合、彼らが支払う罰則や罰金は、かき集める利益に比べると微々たるものです。」
最後にヘア博士は、企業は他者とうわべだけの交流を持つといいます。
「企業の最終的な目的は、大衆に好かれる姿を演じることです。しかし、その真の姿は、およそかけ離れています」
実際、本物の精神病質者は、偏執的な自意識過剰と言う危険な性格を魅力で覆い隠す点で悪名高い。これを企業に当てはめれば、社会的責任が同じ役割を果たしていることがある。企業は偽りの思いやりや気遣いを示せるが、実際、自分のこと以外は何ひとつ考えられない。
企業経営者が、人格的に問題があるというわけではありません。むしろ経営者と言われる人は学歴も教養も常識もあり、人望もあって、家庭に戻れば良き父であり母である場合が多いでしょう。しかし、ビジネスの世界での人格は別なのです。世界的な規模でシェアを奪い合う熾烈な競争を繰り広げなければならない企業経営者は、倒産したライバル会社の社員が自殺しようが、下請けの労働者が過労死しようが、地球環境がとめどなく悪化しようが、気にしていられません。そんなことを考えていたら自分の会社が負け組となって、大切な社員や家族を路頭に迷わせることになってしまいます。企業の持つ宿命的な性質の下では、その構成員が個人としてどれほど善良であろうと関係ないのです。
このような性質を持つ企業が巨大化し、世界中をまたにかけて活動しているのが多国籍企業です。トップから200位までの多国籍的企業だけで世界の経済活動の約4分の1を占めています。まさに『道徳なき商業』が地球上を席巻し、世界を混乱に陥れていると言えるのではないでしょうか。
かつて日本の経営者たちは「株式会社」という西欧起源の制度を日本的な文脈に翻訳して導入しました。日本の会社は、形式上は株式会社でも、実態は社員に生業を提供し、社会に良品を提供することを主な目的とする「公共に奉仕する存在」であろうとしたのです。このような「会社」に慣れ親しんだ日本人は、本来の「利潤追求を唯一の目的」とする企業の姿を知らなかったと言えるでしょう。華やかにみえる"外資系"と呼ばれる企業も、実体は、利益をあげられない者は容赦なく切り捨てられていく厳しい世界です。たとえ日本を襲う"第一の波"である財政破綻を乗り越えても、"第ニの波"であるグローバリゼーションは避けられないでしょう。なぜなら日本政府も経営者たちもエコノミストたちも、それが何をもたらしてきたのかという現実は見ようとせず、市場原理・新自由主義を信望している からです。自由競争社会では、決して本当に公平な競争がおこなわれているわけではありません。「勝ち組」に残っている間は良いのですが、いったん「負け組み」に転落したらどういう目にあうか…。途上国の歴史がそれを証明しているのではないでしょうか?
●コラム 南海泡沫株事件 −バブルの起源−
かつて英国では、株式会社は堕落と醜聞の温床になると懸念され、1720年に株式会社を不法としました。そのきっかけになったのが「南海泡沫株事件」です。
1711年、イギリスでロバート・ハーリー伯爵により南海株式会社が設立されました。南海とは南アメリカ大陸の海岸のことで、この会社はイギリス政府によって南アメリカ大陸との貿易の独占権が与えられました。この時期、イギリスではスペイン継承戦争の時期に生じた政府債務が問題になっていて、英国債の引き受けをおこなう見返りに、南海株式会社は貿易の独占権を手に入れたのです。
当時、東インド会社が、目覚しい利益をあげていたこともあり、南海株式会社の株に人気が集まりました。イギリスは強大になりつつある国家であり、多くの人が富を蓄えていたという背景もあって株価が急騰します。株価が急騰することによって、突然、多くの人が金持ちになり、それを見た他の人々も「我も我も」とこのブームに殺到し、ますます株価を押し上げたのでした。
1720年の1月には128ポンドだった株価が、6月には1050ポンドにもなりました。しかし、当時の南アメリカ大陸はスペインの支配下にあり、イギリスと南米との貿易の拡大は現実にはありえなかったのです。南海株式会社は、ほとんど事業による利益をあげていませんでした。また、将来的にも発展する見通しはなかったのです。南海株式会社の実態は、次第に皆が知ることとなりました。
ところが、この南海株式会社の株騰貴によって、他にも多くの同じ様な模倣者が多く生み出されていきました。まともな会社としては、馬に保険をつける会社、石鹸の製造技術の改善を図る会社、牧師館および教区牧師の家を修繕・改築する会社、私生児を受け入れて養育するもしくは病院を建てる会社などがありますが、毛髪の取引をする会社とか、水銀を可搬性の純金属へ変換する会社とか、永久運動を開発する会社とか、海水から金を取得する会社とか、或いは「大いに利益になる事業をするのだが、それが何であるか誰も知らない」という不滅の会社、等々、まるで冗談のような会社が続々と設立されたのです。
この便乗商法の動きに政府が待ったをかけました。1720年7月には泡沫会社禁止法(バブル法)なる法律が制定され、南海株式会社以外の「株式会社」を禁じる処置を打ったのです。この法律は南海株式会社の株価を維持するための方策でもありましたが、その努力も空しく、南海株式会社の株価は8月に頭打ちとなり、同年12月には124ポンドにまで暴落していきます。その結果、多くの人が破産し、イギリス経済は大混乱となりました。責任者の追求が始まり、南海株式会社に関与した多くの人が、自殺をしたり、財産を没収されたり、刑務所に入れられたのです。この「南海泡沫株事件」が語源となり、のちに「バブル」といわれるようになりました。
●コラム チューリップ投機 −世界初のバブル−
もう一つ、株にまつわる歴史的な事件をご紹介します。世界で最初に起きた典型的な「バブル」です。
1634年、当時のオランダは平和が続き、海洋貿易で富を蓄え、国力が衰退したスペインにかわり、世界の覇権を握りつつありました。オスマン=トルコから入り品種改良を重ねられた美しいチューリップは、富の象徴としてオランダで大流行。豊かなオランダには、お金が余っていましたから、人々はこぞって球根を買い漁るようになり、価格が急騰しました。特に珍しいチューリップの球根の値段は、限りなく上昇し、ついに投機の対象になっていきます。
チューリップ自体には特に関心がない人も、値段が上がりそうだと言われているので買い求める。すると、実際に値段が上がる。それを見て、人々は自分の予想が当たったとして更に自分の予想に自信を深め、更に買い求める。するとまた値段が上がる…という構図です。買えば確実に値上がりするチューリップに、お金持ちも普通の市民も財産をつぎ込んでいきました。また「一定期日に球根を入手できる契約書」の売買、今で言うところのオプション取引もさかんに行われるようになりました。そして、センパー・アウグストゥスという種類の球根は、1個2000ギルダー(市民の平均年収の8年分)から6000ギルダーにまで高騰したのです。ブームの最高潮の時には、球根1つに当時の平均的な労働者の年収の10倍もの値段が付いたということです。今の日本の平均的なサラリーマンの年収を400万円くらいだとすると、球根1つに4000万円くらいの値段がついたわけです。
しかし、1637年のある日、所詮はチューリップの球根であることに皆が気づいたのか、球根の価格は、突然、暴落しました。球根は、貴重な財産から、ただの球根に戻り、多くの人は財産を失いました。また、借金で投機を行っていた多くの人は破産していきました。この影響を受け、オランダ経済全体が長期間の深刻な不況に陥ったそうです。そして、これを機に世界経済の中心地はロンドンに移っていきました。
今も昔も人間のやることにはあまり変わりがないようです。「歴史は繰り返す」とか「喉元過ぎれば熱さ忘れる」とか言われますが、いったい人間は何度同じ過ちを繰り返せば学習することができるのでしょうか?
http://d.hatena.ne.jp/rainbowring-abe/20050831#1125416516
|
|
- アングロサクソン資本主義の次、人喰い21世紀カニバリズム資本主義 【第1回十字軍がシリアのマアッラで人肉食を行った】 愚民党 2008/10/09 20:12:43
(0)
|
|
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
|
|
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。
|
|
|
|
|
|
|
|