が10日、テクニカル上の上値抵抗線だった106円半ばを上抜け、3カ月ぶり高値を更新した。バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長の発言などをきっかけに、市場では米当局が信用リスク問題をにらんだ金融緩和から、インフレとドル安警戒に軸足を移したとの見方が強まっている。ドルは短期的に2月高値の108円台への上昇を見込む声も上がっている。
<米当局のインフレ懸念・ドル安けん制姿勢が明確に>
10日午前の取引でドルは一時106.83円まで上昇。4月半ばから続いてきた102円半ばから106円付近のレンジ相場を上抜けた。最近の取引レンジ上限にあたる106円半ばではこれまで通り、上抜けは難しいと見た短期筋に加え、久々の円安水準とあって輸出企業もドル売り姿勢を強めたが、今回は買いの勢いが勝った。
ドルが数カ月続いた取引レンジを上抜ける最大の要因となったのは、米当局の姿勢の変化だ。これまではサブプライムモーゲージ(信用度の低い借り手向け住宅融資)問題をきっかけとする信用リスク問題への対応を前面に打ち出していたが、前週の3日、バーナンキFRB議長が「ドル安はある程度インフレへ影響を及ぼし、われわれはそのことをはっきりと認識しており、注視する意向だ」と発言。市場ではドルが上昇したが「なぜこのタイミングで、弱いドルを支持してきたFRB議長がドル安けん制とも取れるような発言をするのか」(ある外銀の外為チーフディーラー)と驚きの声が上がった。
しかしその翌日も、再びFRB議長がインフレに警戒感を示したのに続き、9日はニューヨーク連銀のガイトナー総裁、ダラス連銀のフィッシャー総裁らもインフレと通貨安に言及。さらにポールソン米財務長官にいたっては「介入もその他のどのような政策手段も排除しない」と介入も辞さない姿勢を示したことで「当局の姿勢は完全に変わった。自国通貨高誘導が始まった」(別の外銀チーフディーラー)と、相次ぐ発言で市場関係者の視線はドル高方向に動き始めた。
それを決定付けたのが、今回のFRB議長発言だ。日本時間の午前9時過ぎ、ボストン地区連銀主催の会合で「最近のエネルギー価格上昇がインフレと、インフレ期待の上振れリスクを高めた」として、「連邦公開市場委員会(FOMC)は、長期的なインフレ期待による浸食に強く抵抗する」とあらためてインフレに言及。国内経済についても「今四半期の活動は鈍化する見通しだが、景気が大幅な下降局面に入るリスクは過去1カ月で低下したようだ」と楽観姿勢をにじませた。
6日に発表された米雇用統計で失業率が3年半ぶりの水準へ悪化しただけに、FRB議長の姿勢には前週以上の関心が集まっていた。ドル安への直接的な言及はなかったものの、発言は「タカ派的だ。失業率上昇を経てもなお、インフレ警戒姿勢を強調した」(バンク・オブ・アメリカの日本チーフエコノミスト兼ストラテジスト、藤井知子氏)との見方が、ドルの取引レンジ突破につながった。
市場筋によると、106円半ばを上抜けたドル/円の次の上値めどは、昨年12月高値から3月安値までの61.8%戻しにあたる107円半ば。さらに2月高値の108.62円までの上昇も「十分考えられる状況になってきた」(都銀の外為ディーラー)という。
<G3通貨は二極化へ>
当然、原油高を背景とする世界的なインフレの強まりは米国だけの問題ではない。欧州中央銀行(ECB)のトリシェ総裁も5日の理事会後、記者会見で「状況を慎重に分析した結果、インフレ期待抑制を確実にするため、次回の会合で政策金利の小幅な変更を決定する可能性があると考えた」と発言。市場では7月の利上げを示唆するものとの見方から、ユーロ/ドルはわずか2日間で1.53ドル後半から1.57ドル後半まで400ポイント上昇。史上最高値の1.6ドル台から小幅下落した水準にあたる5月高値に迫り、ユーロ/円は7カ月ぶり高値を更新した。
米国のインフレ警戒・ドル安けん制発言と、ECBの利上げ観測の高まり――。ドルとユーロでともに通貨高を招く動きが強まる一方、日銀は金利据え置きが大勢との見方が依然として多いことで、市場では「ドル買いなら対ユーロより対円のほうが走る」(後出の外銀)、「対ドルも対ユーロでも円売りしか思いつけない」(さらに別の外銀チーフディーラー)と、G3通貨の二極化を見込む声が増え始めた。
<メジャー通貨への資金シフトは本格化せず>
ドルとユーロという2大通貨に買い人気が集まっても、その他マイナー通貨からのメジャー通貨への大きなマネーシフトを予想する声はまだ多くない。ある都銀のチーフディーラーは「インフレ懸念は世界的な問題。オセアニアの豪州やアジアの中国、その他東欧の一部マイナー通貨などでも、利上げ期待を背景に買い需要が根強い。経常黒字でファンダメンタルズがしっかりしていている国の通貨も売られにくい」と話す。
市場筋によると、ドルが急伸したこの日のアジア市場では、韓国やタイ、インドが相次ぎドル売り/自国通貨買いの介入に踏み切ったが、買い人気の根強い豪ドル/円は101円前半で一進一退、豪ドル/米ドルも0.94ドル後半のもみあいとなった。FRB議長発言の後はいったんドル買いが優勢となって豪ドル/米ドルも小幅に下落したが「資源高と金利先高観から豪ドルは売られにくい」(別の都銀関係者)と、下げは限られた。
<米利上げの実現性に疑念の声くすぶる>
ただ市場には、今回のドル買いの流れは勢いづかないとする声も残る。失業率が3年半ぶりの悪化を示し、ほぼ予想通りとはいえ景況感指数などの指標も景気減速を示している米国で「本当に近い将来に利上げができるのか」(バンカメの藤井氏)との見方だ。
さらに来月には、7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)が4月声明文で「しっかりした情報開示を行うよう強く促す」と釘を刺した米系金融機関が、第2四半期決算の発表を控える。信用リスク問題は一服との見方が大勢だが「流動性供給で表面上の落ち着きを見せているだけ。外銀のバランスシートが厳しい状況は何も変わっていない。東京ですら、内部にいればそれは実感できる」(ある在京外銀の幹部)という。
ドル高の主因となる米当局の急速な姿勢の変化をめぐっても、思惑はくすぶる。多くの関係者は信用リスク問題の一服と同時に、顕著な原油高でインフレ懸念がさらに顕在化してきたことが背景と見るが「突然すぎる。原油高は今に始まったことではない。米国は中東各国に対し、原油増産を迫る代わりにドルの上昇で(原油が下落してもオイルマネーが保有するドル資産の)目減りを防ぐとでも約束したのではないか」(ある都銀関係者)といぶかる声も上がっている。
10日午前のフェデラルファンド(FF)金利先物1月限FFF9はFF金利が年内に2.695%になる可能性を示唆する水準まで売られた。すでに年内に二度の0.25%の利上げを織り込んだドルは「急激な上昇は見込みにくい。時間をかけて指標をにらみながら、少しずつ上昇するのではないか」(後出の外銀)。前週末時点では、FRBが政策金利を年内に0.5%引き上げる確率はわずか約2%だった。
現在のレートは、時系列のレートはJPNUTKYFXをご覧下さい。
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.
http://jp.reuters.com/article/forexNews/idJPnTK011948520080610
次へ 前へ
▲このページのTOPへ
HOME > 国家破産57掲示板
フォローアップ:
投稿コメント全ログ
コメント即時配信
スレ建て依頼
削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/
since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。
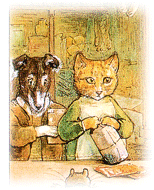
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。