| Tweet |
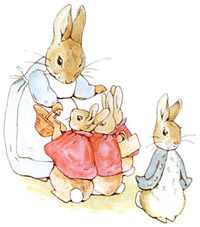
株式日記と経済展望
http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu154.htm
http://blog.goo.ne.jp/2005tora/
--------------------------------------------------------------------------------
湾岸戦争は、米国の唯一の超大国としての世界支配の始まりだった。
12年後に『イラク侵攻』と『占領』をもって、米国の力の限界を露わにした。
2007年10月16日 火曜日
◆イラク占領―戦争と抵抗 パトリック・コバーン(著)
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4846107078.html
◆ぐずぐずに崩壊するイラク 書評 松浦 晋也
http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/bookreview/31/index.html
本書は2002年のイラク戦争前夜から、2006年前半までのイラク情勢を扱っている。原著は2006年10月に出版され、邦訳は今年の4月に発売された。原著出版からそろそろ1年が経過したが、本書の価値は下がっていない。歴史や生活習慣から、政治情勢に至るまで、イラクを熟知した練達のジャーナリストが、現地の生の状況を取材して情勢分析を行った ―― わたしは、本書をイラク情勢を把握するための必読書であると評価する。(中略)
宗派や民族とは別に、イラクの人々は、強固な地縁血縁の社会的網目の中に生きている。地域や血縁に対する忠誠心は、時として国家への忠誠心を上回る。
また、彼らは一般に日本人と比べて血気盛んであり、しかもごく当たり前に武装している。イラクは、男ならば銃を持ち家族や血族を守るのが当然という、米国以上の銃社会だったのである。
実のところ、イラク国民の暴発を防いでいたのは、強固な連帯を誇る各派の社会的コミュニティだった。一族の族長の命令は絶対であった。
しかし、湾岸戦争以降の経済封鎖による困窮がコミュニティを弱体化させていた。困窮は犯罪を多発させ、軍からの武器横流しが横行した。その結果、イラクは一般市民に至るまでが、「血族を守る」という理由から近代的兵器で武装するという状況にあった。
弱体化したコミュニティと、生活苦を背景とした不満の中に、イスラム原理主義が浸透していく。原理主義は、シーア派、スンニ派を問わない。むしろ「血族がやられたらやり返す」というイラク人のメンタリティに、イスラム教の一部の教義がお墨付きを与えたと言うべきだろう。
一神教を信じる血気盛んな人々が、貧困に苦しみつつも近代的兵器で武装している。彼らは三派に分かれており、長年の圧政で相互不信は増大している。人々の忠誠心は独裁者フセインが仕切る国家ではなく、地縁血縁に向けられている。さらに周囲の国には反米と対になったイスラム原理主義が横溢している ―― これほど、テロリズムにとって理想的な培地は他に存在しないだろう。
そんな状況の中に、米国軍は、石油利権に引かれて異邦人の占領者として乗り込んでいったのだった。(中略)
本書の末尾は以下の言葉で結ばれている。
「クウェートからイラクを追い出した1991年の戦勝は、米国の唯一の超大国としての世界支配の始まりだった。それは同時期に、ソ連がうまい具合に崩壊してくれたからでもあった。
そして2003年以降の米国のイラク占領‥‥。それは米国の没落の始まりかも知れない。
サダム・フセインは発作的な傲慢さでもって、クウェート征服という身の丈を超えることをした。それと似た傲岸さでジョージ・ブッシュは12年後に『イラク侵攻』と『占領』をもって、米国の力の限界を露わにして見せたのである。」(本書p.363)(中略)
サダムにはスターリンと違って、あの『ピンクパンサー』の映画に出てくる、クルーゾー警部的なところがあった。自分が仕出かした過ちに学ばず、自信過剰を反省しないで、いつも失敗ばかりしている、あのキャラクターである。」(p.38)
そんな人物が四半世紀近くも権力を維持できた理由は、秘密警察にあった。密告を奨励し、恐怖で国民生活そのものを締め上げる手法で独裁政治を維持してきたのである。
独裁の維持には戦争も有効だった。外敵が存在すれば、国内の締め付けに理由を付けやすくなる。1981年から8年続いたイラン・イラク戦争は、フセインの独裁体制維持にはプラスに働いたろう。1991年の湾岸戦争以降の国際的な経済制裁も、独裁体制維持という観点からすれば、むしろフセインにとっては有意義だったと言えるのかもしれない。
しかし、戦争は同時にイラク国民と経済の両方を疲弊させた。
このように考えてくると、それなりに機能していたイラクという国家が、ぐずぐずに崩壊した理由は、まずなによりもフセインという特異なキャラクターによる独裁政治にあることが分かる。そして、独裁の維持にあたって、秘密警察と戦争が有効であったということも。
いや、むしろ、「独裁者」「戦争」「秘密警察」は、相互に関係していると考えるべきなのかも知れない。この三つは、国家におけるがんのようなものと考えるべきなのだろう。とするならば、これらの発生を防ぐことが、国家の崩壊を回避するにあたって重要だということになる。
逆に、これらを回避できなければ、日本であっても、イラクのような混乱に陥る事があり得る。「日本は単一民族だ」「抱える歴史的経緯が違う」という考えは、たしかにあり得る。しかし、かつてのイラクだって、多民族多宗派で複雑な歴史を抱えつつも、まずまずうまくやっていたのである。
本書を最後まで読み終えて感じるのは、著者のようなベテランジャーナリストの重要性だ。著者は、30年近くイラクを含めた中東を取材し続け、歴史も社会も知り尽くし、取材相手から信用を勝ち得て人脈を作ってきた。
ひとたび戦争や占領というような異常事態になると、このようなジャーナリストが発信する情報が、非常に重要になる。日ごろの取材と人脈なくして、正確な情報を入手することが難しくなるからだ。
著者はアイルランド出身で、英国の新聞社に勤務している。このような「中東スペシャリスト」とでもいうべきキャリアを歩むにあたっては、英国という国が何世紀にもわたって植民地を支配してきた老かいな国であることも無関係ではないだろう。優れたジャーナリストは、国家の安全保障や諜報活動、ひいては世界の安全保障にとっても重要なのだ。
このようなスペシャリストは、2〜3年で記者を別の分野に異動させるような人事システムでは育たない。5年、10年と一つの取材対象を執念深く追い続けることによってのみ、著者のようなスペシャリストになることができる。
現在日本の報道機関は、どこもほぼ例外なく、2年程度で記者を次の部署に異動させる人事システムを採用している。新聞社にもテレビ局にも、スペシャリストと呼べる記者はほとんどいない。日本においては、主に組織のくびきを逃れたフリーランスのジャーナリストがスペシャリストとなって活動している。
フリーランスに頼っているということは、日本の大メディアがスペシャリストを育成する責務から逃げているということでもある。
特にイラクのような場所のスペシャリストになるということは、生命の危機をも受け入れて取材を行うことを意味する。大メディアとしては、社員が誘拐された死亡したりという事態をなるべく避けたい。面倒な取材対象は、後腐れないフリーランスに任せ、ニュースを買い上げるほうが会社経営としては安全だ。
だが、それは資本力のある大メディアが、日本の、ひいては世界の安全保障という責務から逃げていることを意味する。
わたしたちの不幸は、このような本を翻訳によってのみ読むことができるということだろう。本来ならば、本書のような対象に肉薄した本を日本語で書く記者がいなくてはならないはずなのだ。
そのような人材を育成することは、日本のマスメディアの責務であろう。混沌とする世界情勢の中で、今後、スペシャリストとしてのジャーナリストの需要は増えることこそあれ、減ることなどはないはずだから。
(私のコメント)
13日に「国家情報戦略」のことを書きましたが、政府のために情報を扱う仕事が情報部であり、国民の為に情報を扱う仕事がジャーナリストということになるのだろう。だから情報部員とジャーナリストとは仕事としてはほとんどダブっており、スパイのカバーとしては新聞記者などが多い。
日本の報道機関には在日の人が多いようですが、情報部員がカバーとして入り込んでいるのだろう。世論操作も情報部員の重要な仕事の一部だからだ。だから国家として情報部員兼ジャーナリストを養成しているところもある。テレビなどで活躍しているデーブ・スペクターも情報部員兼タレントとして活躍している。
昨日も書いた事ですが、情報部員や国際ジャーナリストとして活躍する為にはその国に20年から30年は暮らして根を生やさないと、とてもその国の情報を得ることは出来ない。ところが日本では大新聞社にしても大テレビ局にしても特派員を2年程度で移動させてしまう。松浦氏の書評にあるように日本企業はスペシャリストの養成を避けている面がある。
企業としてはスペシャリストが出来てしまうと、自由な人員配置が出来なくなり、人事の主導権が奪われることを異常なほど恐れる。スペシャリストは他の人に代えがたい存在となるから企業と対等な関係になり人事を扱いづらくなる事を恐れるのだろう。私もサラリーマン時代に一つの仕事に慣れてくると、こんな楽な仕事で高い給給料もらえるのなら天国と思える時もありましたが、会社はそんな天国のようなポストに安住させてくれはしない。
日本には中東を専門とするジャーナリストはおらず、イラクの状況がどうなっているのかを知る手段は無い。それに対してイギリスには中東に30年も在住するパトリック・コバーン記者がいる。FT紙やインディペンデント氏などの特派員をしていますが、湾岸戦争の時もイラクに留まり報道した。現在もバクダッドなどの危険なところでの取材を続けている。
日本には国家情報機関がないだけでなく、あったとしても優秀な人材がいなくては機能しない。外務省や公安調査庁があったとしても機能しなければ意味がない。アメリカのCIAにしてもカーター時代のリストラで中東の専門家の多くが解雇されて、それがイラク問題を拗らせる原因となった。いったん解雇するとそれに代わる情報部員を養成するのに20年も30年もかかる。
日本の大メディアがこのようなスペシャリストを養成しないのは、国家的にも損失であり百人以上いる大使館よりも一人の有能な情報部員が重要な役割をする。それに対して2年や3年の駐在員では言葉を憶えるのもままならず新聞の切り抜き程度の情報収集しか出来ない。「株式日記」で情報機関を作れと書いて来ましたが人材の養成が一番の問題だ。
私はこの「イラク占領」という本をまだ読んではいないが、歴史的な分析に基づいた記事は読み応えがあるようだ。日本語版の翻訳者である大沼安史しのブログでも次のように書いている。
◆〔イラクから〕 P・コバーン著、 『イラク占領』(仮題) 翻訳を終えて 大沼安史
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2007/02/post_c2c4.html
本書を翻訳しようと思ったのは、蜃気楼のようにつかみがたい、「イラク戦争」「イラク占領」の実態を見事に結晶化させ、描き出しているからだ。「イラク戦争」「イラク戦争」の現実を、内側から「活写」しているからだ。
ぼくは湾岸戦争直前のバグダッドに、新聞社の特派員として二度入り、カイロにも駐在して、その後もそれなりに「中東ウォッチ」を続け、生意気にも「ちょい中東通」を自認していた。が、本書はそんなぼくの「過信」を粉々に打ち砕いてくれた。ぼくはほんとうに何も知らなかった。バグダッドもイラクも、「戦争」も「占領」も。
本書の内容紹介は重複になるので省くが、読み終えた読者はたぶん、コバーン記者の歴史的なパースペクティブの深さに感心させられたことだろう。イラク戦争を歴史のなかに位置づけ、過去の出来事と比較することで、その特殊性を浮き彫りにする(たとえば、一九四五年のベルリンと二〇〇三年のバグダッドの比較、アメリカのイラク支配と大英帝国のインド支配の違い、など)。これは歴史の素養なくして出来ることでない。
もうひとつ、本書を読んで印象に強く残るのは、細かい事実、逸話にこだわるコバーン記者の取材姿勢である(たとえば、イラク人の果樹園をなぎ倒す米軍ブルドーザーの拡声器からジャズが流れていた、との記述)。ジャーナリズムの神もまた、細部に宿り給うのだ。
コバーン記者の諧謔も、読後に余韻を残すものである。絶望的な状況を描きながら、この人は決してユーモアを忘れないのである。(「ダイハード2」というニックネームがついたカナリアのこと、バグダッドのホテルのエレベーターを占拠した「空飛ぶ族長」の話、同じホテルの玄関口のフロアにあったパパ・ブッシュの「踏み絵」と、それを飛びそこなって股グラを痛めた米政府当局者のエピソード、「グリーンゾーン」内の売春宿の逸話、等々……)
そして何よりも、コバーン記者の眼力の鋭さ――。
たとえば、「もし、ブッシュとブレアが、イラクの独裁者が『大量破壊兵器』という、中東にとって脅威となりうる軍事力を保持していると本当に思っていたなら、たぶん攻撃は仕掛けなかったろう」という指摘など、実に鋭利である。
言われてみれば、確かにその通り! ブッシュ大統領は、イラクには「サダムの核」はない、とわかっていたのだ。「大量破壊兵器」はないとわかっていたからこそ、「大量破壊兵器」があると言い立てて、それを口実にイラクへ攻め込んだ……。
(私のコメント)
日本の一番の弱点は情報活動が低調な事であり、日露戦争に勝つまでの日本は、情報宣伝活動にも重点をおいていた。しかしそれ以降の日本は軍隊が強力になるにつれて情報よりも作戦に人材の重点を置くようになった。次第に欧米の政治状況にも疎くなり、国内では軍国主義的な動きが主導権を持ちはじめて、特にアメリカの動きを読み誤った。
外務大臣の松岡洋右もアメリカ留学して9年間滞在してもアメリカの動きを読み誤った。英語が出来るだけといった中途半端なアメリカ認識でかえってアメリカとの外交関係を拗らせてしまった。アメリカのイラク戦争のつまづきもイラクからの亡命者からの情報に頼り、イラクの状況分析を誤った。石油の確保が目的ならばむしろサダム・フセインを買収してしまった方が手っ取り早かったのではないかと思う。
パトリック・コバーンが指摘しているようにアメリカのイラク占領はアメリカの国力の限界を示すものとなり、僅か10年余りで世界帝国アメリカの滅亡のきっかけになるのだろう。サダム・フセインが絶えず戦争を必要としていたごとく、アメリカもまた絶えず戦争を必要としていた。戦争によって栄えた帝国は戦争に敗れることでもろくも滅亡する。
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。