| Tweet |
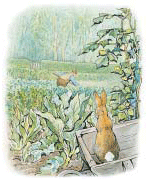
何年もかかる薬事審査、保険点数の削減、新技術に対する異常なまでの低い評価、博士ばかり作り出す医療研究体制の歪さ等々 もういい加減に厚労省も目覚めて欲しいものです。
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/14540.html;jsessionid=52DA83B1A9C9F8C3EE2DF65EF265953F
「医療が経済にもたらす波及効果や雇用創出効果は大きく、EU(欧州連合)のように医療の多様な分野に積極的に投資することが経済の活性化につながり、国を豊かにして国民を幸せにする」―。少子高齢化の進展とともに社会保障負担が増大すれば経済を中心に活性が失われるとする1983年の「医療費亡国論」に端を発する日本の医療費抑制政策に対し、「医療による立国」へ転換すべきと訴える現役医師がいる。
「医療立国論-崩壊する医療制度に歯止めをかける!」を著した帝京大学医学部名誉教授の大村昭人さん(同大学医療技術学部臨床検査科主任教授)は、ダイナミックな理論のイメージからは想像もできないほど、親しみやすい笑顔と柔和な雰囲気を持つ人だ。「世間では医療が崩壊すると叫ばれているが、どうすればよいのか提案することが大事だ」。医療崩壊ではなく、医療立国へ―。大村氏が世間に一歩先行く展望を語るに至った背景には何があるのか。人物像に迫った。(熊田梨恵)
■町医者だった大おじの背を見て
「小さいころから人と触れ合うのが好きで、人と接する職業に就きたかった」。医師になるきっかけをこう語る。1942年、東京生まれ。幼少時代には、福岡の炭鉱地帯で開業医をしていた大おじのところによく遊びに行った。典型的な町医者だった大おじが夜中に患者に呼び出されて出かけていく背中を見送ることもしばしば。患者との信頼関係に支えられ、地域に根差した医療を行う大おじの姿は将来の選択に大きな影響を与えた。中学・高校時代は現在作家の嵐山光三郎氏と同級でともに文芸部に所属するなど、演劇活動に熱中。1年遅れで東京大学に進学した。
当時の東大は青年医師連合を中心として大学医局や厚生省の政策に反対する学生闘争の真っ只中。安田講堂事件で終焉を迎えるころには、医学生のほとんどが大学を去ってしまった。「東大付属病院での研修は半年しかできなかった」と、まともに研修ができる状態ではなかったと振り返り、4年間の臨床研修のほとんどを一般病院で過ごした。
■アメリカで見た日本の医学教育とのギャップ
「研修医時代にハーバード大学の留学から帰国した医師に出会った。病態生理について『すべて理論で説明できる』ということに目からうろこが落ち、アメリカはおもしろそうだと思った」と、日本の臨床医学に足りなかったものが米国の医学にはあると感じた。「日本では『理屈ではなく観察しなさい』と教えられた。大事なことではあるが、なぜそうなるのかというメカニズムを知りたかった」。
1973年、まだ日本人の留学生は少ない時代に渡米した。ワシントン州立大学医学部で麻酔科の研修医としてトレーニングを開始したが、最初は英会話がほとんどできず、専門用語や当直時の救急対応に苦労した。医療現場で普通に仕事ができるようになるまでに3年を要した。
「アメリカはフェアな社会。『臨床』『安全で質の高い医療』『教育』の各分野について、学生や同僚、教授たちそれぞれに人事委員会があり、スタッフ一人ひとりを評価票で評価する。自分の主任教授はそれを見て評価するので正当な評価を受ける」と、やればやっただけの評価が返ってくることにとてもやりがいを感じた。同大の教授に見込まれてユタ州立大学医学部に移ってからは、医学部のスタッフや講師を経て5年目には助教授日本でいう准教授の立場まで昇進した。
「ワシントン州立大では日本の約8倍の数の指導医がいた。マンツーマンで手取り足取り教えてもらえる」と、日本の研修医に比べて米国の研修医教育は充実していたと語る。「日本は論文などペーパーに偏重した教育や評価体制だが、アメリカは臨床や教育の評価比重も大きく、多数のスタッフを動員して医学生に侵襲行為も教え、臨床を重んじている」と、指導医のサポート体制が万全なために医学生に医療行為を教えることができると指摘。日本の指導医研修医は拘束時間が長いが、ユタ州立大では週3.5日の臨床研修業務以外は自分の裁量で研究や勉強などに時間を費やせる自由時間だったためストレスも少なかった。「レーガン大統領による医療の市場原理化で4700万人の医療保険未加入者が出ている今のアメリカの医療の姿は非常に残念だが、医学生に対する教育体制はとてもよかった。日本もせめて指導医の数を2倍にすべきだ」。
■現場で感じた「医療危機」
6年半の渡米生活を終え、知人の縁で帝京大学医学部の麻酔科の助教授として帰国。2003年には同大医学部長に就任、定年を迎えた昨年4月には医学部名誉教授となり、医療技術学部臨床検査科主任教授としてスタッフ教育にも携わっている。
帰国後、日本の医療はどこかおかしいと感じていた。「どんなにがんばっても患者の医療のニーズに応えることができない。提供側は消耗してしまうばかりなのに、患者には理解してもらえない」。特に救急医療の変化を挙げる。「例えば脳梗塞。技術が未発達だったころは2次救急で患者を寝かせておくような対応で済んでいたが、血栓溶解剤ができて早期治療が可能になった。早期のリハビリも求められるようになり、3次救急の需要が増えた。心筋梗塞や糖尿病などほかの病気でも同じだ」。救急医療に携わるスタッフの増員も必要になるが、国が進める医療費抑制政策により救急医療を担う基幹病院から勤務医が離れてしまうなど、人員不足と救急需要の高まりで現場は混乱している。「マスコミも悪い。医療機関は患者を『たらい回し』しているのではなく、ほかの入院患者や救急患者に対応しているから受け入れることができないだけだ」と現場の状況を訴える。「開業医にも昔のように軽症の救急患者を見てもらうことが必要」と、基幹病院だけでなく、開業医も輪番などで救急医療に協力していくことが今後必要と提案する。
■医師や患者を救うために「医療立国」を
「現場の医師たちががんばっているのに報われない。これを見逃すことはできない」。著書「医療立国論-崩壊する医療制度に歯止めをかける!」を昨年5月に発表した。政府が骨太の方針2006で毎年2200億円の社会保障費削減を求めるなど、医療を国の負債とする考えから脱却し、医療に投資することで国を活性化させようとする考えを中心に据えている。特に当時の厚生省の吉村仁保険局長が1983年に発表した、社会保障費がこのまま増大すると日本の社会の活性が奪われるとした「医療費亡国論」とその流れを継いだ現在の医療費抑制制作を辛辣に批判。日本の医療はアクセス、コスト、質の点で優れており、OECD加盟国と比較して病床数辺りの医師数や看護師数は圧倒的に少なく、特に米国と比較すると病床数あたりの医師の数は約5分の1、看護師数は約6分の1となるなど、日本の医療は医療従事者の献身的な努力で支えられてきたが「それも限界に来ている」と指摘している。医療費抑制を求める前に、一般会計の約3倍の225兆円ある特別会計の無駄を省くべきとも主張。その上で、「国は医療に投資し、医療業界の中での雇用を増加させ、医療産業を活性化させることで日本の経済力向上に貢献するべきだ」。
特に「EUの国々では、医療が経済活性化の要であることが認識されている」と訴える。ヨーロピアン・コミッションの05年8月のレポートによると、EU諸国では医療への投資が経済成長率の16〜27%を占める。EU15カ国に限ると、医療制度の経済効果はGDPの7%に相当し、金融の約5%を上回る。「GDPの7%という数字を、日本に当てはめた場合、年間35兆円ほどGDPを押し上げることになる」と、EU諸国では医療・福祉は国の負債ではなく、経済発展の原動力として認識されていることを強調する。この具体的な例としてスウェーデン、フィンランド、デンマーク、ノルウェーなど北欧の国々は租税、社会保険料の国民負担率が非常に高いにもかかわらず、医療福祉産業を育成する中で経済競争力では世界のトップ10の上位を維持している。国の手厚い社会福祉政策の中で女性、高齢者そして障害者でも働く機会に恵まれていて自立する中で社会に貢献もできている。
「日本は素晴らしい技術大国。日本人の高い技術と能力、そしてお金を医療に費やさなければいけない」。正しく医療に投資することで、医療の質も向上し、日本の国力が増して国民の幸せにつながると述べている。
著書では、医療産業を活性化させるため、医療機器の承認を遅らせている薬事法の改正や医薬品医療機器総合機構で医療機器を審査するスタッフの増員のほか、欧米で安全性が確認されている薬品は日本で一括承認することを求めるなど、医療を活性化させるための具体的な提案を数多く挙げている。「崩壊と言うばかりでは何も変わらない。提案していくことが重要」と、医療崩壊を嘆く前に何ができるかを考えることが重要と語った。
「現場にいると忙殺され、複雑な問題をじっくり考えている余裕もないために現場の医師たちが声を出しにくい」と憂慮し、「自分が声を上げて医療の現状に対する理解と協力を求めていきたい」と述べる。「著書はその足がかり。今後は講演や執筆など、様々な形で医療立国を提言していきたい」。
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。