| Tweet |
(回答先: Re: 日本の戦後の引揚者 投稿者 tk 日時 2008 年 3 月 22 日 02:36:17)
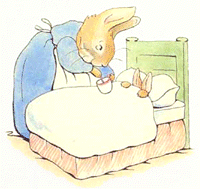
tkさん
昨年母親が亡くなった時に、知り合いに送った散文です。
母は、昭和3年2月15日、当時、日本の植民地でありました京城(けいじょう)今のソウルで生まれた、戦中派、所謂、外地生まれの引揚者です。
引揚者とは、生まれた故郷を無くした人達です。
この頃は死語になりつつある引揚者ですが、私はその息子として、いつも京城の思い出を聞かされて育ちました。
朝鮮半島では、植民者側として、ジャズのかかるステーキ屋で食事しながら、「特攻隊の理不尽さ」を語るなど、当時の内地では味わえないようなモダンな生活を送りつつ、女学校から軍司令部に駆り出され働いていた、軍国少女でした。
しかし終戦1年前、17歳の時、文人で北原白秋や石川啄木とも親交のあった文筆家であり、事業家でもあった父親を京城の飛行機事故で亡くし(当時に飛行機に乗れる身分だったことでも、母親のお嬢さんぶりが想像できますが。)、その後、終戦。
17歳の少女であった母は、持てるだけの物を担いで、山の上の日本神社が炎上し、黒煙をあげる京城から、文字通り逃げるようにして、あこがれの内地に引揚げて来ました。
父を亡くしていたので、祖祖母の出身地である、東北の田舎町に来た訳ですが、身寄りもなく、戦後の混沌の中に投げ出され、必死で生き抜いてきました。
田舎で知り合った私の父と結婚して、田舎に暮らしながら、常に京城の学友が引揚、住んでいる東京に憧れながら、自分も必死で働き、父と共に4人の子供を育て、全員を東京の大学に行かせました。
この苦労は並大抵なものではなかったと思います。
京城でオンドルと呼ばれる床暖房の家に住み、台所にはガス器具が揃っていた生活。ところが、当時の日本の田舎では「七輪でご飯を炊いている」と驚いたそうです。
まだ父が存命のとき、三人で母の故郷、京城に行きました。
懐かしく慣れ親しんだはずの母の故郷は、当たり前ではありますが、植民地時代の面影も薄くなり、韓国の首都、ソウルになっておりました。
自分の通った小学校や、女学校跡、そして住んでいた家を見て、その面影に涙していました。
京城での友人たちは、その殆どが東京に引揚、各方面で活躍される方が多く、戦後30年経ち、落ち着きを取り戻してから、30数年ぶりに行った同窓会は、当時の新聞に大きく取り上げられました。
その後、毎年のように行われる同窓会、50年の時を経ても集まり合い、旧交を深め会い続けるのは、共に故郷を無くした学友同士だったから故だと思われます。
植民地時代だったと言っても、そのような歴史的、政治的な問題を越え、そこは母の生まれ育った故郷でした。
故郷を無くした母親に、自分の原型を見出だすように、私は常に旅人であり続けました。
故郷は、私にとって出る所であり、上京後も、インドや東南アジア、中近東、米国、欧州と、この30年近く、3ヶ月続けて日本にいることがない生活を続けております。
また在日の友人たちにも特別な思い入れがあるのは、そんな母の境遇を逆側から感じるからだと思います。
親の出身地の政治体系は大きく変わり、「自分の知らない国」の国籍を持ち、日本で生まれ、同じテレビを見て、ヒーローを共有した日本籍を持たない友人。
私は体に流れる血より、風土を共にし、思いが通じる友人を大事に思います。
中近東で生活をし、同じ土地で憎しみ会う民族を見た私は、母の様な引揚者、在日の方々も含め、人はなぜ人種を越えて、故郷を共有できないのだとの思いを常に持ち続けております。
逆に言うと、故郷の風土は、人種などに分け隔てて存在しておりません。
それらの想いも、私は母親の中に、自分の原型を見出すのです。
母が亡くなり、悲しみは当然ありますが、母の中に、自分の原型を見出し、私を生み育ててくれたことへの、感謝の念に絶えません。
『かあちゃん、ありがとうございました。』との想いでいっぱいです。
形あるものは、必ず崩れ、人は亡くなる。
今回の母の死は、私の人生哲学である、『その日まで、ただただ精一杯生き続けるだけ』と言う思いを、さらに強くさせました。
|
|
|
|
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
|
|
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。
|
|
|
|
|
|
|
|