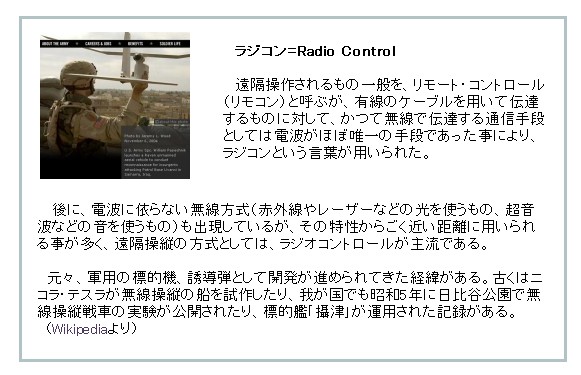| Tweet |
(回答先: てすと 投稿者 姫 日時 2006 年 12 月 05 日 04:45:37)
マインド・コントロールの歴史と極秘にされた人体実験Ⅰ
マインド・コントロールの歴史と極秘にされた人体実験Ⅱ
のつづきになります。
2つのコイル
この問題に最初の解決方法を示したのが、1933年のロジャー・ルークス(Roger Loucks)だった。ジョンズ・ホプキンス大学で考案した彼の方法は2つのコイルの誘電現象を利用したものだった。1つのコイルに流れる電流は、これによって生じた電界の中に置いた別のコイルにも電流を誘導するという現象である。ルークスはこの電流が誘導される方のコイル(二次コイル)をイヌの頭の中にしまい込んだ。この二次コイルからはワイヤーが頭の中に延びて、電気刺激を与えられる脳の部位までつながっている。
そして、頭皮はふさがれ、このようにして刺激装置は「完全に外界からは遮断されているし、頭皮・脳膜を貫くワイヤーは存在しない」。電流を二次コイルに誘発する一次コイルは、頭皮に隠れた二次コイルにちょうど重ねあわせるようにして、皮膚の上に固定される。彼はコイルを伸縮性のバンドを使ってイヌの頭の上にとめることにした。この外部にある一次コイルからはリード線が延びて電流が電源から流されるのである。これが、初めて実験された脳の電気刺激のためのインプラント装置であり、これから発展していく遠隔操作技術の基本でもあった。しかし、ルークスの方法にも次のような制約、問題点が存在していた。
*2つのコイルの相対的位置が安定しない。
*このため二次コイルに発生する電圧・電流が安定しない。
*刺激電流のパラメーター(波の形など)がコントロールできない。
*一次回路に大きな電圧が必要となる。
*一次コイルに電圧を与えるためのコードが接続されているため、
実験動物の行動をやはり制約する必要がある。
これらの問題をすべて解決するには、半世紀以上の時間が必要となる。ルークスの時代は半導体技術もまだ存在していない。トランジスタが実用化されるのは、1950年代に入ってからの話だ。次の突破口はまだ先であり、技術進歩はそれまで一歩一歩進んでいかざるをえなかった。
ラジオ・ボックス
行動の制約は2つのコイルの距離からきていた。主要コイルには電流をコードを使って流す必要があり、主要コイルと皮膚の下にある二次コイルは皮膚をはさんで接近させる必要があったからだ。行動の自由を与えるためには、二次コイルに接続されているコードをなくすか、2つのコイル間の距離をなんとか離す必要がある。最初に試されたのは後者の方法だった。誘導電圧は二つの距離が遠くなれば当然小さくなる。しかし、主要コイルの電圧が大きくなり、それによって生じる電界が強くなれば、その中にある二次コイルの誘導電圧は大きくなる。これを応用すれば、2つのコイル間の距離をもっと離すことが可能となり、その分だけ行動の自由も認められることになる。
ハーバード大学のチャフィー(E.L.Chaffee)とイェール大学のライト(R.Light)が1934年に発表した研究は、この考え方を利用して、サルにある程度の自由な行動を許している。銅線を2000巻した二次コイルはサルの頭皮の下に埋め込まれ、そのコイルからは電極が脳に延びている。誘導を与える主要コイルの工夫を彼らは考えた。3つの主要コイルを作成して、それぞれを90度の位置に配置して木製の箱の内部に取り付けた。このような配置をすることにより、動物が定められた区域内にいさえすれば、かなり一定した電流を二次コイルに誘導することができる。
さらに誘導電流を安定させるために、当時の最先端技術であったダイオードも用いられた。このようにコイル問の距離が長くなり、ラジオ波による電界を利用して二次コイルを誘導する研究が続けられるようになる。次にその主な研究を50年代までみてみよう。技術革新はゆっくりと、しかし確実に進んでいることがわかる。
430キロヘルツ
1936年のスタンフォード大学のフレデリック・A・フェンダー(Frederick A.Fender)による研究では、 6000巻の二次コイルがイヌの頭皮下に埋められた。主要コイルは6つで、檻の上部に取り付けられ、その檻の中ではイヌの自由な行動が許される。フェンダーはチャフィーとライトの実験装置より、スタンフォード大学の方がよりシンプルで安価であると、その優位性を自慢している。一次コイルからの電波周波数は430キロヘルツである。このシステムの問題点としては電極の分極化(このため時間の経過とともに電極の電流が流れにくくなる)、動物の動きによるリード線の分断があげられている。
フェンダーの実験では、この分断による実験中止までの5ヵ月半の期間は、安定した刺激を与え続けることができた。1944年のJ・グレイグ一(J.Greig)とA・リッチー(A.Ritchie)による実験では、フェンダーと同様な装置が用いられており、同じ問題が生じている。その実験の際に使用された電波の周波数は、100キロヘルツである。1946年のケンブリッジのG・W・ハリス(G.W.Harris)は、当初のルークスの研究と同じ、2つのコイルを接近させた方法を採用している。彼はその2つのコイルの距離を変化させて誘導電圧の大きさを調整している。このとき使われた動物はウサギであり、3年間にわたり実験を続けた。
特筆すべきは、これまでの遠隔技術で刺激対象となったのは大脳皮質の表面であったが(運動を許したため電極の位置の安定性に問題があった)、彼はワイヤーを脳の表面から深く探り入れ、ウサギの視床下部(hypothamus)、下垂体まで電極をもっていった。しかし、運動を考慮して脳の中心線に沿ったインプラントを実施している(左右にずれるとワイヤーの位置が安定しないと考えた)。
二次コイルは、1500回転、内径6ミリ、外径2センチ、厚さ4ミリ。電極は当初は銀を使用していたが、長期の使用では不適格な反応を起こすためプラチナを使うことにした。主要コイルは、2700回転、内径1.3センチ、外径4.9センチ、長さ1.6センチである。主要電源には200ボルト、50ヘルツの電流を用い、2つのコイル間の距離が1センチのとき二次コイルに1.2ボルトの電圧を得ている。しかし、ウサギがじっとしていないと安定電圧が生まれないので、実験者は片手でウサギの首を押さえる必要があった。
1メガヘルツ
1949年のニューヨークのジェームズ・ラファーティ(James M.Lafferty)とジヨン・ファレル(John J.farrell)のふたりは、主要コイルの直径を6フィートから10フィートの大きなものを使い、さらに誘導電波の周波数も1メガヘルツという高周波を用いることによって、二次コイルの出力を上げている。こうすることで、比較的小さな電源で必要な刺激を与えることが可能となり、実験動物であるイヌも、およそ3メートルの円の中を自由に動きまわることが可能になった。刺激電流の波形も、送信装置を変調することにより、望む波形が得られ、その電圧もゲルマニウム・クリスタルを用いることによって安定化している。
受信のアンテナも3相コイルとなり、どの位置にいても安定したラジオ波の影響を受けられるようにした。埋め込まれた装置は、8ヵ月半の間、自由に動きまわるイヌの脳に対して順調に刺激を与えることができた。
1950年のカルフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)心理学科のゲンゲレリ(J.A.Gengerelli)とカレジャン(Verne Kallejian)が考え出したのは、ネズミの学習用に考案された遠隔操作の装置だ。ネズミが学習する迷路などが設置されている10×5×5フィートの空間内にはラジオ波が照射され、ネズミの背中には受信装置が固定されている。この装置は、銀の設置台(2.2センチ×6ミリ)の上にゲルマニウム・クリスタルの整流器とアンテナから成っている。ここから一本のリード線が頭部に余裕をもって延びていて、脳に挿入された電極に接続されている。この装置は動物の心理学的実験における要件であるマウントが十分に小さく軽いこと、完全な行動の自由が許されること、刺激の強さ、長さ、周波数が独立に調整できること、刺激が安定的であることを満たしている。
トランジスタ
1953年にベルゼアーノ(M.Verzeane)とフレンチ(J.French)のふたりは、初めて遠隔装置にトランジスタを使用した。トランジスタの出現により、装置の信頼性、機能性は飛躍的に高まっていく(トランジスタがベル研究所において発明されたのは、1947年であったが、実用的なゲルマニウム合金型トランジスタが開発されたのは、1951年のことであった。これにより、トランジスタを使った装置がいろいろと誕生することになる。最初、一般的にでまわった製品は、トランジスタ補聴器で、ベルゼアーノとフレンチが遠隔装置を製作したのと同じ年の1953年のことであった。これからの進歩は加速化する。世界初のトランジスタ・ラジオTR55をソニーが、当時の価格で1万8000円で発売したのは1956年。64年のシャープの電卓が50万円、これが72年のカシオ・ミニで1万2000円となる)。
1.8ギガヘルツ
1956年にドイツで発表されたイェコレク(W.Jechorek)とホルスト(E.von Holst)によるラジオ波誘導を用いた遠隔刺激システムでは、送信において1.8ギガヘルツ(1800メガヘルツ)という高周波と100ワットという高出力を使用している(この年、トランジスタを発明したベル研究所の3人はノーベル賞を受賞している)。
パラボラ・アンテナ
1959年にはアメリカ空軍の協力のもとにイタリアで研究していたボナッツォーラ(S.Bonazzola)とガルチェロッティ(T.Gualtierotti)は次のような発表をしている。彼らはネコの脳を遠隔操作によって刺激した。受信装置と刺激装置はかなり小さくて、被験動物の皮下に恒久的にインプラントすることができる。電気刺激は、動物がどの場所、どんな運動をしていても、一定した強さ、時間の長さで与えることができる。6つのトランジスタを使用したこの装置は受信アンテナ、増幅回路、マルチバイブレーター、トランスフォーマーなどから成り、電源には、ミニチュアの7つの水銀電池が使用されている(各電池は1.5ボルト)。
高感度の性能によって、動物がどんなポジションにいても刺激が与えることができ、30センチ波(1ギガヘルツ)の送信電波はパラボラ・アンテナによって照射され、およそ50メートル離れたところでも、さらにコンクリートや木製の壁の向こうに対象動物がいても、安定した刺激を与えることができる。しかし、バッテリーを使っているため、その寿命は(論文作成時で)約1ヵ月であった。この装置による実験によって、さまざまな運動や行動が誘発、観察された。
ぺ-ス・メーカー
このように50年代になると装置の小型化・軽量化が進み、多様な可能性が実現されていく。脳の電気刺激ではないが、心臓の電気刺激の世界でも同じ進歩が見られる。心臓の電気刺激の装置、つまり心臓のぺースメーカーが初めてつくられたのは、1952年のことであったが、その6年後には、完全な埋め込み型の装置がスウェーデンにおいて開発されている。これには充電式のニッケル・カドニウム電池(ニッカド電池)が使われており、体外から電気誘導によって再充電が行われるようになっている。ラジオ波による電力供給型のぺースメーカーもその後開発され、1959年1月に患者にインプラントされている(しかし、その3週間後には、リード線の断絶により機能が停止し、当の患者は死去している)。
闘牛士デルガド
ニューヨーク・タイムズの一面にも載った有名な脳刺激による遠隔操作のデモンストレーションをここで紹介しておこう。場所はスペインのコルドバのとある闘牛場、その中で赤いケープを片手に持っているのが脳の電気刺激の研究で世界をリードしてきたアメリカ、イェール大学のホセ・デルガド(Jose Delgado)である。もともと彼はスペインの出身で医学のキャリアもここからスタートしている。そこに1頭のアンダルシアの闘牛が登場、牛はデルガドが振る赤いケープに興奮し、彼めがけて突進する。彼は脳については誰よりも知識はあるが、闘牛についてはなんの経験も持っていない。
興奮した牛はデルガドの1メートル手前まできた。そのとき、デルガドは動揺することもなく、もう一方の手で持っていた小さな黒い装置のボタンを押した。すると牛はデルガドに角を突き刺す寸前でその場に静止する。デルガドの持っていたのは遠隔装置で、スイッチが入ると同時に牛の脳に電気刺激が起こり、牛の攻撃性がなくなった。デルガドが別のボタンを押すと、牛は今度は方向を右に変えて彼から速足で遠ざかっていった。これは1964年に行われた実験である(デルガドはESBの先駆的な研究、とくに遠隔技術の研究開発のパイオニアだった。しかし、彼は80年代よりスペインに戻り、今度は電磁波による脳刺激の研究を始める。

デルガドの遠隔操作実験を伝えるニューヨーク・タイムズ紙の第一面記事に掲載された写真。
NewYorkTimes,1965.5.17
極めて弱い磁界により生体に対するさまざまな効果の観察結果を報告した彼の論文は1980~90年代に世界的にも大きな驚きを与えることになる)。
CIAレポート
技術開発が加速化して進められる中、時代は60年代に入る。60年代に入ってまもなくCIAの報告書はリモート・コントロールについて次のように述べている。
「我々は現在、脳の刺激においての『生産能力』を有している」具体的には、「我々は、イヌを決められたコースに従って歩かせるようなプロトタイプ・システムを解明しつつある」
そして、この一年後のCIA文書では、動物への脳刺激の応用の可能性のひとつとして、生物化学兵器の運搬をあげていた。その目的は、「最終的行動タイプの作戦」、っまり「暗殺」計画での使用である。映画『イルカの日』で使われたイルカたちが、その考え方の好例を示すだろう。
軽量化
パーツの高度化・小型化により、比較的簡単な装置でも機能が高まっていく。頭部に固定されるタイプの受信装置も軽量化が進む。60年代初頭に使われたサルのための装置は、そのバッテリーをも含めた重量が、76グラム(warner..1962年)や、45グラム(Uspon.1962年)であったが、マックス・プランク研究所のマウルス(M.Maurus)が使用したものは4グラム、70年代初頭、リスザルには5グラム(Maurus & Ploog.1971年)、ハトに使用したものは、僅か2.5グラム(Zeier.1971年)しかなかった。
電気的自慰行為
先に紹介したオールズとミルナーによる脳の自已刺激実験により、モチベーション、動機付けの研究が発展していく。これは、ムチとアメとの研究と言うこともできる。ムチを伴う行動は避け、アメの行動は進んでこれを行うという原理に基づいたものだ。アメの格好のデモンストレーションの一例がある。映画『イルカの日』のイルカ博士のモデルとなったジョン・C・リリー(John.C.Lily)は、50年代には脳の電気的刺激研究の最先端におり、その時代の研究対象はイルカではなくサルであった。
彼はいくつもの電極を極く簡単に脳に挿入する技術を開発し、1頭のサルの脳に610もの電極を差し込んで、電気刺激を与えるというような研究をしていた。脳自体には痛さを感じる神経が存在しないので、サルでも人間でも、意識がはっきりしたまま電極を脳の深く挿入することができる。そんな研究の中、サルの脳のある部位を電気刺激するとサルがオルガニズムを体験することがわかり、その電気刺激のスイッチをサルの自由にまかせた。電流は3分ごとに流れるようにしてある。自己刺激実験である。するとサルはスイッチを絶え間なく押し続け、電流を自分の脳に与えることによってオルガニズムを3分ごとに楽しんだ。サルはこの電気的自慰行為を1日のうち16時間連続して行い、そして次の6時間は睡眠をとったが、また眠りから覚めると3分ごとのエクスタシーを再び楽しんだのだった。
この記録フィルムがある科学会議の席上で公開された。これは科学界以外にも広く興味を呼び起こしたようで、リリーが所属していた国立衛生研究所(NIH)の所長をとおして、リリーへ講演の要請があった。要請してきたのは、アメリカの諜報界のグループで、FBI、CIA、NSAをはじめ、空軍情報局、海軍情報局、軍、国務省などのスタッフが聴講生になるという話だった。リリーは報告会を秘密会としないという条件のもとに講演の要請を引き受ける。しかし、彼らの関心事は、講演の後の質疑応答でも明白だった。
そのひとりはリリーに、このテクニックの人間への応用の可能性について尋ねたのだ。癩癩(てんかん)、パーキンソン病の患者への応用についてのみリリーは答えた。マインド・コントロールを人間に使用するといったことこそ彼が一番、嫌悪するものであったからだ。結局、この研究の悪用の可能性を憂慮して、リリーは脳の電気的刺激の研究を放棄し、別の分野から彼のテーマである「心」の研究にとりかかるようになる。イルカとの対話の研究は、このようにして開始されるてとになったのである(詳しくは、彼の自叙伝的ノンフィクション『サイエンティスト』が刊行されているので参照されたい)。
サンディア研究所
講演後まもなく、彼が開発した電極のインプラント方法をビデオに撮りたいという依頼の電話が、ニューメキシコのサンディア研究所からあった。その技術を手がけているイルカの研究に応用したいということだった。リリーは、また、作成したビデオが非公開にならないという条件でこれに応じる。しかし、完成したビデオは結局、機密扱いになり、リリーのもとにコピーを送ることすら許されなかった。
山登り
このビデオを撮りにリリーのもとを訪れた研究者が、軍のために動物の遠隔操作の研究を進めていたことが後に明らかになる。彼のある研究発表では、ロバを対象とした遠隔操作のデモンストレーション映画が上映された。電極を脳に埋められたロバは険しい山の予定のコースを「従順」に進んだ。しかも、その決められたコースはあくまでも定規で引いたようにまっ直ぐで、ロバは脇見もせず地形をも無視して突き進むのだった。また、コースの変更は遠隔操作によって可能だった。もし、このロバが爆薬を抱えていれば、あらゆる地形を歩いて進む4本脚の「スマー卜爆弾」となることだろう。ロバが運ぶものは小型の核爆弾かもしれない(サンディア研究所はニューメキシコのカークランド空軍基地内にある。この研究所は核爆弾の研究開発で有名である。同空軍基地内にある博物館侯日本に投下されたニタイプの原爆をはじめ、数多くの原水爆が展示されており、ここを訪れると、この兵器体系の開発・研究の歴史をよく理解できる)。
『サイエンティスト』では、この科学者の名前は公表されていないが、彼の名はニューメキシコのイヴオール・ブラウニング(Ivor Brownig)だと思われる。彼は電極をロバの脳の視床下部にある「快楽」を与えてくれる部位に挿入した。アンテナをつけたそのロバは、送信機からの電波を受けながらニューメキシコにある2000フィートの山を決められたコースで登り、そして彼がスタートしたその地点に戻ってきた。アメとムチ「報償」と「罰」のテクニックを応用したものである。「ロバがあのようにして、コースから外れないように進むのを誰も見たことはないでしょう」と、ブラウニングは回想している。
自由なハト
この技術の初期の実用例を紹介しよう。ブラウニングのロバのテクニックをハトに応用して、小さ荷物を運搬させた。場所はフランスのパリである。CIAはパリにあるKGBの秘密集会所の1つの盗聴を計画した。問題はいかに、盗聴器を設置するかだ。窓があったのでそこに設置しようとした。そこは高いところだが、夜中にハシゴをかけるわけにもいかない。そこで遠隔操作のハトが登場するハトに盗聴器を取り付け、目的の窓のところまで飛ばし、そこでじっとさせて中の会話を聞かせて、CIA側に送信してもらおうという計画だった。結果は成功した。ハトはコントロールされた自由の戦士だった。
ラジコン
半導体も普及し、脳の遠隔操作の「マイコン・セット」(マインド・コントロール用の装置)は製作がより簡単になった。また、必要な費用もどんどん下がる。1968年にチューリッヒのツァイア(Zeier)たちが紹介したハト用の受信装置は4ドルくらいで製作が可能だった。1975年に紹介されたマクシム(Maxim)による方法は、市販のラジコン(ラジオ・コントロール)のユニットを利用した重さ63グラムの受信装置で、コントロールの範囲は600メートルとコスト・パフォーマンスにおいても優れている。
こうして誰でも、動物の「マイコン・セット」が作れるようになった。では、インプラントはどうか。脳に電極を、それもこちらの望む個所に挿入するのは至難の技だろうか。ジョン・リリーは簡単に脳に電極を埋め込む方法を考案した。彼はこの方法を使って一匹のサルの脳に610もの電極を挿入している。
「適当な装置をもったものなら誰でも、電極を使っているという外的な証拠を残さずに、この技術を人間に秘密裡に施すことができるということだ。もしこの技術が秘密機関の手に渡つたら、彼らは人間に対する完全な制御カを獲得し、人間の信念をあっという間に変えることができるだろう。しかも彼らが何をしたかについての証拠をまったく残さずに」(『サイエンティスト』菅靖彦訳、平河出版社・125頁)
人間のコントロールはそんなに単純ではない。ネコより人間の行動が複雑であることは、両者の脳を比較すればあきらかだろう。いったい、人間へのESB技術はどこまで進んでいるのだろうか?人間は人間を電気仕掛けのおもちゃのようにコントロールすることなどできるのだろうか。右に行かせたり、左に行かせたり、笑わせたり、泣かせたり、怒らせる、また精神までをコントロールすることができるのか。人間の操り人形化はどこまで可能だろうか。
(つづく)
次回こそはインプラント(人間操作)の解明に迫ります。一挙に掲載したいのですが、個人の情報処理能力に限界があり、なぜか分割してしまいました。伝書鳩は(やはり!)メソポタミア文明から伝わる技術のようです。文明は未来にも過去にも進化してきています。(笑)
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。