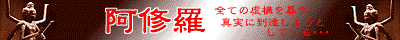
| ★阿修羅♪ > 戦争71 > 341.html ★阿修羅♪ |
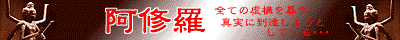
|
| Tweet |
ハタミ政権、改革が挫折
十七日投票のイラン大統領選は、穏健保守派のラフサンジャニ前大統領がリードしている。雇用状況の改善や、核開発問題などで国外からの圧力をはね返すには「実力者」の“再登板”が望まれた、という構図だ。だが、いずれの有力候補が勝っても公約実現には多大な困難が伴う。イスラム政権の問題点を探った。 (テヘラン・嶋田昭浩)
●対米どう対応
選挙戦終盤の十四日夜。テヘラン北部の商店街のビルに、情報通信事業関係者が百人近く集まった。前大統領の支援集会だ。男性弁士は「ラフサンジャニ氏だけが先端技術の普及に熱心。勝利はオフィスの利便化につながる」と持ち上げた。
同氏の選挙運動は「業界団体などを通じての強力な集票活動が持ち味」だ。首都中心部の選挙対策本部ビルの上階には、業界団体のほか、教育、芸術、スポーツなどの分野ごとに整然と分かれたデスクを設け、選挙運動を調整。日本の「組織選挙」をほうふつさせた。
前大統領の“売り”は「実力者」であること。
「ラフサンジャニ氏はイスラム革命の指導者ホメイニ師に近かった。一九八九年の同師の死後、ハメネイ師を最高指導者に押し上げた一人がラフサンジャニ氏。キングメーカーとして最高指導者にも影響力を持ち、思うことをやれる」とイランのベテラン記者は言う。
前大統領は選挙期間中「緊張緩和政策」を口にし、対米関係改善に意欲を見せた。しかし、対米協議には、イランが生存権を認めないイスラエルとの関係見直しがつきまとう。保守派ならではの課題だが、指導部をまとめるのは容易ではない。
●改革派は棄権
一方、十四日午後には改革派のモイーン元高等教育相が首都中心部のテヘラン大学前で一万人規模の集会を開催。だが、ほぼ同時刻に首都北部の刑務所前にも、テヘラン大生らが集まった。獄中でハンガーストライキを続ける活動家らの釈放を求める人々だ。
治安当局側は退去を促したが強硬措置はとらず、なかなか立ち去ろうとしない数十人の支援者に対し、言葉での説得を繰り返す。選挙期間中とあって、外国報道陣の目を意識している。
支援者の一人、法学部の女子学生アニタさんは「ハタミ大統領の八年間で独裁的手法がより強化された」と嘆いた。大統領を「独裁的」とみるのではない。大統領の穏健改革路線を封じ込めるために、保守派が司法当局を通じて改革派系新聞の発行禁止処分などを命じてきたからだ。
本来、アニタさんらの票は、人権問題に積極的で、政治犯の釈放を要求するモイーン氏に流れてもおかしくない。だが、アニタさんは「どの候補も違いがない。真の民主選挙ではない」として、ボイコットするという。
●イスラム基準
今回の大統領選では、千人以上が立候補登録したが、保守派が支配する護憲評議会の事前審査で出馬が認められたのはわずか八人。このうち七人が立候補した。
昨年二月の国会選挙でも同評議会は改革派の現職議員らを失格とし、現議会は保守派が優勢だ。たとえ議会で法案を通したとしても、同評議会が「憲法違反」と判断すれば差し戻される。憲法は基本的人権を保障しながら、あくまで「イスラム教の基準の制限内で」と明記。モイーン氏の「人権政策」には実効を疑問視する声が絶えない。
「ハタミ大統領に期待したが、何も変わらなかった」。国民の失望感は小さくない。保守派のガリバフ氏の顧問アスガリ氏も、「国民は政治的議論に嫌気が差している」と指摘。棄権による低投票率も懸念される。
だが、低投票率は、現指導部の正統性という体制の根幹を揺るがす。今回の事前審査で当初、不適格とされたモイーン氏ら改革派二人を、最高指導者ハメネイ師(保守派)が“救済”し出馬を認めさせたのも、投票率の引き上げが狙いだったのは明らかだ。
■投票始まる 初の決選投票も
【テヘラン=嶋田昭浩】イラン大統領選挙の投票が十七日行われた。二期八年務めたハタミ大統領の任期満了に伴う選挙。内政では同大統領の改革路線が保守派の抵抗で頓挫する一方、核問題で外圧が強まる中、今後のイランの行方を決める重要な節目となる。
選挙には七人が立候補。穏健保守派のラフサンジャニ前大統領が最有力で、改革派のモイーン元高等教育相が追う展開。ただ、当選には50%を超える得票が必要。同国初の上位二者による決選投票の可能性も高まっている。ハタミ大統領の改革失敗に失望して棄権する市民も多く、投票率も焦点だ。投票は同日夜の締め切りで即日開票。十八日中にも結果が発表される。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kakushin/20050618/mng_____kakushin000.shtml
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。