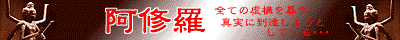
| ★阿修羅♪ > 狂牛病・遺伝子組み換え11 > 185.html ★阿修羅♪ |
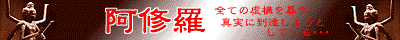
|
| Tweet |
(回答先: 米で2例目のBSE確定 日本の輸入再開に影響か─「共同通信」 投稿者 天木ファン 日時 2005 年 6 月 25 日 07:54:36)
BSE:米が確認検査方法改善を表明 不十分と日本専門家
米国で2頭目となるBSE牛が確認され、米国はこれまでの確認検査方法の改善を表明した。しかし、それでも米国の検査は対象頭数が少なく偏っており、BSEの広がりを正しく捕らえるのに不十分だと、日本の専門家は疑問視する。米国産牛肉の安全性を検討している食品安全委員会は、米国内でのBSEの広がり具合を参考に審議する方針で、検査体制は重要な問題になりそうだ。
米国は、03年12月に初のBSE牛が出て以降、約38万8000頭を検査した。今回の2頭目を含め単純計算ではBSE牛は約19万頭に1頭になる。米農務長官は会見で「牛肉で被害を受ける確率より、食料品店に行こうと道を渡る途中でけがをする確率の方が高い」と胸を張った。
ただ、米国で食肉処理される牛は年間約3500万頭で、検査されたのは1%に満たない。さらに検査対象は、ふらつきなどBSEが疑われる症状のある牛や死亡した牛の約6割に限られ、見かけ上、健康な牛は対象外だ。しかし、日本ではこれまで感染牛とされた20頭のうち、症状からBSEが疑われた牛は一頭もいなかった。
米国は、BSE牛を効率よく発見する目的で、ヨーロッパでのBSE発見率に基づいて検査体制を決めたという。これに対し、食品安全委プリオン専門調査会の吉川泰弘座長は「ヨーロッパの牛は多量の異常プリオンを摂取し、食肉処理前に症状が出やすかったのだろう。日本や米国のように異常プリオンが比較的少ないと、症状が出ず処理される牛が増えると考えられる」と話し、症状のある牛の検査だけでは不十分だと指摘する。
ヨーロッパのBSE専門家らで作った国際調査団は昨年2月、健康な牛も検査対象に含めるよう米国に勧告したが、米国は従わなかった。
また、調査会の山内一也委員は「米国は2頭目の牛がいったんは陰性と判定された理由に、検査手順などに問題があった可能性を挙げている。検査技術に自信がないとしか思えない」と不信感を表している。【高木昭午】
http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/america/news/20050626k0000m030069000c.html
BSE感染牛:日本、米国の業界など反応
◆消費者団体と外食業界、異なる声
米国で24日、2頭目の牛海綿状脳症(BSE)感染牛が確認されたことで、国内の消費者団体から米国産牛肉の輸入再開について慎重な検討を求める声が上がる一方、外食業界は早期輸入再開を求めている。
専門家で構成する食品安全委員会プリオン専門調査会は、輸入再開の是非を諮問され、「生後20カ月以下」の米国産牛の安全性を科学的に検証している。
全国消費者団体連絡会の神田敏子事務局長は「米国の検査体制などは日本に比べて不完全なので、(2頭目は)予想通り。食品安全委は外圧に負けず、しっかりと審議してほしい」と述べた。
一方、外食産業界は、「『生後20カ月以下』などの輸入条件は、感染牛が出ても安全なように設けたもの」と冷静に受け止める。必要な牛肉量を確保するため、「生後30カ月以下」への基準緩和を要求している牛丼チェーンの吉野家ディー・アンド・シーは、「まずは(20カ月以下で)輸入を再開することが大切」(企画室)と迅速な審議を求めた。【望月靖祥】
◆再開遅れれば圧力強化
【ワシントン木村旬】米国は2頭目のBSE感染牛が確認されても、早期輸入再開を迫る姿勢を変えていない。再開時期がずれ込めば、対日圧力が一段と強まるのは必至だ。
米国最大の畜産団体、全米牛生産者牛肉協会は24日、「38万8000頭を検査して、感染牛は1頭だけ。米国牛は安全で、再開交渉に影響を与えるべきではない」との声明を発表し、農務省に強い態度で交渉に臨むよう促した。
上下両院では3月、日本が早期再開に応じなければ、米国政府に経済制裁を求める決議案が提出された。夏の休会前の7月末にも採決する動きがある。日本政府は、輸入再開に関する食品安全委プリオン調査会の答申を7月末にも予定していたが、今回の感染牛確認で答申が遅れると、決議案が可決される事態にも発展しかねない。
http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/america/news/20050626k0000m020055000c.html
▲このページのTOPへ HOME > 狂牛病・遺伝子組み換え11掲示板
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。